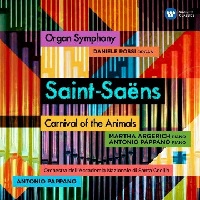★★★★★ サンサーンス作品の愉悦を、聴き手に存分に味わわせてくれるアルバム
2019年のチャイコフスキー国際コンクールで優勝したフランスのピアニスト、アレクサンドル・カントロフ(Alexandre Kantorow 1997-)が、高名なヴァイオリニストであり指揮者でもある父、ジャン=ジャック・カントロフ(Jean-Jacques Kantorow 1945-)と協演して録音したサンサーンス(Camille Saint-Saens 1835-1921)のピアノと管弦楽のための作品集。収録曲は下記の通り。
1) ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.22
2) ウェディング・ケーキ(カプリース・ワルツ) op.76
3) アレグロ・アパッショナート 嬰ハ短調 op.70
4) ピアノ協奏曲 第1番 ニ長調 op.17
5) オーベルニュ狂詩曲 op.73
6) 幻想曲「アフリカ」 op.89
オーケストラはタピオラ・シンフォニエッタ。
1)は2021年、2,5)は2018年、3,4,6)は2020年の録音。ピアノ協奏曲の第3番~第5番を収録したアルバムは既出であり、当盤によってサンサーンスのピアノ協奏曲の全曲録音が完成したことになる。
収録曲中もっとも有名なのは、ピアノ協奏曲第2番で、現在ではサンサーンスの代表作の一つとしての地位を占めている。この曲は、いきなりピアノ独奏のカデンツァで開始されるが、アレクサンドル・カントロフのピアノは、重厚な質感を持った光沢あるタッチで、冒頭から聴き手を音楽の世界に引き込んでくれる。エネルギーを溜めては放つという呼吸に重力感があり、その振幅が心地よい。踏み込みの大きいピアニズムは、浪漫的であり、ヴィルトゥオーゾらしく、サン・サーンスの楽曲によく合致する。オーケストラは透明感のある響きでこれをサポートしており、ソツがない。情感に訴えるパートでも、旋律の性質に沿った自然さがあるので、決してオーバーアクションにならないところも美点と思う。第2楽章の華やかさは、ピアノと管弦楽の繊細なやり取りが楽しく、第3楽章のスピーディーなイタリアふう舞曲は、あちこちに放散する音の華やかな散らばりが印象的。ピアノの技巧の冴えは流石だ。
ウェディング・ケーキ(カプリース・ワルツ)、アレグロ・アパッショナートは、いずれも録音機会の多い作品ではないが、特にウェディング・ケーキは楽しい気分に満ちた作品で、いかにもサンサーンス的な外向性があるが、アレクサンドル・カントロフのピアノがビタリとはまるのは、当然といったところだろうか。
ピアノ協奏曲第1番は循環形式を踏襲した作品。アレクサンドル・カントロフのピアノは、全体的な流れがすばらしくスムーズであり、その中で、適度な緩急をもつ自在性があって、ここでも抜群の順応性を示している。終楽章のオーケストラとの音の融合は、絶対的な美しさを存分に味わわせてくれるだろう。
末尾に収録された幻想曲「アフリカ」は、ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」を彷彿とさせるもので、アラビア音楽風のエスニシティをサンサーンスなりの表現で音化した作品。これも録音の機会の多い作品ではないが、当盤のような優れた演奏で聴くと、結構楽しめると思う。
サンサーンスの書いたピアノと管弦楽のための諸作品を集約し、録音時間なんと85分超の長時間収録版となっており、量的な面でもサービスの行き届いたアルバムとなっています。
|