 |
交響曲 全集 交響曲 第10番~アダージョ ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 ヨーロッパ合唱アカデミー フライブルク大聖堂児童合唱団 カルフ・アウレリウス児童合唱団 S: バンゼ ベジガー マルク ホイットルジー レイ MS: カリッシュ グリューネヴァルト A: ペツコヴァー T: ウインズレイド Br: マイケルズ=ムーア Bs: リカ レビュー日:2014.8.22 |
| ★★★★★ モダニズムに徹した鋭利な知の切れ味を堪能する新解釈のマーラー全集
ドイツの指揮者ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-)が、1988年から2003年にかけて、南西ドイツ放送響と製作したマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲全集。CD13枚組のBox-Set。交響曲第10番は第1楽章のみ(2005年にクック版の全曲を録音、別売)。「大地の歌」は含まれない(1992年に第1,3,5楽章、2002年に第2,4,6楽章を録音したが、当アイテムには含まれなかった)。収録内容の詳細は以下の通り。 【CD1】 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 2002年録音 【CD2-4】 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」 1996年録音 ユリアーネ・バンゼ(Juliane Banse 1969- ソプラノ) コルネリア・カリッシュ(Cornelia Kallisch 1955- メゾソプラノ) ヨーロッパ合唱アカデミー 交響曲 第3番 ニ短調 1997年録音 コルネリア・カリッシュ(メゾソプラノ) ヨーロッパ合唱アカデミー フライブルク大聖堂児童合唱団 【CD5】 交響曲 第4番 ト長調 「大いなる喜びへの讃歌」 1988年録音 クリスティーン・ホイットルジー(Christine Whittlesey 1956- ソプラノ) 【CD6】 交響曲 第5番 嬰ハ短調 2003年録音 【CD7,8】 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」 1999年録音 【CD9】 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」 1993年録音 【CD10,11】 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」 1998年録音 クリスティアーネ・ベジガー(Christiane Boesiger ソプラノ) アレッサンドラ・マルク(Alessandra Marc 1957- ソプラノ) マーガレット・ジェーン・レイ(Margaret Jane Wray ソプラノ) エウゲニー・グリューネヴァルト(Eugenie Grunewald 1956- メゾソプラノ) ダグマル・ペツコヴァー(Dagmar Peckova 1961- アルト) グレン・ウインズレイド(Glenn Winslade 1958- テノール) アンソニー・マイケルズ=ムーア(Anthony Michaels-Moore 1957- バリトン) ペーター・リカ(Peter Lika 1947- バス) ヨーロッパ合唱アカデミー カルフ・アウレリウス児童合唱団 【CD12,13】 交響曲 第9番 ニ長調 2003年録音 交響曲 第10番 ~ 第1楽章アダージョ 1989年録音 たいへん高品質かつ均質性の高い全集だ。どの交響曲も、指揮者のスタイルをしっかりと投影し、解析的で、情緒を抑制しながらも、自然で音楽的な起伏に満たされている。この全集は、特にマーラーの音楽に存在する構造的な秘密を解明し、そこから導かれる「力」の存在に意識的でありたいと思う聴き手には、絶好のものだ。ギーレンは、あきらかにこれらのマーラーの音楽から、「情」ではなく、「知」に働きかけるものに焦点を当てている。明瞭にされる声部、音型の変換、構造上の楽器の役割、そういったものを厳密に定義付け、細部を突き詰めることにより、音像を作り上げ、音楽を構築していく。建築学的な音楽と言っても良い。しかし、音色は決して冷たくはなく、むしろ不思議な暖かさを宿し、的確な起伏により、新鮮な高揚感を得る。鮮烈な興奮を聴き手に与えてくれる。 ごく簡単に、私が当演奏から受けた印象を、各曲ごとにまとめると、以下の様な感じになる。 第1番;一つ一つの楽器の明朗な響きと、そして、濁りのない合奏音によって、瑞々しく描かれている。 第2番;細かいモチーフを繋いだダイナミクスへの動線、さらに休符の意味まで厳密に突き詰めた演奏で、この曲の劇場的な一面と一線を画している。 第3番;アダージョまで徹底したインテンポの表現で、鋭く線的に描かれたシャープなスタイル。シャイーに近いが、ギーレンの方がやや即物的な味わい。 第4番;厳密性がややシニカルな味わいを見せる。天国の音楽と言うより、瞬間瞬間の音色を追求。 第5番;引き締まったテンポで、クールに徹したモダニズムの極致的美演。 第6番;全体の中では古典的なアプローチ。だが新ウィーン楽派に連なる表現主義的な面をよく伝える。 第7番;従来のロマンティックな解釈とは完全に一線を画した演奏。第4楽章の各モチーフの扱いに卓越した冴えを見せる。 第8番;オペラ的なショルティとは対極をなす名演。テクスチャーの織り込みが細かく、驚かされる。終幕近くのソプラノがマジカルな効果を放つ。 第9番;オーケストラの技術を駆使した演奏。この曲の場合その成果が暖かみではなく、不安や恐怖の感情へと誘導されるのを感じる。独奏ヴァイオリンの深いニュアンス。 第10番;第9番に近いがより暗黒的、虚無的なものを意識させる。 以上、当然の事ながら、それぞれの感想がその曲固有のものというわけでなく、全集を通じて重複するものもあるが、私の素直な感想を曲毎に書くと、このようになる。 いずれにしても、素晴らしい全集だと思うので、是非推奨したいが、ギーレンのマーラー・シリーズは、単品でそろえると、併録してある楽曲がなかなか興味深いので、経済的に余裕のある人は、そちらの方がいいかもしれない。 バーンスタイン(Leonard Bernstein 1918-1990)やショルティ(Georg Solti 1912-1997)とは大いに聴き味を異にするマーラーではあるが、彼らの演奏を支持する人であっても、新たな感興を呼び覚ましてくれるギーレンのマーラーだと思うので、広く推薦したい。 |
|
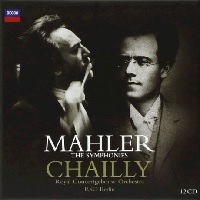 |
交響曲 全集 シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 ベルリン放送交響楽団 プラハ・フィルハーモニー合唱団 レビュー日:2015.2.8 |
| ★★★★★ 現代を代表するマーラーの全集
リッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)は、1988年から2004年まで、コンセルトヘボウ管弦楽団の常任指揮者を務めた。その間、デッカ・レーベルに数々の素晴らしい録音を残したが、その白眉と言えるのが当マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の全集ではないだろうか。当シリーズはシャイーが常任指揮者となった翌年である1989年の第6番の録音から開始され、常任指揮者の任を務めあげた最後の年である2004年の第9番の録音により締めくくられている。だから、この全集は、指揮者とオーケストラの一定期間の成果を、同心円状に集約したものと言うことができるだろう。収録内容と録音年を以下にまとめよう。 1) 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 1995年録音 2) 交響曲 第2番 ハ短調「復活」 2001年録音 ソプラノ: メラニー・ディーナー(Melanie Diener 1967-) メゾ・ソプラノ: ペトラ・ラング(Petra Lang 1962-) プラハ・フィルハーモニー合唱団 3) 交響曲 第3番 ニ短調 2003年録音 メゾ・ソプラノ: ペトラ・ラング(M) プラハ・フィルハーモニー合唱団 オランダ児童合唱団 4) 交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」 1999年録音 ソプラノ: バーバラ・ボニー(Barbara Bonney 1956-) 5) 交響曲 第5番 嬰ハ短調 1997年録音 6) 交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」 1989年録音 7) 交響曲 第7番 ホ短調「夜の歌」 1994年録音 8) 交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」 2000年録音 ソプラノ: ジェーン・イーグレン(Jane Eaglen 1960-)、アン・シュヴァネヴィルムス(Anne Schwanewilms 1967-)、ルート・ツィーザク(Ruth Ziesak 1963-) アルト: サラ・フルゴーニ(Sara Fulgoni 1964-)、アンナ・ラーソン(Anna Laarson 1966-) テノール: ベン・ヘプナー(Ben Heppner 1956-) バリトン: ペーター・マッテイ(Peter Mattei 1965-) バス: ヤン=ヘンドリク・ローテリング(Jan-Hendrik Rootering 1950-) プラハ・フィルハーモニー合唱団 オランダ放送合唱団 聖バーヴォ教会少年合唱団 9) 交響曲 第9番 ニ長調 2004年録音 10) 交響曲 第10番(クック版) 1986年録音 なお、交響曲第10番のみ、シャイーがコンセルトヘボウ管弦楽団に就任する前に、ベルリン放送交響楽団と録音したものとなる。 私は、この録音が一つの必然から生まれた名盤だった、とも思う。と言うのは、コンセルトヘボウ管弦楽団は、マーラー自身がしばしば指揮台に立ったオーケストラである。また、1895年に24歳の若さで、このオーケストラの首席指揮者となったメンゲルベルク(Willem Mengelberg 1871-1951)は、徹底した訓練を施し、世界に最たる技術と音響を誇るオーケストラに仕立て上げ、つねにその時点での最高水準のマーラーを演奏したと言われる。また、シャイーの前任であったハイティンク(Bernard Haitink 1929-)も、1962年から71年にかけて、マーラーの全曲録音を行っている。 そのような背景から、マーラーの交響曲の表現に練達したオーケストラに、現代的で卓越した感性を持ち、知的で洗練されたスタイルを究めたシャイーという指揮者が出会い、マーラーの交響曲を、これまた世界最高水準であるデッカの録音技術によって、全曲収録したのである。だから、その全集が、現代の音楽芸術を代表するといってもよい素晴らしいものになったとして、どのような不思議があるだろう。考えれば考えるほど、それは当然の帰結であったに相違ない。 ことに、第3番は、この巨大なオーケストラに織り込まれた様々な要素を鮮やかに関連付けし、音楽的な転結を施した素晴らしい録音だ。今後、この録音を上回るものがあらわれるかどうか、と思ってしまう。 第7番は、前年のギーレン(Michael Gielen 1927-)盤とともに、この曲が現代音楽への橋渡しをする精緻なプロトタイプを集合させたものであることを示す最初のものの一つと言って良い。新ウィーン楽派的な微細な響きの連続が見事。 第4番は、マーラーが施した詳細な強弱記号を克明なコントラストで再現。第1番、第5番、第6番では、いずれもオーケストラの機能美で、焦点の解像度を上げることで、音世界の広がりを表現して見せた。 他の曲もいずれも詳細に織り込まれた音響が見事な造形美を作り出していると言って良い。また、録音の鮮明さは、各音の輪郭をくっきりときざみ、表現者の周到な試みをことごとく拾うことに成功している。静寂が本当の音楽的静寂として生きているし、迫力も迫真のリアリティに満ちている。当代最高と言っても良いマーラーの全集だと思う。 ところで、シャイーは「大地の歌」を録音しておらず、本全集にも当然のことながら含まれていない。これは、いずれ登場するのを待ちたい。 |
|
 |
交響曲 全集 交響曲 第10番~アダージョ 大地の歌 さすらう若人の歌 亡き子を偲ぶ歌 「若き日の歌」より6曲(自我に起る感情、春の朝、もう会うことはない、シュトラスブルクの砦で、夏の歌い手交代、いたずらな子をしつけるために) シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 合唱団 シュターツカペレ・ドレスデン S: プロウライト グルベローヴァ ステューダー ブラーシ ジョー MS: ファスベンダー マイヤー 永井和子 フェルミリオン A: シュヴァルツ T: ルイス Br: アレン ターフェル Bs: ゾーティン レビュー日:2016.12.21 |
| ★★★★★ 初出時は高価だったシノーポリのマーラーが、廉価でまとまりました。
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)が1985年から96年にかけて録音したマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲全集が廉価box-setとなったもの。12枚組のCDには、交響曲と併せて収録されていた歌曲なども含まれており、その12枚の内容は以下の通りとなる。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ニ長調「巨人」(1989年録音) 2) 交響曲 第2番 ハ短調「復活」;第1楽章(1985年録音) 【CD2】 交響曲 第2番 ハ短調「復活」;第2~5楽章(1985年録音) ソプラノ: ロザリンド・プロウライト(Rosalind Plowright 1949-) メゾ・ソプラノ: ブリギッテ・ファスベンダー(Brigitte Fassbaender 1939-) フィルハーモニア合唱団 【CD3】 交響曲 第3番 ニ短調;第1~5楽章(1994年録音) 【CD4】 1) 交響曲第3番 ニ短調;第6楽章(1994年録音) アルト: ハンナ・シュヴァルツ(Hanna Schwarz 1943-) ニュー・ロンドン児童合唱団 フィルハーモニア女声合唱団 2) 交響曲 第7番 ホ短調「夜の歌」;第1~3楽章(1992年録音) 【CD5】 1) 交響 曲第7番 ホ短調「夜の歌」;第4、5楽章(1992年録音) 2) 交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」:第1部(1990年録音) 【CD6】 1) 交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」:第2部(1990年録音) ソプラノ: シェリル・ステューダー(Cheryl Studer 1955-) ソプラノ: アンジェラ・マリア・ブラーシ(Angela Maria Blasi 1956-) ソプラノ: スミ・ジョー(Sumi Jo 1962-) メゾ・ソプラノ: ヴァルトラウト・マイヤー(Waltraud Meier 1956-) メゾ・ソプラノ: 永井和子(1955-) テノール: キース・ルイス(Keith Lewis) バリトン: トーマス・アレン(Thomas Allen 1944-) バス: ハンス・ゾーティン(Hans Sotin 1939-) サウスエンド少年合唱団 フィルハーモニア合唱団 2) 「さすらう若人の歌」(1985年録音) 第1曲 恋人の婚礼の時(Wenn mein Schatz Hochzeit macht) 第2曲 朝の野を歩けば(Ging heut' morgens ubers Feld) 第3曲 僕の胸の中には燃える剣が(Ich hab' ein gluhend Messer) 第4曲 恋人の青い目(Die zwei blauen Augen) メゾ・ソプラノ: ブリギッテ・ファスベンダー 【CD7】 1) 交響曲「大地の歌」(1996年録音) メゾ・ソプラノ:イリス・フェルミリオン(Iris Vermillion 1960- メゾ・ソプラノ) テノール:キース・ルイス(テノール) 2) 交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」;第1楽章(1991年録音) 【CD8】 1) 交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」;第2~4楽章(1991年録音) ソプラノ: エディタ・グルベローヴァ(Edita Gruberova 1946-) 2) 亡き子を偲ぶ歌(1992年録音) 第1曲 いま太陽が燦々と昇ろうとしている(Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n) 第2曲 いま私はわかった。なぜそんな暗い炎を(Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen) 第3曲 おまえたちのおかあさんが戸口から歩み入るとき(Wenn dein Mutterlein) 第4曲 よく私は子供らはただ散歩に出かけただけだと考える(Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen) 第5曲 こんな嵐のような天候の中で(In diesem Wetter!) バリトン: ブリン・ターフェル(Bryn Terfel 1965-) 【CD9】 交響曲 第5番 嬰ハ短調(1985年録音) 【CD10】 1) 若き日の歌~バーンズ(Harold Byrns 1903-1977)によるオーケストラ版(1985年録音) 第3集 第5曲 うぬぼれ(Selbstgefuhl) 第1集 第1曲 春の朝 (Fruhlingsmorgen) 第3集 第4曲 もう会えない! (Nicht wiedersehen!) 第3集 第1曲 シュトラスブルクの砦に(Zu Strassburg auf der Schanz') 第3集 第2曲 夏に小鳥はかわり(Ablosung im Sommer) 第2集 第1曲 いたずらっ子をしつけるために(Um schlimme Kinder artig zu machen) バリトン: ベルント・ヴァイクル(Bernd Weikl 1942-) 2) 交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」;第1~3楽章(1986年録音) 【CD11】 1) 交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」;第4楽章(1986年録音) 2) 交響曲 第9番 ニ長調;第1,2楽章(1993年録音) 【CD12】 1) 交響曲 第9番 ニ長調;第3,4楽章(1993年録音) 2) 交響曲 第10番 嬰ヘ短調;アダージョ(1986年録音) オーケストラは、「大地の歌」のみがドレスデン国立管弦楽団で、他はすべてフィルハーモニア管弦楽団。12枚に収めるため、楽曲の途中でCDを入れ替える手間が多いが、廉価を最優先したサービスと捉えるべきだろう。 さて、吉田秀和(1913-2012)氏は、シノーポリのマーラーをとても評価していて、「マーラーも交響曲を一つの世界と心得、すべてが鳴動する音楽を書きたがった。だが現実にそういう演奏に出会うことはめったにない。シノーポリには少なくともその志向があり、そこからあの荒涼と明るさ、すごさとやさしさの放射が発生してくる。」と記述していた。 私があらためてこの全集を聞いた時、この吉田氏のコメントに、全面的に同意するという感想にはならないのだけれど、もっともそのコメントに合致する傾向を感じたのが第1番である。シノーポリはテンポを大きく変動させ、全体を揺らすようにして、一つの音楽世界を描き出していると感じた。逆に、最後の録音となった「大地の歌」では、淡い色彩でシャープに描かれた音世界が、墨絵のような鮮やかな心象に直結し清々しかった。また一方で第8交響曲では、他に類のないほどの熱血性に溢れた演奏であり、血沸き肉躍ると形容したいほどの燦然たる讃歌となっている。 かように、私の印象では、シノーポリのスタイルは、楽曲ごとに若干以上の「差」を感じさせるものとなっている。しかし、いずれにしても、上述の3曲は、どれも素晴らしい演奏と感じたが、他に精妙に美しく仕上げられた第5番、第8番の表現に通じる熱い表現を聴ける第3番、第7番、第9番など、私はいずれも楽しませていただいた。 シノーポリは、独自色豊かなテンポ設定を施すことが多い。第6番(特に終楽章)、第10番では、異様と言いたいほどのスロー・テンポを採用している。私の感性では、これらについては、優れた音楽表現とは感ぜられないところがあり、聴いていて、気持ちの逸れるところがあった。また、第4番の第1楽章ではハイテンポで驚かされたが、こちらも私にはやや座りの悪さが残る。 しかし、全集としてみたときに、演奏・録音の品質は高い。オーケストラの音色は全般に混濁なく輝かしいサウンドで貫かれていて、逆に泥味のないクリアさがやや健康的なマーラー像に傾斜しているが、そのことを受け入れれば、十分に楽しめる内容となっている。 また、歌曲もいずれも品質の高いものだと思うが、中でもバーンズの編曲による「若き日の歌」は、他の録音が少ないこともあり貴重だ。「もう会えない!」は、多くのマーラー・ファンにとって、宝となりうるものだと思う。 |
|
 |
交響曲 第1番「巨人」 ホーネック指揮 ピッツバーグ交響楽団 レビュー日:2009.10.30 |
| ★★★★☆ 新しい価値軸のマーラー・・・なのか?
ホーネックとピッツバーグ交響楽団という私たち日本のファンには耳新しい顔合わせによるマーラーの第1交響曲の録音がたいそう評判なので聴いてみた。2008年のライヴ録音である。 ちなみに、私はこのディスクを聴く前に既に相当な情報に晒されてしまっていて、この演奏に尋常ではないものを若干期待してしまった。なので、最初聴いたときは、「意外に普通な演奏だな」というのが正直な感想となった。 しかし、確かに最近の演奏にはない「表現手法」があると思い、それについて書いてみる。マーラーの音楽は自然や苦悩、あるいは生命と死といったテーゼがよく反映されていると言われるし、実際そうだと思うが、音楽演奏の上で、これらの抽象的な概念をいかように助長するのかは難しいところである。例えば「この演奏は、諦観がよく出ている」などと言うとき、その諦観の印象が何に起因していて、それがどのような感受性に照らされたものなのか、私は気になる性分である。もちろん、自分が感じたエモーショナルな動きをそのまま伝えたに過ぎないこともあり、私もそういうことを言ったりする。けれども突き詰めて問われると、表現しがたい部分に行き当たってしまう。「この低音の不気味さが・・・」とか言ったりするけど、それが正解かというとそれも違うというような。 話がずれたけれど、ホーネックの「巨人交響曲」は、マーラーが書いた音符のうち、純粋に旋律とこれを保持するための支えの音以外に存在する、言ってみれば「効果音」に近いものを、前面に押し出し気味にした演奏と言える。これもよく言われるが、分かり易く書くと「鳥の声」のような比較的描写性の高い部分。 最近のマーラー演奏の主流は、たぶん音楽としての合目的性により音の主従を階層化させ、洗練させていくものだと思う。なので、それに慣れた状態で聴くと、確かにホーネックは新鮮だ。けれども、例えばシャイーが第4交響曲で、あえて音の主従の呪縛を放って、音楽の彩りに新しい価値を獲得したような、そこまでホーネックの演奏がたどり着いているというところまでは感じなかった。(それこそ私の感受性の問題かもしれないが) もちろん演奏は面白いし、いい演奏だと思う。熱がある。オケもウマい。だがこの音楽が自分への訴えかけとしてズシンと来たか?と言えば、ちょっと違うかな、と感じられた。 |
|
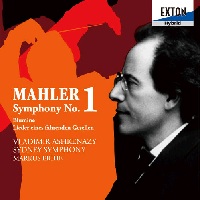 |
交響曲 第1番「巨人」(花の章付) さすらう若人の歌 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 Br: アイケ レビュー日:2010.10.28 |
| ★★★★★ びっくり!マーラーの「巨人交響曲」に現れた快録音
マーラーの「巨人交響曲」に目も覚めるような快録音が登場した。おそらく、このCDの制作に関わった人たちにとっても会心の一枚なのではないだろうか? このマーラー最初のシンフォニーは、マーラーが、はじめてその内面を交響曲という形で表したものであるが、マーラーの場合、その「内面性」がすこぶる強く作品に投影されていたとされる。一般的な解釈では、「死生観」「愛憎」「葛藤」「自然への畏怖」などが述べられることが多いし、じっさいに曲を聴くと情念的な表現が多く、そのような「解釈」と合わせて聴き手に説得力をもたらしてきた。なので、多くの芸術家がマーラーの作品を表現する場合、自己の中にある感情解釈を経て、強い主張を音楽に宿そうとしてきた。もちろんそれはおそらく正しいことで、その結果として、古今、多くの「名演」が生まれ記録されてきた。 その一方で、最近になって、もっと即物的にこの音楽を解釈しようという考えも目立ってきた。「私の感じ方で」という前置きが必要だけど、インバルやシャイーはそういったクールなマーラーを一つ突き詰めた感がある。 それで、アシュケナージのこの新しい録音がどこにあるかと言うと、後者に近い。いや、後者に近いのだけど後者ではない。むしろ両者の中庸を見事に射抜いた演奏、に私には聴こえる。おそらく、アシュケナージという音楽家が、元来ストレートな音楽スタンスを持っていたことに加え、そのアーティスト人生において、マーラーという作曲家を振るのにちょうどいい、ビタリのタイミングに行われた録音だったのではないだろうか。 全楽章において管弦楽の瑞々しい響きが滔々と流れる。テンポは弛緩なく淀みなく自然な心地よさ。そしてその自然なスイングの力点が見事な振幅のエネルギーをもって、ピンポイントにクリティカル・ショットを繰り出す。その心地よさ。終楽章はドラマティックな盛り上がりに不足なく、しかも熱中し過ぎない視点がつねにキープされている。フィナーレは壮大に盛り上がるが、それを支えるのは適度なエネルギーの蓄積と放流を繰り返す小さなタメだ。これがまた良い。マーラーの音楽が、真っ直ぐに聴き手の体の中に流れ込むような錯覚をおぼえる。 また、このシニフォニーと切っても切れない縁のある二作品が収められているのもこのアルバムの優れた点。バリトン独唱のマルクス・アイケも気持ちよい透明な声であり、いよいよ快録音快演奏の完成度を高めている。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第1番「巨人」 ベルク(ファーベイ編オーケストラ版) ピアノ・ソナタ シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2015.2.8 |
| ★★★★★ 1995年録音であるが、いまなお鮮明な魅力を放っています
リッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、コンセルトヘボウ管弦楽団による1995年録音のディスク。ベルク(Alban Berg 1885-1935)の「ピアノ・ソナタ 作品1」をオランダの作曲家ファーベイ(Theo Verbey 1959-)が管弦楽曲に編曲したものと、マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲 第1番 ニ長調「巨人」 の2曲を収録。 シャイーとコンセルトヘボウ管弦楽団によるマーラーの交響曲全集の一環として製作されたものだが、さまざまな点で画期的な録音となった。 マーラーの音楽は、大雑把に言ってしまうと、長い間、高貴ロマン派特有の情熱と倦怠、純粋と混沌の入り混じったものとして捉えられ、そのやり場のない情熱や絶望を力強く、衝撃的に解釈する演奏が行われてきた。これまたざっくり言ってしまうと、その方法論を究極まで高めた演奏として、バーンスタイン(Leonard Bernstein 1918-1990)の数々の録音は、いまなお多くの人の魂をゆさぶり続けている。 しかし、20世紀末になって、そこにまったく違った視点でアプローチする世代が表れてくる。その代表格と言えるのがシャイーであった。シャイーのマーラーは、徹底した楽曲の構造解析にその基礎を置いている。シャイーの父親は、ヒンデミット(Paul Hindemith 1895-1963)門下の音楽学者であったそうだが、シャイーの指揮ぶりと、ヒンデミットの理論に基づく音楽の体系化及び組織化との間には、相応の因果関係を認めてもいいのではないだろうか。すなわち、シャイーはこの交響曲を構造するモチーフや、保持音の一つ一つを解きほぐし、観念的な呪縛を解いた上で、それら一つ一つの距離を綿密に設計し直すことで、結果として音楽を構成することを目指している。 私の書き方は、観念的過ぎるだろうか?つまり、シャイーのマーラーは主情的な方法ではなく、主知的な方法で演奏が行われたものであり、そのために熱や混沌といった不確定要素が退けられているのだ。聴こえてくる音は、あくまで楽器が持っている原色を純粋に積み上げたものであって、オーケストラの奏者は、個の情を入れ込ませることなく、ひたすら司令塔の指示に従って、音を提供する。 他方、バーンスタインの演奏を聴くと、その熱血性、多少の乱れがあっても総体として強く前進し、激しいアゴーギグを交え、「とにかく全力で付いて来い」という一意的な求心力が伝わってくる。それが彼の魅力なのだけれど、マーラーの音楽の要素の一面があまりにも強調されている、という風にも私は受け取れる。 シャイーの演奏は、例えばこの第1交響曲冒頭の静謐から音楽が生まれていく過程における音型の役割が、その後の新ウィーン楽派につらなる細分的なものが連なっているものであることに気付かせてくれる。マーラーは、これほどまでに理知的に突き詰めた音楽を書いていたのだ、と知る。それが、新鮮な感動となる。新しい魅力に満ちている。当第1交響曲であれば、特に第4楽章の瑞々しい抒情詩的な情感と鮮明な音像によって、聴き手の魂をリフレッシュする。 もちろん、この録音からすでに20年が経過しており、今となっては、同様のアプローチも多くある。しかし、シャイーのこの録音のクオリティの高さは、今なお圧倒的と言っていいものだと思う。 併録されたベルクのピアノ・ソナタの管弦楽版も面白い。こちらは当盤が初録音だったと記憶しているが、新ウィーン楽派の傑作を管弦楽曲化して組み合わせるというのは、いかにもマーラーに相応しいし、慎重に練り上げられた音色は、原曲の魅力を損なうことなくベルクらしいテイストを出すことに成功している。 |
|
 |
交響曲 第1番「巨人」 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 レビュー日:2016.12.12 |
| ★★★★★ オーケストラを用いて自然界と若き人間の「ゆらぎ」を描いた演奏
マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)と同時代を生きたオーストリアのヴィオラ奏者ナターリエ・バウアー=レヒナー(Natalie Bauer-Lechner 1858-1921)は、マーラーとの親交を詳細に綴っており、現在その回想本も入手できるようになっている。中でバウアー=レヒナーがマーラーの第1交響曲の第1楽章と第3楽章の素晴らしい効果について、その感激を述べると、マーラーは以下のように答える。「それは僕の楽器の扱いのせいなんだ。第1楽章では響きは光り輝く音の海の彼方に消えてゆく。太陽そのもが輝きのうしろで見えなくなるように。第3楽章では楽器は違った装いをつけ、変な姿でさまよい歩く。黒い影が通りすぎるみたいに鈍く重苦しく響かなければならない。カノンの旋律はいつもはっきり聞こえるように、僕はさんざん考えた。もし小さな持続音を出したいと思ったら、それを簡単に出せる楽器を使わず、やっとできるような楽器にひかせるのだ。コントラバスとファゴットは最高音域で喉をしぼり、フリュートは低音域で喘ぐというように・・」 マーラーが第1交響曲で、自然、そして若い人間の苦悩を描いたとされる。この交響曲は、冒頭で、弦楽器陣がイ音をフラジオレット(弦をごく軽く指で押さえて鳴らす奏法)で響かせる持続音から開始されるが、これは、もともとはフラジオレットの指定がなかったらしい。マーラーは「ブダペストで、全音域でイ音を出すのをきいた時、それは僕が望んでいた微光にきらめくような大気を現すには物質的すぎると感じた。それで僕は上はヴァイオリンから下はコントラバスまで全弦楽器にフラジオレットで弾かせることを思いついたんだ・・・」と述べたと伝えられている。印象的な冒頭のフラジオレットは、大気の背景的な均一性、そしてその背景が持っている揺らぎを、同時に表現する方法として案出されたのだ。 シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)がフィルハーモニア管弦楽団と録音した一連のマーラーのうち、この交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」は、1989年に第4弾として録音された。私には、これがシノーポリのマーラーとしては、第1弾の第5交響曲に続く成功だったと感じられる。 このシノーポリの第1交響曲の演奏からは、全体的な揺らぎの効果が良く感じられる。冒頭の例の「大気」感も雰囲気があるし、その後もオーケストラをドライブして、全体的な「揺らぎ」の演出がある。この「揺らぎ]」は、音量の強弱とともに、テンポの流動感によっても引き起こされる。音色の一つ一つが吟味されていることはもちろんだが、特に全体が速足になるような箇所での力強い畳み掛けにおいて、これに付随して起こる楽器の強弱のコントラストの妙が巧みだ。特に音量が多くなる個所で、その作用は増幅し、なかなか心地よいエネルギッシュな放散に導いてくれる。特有のタメを随所で効かすことになるので、聴く人によってはより円滑な流れを求める人もいるかもしれないが、シノーポリの意図は徹底しているし、最終的に音楽としてよく消化できているという印象を私は持つ。そういった意味で、前述の成功を感じるのである。 マーラーの第1交響曲の浪漫的、情動的な部分をよく咀嚼し、考察した演奏と感じられ、シノーポリのマーラーの中でも特に成功を感じさせる1枚となっている。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第1番「巨人」 ヴェーベルン 夏風のなかで ロト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 レビュー日:2019.12.3 |
| ★★★★★ マーラー自身の言葉を想起させてくれる録音
フランスの指揮者、フランソワ=グザヴィエ・ロト(Francois-Xavier Roth 1971-)と南西ドイツ放送交響楽団による以下の2つの楽曲を収録したアルバム。 1) マーラー(Gustav Mahler 1860-1911) 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 2) ヴェーベルン(Anton Webern 1883-1945) 大管弦楽のための牧歌「夏風のなかで」 2011年の録音。 魅力的なアルバムだ。マーラーのシンフォニー、それとヴェーベルン作品の中で後期ロマン派の作風時代の代表曲である「夏風のなかで」という組み合わせ。以前、ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)にもマーラーの第6番とヴェーベルンの「夏風のなかで」のカップリングというアルバムがあったが、この清々しい青々とした管弦楽曲は、マーラーの第1との組み合わせが、より相応しいように感じる。 さて、当盤の演奏だが、両曲とも新鮮なさわやか味に満ちた演奏。ロマン派的濃厚さより、解析的な響きが支配的で、純器楽作品としての真摯に扱ったようなアプローチだ。 マーラーでは特に第1楽章が素晴らしい。ことに緊張感を高めながら、音楽がその色合いを変える様が美しい。第1楽章の8分台後半あたりから、素晴らしい雰囲気だ。この場所で、私はマーラーの以下の言葉を思い出した。 「ここで僕の考えを表現するのはとてもむずかしかった。どこまでも同じように青く拡がる大空を考えてごらん。変化や対照のいろいろなニュアンスを出すよりずっとむずかしいだろう。これが全体の土台。そこに時々かげりが生まれ、薄気味の悪い、ぞっとする気分になったりする。でも天そのものは曇るわけでなく、永遠の青で輝きつづける。ただ、それは僕達にとってだけ突然不気味なものに変わる。晴れた日にあちこち日差しのもれる森にいると、急にぞっとするように・・・」 これは、マーラーが自身の第4交響曲の第4楽章について語った言葉だけど、私は、この演奏を聴いていて、この第1楽章の中間部で突然ゾワッとするような不思議な感触を味わい、すぐにマーラーのこの言葉を思い出したのだ。ロトの演奏は、緊迫感が高く、かつ管弦楽が緊密にコントロールされているため、ちょっとした変化が、聴き手の心象に大きな影響をもたらす。その象徴的な個所が第1楽章にあると思う。 第2楽章は軽く、吹き抜ける薫風を思わせる鮮やかさ。第3楽章の中間部も同様の魅力がある。終楽章は緻密に音を積み上げて巨大な構造を作り上げた芸の細かさがある。全般にテンポは一般的だが、音響は新鮮な味わいを感じさせるマーラーだ。 ヴェーベルンも素晴らしい内容。この楽曲がもつ若々しい魅力に満ちていて、喜びに満たされる演奏だ。マーラーの第1交響曲とともに、若き芸術家が、これから歩むべき道のりを見つめるような「希望」を思わせる情感がある。 |
|
 |
交響曲 第1番「巨人」 第2番「復活」 ケーゲル指揮 ライプツィヒ放送交響楽団 合唱団 S: プロイル A: ブルマイスター レビュー日:2021.7.13 |
| ★★★★★ ケーゲルという指揮者の存在感を伝えるアルバム
ヘルベルト・ケーゲル(Herbert Kegel 1920-1990)指揮、ライプツィヒ放送交響楽団の演奏で、70年代にライプツィヒでライヴ収録されたマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の2つの交響曲が収録されている。CD2枚組で、【CD1】に第1交響曲と第2交響曲の第1楽章が収録され、【CD2】に第2交響曲の第2楽章以降が収録されている。 指揮者の情念が如実に伝わる演奏。現在の演奏の多くは、おおむね、基本的な音楽の構成をまず尊び、そこにニュアンスを加えて仕上げていくような印象をもたらすもの。この演奏のように、指揮者の「俺はこう表現するんだ」という意欲が、ぐっと前面に出てくるスタイルは珍しくなった。また、そのような演奏を試みても、成功させるような力量と芸術性の双方を備えた、いわゆる巨匠的芸風の指揮者が、少なくなったとも感じる。その背景は様々にあるが、私個人的には、世の中にあふれる情報が、平均化や均質化に働く性質を持っているのではないか、と感じている。それがいいことなのか、悪い事なのかは、私にはわからないが。 それで、このケーゲルの演奏は、そういった意味で、固有の魅力を感じさせる。特徴的なのは、随所でみられる音の「ねばり」で、ぐっと音を引くような、瞬発的な原則があり、その瞬間に聴き手の側が、身を前に乗り出すような引力が生じる。管弦楽の響きも、情熱的であるが、オーケストラはパレットとしては澄んだ響きをもっていて、結果として、情念をもった表現の細部を、鮮やかな陰影の輪郭が覆っていて、結果として、ネバリがあるのにスキッとした響きが導かれる。これがケーゲルの力量なのだろう。凄い指揮者だ。 交響曲第1番では偶数楽章にこの演奏の特徴が良く表れている。第2楽章は前述の「ねばり」が冒頭から全面展開。特徴的なリズム感の中で、旋律が歌われる。第4楽章は、踏み込みの激しさが凄い。確かに現代の一流オーケストラの演奏と比較すると、ライヴということもあって、粗さも目立つのだが、それらがすべて迫力に還元されるような圧巻の力強さが満ちている。交響曲第2番は、より没入感の強い演奏で、楽曲が進むほどその傾向が強くなる。特に金管群は、つねに全力で表現することを求められ、多少のゆらぎもなんのそのといった塩梅。交響曲第1番のようにわかりやすい「ねばり」はないかもしれないが、ここぞという時のタメや踏み込みはやはり強烈だ。合唱はきわめて壮麗。この曲の劇的な側面を衒いなく歌い上げ、しかも芸術的な薫りを存分に感じさせるみごとな熱演だ。ケーゲルという指揮者がどういう芸術家だったか、このアルバムは的確に伝えてくれていると思う。 |
|
 |
交響曲 第1番「巨人」(2種) 第2番「復活」 第4番「大いなる喜びへの讃歌」 第5番 第9番 大地の歌 歌曲集「さすらう若人の歌」 歌曲集「若き日の歌」から 「思い出」「別離と忌避」「再び相まみえずに」「私は緑の森を楽しく歩いた」「夏に小鳥はかわり」「ハンスとグレーテ」「春の朝(たくましい想像力)」 ワルター指揮 コロンビア交響楽団 ニューヨーク・フィルハーモニック ウェストミンスター合唱団 S: クンダリ A: フォーレスター MS: ミラー T: ヘフリガー S: ハルバン レビュー日:2012.3.12 |
| ★★★★★ ワルターの香り高きマーラー
往年のドイツの名指揮者ブルーノ・ワルター(Bruno Walter 1876-1962)がCBSレーベルに録音した一連のマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)作品を7枚のCDに収録したBox-set。同じ企画のモーツァルトのところにも書いたけど、LP時代を知るものにとっては、思わず「これってアリなの?」と呟いてしまいそうなほど、価格と中身のバランスが、消費者側に有利なアイテムだ。収録内容をまとめよう。 1) 交響曲第1番「巨人」 コロンビア交響楽団 1961年録音(ステレオ) 2) 交響曲第2番「復活」 ニューヨーク・フィルハーモニック S: クンダリ A: フォーレスター ウェストミンスター合唱団 1957-58年録音(ステレオ) 3) 歌曲集「さすらう若人の歌」 MS: ミラー コロンビア交響楽団 1960年録音(ステレオ) 4) 交響曲第4番「大いなる喜びへの讃歌」 ニューヨーク・フィルハーモニック S: ハルバン 1945年録音(モノラル) 5) 交響曲第9番 コロンビア交響楽団 1961年録音(ステレオ) 6) 交響曲第5番 ニューヨーク・フィルハーモニック 1947年録音(モノラル) 7) 交響曲「大地の歌」 MS: ミラー T: ヘフリガー ニューヨーク・フィルハーモニック 1960年録音(ステレオ) 8) 交響曲第1番「巨人」 ニューヨーク・フィルハーモニック 1954年録音(モノラル) 9) 歌曲集「若き日の歌」から 「思い出」「別離と忌避」「再び相まみえずに」「私は緑の森を楽しく歩いた」「夏に小鳥はかわり」「ハンスとグレーテ」「春の朝(たくましい想像力)」 S: ハルバン ニューヨーク・フィルハーモニック 1947年録音(モノラル) ワルターはマーラーの弟子であり親友でもあった。景勝地シュタインバッハで夏の休暇を楽しむマーラーを訪ねたワルターが美しい景色に見とれていると、マーラーが「それ以上眺める必要はないよ。全部私の今度の交響曲にしてしまったからね。」と言ったのは有名だ。マーラーの死後に彼の交響曲「大地の歌」と第9番を初演したのがワルターである。 マーラーはユダヤからカトリックに改宗したが、ワルターは終生ユダヤ人だった。そのため、第二次大戦で彼は拠点をドイツからオーストリアへ、そしてアメリカへと移さざるを得なくなる。そうして、アメリカで数々のマーラーの名録音が生まれた。それがこのアルバムだ。 もう一つ逸話を。当時CBSはマーラーの第1交響曲を録音するにあたり、指揮者にバーンスタイン(Leonard Bernstein 1918-1990)を起用することも考えていて、当人も乗り気だった。しかし、ワルターとのレコーディングが先に終了したことから、シェアの問題もあり、バーンスタインに計画の中止を申し出た。彼は承服しなかった。そこで、CBSのスタッフは実際に録音されたワルターの演奏をバーンスタインに聴いてもらった。聴き終わったバーンスタインは「素晴らしい。これは彼の交響曲だ。」と延べ、自ら録音の中止を快諾したそうだ。ワルターの音楽の価値、バーンスタインの大きな人柄など様々なことを示すエピソードだ。 ワルターの演奏は、典雅さと苛烈さがあり、その表出度のバランスが曲や演奏によって異なるのだけれども、どれも高い香りを感じさせるものだと思う。第1番、第2番は今なお名演の誉れが高いもので、私も初めて第2交響曲を聴いたのがこのワルターの劇的な演奏だった。懐かしいし、現代でも通じるシャープな迫力に満ちている。また「大地の歌」は1952年のウィーンフィルとの名盤が名高いが、こちらも味わいのある演奏だと思う。いずれにしても、半世紀を過ぎた今でも、多くの人に愛聴される歴史的録音だろう。 |
|
 |
交響曲 第2番「復活」 P.ヤルヴィ指揮 フランクフルト放送交響楽団 オルフェオン・ドノスティアラ S: デセイ MS: クート レビュー日:2010.12.16 |
| ★★★★★ 「復活交響曲」の醍醐味を堪能できる名盤
ドイツの主力オーケストラを中心に活躍しているパーヴォ・ヤルヴィがマーラー生誕150周年にあたる2010年にリリースした意欲的な録音。(録音は2009年) 私はマーラーのこの作品を昔からよく聴いてきた。たぶん、マーラーの交響曲の中で最初に聴くようになったのがこの曲だったと思う。第1楽章の導入はメチャクチャカッコイイし、最後の壮麗な合唱もとてもわかりやすい。いかにも明瞭な頂点を築き上げていて、音楽のもつ「抽象的な性質」がすごく直裁なイメージに帰結している(それを一言で言うと「わかりやすい」と言うのだけれど)。しかし、私の場合、ある時期からマーラーの交響曲でも第6番以降の作品が好きになり、第5番以前のものはあまり聴かなくなった。第6番以降の作品の方が、抽象性が高く思われ、その分、指揮者やオーケストラによる違いを楽しめる幅があるように思えたのだろう。 その傾向は今でもそうなのだけれど、でも最近やっぱり初期の交響曲もいいよな、と思い、再びいろいろ聴くようになった。面白いディスク、話題のディスクが多く出てきたという背景もあるだろう。このヤルヴィの第2番もなかなか清冽な印象を残してくれる。 第1楽章の冒頭から音の立ち上がりが克明で、シャープに陰影を描き出す。非常に心地よいテンポで、劇的な弦によるフラグメント一つ一つが適切なベクトルを内包していて、曲想を機敏にかつ的確に描き出していく。オーケストラの音色も素晴らしい。鮮明でありながらその発色によって音楽を過美にすることなく、滋味を感じさせながら外交的な力強さを思い切り開放してくる。やはりこの曲はこれくらい思い切りやってくれたほうがスキッとして気持ちいい。第2楽章の温もりを感じさせる弦のグラデーションも見事で、適度な水分を含むような木目調の肌触りを思わせる。合唱導入直前の幻想的なオーケストラの呼応も雄大でファンタスティックな味わいに満ちており、「マーラーの第2交響曲を聴いている」という実感に満ちることができる。終楽章も見通しの良い指揮ぶりでありながらここぞと言うときに鋭角的な集中線によって描かれる音楽のスケールはきわめて大きい。「復活交響曲」の「らしさ」を満喫させてくれる名演・名録音だと思う。 |
|
 |
交響曲 第2番「復活」 ブーレーズ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン楽友協会合唱団 S: シェーファー M: ヤング レビュー日:2010.11.1 |
| ★★★★★ 通俗性を包み込むような直線的な響きが印象的
ブーレーズは1994年にウィーンフィルとマーラーの交響曲第6番を録音して以降、続々とマーラーの交響曲を録音した(再録音になる曲も含む)。この交響曲第2番は2005年の録音で、ブーレーズらしい確かな設計図に沿った演奏を披露している。 この交響曲第2番という作品は、熱烈な愛好家がいる一方で、やや距離を置きたがる傾向の人もいる。・・とこう書くと、どんな曲でもそうじゃないか、と思うのだけれど、このシンフォニーはそれがより強く出るように思う。確か、この曲のみを振り続けている指揮者もいた。一方で、巨匠と言われる指揮者の中に、この曲に手を出さなかった人も多くいた。 思うに、この音楽がもつ劇的な要素があまりにも多弁であるため、その多くを引き出そうとした場合、どうしても通俗的な性質が、ガバッと外に出てくるようなところがあって、それで時折敬遠されるのではないだろうか?音楽が多弁だなんて、それこそ概念と認識の問題だとは思うけれど、状況から察してそのように思える。実はこれと同じ性向の曲として、チャイコフスキーの「マンフレッド交響曲」があると思うのだけれど、いかがだろうか? いろいろ余談を書いてしまったけれど、ブーレーズの解釈は、早いテンポで曲の輪郭を引き締めながらも、劇的効果を踏まえて適度に浪漫的な表現に踏み込んだもので、思いのほかオーソドックスな感じがする。ブーレーズであればもっと解析的と言うか、鋭利な冷たい視点から照らすような演奏になるのかと思ったけれど、なかなか熱血な面があり、曲の中に入って熱をきちんと外に放散させている。やはり、この曲の場合、どのような指揮者がやっても、大きく違った解釈にはならないのだろう。 しかし、中にあってブーレーズらしいのは、声楽が入ってくる部分での、オーケストラと声楽の平行な扱いにある。ミシェル・デ・ヤングの独唱による「原光」は厳かで、まるでオーケストラの楽器の一つのように聴こえる。その平行に配置された音が、特有の空間を直線的に満たしていき、なんとも美しい。終楽章の合唱もそう。決して「壮大過ぎない」端麗な歌唱であるが、それゆえに神々しさがあり、光のようにまっすぐに音が差し込む。この曲が持っている「仰々しさ」や「通俗性」を包み込むようで、ここばかりは思わず「さすがブーレーズだなー」と感心してしまった。 そのようなわけで、自分にとって印象深い「復活」の一枚。ちなみに収録時間80分越で1枚にまとまっています。それも良し。 |
|
 |
交響曲 第2番「復活」 さすらう若人の歌 亡き子を偲ぶ歌 「若き日の歌」より6曲 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 合唱団 S: プロウライト Ms: ファスベンダー Br: ヴァイクル レビュー日:2016.12.6 |
| ★★★★★ バーンズがオーケストレーションした初期の歌曲が、特に聴きものです。
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)指揮、フィルハーモニア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)シリーズで、1985年の録音。同年に先行して録音された第5交響曲に続く第2弾であった。CD2枚からなる当アルバムは、交響曲第2番を中心に、歌曲も収録された。その内容は以下の通り。 若き日の歌(Lieder und Gesange)~バーンズ(Harold Byrns 1903-1977)によるオーケストラ版 1) 第3集 第5曲 うぬぼれ(Selbstgefuhl) 2) 第1集 第1曲 春の朝 (Fruhlingsmorgen) 3) 第3集 第4曲 もう会えない! (Nicht wiedersehen!) 4) 第3集 第1曲 シュトラスブルクの砦に(Zu Strassburg auf der Schanz') 5) 第3集 第2曲 夏に小鳥はかわり(Ablosung im Sommer) 6) 第2集 第1曲 いたずらっ子をしつけるために(Um schlimme Kinder artig zu machen) バリトン: ベルント・ヴァイクル(Bernd Weikl 1942-) さすらう若人の歌(Lieder eines fahrenden Gesellen) 7) 第1曲 恋人の婚礼の時(Wenn mein Schatz Hochzeit macht) 8) 第2曲 朝の野を歩けば(Ging heut' morgens ubers Feld) 9) 第3曲 僕の胸の中には燃える剣が(Ich hab' ein gluhend Messer) 10) 第4曲 恋人の青い目(Die zwei blauen Augen) メゾ・ソプラノ: ブリギッテ・ファスベンダー 11) 交響曲 第2番 ハ短調「復活」 ソプラノ: ロザリンド・プロウライト(Rosalind Plowright 1949-) メゾ・ソプラノ: ブリギッテ・ファスベンダー(Brigitte Fassbaender 1939-) フィルハーモニア合唱団 第2交響曲は、作曲者が、「第1楽章の後に少なくとも5分間以上の休みを置くこと」と指示している。それで、CD2枚組の場合、1楽章までと2楽章以降を別のCDに収録する形をとることがあるのだが、このアルバムは第2楽章までと第3楽章以降で収録CDを分割しており、CD構成の点で変わっている。せっかく歌曲を頭に持ってきているのだから、1楽章と2楽章の間で分割した方がいいのでは。。 それはさておいて、内容。まず冒頭に「若き日の歌」がある。これは、マーラー20歳のころに書いた全3集14曲からなる本来ピアノ伴奏による歌曲である。しかし、その後、マーラーは、歌曲にオーケストラの伴奏を与えることで、その世界観を大きく変えた。そのため、この初期の歌曲についても、後年、別の作曲家たちが、伴奏のオーケストラ化を試みている。例えばベリオ(Luciano Berio 1925-2003)は14曲中11曲について編曲を行っている。ここでシノーポリが取り上げているのは、ドイツの指揮者、バーンズによる編曲で、マーラーのスタイルと踏襲するイメージの強いものだ。 これがまず面白い。オーケストラ伴奏を施すことによって、マーラーの歌曲「らしさ」が増幅したとでも言おうか。しかも、旋律的なものは、後の交響曲群や歌曲群と、どこか通じたところがあるから、なかなか見事な聴き味となっている。「もう会えない!」など、後の充実した歌曲群に含まれても、十二分に機能しそうな雰囲気。他に録音も少ないだけに、実にありがたい録音となっている。 「さすらう若人の歌」は、当然のことながら多くの録音があり、その中にあって当盤は良演の一つといったところだろうか。ファスベンダーの激しさを伴う歌唱は、第3曲が特にふさわしいだろうか。 メインとなる復活交響曲は、シノーポリらしい音がよく整えられた演奏。出来る限り音の減衰をしっかりフォローしようという心得があり、そのため、音の間隙をやや長めにとり、全般に制御の効いたサウンドで、そのため、艶やかな弦の響きは細かいところまでよく抑えられている。テンポは落ち着いたものだが、過度に劇性を弱めることなく巧みなコントロールが行き届いている。現代的な緻密さをもったマーラーとなっている。 |
|
 |
交響曲 第2番「復活」 フェドセーエフ指揮 モスクワ放送交響楽団 モスクワ国立室内合唱団 S: ヴォズネセンスカヤ A: ぺツコヴァー レビュー日:2021.2.24 |
| ★★★★★ フェドセーエフ指揮のマーラーの交響曲第2番【注 投稿時対象サイトが複数の異なるアイテムのレビューを共有していたため、識別のためのタイトルです】
ウラディーミル・フェドセーエフ(Vladimir Fedoseyev 1932-)指揮、モスクワ放送交響楽団の演奏によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」。合唱はモスクワ国立室内合唱団、ソプラノ独唱はエレナ・ヴォズネセンスカヤ(Elena Voznessenskaya)、アルト独唱はダグマル・ペツコヴァー(Dagmar Peckova 1961-)。 2002年のライヴ録音。 全曲の演奏時間は79分で、1枚のCDに収録されている。 さて、演奏であるが、なかなか耳に新しい、特徴的な復活交響曲である。モスクワ放送交響楽団というオーケストラ、私には、ロジェストヴェンスキー(Gennady Rozhdestvensky 1931-2018)がこのオーケストラと録音した数々の「泥臭い・・・それが魅力的」な演奏の印象が強いが、当盤で聴くサウンドは、まったく別モノのように、垢抜けしていて、明るいサウンドを作り出している。 フェドセーエフの指揮は能弁だ。第1楽章冒頭は、かなり速いテンポで開始され、とてもシャープな感覚で音楽を刻み込んでいき、構造的な均衡感を導くが、甘美な部分では一転してテンポを落し、こまやかなニュアンスを添えながら、音楽の情感を描き出す。その変化は急激であるが、決して不自然な繋がりとはならない前後の脈絡があって、その臨機応変さが面白い。ライヴゆえの肌理の粗さはところどころに残しているが、全体として指揮者の表現したいことを徹底した感があり、そういった意味で説得力があり、アラの部分はさほど気にならないと言える。 第2楽章も主部は速めだが、中間でぐっとテンポを変える。ここで紡がれる木管の主題は、情緒が濃厚に乗っていて、おもわずうっとりさせられる部分だ。しかし全体像としては締まった感触があり、終りに向けてキビキビした雰囲気が支配している。 第3楽章は、比較的遅めのテンポとなる。この楽章では特に楽器の音色が面白い。とにかく従来の演奏のどれともことなる全体的な響きがあって、それゆえの感興があり、私は楽しんだ。 第4楽章ではペツコヴァーの歌唱の素晴らしさがなんといっても印象的で、フェドセーエフもそこにスポットライトを当てたような演出を感じさせる。 第5楽章もいよいよ緩急の起伏が激しく、線的でありながら、情感も必要に応じて盛るという、フェドセーエフのマーラー観がはっきり描かれた演奏になっている。別動隊の音のバランスも特徴的ではあるが、これはライヴ会場の物理的制約のせいなのかもしれない。 全体としては、明るい音色で緩急差の演出による構造的対立性の明瞭化により、この巨大な交響曲を一つの文脈で解きほぐした面白味があり、この曲における一つのユニークな秀演として、存在感のあるものとなっていると思う。 |
|
 |
交響曲 第2番「復活」 ハイティンク指揮 シュターツカペレ・ドレスデン ザクセン州立ドレスデン歌劇場合唱団 ドレスデン交響合唱団 S: マルギオーノ A: ネス レビュー日:2022.7.19 |
| ★★★★☆ 外連味たっぷりの終楽章。フィナーレに壮大なクライマックスを築き上げた演奏
ベルナルド・ハイティンク(Bernard Haitink 1929-2021)指揮、シュターツカペレ・ドレスデン、ザクセン州立ドレスデン歌劇場合唱団、ドレスデン交響合唱団の演奏による、マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第2番ハ短調「復活」。ソプラノ独唱はシャルロッテ・マルギオーノ(Charlotte Margiono 1955-)、アルト独唱はヤルド・ファン・ネス(Jard van Nes 1948-)。 1995年2月13日にドレスデンでライヴ録音されたもの。CD2枚組で、1枚目に第1、第2楽章、2枚目に第3楽章以降が収録されている。 当録音のちょうど50年前にあたる1945年2月13日は、ドレスデン空爆により、多くの死者が出た日で、以来、ドレスデンでは毎年、この日に追悼のコンサートが行われ、レクイエムが演奏されてきたのだが、50周年にあたる1995年は、マーラーの復活交響曲がプログラムに選ばれた。葬送行進からはじまり、クロプシュトック(Friedrich Gottlieb Klopstock 1724-1803)の頌歌により、高らかに「復活」を歌い上げて締めくくる楽曲こそ、50年の節目にふさわしいと、ハイティンクも考えたのだろう。 演奏は、落ち着いた足取りで開始されるが、やがて、かなりダイナミックレンジの広いスタイルが採用されていることがわかる。これは演奏会場等の空間的条件によるものか、それとも録音における機器的なものか分からないが、弱音は小さく、強音は大きくといった感じであり、そのため、再生する環境をかなりの程度選ぶ録音だと感じる。両方の部分で、十分な情報量を聞き取ろうとした場合、環境によっては、たびたびヴォリューム調整が必要となる可能性がある。 演奏自体は、このオーケストラらしい、融合度の高い合奏音が魅力で、特に木管楽器のフレーズは、どのような場所であっても、周囲に調和的であり、情感もたっぷりしている。ハイティンクの解釈自体はオーソドックスなもので、早くも遅くもないテンポを守りながら、堅実なサウンドを作り出している。 ハイティンクの意図のうち、当演奏から特に強く感じるのは、楽曲の最後の壮麗壮大なフィナーレを描きあげることが、このたび機会音楽として奏されるに際して、重要なテーマであると考えていたであろうこと。そのため、楽曲が進行するにつれて、音響は輝かしさを増し、後半になるにつれて踏み込みの効いた演出が添えられてくる。第5楽章のドラムロールの鮮やかさ、合唱導入直前に、透明な木管と、舞台裏の金管によっておりこめられる神妙な気配、そういった、人の気持ちに作用するアクセントが濃厚、濃密になり、より聴き手の気持ちに踏み込もうとしてくるようになる。こうなってくると、前半に、弱音を徹底して小さく奏でることで、ダイナミックレンジの幅をあらかじめ広めに設定していたことも、演出の幅を獲得するためだったことがわかってくる。 演奏は、オーケストラ、独唱、合唱とも、見事な雰囲気を醸し出しており、立派なものである。ただし、前述の通り、CDとしてメディア化された時点で、再生環境を選ぶ要素が強まったこと、またかなり演出的な側面を持っていることがあって、繰り返し再生や向けとして、あるいはこの楽曲の代表的な録音としては、個人的には当盤を推しづらいところもある。逆に言えば、相応の再生環境で、一期一会の心持で聴くのであれば、かなりの陶酔感を得られる録音でもあるので、この楽曲に、どのような気持ちで向かい合いたいかという、聴き手の気持ちによっても、印象が大きく変わるはずだ。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第3番 バッハ 管弦楽組曲(マーラー編) シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2005.1.1 再レビュー日:2013.12.19 |
| ★★★★★ すばらしい名録音!名サウンド!
マーラー最初の「出版物」はブルックナーの第3交響曲<ワーグナー>のピアノ用編曲版であった。思えばブルックナーの第3交響曲の惨憺たる初演で、ごく数人だけがブルックナーの才能を見抜き、畏怖し戦慄したのだが、その一人がいまだ17才のマーラーだったのだ。天才は天才を知る。 マーラーがブルックナーの才能を知ったように、ブルックナーもまた若きマーラーの才能を認めていた。その証拠が上記初出版物の件である。マーラーと36歳の年齢差を感じさせない交遊を思わせるエピソードだ。 ブルックナーの死はこのマーラーが第3を完成したころである。マーラーの死の陰りが途切れない人生にシンクロしていく。 ところで・・・指揮者としての仕事がない時期にマーラーはアッター湖畔で作曲をすすめたのだそうである。第3完成の報を聴きはせ参じたワルターは美しいアッター湖畔にみとれた。そのワルターに向かって「もう見る必要はないよ、全部書き尽くしてしまった」。第3は朝の交響曲であり、それも夏の朝のけだるい曙光を感じる。シャイーの当盤は素晴らしい録音にサポートされた潤いに満ちた名録音。まさに録音芸術! オケの瑞々しい響き、繊細な弦、管の細やかな表情をことごとくマイクが捕らえきっている。さすが世界最高と思われるデッカの録音である。演奏は至極穏当なテンポで奥行きの深く、色彩感豊なスケールの大きい音楽を展開。 一方で緻密な設計は室内楽的ともいえる緊迫感をもっている。3楽章でたゆたう弦をバックにトランペットがpで歌うシーンの美しさは特筆に価する。 |
|
| ★★★★★ 驚異的な成功作!シャイーによるマーラーの第3交響曲
リッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、コンセルトヘボウ管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の“交響曲 第3番 ニ短調” と、マーラーがバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)の原曲を編曲した“管弦楽組曲”を収録した2枚組アルバム。2003年の録音。マーラーの交響曲でメゾ・ソプラノ独唱を務めるのはペトラ・ラング(Petra Lang 1962-)。 マーラーの交響曲第3番は難物だ。全部で6つある楽章、全曲で100分に及ぶ演奏時間。第1楽章だけで30分を越える巨大さ。第4楽章から登場するメゾ・ソプラノの独唱が、第5楽章では女声合唱をバックに「子供の不思議な角笛」から転用された「3人の天使がやさしい歌を歌う」に引き継がれ、さらにその後に純器楽による荘厳な終楽章が続くという音色の変転の激しさ。曲想は全般に明朗であるが、悲劇的にも取れる様々なニュアンスを宿す。1楽章は行進曲のような側面と、これを相反する印象をもたらす重々しいフレーズが混在し、一様ではない世界観をもたらす。 この難解な楽曲に見事な解釈を与えたのがこのシャイーの名演だ。実際、私は、この録音を聴いて、はじめてこの楽曲がどういう音楽なのか、わかったように思う。この楽曲に関しては、楽曲が持ついくつかの性質に焦点を当てて演奏をまとめようとしても、楽曲が持っている他のいくつかの要素は効果が減じられてしまう。実際、世で名演と呼ばれる多くのものについても、私の場合「ここは良かったけど、あそこはそれほど感心しなかった」というものがほとんど。中で、いちばん良いと思ったのがショルティ(Sir Georg Solti 1912-1997)が1982年に録音したもので、徹底して音響的な完璧を達成した録音で、その完璧性によって「失われるいくつかの性質」を一顧だにしない気風が爽快だった。 しかし、シャイーはこの音楽の多様な含みの、ほとんどすべてを表現する、信じられないほど高度な演奏を記録することに成功した。指揮者の卓越した力量のみならず、オーケストラのきわめて高等な技術により、この録音は行われた。 長い曲だけに、その成功をもたらしている要所を例示しはじめると、キリがないのだけれど、例えば第1楽章、トロンボーンに嘆きの哀しい色が感じられる一方で、ホルンに人の声に通じるぬくもりのある柔らかさを担わせ、音楽全体の深みを与えているところ、またクライマックスの直前で、アンサンブルに特有の揺らぎを与え、劇的効果へ結びつけるところ、第3楽章を少し速いテンポで開始し、第4楽章以降の展開への「先見」の役割を果たさせているところ、第5楽章が強い響きで開始されながら、ラングによる歌唱が絶妙のフェルマータで終えられ、深いアダージョの開始に繋がるところ。そしてアダージョで開始される荘厳で深い祈りに似た終楽章の、感動的なコーダの到来を告げるピッコロとフルートの意味深な響き・・などなど。 また音響的なバランスの精妙さも凄い。この点で特筆したいのは第3楽章で、ハープ、コントラバスといった楽器の距離感と音色的な配合が、実によく練り上げられている。この楽章で、弱音で奏でられるトランペットの歌が、これほど透明感を持って精妙に美しく響き渡るのは、そこまでの音響構成が絶妙で、的確に進行されてきたためだ。そのような「前後の関連付け」があってこその、“胸が震えるほどの美しさ” である。 以上の様な、多くの周到な用意があって、この交響曲が持つ多面的な要素は、すべてが活気づいている。第3楽章の牧歌的旋律がこれほど内的な力を持って響くこと、両側の楽章と違和感なく調和した第5楽章が活力に溢れていること、終楽章のアダージョが深淵な様相を持って、深い呼吸のような脈を持つこと。 これらの成功は、シャイーが長大で、時に奇怪な印象をもたらしかねない第1楽章を、まずは見事に掌握したことが大きい。あとは各楽章ごとの性格を慎重に吟味し、構成を熟考し、色と気配を与えていったに違いない。 そして、この名演が、デッカの無類に素晴らしい録音により記録されたことは、かけがえの無い貴重なことに思う。 なお、当盤には、マーラーがバッハの管弦楽曲第2番と第3番から編んだ「マーラー版管弦楽曲」が収録されている。曲の構成は、 1) 第2番の序曲 2) 第2番のロンドとバディヌリー 3) 第3番のアリア 4) 第3番のガヴォット となっていて、有名なG線上のアリアが含まれる。基本的に原曲と大きな差異はないが、大編成の管弦楽で演奏が出来るような意図で選曲と編曲が行われているため、通常のものより、スケールの大きい響きが楽しめる。これまで、ほとんど録音はなかったが、シャイーの優れた演奏がラインナップに加わったことは歓迎されるだろう。 なお、同内容の輸入盤も取り扱いがあります。 注: 本レビューは2005年に投稿していたものに、一部修正を加え、再投稿したものです。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第3番 シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 アシュケナージ指揮 ベルリン・ドイツ管弦楽団 ベルリン放送合唱団 RIAS室内合唱団 MS: フェルミリオン レビュー日:2010.10.26 |
| ★★★★★ シンプルに整った演奏。オーケストラの自発性に主眼を置いたマーラー
アシュケナージ指揮ベルリン・ドイツ管弦楽団によるマーラーの交響曲第3番とシェーンベルクの交響詩「ペレアスとメリザンド」。合唱は、ベルリン放送合唱団とRIAS室内合唱団。メゾソプラノ独唱はフェルミリオン。1995年から96年にかけての録音。 クラシック音楽のファンを長年やっていると、ときおり何ともやるせない感情が起こるものである。このディスクはかつてデッカから、455 089-2の番号で、ヨーロッパで限定的に販売されたもので、後日これを知った私が購入しようとしてもすでに在庫は無かった。その後、ハンブルクの中古店のインターネット販売で当品を見つけた私は、さっそくメール交換の上、随分何年か越しでやっと入手したものである。そのディスクがあっさりこのような廉価版で流通されてしまうとは! 別にこのような経験はこのディスクに限らず、やっと高価で入手した中古版が、何ヵ月後かにあっさりと廉価で再リリースされるようなことはザラである。もちろん、良いソフトが多くの人に入手可能になることは、歓迎すべきことで、良かったと思うけれど、人間の感情の起伏というのは実に微妙なものである。 いきなり関係ない個人的感情を書き連ねてしまった。申し訳ない。 演奏を聴いてみよう。アシュケナージのマーラーは実にヒューマンなマーラーである。ことさら精緻な表現に長けているわけではなけれど、音色にはぬくもりがあって、つねにある一定範囲内の温度でやさしくキープされている。第1楽章の金管のファンフアーレも決然と、というより厳かな雰囲気がある。中間楽章もマイルドな味わいであるが、基本的にインテンポで音楽のスタイルとしてはシャープ。音楽の調和の融合度が高く、肌触りが良い。ことに終楽章は弦の合奏にその暖かい雰囲気がよく表出していて好ましい。それでいて力強い踏込みや、脈打つようなエネルギッシュな表現も含んでいて、音楽の起伏のスケールを大きく感じさせる。 シェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」は演奏時間およそ45分の4管編成による大規模な作品で、シェーンベルク唯一の交響詩だ。ロマン派の色彩を湛えた豊穣な音色が特色で、「グレの歌」とともに作曲者初期の作風を代表するもの。本盤では、デッカの秀逸な録音により魅力がよく伝わる。弦楽器の内省的なハーモニーが魅力で、統一感のとれた好演。知名度はいまいち低いが、成熟した後期ロマン派ならではの音楽を堪能できる。 それにしても「限定盤」のステイタスも、もうちょっと確保してほしい・・・というのは私の勝手な意見ですけれど。 |
|
 |
交響曲 第3番 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 フィルハーモニア女声合唱団 ニュー・ロンドン児童合唱団 A: シュヴァルツ レビュー日:2016.12.19 |
| ★★★★★ オーケストラの出力をフルに活かし、巧みにまとめられたマーラーの第3交響曲
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)指揮、フィルハーモニア管弦楽団による、マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲全曲録音のうち、最後に録音されたのが当盤で、録音年が1994年。末尾を飾ったのは、大曲「交響曲 第3番 ニ短調」となった。 第4楽章のアルト独唱はハンナ・シュヴァルツ(Hanna Schwarz 1943-)、第5楽章の合唱は、フィルハーモニア女声合唱団とニュー・ロンドン児童合唱団。 シノーポリは当録音の2年後にドレスデン国立管弦楽団を指揮して、交響曲「大地の歌」を録音するのだが、1985年の第5交響曲の録音から始まったフィルハーモニア管弦楽団との「番号付き」交響曲の全集は、本盤で一応の完結と見做せる。 シノーポリのマーラーは、全般にテンポ設定に独特のものがあり、曲によっては、私には聴き馴染にくいものもあったのだけれど、最後に録音された第3交響曲は、王道的な名演と言っていいだろう。テンポは第1楽章と第6楽章が早めな以外、平均的なもので、その変化の程度も、他の楽曲の録音と比較すると、大きくない。巨大な姿を持つ第3交響曲の威容に似つかわしい構えの演奏だ。また、第1楽章を中心に、シノーポリの熱血的な面が現れた演奏でもあり、オーケストラ全体を揺らすような咆哮は、聴き手の気持ちを強く鼓舞するものだろう。 まとまりにくいこの楽曲を、成功に導いた演奏だと考えるが、それには声楽を伴った2つの楽章が、前後の関係も踏まえて、うまくまとまっていることが大きく寄与している。第4楽章のシュヴァルツの独唱は、ストレートで安定した声質が曲想によく合い、厳粛な雰囲気をまとい、曲の神秘性をよく引き出している。第5楽章の天使たちの合唱は、短いが性格的な音楽で、私はしばしばこの場所に突飛な印象を持つのだけれど、シノーポリの演奏は、ある意味淡々としていて、全体の流れがきれいに収まっている。引き続く荘重な終楽章とともに、健康的に音楽が運んで行く。この終楽章は間断ない進みで、一筆書きのように気持ちよく一息で描かれたような演奏となっており、スムーズに到達するフィナーレは、高らかに締めくくられる。以上のように、特に後半の音楽の全体的な呼吸のようなものが自然で、とても聴き易くまとまっている。 シノーポリの全集完結を祝うような、明朗な響きも美しく、高い燃焼度を伴って、隅々まで響き渡った心地よさに満ちている。 |
|
 |
交響曲 第3番 ロト指揮 ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 スコラ・ハイデルベルク女声合唱団 ケルン大聖堂児童合唱隊 ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 コントラルト:ミンガルド レビュー日:2020.4.13 |
| ★★★★☆ 精密に統制されたマーラーの第3交響曲
フランスの指揮者、フランソワ=グザヴィエ・ロト(Francois-Xavier Roth 1971-)とケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の「交響曲 第3番 ニ短調」。 第4楽章のコントラルト独唱はサラ・ミンガルド(Sara Mingardo 1961-)、第5楽章のコーラスはスコラ・ハイデルベルク女声合唱団、ケルン大聖堂児童合唱隊、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団。 2018年の録音。 マーラー自身の指揮により、この曲の初演を行ったのが、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団であったとのこと。オーケストラにとって由緒ある楽曲ということになる。 さて、当演奏であるが、非常に制御の効いた演奏である。徹頭徹尾計算しつくして、音量、音価、音色、いずれをとっても精緻である。結果として、トータルなサウンドは、とても透明なものとなっており、燃焼的な性格を抑えて、室内楽的な緊密さをつくっている。それにしても、この巨大な交響曲を「室内楽的」と形容するというのは、私としても抵抗はあるのだけれど、他に妥当な表現を思いつかない。 私にとって、印象的なのは第1楽章と第5楽章である。第1楽章の行進曲の部分のハキハキとした明るさ、明晰なトロンボーンは、優秀な録音とあいまってリアルな質感を伴い、眼前で吹奏が繰り広げられているような錯覚を催す。そういった感覚も、ある意味「室内楽的」と言いうるだろう。テンポは終始落ち着いているが、遅いと感じさせるほどではない。とにかく混濁を避ける観点で音は構成されており、それゆえのきめ細かいフレーズの音色変化があり、楽しい。ただ、そのあたりの演出も、大曲的というより、やはり室内楽的な印象を私は受ける。第5楽章では、合唱による「ビム・バム」を、きわめて抑制的、楽器的に扱った全体像を貫いていて、とてもフラットな味わいになっており、スムーズだ。現代的な感覚美を感じる表現で、ロトの考え方が明瞭に伝わる部分となっている。 音色は美しいが、フレーズに宿る情緒や情念といったものは、当然の事ながら軽め。その結果、第2楽章など、いかにも淡くなっており、聴き手によって評価が分かれるところだと思う。第3楽章のポストホルンはきれい。ただ、現代では、このレベルの録音は多くあり、目立って見事というわけではない。第4楽章、第6楽章もソツなくまとまっており、全体のつながりはとても自然。他の演奏と比べて、重量感が減じているので、この大曲を聴き通しても、胃もたれのない健康的な味わいがのこる。 新鮮味を感じる演奏ではあるが、この交響曲には、もう一つ、強い主張が欲しいような気もする。 |
|
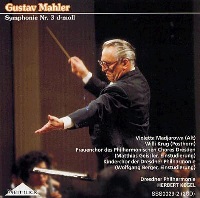 |
交響曲 第3番 ケーゲル指揮 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 ドレスデン・フィルハーモニー女声合唱団、少年合唱団 A: マジャロワ レビュー日:2021.5.19 |
| ★★★★☆ ケーゲルの情念を感じさせるマーラーの第3
ヘルベルト・ケーゲル(Herbert Kegel 1920-1990)指揮、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団、ドレスデン・フィルハーモニー女声合唱団、少年合唱団の演奏で、マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の「交響曲 第3番 ニ短調」。1984年、ライプツィヒにおけるライヴ録音。第4楽章のアルト独唱は、ヴィオレッタ・マジャロワ(Violetta Madjarowa)。 マーラーの第3番のように、人気もあり、録音映えする楽曲となると、CD時代以降に様々な録音がリリースされて、その演奏も概して洗練化の傾向が顕著であるが、そのような演奏に慣れると、ケーゲルの演奏には、独特の情念がこもっているように感じられる。オーケストラの技術的には、現代の世界の一流オーケストラと比較してしまうと、ライヴ一発どりということを踏まえても、若干落ちるところは否めないが、それでも、ケーゲルという指揮者は、音色に強い情感を与え、全体の起伏にも主情的なものがあり、それに感応する聴衆には、濃厚なメッセージ性が感じられるものにちがいない。 音色の情念的な特徴というのは、様々な場面で聴かれるが、例えば第1楽章冒頭のファンファーレがおわったあとのティンパニの音や、第4楽章で背後から鋭く姿を現す木管の音色など、私には、彼岸から聴こえてくる音を連想させる。どこか不安定でいて、それでいて、なにか暗示があり、何かを警告しているような不穏さがある。なので、この演奏で聴くマーラーの第3番は、他の演奏と比べて、私には色合いが暗く感じられる。そして、それがケーゲルによるマーラーの第3なのだろう。 時にタメの大きなスタイルを用いて抑揚を大きくとるところも目立つ。また、弱音域にはたいへんな緊張感があって、それが全体に雄弁な印象をもたらしている。終楽章も、一見朴訥としているようであるが、静謐な緊張から終幕の開放へむけて、ケーゲルなりの思いが乗った演奏とも思える。 全般に、現代では聴けないスタイルの演奏であり、それが記録され、メディアを通して聴くことができるのは、フアンにはありがたい。オーケストラの響きにところどころ薄味が過ぎると感じられるところがあり、録音も上質とは言えず、それらを私は当盤の欠点と考えるが、この演奏固有の魅力が存在することを否定するわけには行かない。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第4番「大いなる喜びへの讃歌」 ベルク 初期の七つの歌 シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 S: ボニー レビュー日:2015.6.1 |
| ★★★★★ マーラーの第4交響曲に精通したオーケストラによる明晰な演奏
リッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、コンセルトヘボウ管弦楽団による1999年録音のアルバム。収録曲は以下の2曲。 1) マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」 2) ベルク(Alban Berg 1885-1935)7つの初期の歌(夜、葦の歌、ナイチンゲール、無上の夢、部屋のなかで、夢を讃える、夏の日々) ソプラノ独唱はバーバラ・ボニー(Barbara Bonney 1956-)。 シャイーによるマーラーの交響曲全曲録音シリーズの中の1枚。このシリーズは、カップリング曲もなかなか面白いが、当盤にはマーラーの影響を強く感じさせるベルクの歌曲が併録されている。マーラーの交響曲の第4楽章「天上の生活」から、ボニーの歌唱が連続し、アルバムとしての一貫性を高めている。 マーラーの交響曲第4番という作品は、コンセルトヘボウ管弦楽団の録音史において、たびたび重要で象徴的なものが作られてきた。1939年のメンゲルベルク(Willem Mengelberg 1871-1951)をはじめ、1952年のベイヌム(Eduard van Beinum 1901-1959)、1961年のショルティ(Georg Solti 1912-1997)、ハイティンク(Bernard Haitink 1929-)には20世紀中に1967年、1982年、1983年の3種の録音があるほか、2006年のものもある。さらにバーンスタイン(Leonard Bernstein 1918-1990)も、1987年の録音に際して、このオーケストラを選んだ。 こうしてみると、この交響曲の録音に関しては、コンセルトヘボウ管弦楽団のものを聴き通せば、一通りの名演を押さえられる、といっても過言ではない頻度である。マーラーの演奏、特に第4番の演奏に関して、ゆるぎない歴史をもつオーケストラであることは間違いない。 中でも個人的には、当シャイー盤とショルティ盤が好きだ。しかし、この両者の録音まったく雰囲気が違う。シャイーは、ややスローなテンポを主体とし、巧妙なルパート奏法で、曲想の細やかな表現を徹底している。さらに、マーラーが書き込んだ実に細かい強弱記号、これはある楽器が強音のとき、他の楽器は弱音といったような、かなり幅のある多様な重ね合わせが用いられているのだが、シャイーはこれをかなり厳密に表現している。 その結果として、音楽は特有の凹凸を持った印象になる。全体としては精緻で精妙なのだが、思わぬ打楽器や管楽器の強調がある。これはショルティが作り出した太い中心線を持った彫像的な音楽とはまったく別の世界で、一種のモダンアートを感じさせる。この色彩感がとても面白い。すべてが音楽として合理的な表現ではないのかもしれないけれど、それが新たな調和性を見出しているとさえ聴こえるのは、シャイーの手腕と、オーケストラの技量によるところだろう。偶数楽章の美しさは圧巻で、満点の星空の元を歩いているようだ。ボニーのストレートな歌いぶりも素晴らしい。 ベルクの歌曲も、夜の気配を色濃くたたえたもので、マーラーの楽曲からの雰囲気的な連続が心地よい。この曲の録音では、ブリジット・バレイズ(Brigitte Balleys)のロマンティックなものも好きなのだが、より感覚的な鋭さを感じさせる当録音は、作曲当時の芸術風潮を感じさせるものだと思う。 録音から15年程度経過したか、まったく古さを感じさせず、今聴いてもたいへん新鮮な味わいだ。 |
|
 |
交響曲 第4番「大いなる喜びへの讃歌」 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 S: グルベローヴァ レビュー日:2016.12.14 |
| ★★★★☆ 絵画的イメージを感じさせるシノーポリによるマーラーの第4交響曲
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)指揮、フィルハーモニア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)チクルスの第6弾で、1991年録音の交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」。終楽章のソプラノ独唱はエディタ・グルベローヴァ(Edita Gruberova 1946-)。 それまでの録音でもかなり大胆なテンポ設定と変化を用いてきたシノーポリのマーラー。特にいくつかの楽曲で極端にスローなテンポをベースにしたところなど、私の中で判断に迷うところもあったのだが、この第4交響曲の第1楽章は逆に早い。機敏なテンポでサクサク進みながら、軽く明るい響きで、この音楽の楽天性を描いているよう。ただ、このテンポで、様々な音がややスリップ気味に思えるところもあり、あまりにもあっさりした感もある。第6交響曲や第10交響曲のアダージョで、逆にスローな進行の中で、緻密な織り込みを目指したスタイルと大きな違いがあって、驚かされる。確かに、第4交響曲と第6交響曲は、様々な点で好対照であるので、テンポの点でも逆転的に誇張する方法論はあるかもしれないけれど、いずれにしても、ちょっと極端かもしれない。 中間楽章以降は、いくぶん普通の展開で、明るさの中に垣間見られる暗さに、すっと焦点を当てるような雰囲気があって面白いが、しばしば長大さを感じさせる第3楽章では、瞬間瞬間の美しさに心洗われる半面、音楽としての前後の関連性はさほど感じられず、求心性という点では、どちらかと言うと拡散しているかもしれない。 第4楽章は、いかにもさりげない冒頭と末尾の雰囲気がきれい。グルベローヴァのあどけなさを感じるほどの爛漫な独唱はこの曲に相応しいとも言えるが、人によっては、より陰りがほしいかもしれない。 私が当録音を聴いて、マーラー自身がこの曲の終楽章について語ったとされる以下の言葉を思い出した。 「ここで僕の考えを表現するのはとてもむずかしかった。どこまでも同じように青く拡がる大空を考えてごらん。変化や対照のいろいろなニュアンスを出すよりずっとむずかしいだろう。これが全体の土台。そこに時々かげりが生まれ、薄気味の悪い、ぞっとする気分になったりする。でも天そのものは曇るわけでなく、永遠の青で輝きつづける。ただ、それは僕達にとってだけ突然不気味なものに変わる。晴れた日にあちこち日差しのもれる森にいると、急にぞっとするように・・・」 「こんなに子供みたいに単純で、自分を全然意識していないようなテーマをどう楽器に移すか、今までにない苦労をさせられちゃったんだ・・・・これが最初に姿を現す時は、陽の光が差す前、花についた朝露のしずくみたいにまるで目立たない。でも朝日が野原に当たりはじめると、その光線は真珠のような露のひとつひとつに反射し、何千という色と光に分解し、そこから光の洪水のような反映が僕らを照らすのだ」 あるいは、シノーポリによる第4交響曲の音楽作りにおいて、上の引用と同様のイメージがあったのかもしれない。そういった意味で、この演奏は、瞬間の描写的な性格が濃く、どこか絵画的な雰囲気を持っている。その面白さがある一方で、音楽ならではの前後の結びつきに相当するところで、より優れた解決法がありそうという気持ちを、どこか残させる部分もありました。 |
|
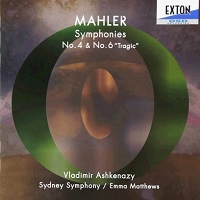 |
交響曲 第4番「大いなる喜びへの讃歌」 第6番「悲劇的」 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 S: マシューズ レビュー日:2015.3.9 |
| ★★★★★ EXTONが、やっとお蔵から出してきたアシュケナージのマーラー、2タイトル
アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)指揮、シドニー交響楽団の演奏によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲2曲がEXTONレーベルからリリースされた。収録されているのは以下の2曲。 1) 交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」 2) 交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」 1)のソプラノ独唱はエマ・マシューズ(Emma Matthews 1970-)。 アシュケナージとシドニー交響楽団によるマーラーの交響曲全集は、すでに2011年のうちに全曲を録音している。しかし、当初シリーズをリリースする予定をアナウンスしていたEXTONからは、第1番、第5番、大地の歌の3点がリリースされたあと、後続がなかった。一度、某雑誌で、全集発売予定が掲載されたにもかかわらず、これもいつの間にか水に流されていた。 しかし、当該全集については、シドニー交響楽団による自主制作レーベルであるsydneysymphonyが発売しており、私は、事務所に問い合わせたうえでそちらを購入した。いずれも江崎友淑氏が編集を担当したもので、既発版を聴いたところ、EXTONの国内盤とまったく同内容である。 かようなわけで、私が聴いたのはsydneysymphonyからリリースされた同音源によるCDである。交響曲第4番は2010年、第6番は2011年の録音で、いずれもライヴ音源に、セッション録音で修正を加えた仕上がり。 アシュケナージにとって、第4番の録音はこれが最初、第6番はチェコフィルとの2001年の録音に続く2度目のもの。いずれも細部までくっきりと焦点のあった、聴き易い仕上がり。 第4番は冒頭からなめらかで透明な音色で、明朗な響き。テンポは少し早めで、強い演出は行わず、無理のない運びで流麗な音楽を導いていく。中間楽章の木管のトリル音などが浮き立つような美しさで、この曲のタイトルにもなっている天上の世界をさわやかに描き上げている。第3楽章の微睡(まどろ)むような音楽も、鮮明かつ克明なタッチで描かれていて、とても覚醒した意識を感じさせる。第4楽章はマシューズの歌唱ともども伸びやかでおおらかだ。ちなみにマシューズは、アシュケナージとの第2交響曲でもソリストを務めている。 第6番は、かなり早めのテンポを主体としている。特に第1楽章冒頭のリズムを聴いたとき、多くの人は「おやおや、このテンポでオーケストラは最後まできちんと弾けるのだろうか?」と思うかもしれない。その点は心配無用で、特におろそかになったりするところはなく、引き締まった演奏と感じる。基本的にテンポが速いだけでなく、おおよそイン・テンポも守られているため、例えば第1楽章のアルマの主題と呼ばれる甘美な第2主題も、浪漫的に大きく膨らますようなことはせず、むしろ軽やかな浮遊感に押しとどめ、甘さを引き締めた厳しさがある。そのような演奏は、人によって「硬い」イメージになるかもしれない。しかし、この音楽が本来持っているエネルギーは甚大なので、さらに過熱するより、線的に把握し、スリム化して響かせる方が、聴き易いという面がある。 私は、この曲については、テンシュテット(Klaus Tennstedt 1926-1998)の熱演も好きだし、ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)の鋭角的で知的な演奏も好きで、気分によって様々というのが正直な気持ちだが、当アシュケナージの演奏には、ドホナーニに近いところがある。ただ、アシュケナージの方が、弦のグラデーションが連続的で、やや聴き手の安寧の感覚への働きかけが強い。 第2楽章にアンダンテ、第3楽章にスケルツォを配している。私個人的にはどちらの順番がいい、というのは特にない。アンダンテは耽美的であるが、沈溺することのない一線が常に意識されている。スケルツォは第1楽章と同様に颯爽と進む。巨大な第4楽章も、味わいとしてはあっさりしたスタイルであるが、オーケストラの自然なアンサンブルが美しく、次々と場面が切り替わっていくような能動的な心地よさを感じさせてくれる。ハンマーは2度打ち鳴らされるが、全体に速い流れの中での出来事となっていて、象徴的な意味合いはそれほど強調されない。むしろ、必要な音楽的効果として、嵌まるべきところに嵌ったような合理的な響き。この交響曲にタイトル通りの「悲劇」を求めるなら、他にもっと劇的な演奏は多くあるのだけれど、アシュケナージのシャープな演奏は、ひとつの現代的解釈として、十分に聴き味のあるものだと思う。 それにしても、これらの録音が、なぜ今になってリリースされることになったのか?録音から4、5年が経過してしまっては、話題性という点でも不利だと思うのだが。今一つ腑に落ちないタイミングのリリースではある。 |
|
 |
交響曲 第5番 ショルティ指揮 シカゴ交響楽団 レビュー日:2004.3.6 |
| ★★★★★ 世界最精鋭部隊の「名詞代わり」の1枚
初演のあと、マーラーは「第5番は呪うべき作品だ。誰もがこれを理解していない」と書いている。しかし、「やがて私の時代が来る」とも言ったという。実際、現在ではマーラーは重要なレパートリーの一つである。 この録音はショルティ/シカゴ交響楽団という世界最精鋭部隊の「名詞代わり」の1枚として伝説的な録音だ。とにかく凄まじい演奏。冒頭のトランペットのファンファーレからただならない気配が支配し、その空気が全曲を覆う。この緊迫感に耐えられるかが聴く側の勝負どころ。管だけでなく弦のアタックも強烈。ハーセス(トランペット)、フリードマン(トロンボーン)、クレヴェンジャー(ホルン)らに率いられた金管陣はそれぞれが精鋭の一個師団のようだ。 |
|
 |
交響曲 第5番 ショルティ指揮 チューリヒ・トーンハレ管弦楽団 レビュー日:2007.8.31 |
| ★★★★★ ショルティよ、永遠に!
ショルティが亡くなる直前のライヴの模様を収めたもの。曲目はマーラーの交響曲第5番だ。これが最後の録音となるそうだが、不思議な運命を感じる。まず、オーケストラがチューリヒ・トーンハレ管弦楽団であるが、このオーケストラはショルティがデッカと契約して最初の録音を行ったオーケストラ(1947年のこと)だということがまず一つ。そして、ショルティがシカゴ交響楽団と最初に録音した曲もマーラーの交響曲第5番(1970年のこと)だったことがもう一つ。さらに言えば、ショルティが世界大戦時を過ごしたスイスで最後の録音となったことにまで運命的なものを感じてしまう。 演奏を聴いての感想だが、この巨匠は最後まで見事に自分のスタイルを貫いたのだな、ということがよくわかる。チューリヒ・トーンハレ管弦楽団は、シカゴ交響楽団と比べたとき、その力量では分が悪いのは否めない。しかし、ショルティはこのオーケストラからも卓越したドライヴで「ショルティ・サウンド」を引き出したといえよう。それは枯淡の境地でも老境の熟達でもなく、まさにショルティの純粋な音楽への信念そのものの結晶のように感じられた。そういった点では、むしろ91年にシカゴ交響楽団とライヴで録音したものより、この録音の方が若々しい萌芽と明確な方向性を感じるのは、オーケストラとの新鮮な顔合わせからだろうか。 金管の膂力の伝わる張りのある音色はまさにショルティならでは。やや早めのインテンポで聴き手を引っ張る推進力も見事。衰えを感じさせないどころか、時計が早まるかのような求心力にはなぜか「若さ」を感じてしまう。そのショルティの力の源は何処から来たのだろうか。 |
|
 |
交響曲 第5番 プレートル指揮 ウィーン交響楽団 レビュー日:2008.5.25 |
| ★★★★★ きわめて内容の豊かな第3楽章が圧巻
ジョルジュ・プレートル(Georges Pretre 1924-)指揮によるマーラーの交響曲が二つ同時にCD化された。いずれも1991年のライヴ録音である。 フランスものの指揮者としては元来高名だったプレートルだが、2008年のウィーンフィルのニューイヤー・コンサートを指揮したことから、このマーラー録音も発掘されCD化とあいなったのだと思う。 あくまで私の感想だけれど、この第5番は同時発売された第6番に比べても、とてもいい内容だと思う。曲の古典性がプレートルと楽団の持っている「鬼気迫る」的な感情の表出にうってつけだったのではないだろうか。 中でも第2楽章、第3楽章、第5楽章が素晴らしい。第2楽章はちぎっては投げ、ちぎっては投げの冒頭から、音間の緊張感の高まりがことに明晰で、タイミングが心地よい。文字通り「嵐のような激動ぶり」を表している。第3楽章は抜群。この楽章はシェルヘンがカットして演奏したように、場合によって「長すぎる」と感じられるし、また、この楽章が長すぎると感じられては、この曲の構造も真ん中で分離されてしまい脆くなる。プレートルはうまい。第2楽章の熱感をたくみに漂わせながら、ユーモアを交え、躍動感のあるクライマックスを築く。弦楽陣の力強いアンサンブルが曲の形をしっかりと支えているし、その弦楽器陣に基盤を支えられて築き上げられる金管の壮麗な咆哮は重量感たっぷり。全曲を通してもっとも印象にのこったのは第3楽章の終結部付近で、全管弦楽の勇壮な押し出しは特筆もの。第5楽章も同様に力感に溢れ。かつ流れの明晰な音楽となっている。 ただ、CD編集上の問題点だけれど、楽章間の「がさつき」や、調音まで収録するのはどうだろうか。しかもこの時間も含めて「演奏時間」として表記されている。言うまでもないが、「演奏時間」はおおよそのテンポの目安として重要なデータである。収録するならせめてトラックを別に割り振って、きちんとした演奏時間を表記してもらいたい。 |
|
 |
交響曲 第5番 マーツァル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2009.5.24 |
| ★★★★★ 良心的で模範的なマーツァルのマーラー
マーツァルの演奏は良心的で模範的である。チェコフィルという豊穣な音色を持ったオーケストラを、余力を持ってドライヴし、無理なことはせず、落ち着いた足取りで音楽を進める。余裕があるだけ、部分部分で配慮の行き届いた楽器本来の音が聴こえる。いかにも高級車といった感じの演奏だ。 特に良い効果が上がっているのが第2楽章で、テンポを急ぎはしないが音のダイナミクスで適切な起伏を描く。「嵐のように」とはならないが、深い谷を見下ろすようなスケールがある。両端楽章は金管のまろやかで量の豊かな響きが全体の印象を確かなものにしている。いかにもしっかりとした土台の上にある堅牢な楽曲となる。 有名な第4楽章アダージェットも、不必要なことはせず、きわめて自然に弦を響かせていて好感がもてる。 他方まじめすぎるのが若干災いした感があるのが第3楽章。やはりこの楽章は難しい。マーツァルのカラーは出ているのだけれど、少し退屈な展開だ。元来、この楽章は内容から言っても少し長過ぎるのだ。 しかし、総じてまじめで良心的な演奏であり、健やかな音楽性が息づいている点は高く評価したい。 |
|
 |
交響曲 第5番 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 レビュー日:2010.12.10 |
| ★★★★★ 美音の連続でマーラーの音楽の「美しさ」を自然に発露した快演
第1番で鮮烈なスタートを切ったアシュケナージ指揮シドニー交響楽団によるマーラー・チクルス。ほとんど間を空けずに第5番の登場となった。こちらも第1番と同じくマーラー生誕150周年に当たる2010年の録音・リリース。ライヴ音源に一部スタジオ録音したものを併せている。エディットのレベルは高く、編集点などはまったくわからない。 一聴して前作の第1番と同様に瑞々しく清冽な音響が広がる。同じコンビによるエルガーではやや鋭い金管の響きが聴かれたが、このマーラーでは洗練の度合いがまた一段と高くなっており、音色はより的確に融合し、しかし互いに主張と存在感をしたたかに示している。立体的な音色は心地よい広がりをキープしていて、高い頂から平野を見下ろすような壮観さがあるとともに、吹き抜ける風を感じるような爽快さがある。 第1楽章冒頭のトランペットはアシュケナージらしい柔らかいトーンであるが、芯のあるきちんと鳴り切った響きになっている。続く管弦楽の合奏も濁りのない美しい音色で、無理のないテンポ設定で、適度に速く、しかし快適に鳴るサウンドが好ましい。第2楽章は激しさを強調せず、第1楽章で作られた品位ある雰囲気を踏襲し、しかしダイナミックな起伏があり表情付けも的確に決まる。時として小さく踏み込んでくるところもあるが、常に高い視点でのリミッタが働いていて、音楽の外面はことのほか美しい起伏で覆われている。第3楽章は歌に満ちた楽しい音楽で、この楽章を聴いて「もっと聴いていたい」と思わせてくれる数少ない演奏の一つ。近年ではジンマン以来の出来栄えと言っていい。第4楽章はヒューマンで暖かい。クライマックスでも激情を吐露するようなものではなく、明るい色彩感に溢れている。この楽章を用いた高名な映画としてヴィスコンティの「ベニスに死す」があるが、おそらく地中海性気候のベニスの夕刻は、このアダージョのような雰囲気に包まれているのではないかな・・・と思わせるような演奏だ。終楽章は下手に騒がしくなると聴きにくいところもあるが、アシュケナージはさすがに音の強弱の範囲をコントロールしていて、美音の連続となる。それでいて内省的な音楽の含みも良く伝わってくるのはオーケストラとこの指揮者の信頼関係のなせる技に違いない。 総じて、これまた第1番に引き続いて素晴らしい出来栄え。今後「大地の歌」「交響曲第8番」などもリリースされるという。これまで声楽を含む作品でも優れた演奏を披露してきたアシュケナージだけに、今後の展開にも期待が込められる。 |
|
 |
交響曲 第5番 ジンマン指揮 チュリッヒ・トーンハレ管弦楽団 レビュー日:2010.4.30 |
| ★★★★★ こういうマーラーを「現代的な演奏」というのかな。
蜜月の関係と言ってよいジンマン指揮とチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団によるマーラー・シリーズ。交響曲第5番は2007年の録音。 ウェルバランスで見通しのよい演奏だ。演奏全体の印象は柔らかめのマーラーといった感じで、例えば終楽章のホルンの響きなど、なかなか聴けないぐらいのデリカシーを持って響いている。「デリカシー」というのも難しい言葉で、これは当然のことながら弱く吹くというだけではない。細心の注意を払って、周囲すべての情報量を的確な配分で理解し、そこに自分のポジショニングを冷静に見出し、自然に自らを置く・・・、と「くどく」説明するとそんな感じである。これは何もホルンに限らず、この演奏がそういう演奏で、その部分が象徴的に感じられるということだ。 第1楽章冒頭のファンファーレも、厳かでありながら柔らかく、その印象は「洗練」という言葉がぴったりかもしれない。管楽器陣はやや控える趣だが、これも先ほどの「デリカシー」を持ったポジショニングと思う。激動するようなクレッシェンドでは、たしかに楽想は激しくなるが、音と音の間隔が常に一定の距離感を保っていることで、全体の透明な印象、楽器の音色の把握しやすさに繋がっている。 第3楽章もこれくらいクールにやった方が聴きやすくなる。劇場型のバーンスタインと対照的。バーンスタインの棒ではここが緩む。囲碁用語で言うところの「緩着」である。同じ劇場型(と私が思っている)ではプレートルが数段ウマいと思うのだけれど。 高名なアダージェットも耽美性より明朗な叙情性を引き出した感があり、ある意味健康的である。他の録音ではシャイーの録音が当盤に比較的近いものかと思うが、シャイーの解析はもう少し鋭角的で照射角度が異なるイメージだ。また、当盤はブーレーズのようなドライな演奏とも違う。まろやかで透明である。 このようなスタイルのマーラーは、確かに「現代的」というイメージを抱かせる。良好な視界、音の明瞭な把握とともに、流線型のフォルムが、現代技術を反映した建築物やIT機器~その機能性やスタイル~から受ける印象と似通うものがあるのだろう。熱演爆演を期待する人には不向きだが、私にはとてもしっくりくる、落ち着いた録音に思える。 |
|
 |
交響曲 第5番 バルシャイ指揮 ユンゲ・ドイチェ・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2011.4.4 |
| ★★★★★ ドイツの学生オーケストラの力量を見せつけられるディスク。
ルドルフ・バルシャイ(Rudol'f Borisovich Barshai 1924-2010)指揮、ユンゲ・ドイチェ・フィルによる演奏でマーラーの交響曲第5番。録音は1999年。 同じ顔合わせによる録音として、バルシャイ自らが補筆修正したバルシャイ版によるマーラーの交響曲第10番の録音が有名だけれども、演奏自体の完成度という点ではおそらくこの第5番の方が高いと思われる。 ユンゲ・ドイチェ・フィルはドイツの音楽科の学生により編成されたオーケストラであるが、力量豊かで、ヨーロッパの音楽教育の質の高さを実感できるものとも言えそうだ。 基本的にはインテンポのスタイルであるが、第3楽章でやや遅め、第4楽章でやや速めという印象。バルシャイの指揮は過度に思いを込めない構造型の演奏に思うけれども、トランペットを中心として、かなり突っ込んだ音を出す部分もあり、時折自分でも御しきれないところがあるようだが、音楽の枠組みにはきちんと入っていて、気持ちの良い踏み外しとして聴くことができる。 第1楽章冒頭のファンフアーレは重めで深刻な形相を持っていて、印象が強いが、この印象の支配はおおむね第2楽章まで持続している。金管の鳴りが全般に重めだけれども、テンポを引きずらせるようなことはなく、全体としてオーケストラは機動的でよく反応している。 第3楽章はともすれば「長過ぎる」と感じられる音楽だが、バルシャイはある程度その面もクリアしていて、多少色彩を変えながら興味を冷まさずに音楽を流れに乗せていると思う。 有名な第4楽章のアダージェットでは特に甘美性を強調することもなく、淡々と進める。ニュアンスに乏しいこともなく、抑制の方向でコンパクトにまとめた感じ。 終楽章はスケールの大きな音楽を、真面目にアプローチした印象で、やや平板なところもあるけれど、音響的にも十分に鳴っていて、感情を開放する瞬間もあり、存分にエネルギーが放出されている。 それにしてもこの演奏が学生オーケストラによるものというのは凄い。バルシャイという人は学生に慕われていたのだろう。どこでも不自然さのない、調和のとれた音楽を聴くことができるし、マーラーの第5交響曲の名盤の一つに数え上げる人がいたとしても、なんら不思議はない録音だと思う。 |
|
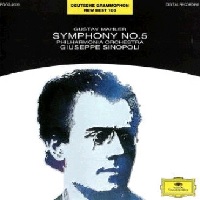 |
交響曲 第5番 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 レビュー日:2012.7.31 |
| ★★★★★ 精神科医としてのステイタスが生きる?! シノーポリのマーラー
2001年、公演中に急死したイタリアの名指揮者、ジュゼッペ・シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946- 2001)の往年の録音が廉価なBox-セットとなったこともあり、いろいろ聴かせていただいている。このフィルハーモニア管弦楽団を指揮して1985年に録音されたマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第5番も、当時はかなり話題になったものらしい。 シノーポリという芸術家のステイタスの一つに「精神科医」という肩書きがある。精神科医であった彼は、音楽作品の分析にあたって、そのような専門的背景も参考にしているといったコメントがあり、聴き手にもそういった興味をわき起こさせた。 実際、「精神分析」といキーワードで、想起しやすい作曲家となると、マーラーあたりは筆頭になってもいいのではないか。幼少のころから兄弟たちの死に接し、自己の精神になみなみならぬ興味を持ち、フロイト(Sigmund Freud 1856- 1939)の診察を受け、「人生は死への序曲に過ぎない」といった死生観を持ち、ユダヤからカトリックへ改宗した世紀末の作曲家、マーラー。その交響曲を現代の精神科医が振って演奏するわけである。 実際、シノーポリはマーラーを得意としたし、私も彼の指揮した「大地の歌」などには深い感銘を受けてきた。けれども、なぜか他の録音を聴かなかった。なぜだろう?いちばんに思い当たるのが、(私の記憶では)彼の録音がなかなか廉価で発売されなかったからである。なんとも単純な精神発想の持ち主で申し訳ないが。 それで、今改めてこの名交響曲を聴いた。私が聞く限り、シノーポリの演奏の大きな特徴は以下の2点と思う。1) ほとんどの楽器の音が再生機から聴き取り可能なように音量のバランスが精密に計算されている 2) 持続音になめらかな強弱を与え、これを重ねることでニュアンスを生み出している。 その結果、この交響曲の激しく荒々しい面はやや緩和され、一方で甘美性や抒情性がより発露する傾向が引き出されている。マーラーの楽曲の耽美的な性格は、言わずもがなのことであるが、シノーポリはその甘美な部分をことさら万遍なく掬い取ることを主眼としているように感じる。これが解析的とか分析的という文句で表現されるものに相応しいかどうかわからないが、サウンドの美しさは見事で、熱っぽくないのに陶酔的であり、それがシノーポリのマーラーなのであろう。私が良く聴いた彼の「大地の歌」の印象とも通じるものだ。長大さを感じることのある第3楽章も、豊饒な音色が十分な魅力を伴って鳴り響く心地よさが横溢している。映画「ヴェニスに死す」で使用されて以来あまりに高名な第4楽章のアダージェットも、耽美で官能的とも言えるサウンド。この2つの楽章によりはっきりしたシノーポリの刻印を感じる。 これをきっかけに、これまで聴きもらしていたシノーポリの他のマーラーにもあらためて興味が湧いてきた。この芸術家の貴重な遺産が、広く音楽愛好家に聴かれ続けることを願う。 |
|
 |
交響曲 第5番 ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 レビュー日:2014.8.19 |
| ★★★★★ 解析的で、暖かい起伏を備えた玄人肌のマーラー
ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-)指揮、南西ドイツ放送交響楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第5番嬰ハ短調。2003年の録音。 明らかに現代的な感性を鋭く反映したマーラーだ。最近の主流と言っても良い。ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)、ブーレーズ(Pierre Boulez 1925-)、シャイー(Riccardo Chailly 1953-)といった人たちに試みられてきた精妙で解析的な響きに満ちている。 スタイリッシュな感触に満ちたギーレンのマーラーは、音楽を明晰に響かせる一方で、厚さや重さを排し、心地よいスピード感と、ライトなカラーを身にまとう。 第2楽章の「嵐の様に激動して」などを聴くと、そこにあるのは、作曲衝動の源泉にあったであろう熱いパッションは、冷静な芸術家の表現への意志によって、ほどよく整形され、美しいフォルムを身にまとっているのを感じる。第3楽章も、全体を軽やかに歌い上げ、重々しさとは無縁の響き。その一方でピチカートの隅々まで血の通った表現を感じさせ、決して冷たい光沢を感じさせるものではない。 この解析性と、人間的なぬくもりの両立という点で、この演奏は特徴的であり、同曲の数ある録音の中でも特徴的な位置を占めるものと言えそうだ。 有名な第4楽章のアダージェットは、早めのテンポで引き締めた心地よさがあり、耽溺することがない。人によっては、より濃厚な情感を期待するかもしれないが、この演奏は、制約によって獲得られる美観を、ことのほか重視しているのだ。しかし、弦楽器陣のソノリティ自体の美しさと、的確で心地よい進行により、いつのまにか十分と言える満足感を得たことに気付く。 軽やかで明晰ではあっても、この演奏は迫力不足を感じるものでもない。それはオーケストラの優れた技量があってこそだと思うのだが、フレージングの構築が巧みで、高揚感を巧妙に演出し、聴き手の気持ちを心地よく導いてくれるためである。まさにプロフェッショナルな音楽だろう。だから、両端楽章のクライマックスでも、非常に聴き易いサウンドで、天に舞い上がる様な上昇感を導いている。それは迫力として作用するものだ。 私にとっても、ここ10年くらいの同曲の録音の中でも、ジンマン(David Zinman 1936-)、アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)とともに印象に残る一枚となっている。 |
|
 |
交響曲 第5番 ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2019.3.11 |
| ★★★★☆ 2002年、ラトルが芸術監督就任時に振ったベルリン・フィルとのマーラーの第5
2002年から2018年までベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者兼芸術監督を務めたサイモン・ラトル(Simon Rattle 1955-)が、その前半に録音したものが廉価のBox-setとなったので、この機会に入手して聴いている。 その1枚が当盤に相当するが、これは就任直後の2002年に行われたライヴ録音。曲目はマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の「交響曲 第5番 嬰ヘ短調」。アバドの後任として世界最高のオーケストラの首席指揮者兼芸術監督に就いたラトルの「名刺代わりの録音」といったところで、EMIからスピーディーにリリースされたことを覚えている。私が今まで効かなかったのは、単に流行りに飛びつきたくないという性分からだっただろうか。 それから16年以上も経過して、やっと私はこの録音を聴いたことになる。 なるほど、これはなかなか見事な演奏だろう。とにかくラトルの「コントロールしよう」という意志が明瞭で、隅々までその設計に基づいた音響が構築されている。ダイナミックレンジは広く、テンポもある程度自在。そして、瞬間瞬間の全体的なソノリティを、きめこまかう調節して、立体的で鮮明な音像が築き上げられている。 第1楽章はややゆったりとしたテンポで開始。その後、コントラストを明瞭にしながら、テンポにある程度の変動をあたえつつ、激しいものと静謐なもののギャップを描き出していく。楽章全体として「序奏」の性格を強く引き出そうとしたのではないだろうか。第2楽章に入ると、いよいよ動きが活発化し、様々な強弱の対比が描かれるが、概して指揮者の強い制御を感じさせる。ハーモニーの光沢感や、メカニカルな冴えは鮮やかであり、この楽章のスコアを克明に照らし出すという点で立派な成果になっている。 だが、このスタイルだと、第3楽章にはやや長さを感じてしまうところがある。オーケストラの自発的な要素、自然発揚的な情感を活かして引き出していくような要素が欲しくなるのだ。ただ、この楽章だけスタイルを変えるというのも実際問題難しいだろうし、やったところで、解決のつかない別のことが持ち上がってくるようにも思えるから、難しいのかもしれない。終結部の全管弦楽による推進の力強さは見事で、結びでうまく締めたといったところだろうか。 第4楽章のアダージェットはとてもなめらかで透明。この音楽は、とくに後半は熱を帯びたようになってくるのだが、ラトルは冷静で、常に一定の距離感が保たれている。ベルリン・フィルの弦楽器陣のゴージャスな響きが、淡々と流れていく様は、不思議と即物的な感覚を催させてユニークだ。第5楽章は運動的な展開が心地よいが、ここでもラトルの制御は緻密と言ってよい。そのため、これは3楽章でもそうだったのであるが、どこかユーモラスなフレーズや、ちょっと風合いを感じさせるような音型が、きわめて無表情に感じられるところがあり、ときおり思わぬメタリックな感触を味わう瞬間がある。 全体的に全合奏の彫像性、克明な描写力は見事。その一方で、マーラーらしい情念的なものが、時折抜けたように響くのが、当演奏のスタンスを考えると、「ないものねだり」なのかもしれないが、やや物足りなさを感じさせる。 |
|
 |
交響曲 第5番 フェドセーエフ指揮 モスクワ放送交響楽団 レビュー日:2021.2.24 |
| ★★★★☆ フェドセーエフ指揮のマーラーの交響曲第5番【注 投稿時対象サイトが複数の異なるアイテムのレビューを共有していたため、識別のためのタイトルです】
ウラディーミル・フェドセーエフ(Vladimir Fedoseyev 1932-)指揮、モスクワ放送交響楽団の演奏によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲 第5番 嬰ハ短調。2000年のライヴ録音。 なかなか不思議な感じのマーラー、といったところだろうか。全般にクールで軽い印象であるが、それゆえの面白さや精度の高い輝きといったものをそれほど感じない。全体としては、スリムでスッキリした感じで、胃もたれ感はないのだが、マーラーの第5における清涼な演奏として、当盤を挙げるかというと、ちょっと微妙なところである。 第1楽章の冒頭から、タメの少ないインテンポな解釈で、ここだけ取るとショルティに近いものを感じるが、ショルティの様に合奏の精度を輝かしく練り上げているわけではない。そのため、よく言えば中庸、悪く言えば凡庸にも聴こえてしまう。とはいえ、流れの良さは維持されていて、聴きにくかったり、引っかかったりするわけではない。処理自体はスムーズで、フェドセーエフとオーケストラの手堅い運びが感じられる。 第2楽章も、曲との間に一定の距離をおいた客観性が支配する。この楽章には、マーラーならではの激情的なものが横溢するのであるが、当演奏は、つねに一定の角度から状況を俯瞰するような印象で、各パーツの動きが分かりやすくて面白い。 だが、第3楽章は、この手法だと、やや面白くないと思う。実際、この楽章に所要している時間も長く、聴いていても、感覚的に長さを感じさせてしまう。明晰さを打ち出すにも、もう少しテンポが速かった方が良かったと、個人的にはそう感じてしまう。 第4楽章はなかなか良い。淡々としているが、要所でアクセントが効いており、概して聴き味に不足感は生じないと思う。ただ、一般的な名演と称されるものと比べると、インテンポが前面にあるので、タメの利きが少なく、その点で好悪が分かれるだろう。 終楽章はたいへん軽やかで、ロシアの指揮者とオーケストラが奏でる音楽とは思えないほど、重々しさがない。確かにこの楽章はそういうスタイルでもいいのかもしれないが、かなりアッサリした仕上がりで、いつのまにかサラッと終わるような感じ。 概して、他の演奏の印象とは大きく異なる不思議なマーラーと感じた次第。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 T.トーマス指揮 サンフランシスコ交響楽団 レビュー日:2004.3.6 |
| ★★★★☆ 同時多発テロの直後のサンフランシスコの録音
マーラーは、初演の時にこの曲を「悲劇的」と紹介した。マーラー好みの4度や6度の音程の飛躍を多くの主題で用いている。声楽を含まない4楽章構成はスタイリッシュだ。 しかしオケの規模は大きい。とにかく打楽器群の陣容が凄まじい。2組のティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タム・タム、グロッケンシュピール、シロフォーン、むち、ハンマー、ヘルデングロッケン(カウベルとも呼ばれ家畜用の鈴)、ティーフェス、グロッケンゲロイテ(低音の鈴、鐘に近い)、チェレスタ(できれば2台、またはそれ以上)。いったい何をやるのだ?という感じだ。 マーラーは、妻のアルマに終楽章で3度打ち鳴らされるハンマーについて、「英雄は敵から3回攻撃を受け、3回目に木のように倒れてしまう」と語ったとのことである。そして、曲はその後、悲劇的で沈んだような重々しい結尾で結ばれる。そこには死に対する諦観も感じられよう。 さて、肝心の演奏だが、このティルソン・トーマスの演奏は2001年9月12日から15日にかけて行われたコンサートの際に録音されたものである。つまり9月11日の同時多発テロの直後であり、この悲劇的交響曲が湛える憂いは深く感じられる。冷静にタクトをさばきながらも各所で聴かれる慟哭のような低音が印象に残る。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第6番「悲劇的」 シェーンベルク 5つの管弦楽曲 ヴェーベルン 夏風の中で ドホナーニ指揮 クリーヴランド交響楽団 レビュー日:2005.1.13 |
| ★★★★★ 中央突破力に圧倒されるマーラーの第6
ドホナーニという指揮者は日本でももっと評価されていいのではないか?このマーラーの第6交響曲と新ウィーン楽派の2曲を収めたCDを聴いてそんな思いを強くした。 マーラーの第6交響曲は大変な傑作であるが、複雑な曲でもある。例えば1楽章、2楽章はともにイ短調で、それが4拍子から3拍子へと変るので不気味な怪異性が強調される独特の効果を放つ。これを嫌って2,3楽章を入れかえる指揮者もいるほど。(実際マーラーもこの楽章の順序には相当悩んだようだ) 加えて巨大な編成がある。確かに声楽を含まない4楽章構成はスタイリッシュだ。しかしオケの規模に目をやれば・・・とにかく打楽器群の陣容が凄まじい。2組のティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タム・タム、グロッケンシュピール、シロフォーン、むち、ハンマー、ヘルデングロッケン(カウベルとも呼ばれ家畜用の鈴)、ティーフェス、グロッケンゲロイテ(低音の鈴、鐘に近い)、チェレスタ(できれば2台、またはそれ以上)。いったい何をやるのだ?という感じだ。 そして終楽章のとてつもなく大きな展開部。2度打ち鳴らされる慟哭のハンマー!この曲が「悲劇的」と称される所以だ。 ところで、このドホナーニ盤だが、一聴してパーカッションや弦楽器のきわめて瑞々しい鮮明な響きに驚かされる。オケの距離感がきわめて適切に再現されており、理想的な録音である。 1楽章開始とともに鋼鉄の意志でひたすら終結部にむけてしっかりとした足取りで進んで行く。決して乱れることなく整然と、どのような音楽的技術的障害もものともせず突き破りるその凄まじい中央突破力に圧倒される。しかも知的だ。 マーラー好みの4度や6度の音程の飛躍や第1楽章第1主題のあとで管によって奏される長3和音から短3和音への進行をその後も巧みにさばき続ける。鮮やかな手腕と言うほかない。 併録されたシェーンベルクの作品は12音音楽への転轍期に作られた重要作。新たな形式と表現の融合が試みられる。またヴェーベルンの作品は初期の管弦楽のための描写音楽といってよく、ロマン派の影を色濃く残している。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 プレートル指揮 ウィーン交響楽団 レビュー日:2008.5.25 |
| ★★★★☆ 最近では珍しい古風な劇場型マーラー
ジョルジュ・プレートル(Georges Pretre 1924-)指揮によるマーラーの交響曲が二つ同時にCD化された。いずれも1991年のライヴ録音である。 プレートルはパリ音楽院でトランペットを専攻し、その後、ジャズ楽団のメンバーだったが、クリュイタンスらに師事して指揮者に転向した。オペラ、管弦楽曲ともフランスものを中心にしたレパートリーが知られ、発売される録音もこのジャンルのものが多かった。しかし、2008年のウィーンフィルのニューイヤー・コンサートを指揮したことから、その他のジャンルにおける彼の活動が注目されるようになり、このような録音も出てきたものだと思う。 当盤に収録されたマーラーの第6番を聴いてみての印象であるが「うーん、これはまたずいぶん古典的なマーラーで・・・」というのが第一。その印象の原因は、細かく表情付けを施し、音楽のテンポを揺らす演奏スタイルにある。実際、最近のマーラー演奏は、基本的にテンポの変動は大きくなく、精緻さに重点を置くものが多い。私のよく聴くシャイー、ブーレーズ、ドホナーニといった人たちのマーラーはおおむねそうだと言って間違いないだろう。マーラーの近代演奏史を紐解けば、バーンスタインに代表される「劇場型」と、ショルティに代表される「造型型」に分けられると思うが、この演奏はあきらかに前者に属する。前者の演奏の場合、その感性を聴き手が完全な信頼感を持って共有できるかどうかがポイントとなる。一回きりのライヴではなく、繰り返し再生を前提とするメディアでは、そこが重要だ。 第6番という楽曲が複雑多岐な要素を持っていることもあって、私の感覚ではこの演奏における様々な情念を吐露するような演出は、時としてバランスをはずしていると感じられた。もちろん悪い演奏というわけではない。そこには現代ではあまり聞けない(貴重な)マーラーの「俗っぽさ」の発露があり、熱血な何かはもちろん感じ取れる。畳み掛ける性急さと圧搾したエネルギーの解放には人間的な感情がこもっていると思う。名演なのだろう。ただ、録音の弱みもあって、音が部分的に痩せたり、特に弦楽器陣のアンサンブルが濁る感じもある。聴き手がどこに重い価値を置くかで、この演奏の評価は大きく変わりかねないだろう。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 ゲルギエフ指揮 ロンドン交響楽団 レビュー日:2010.11.17 |
| ★★★★☆ ゲルギエフらしい常動感・躍動感溢れるマーラー
ロンドン交響楽団の主席指揮者となったワレリー・ゲルギエフは自主制作レーベルLSO Liveからマーラーの交響曲を連続してリリースしており、この第6番は2007年録音。 ゲルギエフという指揮者は、手兵サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場管弦楽団とともに楽壇に華々しく登場し(もちろん、人知れぬ長い蓄積あってのことだが・・)その後ウィーンフィルやこのロンドン交響楽団もどんどん振るようになった。まさに「勢い」を象徴する指揮者だけれど、作り出す音楽もそんなゲルギエフのイメージにピッタリで、勢いがあって、機敏に動き回る。チャイコフスキーやリムスキー=コルサコフの爆演はその典型で、私もずいぶん楽しませてもらった。また、プロコフィエフも面白かった。 一方、ショスタコーヴィチなどでは、私にはその機敏によく動き回るさまが、音楽の気宇と少し齟齬をきたすように思われるところがあり、同時代の指揮者では、例えばヤンソンス、アシュケナージ、バルシャイといった人たちの方がショスタコーヴィチの音楽が正しく機能しているようにも思われた。この「正しく」という表現は微妙ですけど・・・ それで、マーラーを聴くとどうなるか?と思ったのだが、やはり早いテンポで、きわどい多彩な表情付けがあって、濃厚な部分と淡白な部分の描きわけが面白く、聴かせる演奏になっている。特に両端楽章は「出来ることは全部やってみました」といった饒舌さがあり、様々なデュナーミクで音楽に起伏や表情を与えていて、しかもスピードがあるからどんどん移ろっていくところが特徴だろう。まるで熱帯地方で成長する入道雲のような。 それで、このマーラーを聴くと、結構いろんなことがあって、聴く方も少し消耗してしまうようなところがある。それはそれでいいのだろうけど、どこかマーラーの音楽の場合、もっとガチッとした重心があるのではないか?と思わせてしまうところもある。これは確信犯的にやっていることだから、それでかまわないとも言えるのだけれど。それと、録音の印象のことだが、少し平板な印象を受ける。奥行き感が今ひとつで、弱音がやや痩せた音に聴こえるところがある。もう少し潤いが残っていた方が個人的には好みだ。 とはいえゲルギエフならではのエネルギッシュなマーラーであり、第6番はこんな風にどんどんアクセントを付けていけるんだ、ということを気付かせてくれる楽しみがある。これはこれで一興といった演奏と思う。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 レビュー日:2014.4.5 |
| ★★★★★ 現代的な感覚で、颯爽とした快速演奏
アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)指揮、シドニー交響楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」。2011年の録音。ダウンロード版と同音源によるシドニー交響楽団自主制作レーベルsydneysymphonyからリリースされているCDメディア(SSO 201103)を聴いての所感等を書く。 アシュケナージとシドニー交響楽団による11曲からなるマーラーの交響曲全曲録音は、2010年2月から2011年11月までの比較的短期間で製作された。第6番は、7番目に録音されている。この全集は、全てライヴ録音と銘打たれているが、別にセッションで録音されたものにより、細部を編集している。そのため、聴き味はほとんどセッション録音といった品質で、拍手も含めて、実演時の雑音などもカットされている。 バランス・エンジニアを担当しているのが、オクタヴィア・レコードの江崎友淑氏で、さすがに美麗な仕上がりとなっている。この全集は、日本ではExtonレーベルが発売することが想定されていたのだが、2014年4月の時点で3点しか発売されておらず、後続するのかは不明である。私はその発売を待ちきれず、sydneysymphonyの全集を購入させていただいた。 アシュケナージにとって、第6番の録音は2度目で、1度目はチェコフィルハーモニー管弦楽団と2001年にセッション録音したものがある。そちらもエディットはオクタヴィア・レコードのスタッフによって行われたものであった。いずれも細部までくっきりと焦点のあった、聴き易い仕上がりだと思う。アシュケナージのこの曲の演奏スタイルは一貫していて、かなり早めのテンポを主体としている。NHK交響楽団を振った時も同様のテンポだった。特に第1楽章冒頭のリズムを聴いたとき、多くの人は「おやおや、このテンポでオーケストラは最後まできちんと弾けるのだろうか?」と思うかもしれない。その点は心配無用で、特におろそかになったりするところはなく、引き締まった演奏と感じる。 基本的にテンポが速いだけでなく、おおよそイン・テンポも守られているため、例えば第1楽章のアルマの主題と呼ばれる甘美な第2主題も、浪漫的に大きく膨らますようなことはせず、むしろ軽やかな浮遊感に押しとどめ、甘さを引き締めた厳しさがある。そのような演奏は、人によって「硬い」イメージになるかもしれない。しかし、この音楽が本来持っているエネルギーは甚大なので、さらに過熱するより、線的に把握し、スリム化して響かせる方が、聴き易いという面がある。私は、テンシュテット(Klaus Tennstedt 1926-1998)の熱演も好きだし、ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)の鋭角的で知的な演奏も好きだ。気分によって様々というのが正直な気持ちだが、当アシュケナージの演奏には、ドホナーニを彷彿とさせるところがある。ただ、アシュケナージの方が、弦のグラデーションが連続的で、やや聴き手の安寧の感覚への働きかけが強い。 第2楽章にアンダンテ、第3楽章にスケルツォを配している。私個人的にはどちらの順番がいい、というのは特にない。アンダンテは耽美的であるが、沈溺することのない一線が常に意識されている。スケルツォは第1楽章と同様に颯爽と進む。 巨大な第4楽章も、味わいとしてはあっさりしたスタイルであるが、オーケストラの自然なアンサンブルが美しく、次々と場面が切り替わっていくような能動的な心地よさを感じさせてくれる。ハンマーは2度打ち鳴らされるが、全体に速い流れの中での出来事となっていて、象徴的な意味合いはそれほど強調されない。むしろ、必要な音楽的効果として、嵌まるべきところに嵌ったような合理的な響きだと思った。 この交響曲にタイトル通りの「悲劇」を求めるなら、他にもっと劇的な演奏は多くあるのだけれど、アシュケナージのシャープな演奏は、ひとつの現代的解釈として、十分に聴き味のあるものだと思う。そういった点と録音が優秀なことも踏まえて、当盤が、私の好きなこの曲の録音の一つであることは、間違いない。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 第10番~アダージョ シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 レビュー日:2016.12.9 |
| ★★★★☆ 丁寧にゆっくりと整えられた演奏ですが・・
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)指揮、フィルハーモニア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)シリーズの第3弾で、以下の2曲を収録。 1) 交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」 2) 交響曲 第10番 嬰ヘ短調 ~アダージョ 1)は1986年、2)は1987年の録音。 シノーポリがこの時期に行った一連のマーラーの録音は、全般にゆったりした落ち着いたテンポを取るが、中でもこの2曲は特にスローだ。マーラーの交響曲群の中でも第6交響曲は、全編にみなぎる激しい悲劇性に強い特徴がある。しかし、この曲と対峙したとき、指揮者が選択するテンポはかなり幅広い。簡単な見極め方として、この曲がCD1枚に収まっているかどうか、という点がある。CD1枚で収録されていてれば、平均的なものか、早めのものと見做せるだろう。しかるに、このシノーポリの演奏は、第1楽章25'11、第2楽章13'40、第3楽章19'54とここまでで1時間に達し、その後第4楽章にさらに34'31を費やしている。 その結果、全体的な印象は、実に巨大な音楽と対峙している、というものとなる。それぞれの音の減衰の効果を十分に聴き手に届けようと言う丁寧な織り込みは、音響に甘味を増す。交響曲第6番の第1楽章のアルマのテーマ、そして第3楽章など、うっとりした情緒がにじみ出した音楽になっていると言えるだろう。しかし・・、と私は以下の点を併せて指摘したい。 音楽をスローなテンポで表現する場合、時間の進行の遅さに伴う「深まり」を聴き手は求めるものだ。ところが、シノーポリの演奏は、どこか客観的で俯瞰的。楽曲そのものから距離を置いたような不思議なクールさが取り巻いている。これが私の中で、スローなテンポと抱き合わせの良くない印象に思える。前述の様に甘味が聴き手を誘ってくれる個所は良いのだけれど、それ以外の場所で、しばしばそれは単なる「間延び」のように感ぜられる。第6交響曲では、特に終楽章が問題だ。この楽章は、マーラーが書いた実に凄い音楽の一つなのだけれど、シノーポリの演奏では、その凄味が薄まり、どこか退廃的なものになっている。熱気がないと言うわけではなく、最初のハンマーの一撃のあとの盛り上がりなど巧いのだけれど、全体的な冗長さによって、楽章全体のパーツの関連性が薄まっているのだ。だから、この楽章の凄味の原点である聴き手への「連続攻撃」的な悲劇が、どこか途切れ途切れになった印象を受けてしまう。確かに細部は克明に描かれているのだけれど、音楽としての構造的な関連性の弱まりをどこかに感じてしまう。ちなみに、私がこの楽章に感銘を受けた録音とその演奏時間を書くと、ショルティ/シカゴso(27'42)、ドホナーニ/クリーヴランドo(29'40)、テンシュテット/ロンドンpo 91年ライヴ(30'56)といったところです。 第10交響曲のアダージョも遅い。32’47を費やして、実にゆったりと流れる。楽曲が持っている雰囲気から、シノーポリのアプローチはむしろこの曲の雰囲気に合っているように思う。研ぎ澄ましたような弦の艶やかな表現は、鮮明な感覚を伴って迫ってくる。とはいえ、やはりところどころで、流れに深まりより薄さを感じざるを得ないところが残る。 以上のように、美しい魅力的な部分もあるけれど、全体的には、音楽の脈の弱さを感じさせるところがありました。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 ピアノ四重奏曲 エッシェンバッハ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 p: エッシェンバッハ vn: キム va: チャン vc: バルタチギル レビュー日:2018.7.4 |
| ★★★★☆ フィラデルフィア管弦楽団のサウンドを存分に味わえる録音
エッシェンバッハ(Christoph Eschenbach 1940-)指揮、フィラデルフィア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」 と、エッシェンバッハがピアノを務め、同管弦楽団員との共演による、同じくマーラーの ピアノ四重奏曲 イ短調 を収録。交響曲は2005年、ピアノ四重奏曲は2006年のライヴ録音。ピアノ四重奏曲の弦楽器奏者は、ヴァイオリンがデイヴィッド・キム(David Kim 1963-)、ヴィオラがチューン=ジン・チャン(Choong-Jin Chang) 、チェロがエフェ・バルタチギル(Efe Baltacigil 1978-) 。いずれの曲も末尾に拍手が収録されている。 マーラーの交響曲第6番は、CD1枚で収録されるケースが多いが、テンポ設定によっては1枚で収録しきれない。エッシェンバッハの当演奏では、改訂版を用い、かつ中間2楽章の入れ替えは行われていないのだが、第3楽章のアンダンテがかなりスローなテンポで、17分を要す内容となっていて、そのこともあって2枚組のアルバムとなったのだろう。この第3楽章までが1枚目、第4楽章と、別に機会に録られたピアノ四重奏曲が2枚目に収録されている。同じイ短調の楽曲同士で組み合わせた形といって良い。 前述の通り、第3楽章がゆったりしている以外は、全般にテンポは一般的なものを基準とし、そこに主観的な揺らしを加えたものと言って良い。ヴァイオリンを両翼に配置したオーケストラは、エッシェンバッハの棒の元、中音域に厚みがある中央ヨーロッパ的といって良い音響を美しく響かせているのが好印象だ。また、第1楽章と第2楽章は、元来性格的な類似から、2楽章と3楽章を入れ替える等の論点のあるところであるが、エッシェンバッハは、第1楽章と第2楽章の一貫性をむしろ強めるスタイルを堅持し、堂々と音楽を進めている。音響はこまかい配慮がなされていて、特にカウベルの響きが、単に打楽器的には用いられず、旋律を成すように扱われるところにこの演奏の象徴的なものを垣間見る。また、第2楽章で意味深なトロンボーンの響きが入るのも興味深い。 全般に前2楽章は、悲劇的なものを強調するというより、純音楽的に処理された感が強い。緊密に構築されている一方で、爆発的なものはないと言っていいだろう。むしろ中庸の美をたもつ配慮が徹底している。それに比べると後半2楽章は浪漫的な表現が現れる。第3楽章の耽美は、テンポを落とすことで強調されている。第4楽章のハンマーは2度打ち鳴らされるが、ハンマーのあとの小さなタメを経て、牧歌的な主題に転化していくところなど、この音楽の恐ろしさがよく引き出されているだろう。 マーラー10代の作品、ピアノ四重奏曲が収録されたのは良いサービスだ。まだどこかブラームスを思わせる作風であるが、哀愁ただよう楽曲に相応しい繊細なアプローチが繰り広げられている。 交響曲第6番には、名演名録音が多く、それらと比べた時にこの盤ならでは、というものが今ひとつないかもしれないが、この交響曲の解釈として一つの合理的な形を示したものであり、特にヴェリゾン・ホールという音響効果の高い演奏会場を活かしたオーケストラ・サウンドの美しさは、当盤の魅力にほかならないだろう。 |
|
 |
交響曲 第6番「悲劇的」 ヴィト指揮 ポーランド国立放送交響楽団 レビュー日:2018.10.3 |
| ★★★★★ 高度に設計された熱血性。骨太で豊かな味わいに満ちたヴィトの「悲劇的」
アントニ・ヴィト(Antoni Wit 1944-)指揮、ポーランド国立放送交響楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲第6番 イ短調 「悲劇的」。ヴィトによるマーラーの交響曲全集の一貫として1992年に録音されたもの。 ヴィトは、さほど知られていないかもしれないが、現代を代表するマーラー指揮者という一面を持っていて、そのスタイルは基本的に骨太で熱血的なものと言って良いだろう。旋律線を強く表出する表現は、古典的な印象を持つが、知的な均衡感や、全体のバランスへの配慮もあって、濃厚に過ぎたり、浪漫性を強調し過ぎたりして、胃もたれするようなものにはならないので、私もなかなか気に入っている。 中でもこの第6番は見事と言って良い出来栄え。全曲が2枚のCDに収録されていて、第2楽章にスケルツォ、第3楽章にアンダンテという配置を遵守している。演奏時間を見ると、23'41、12’49、16’04、31’10だから、ほぼオーソドックスなテンポによる解釈といって良く、長時間収録にすれば、1枚でも収まるだろう。(そう考えると、2枚組という規格に若干の割高感は感じるのだが) ただ、演奏そのものは素晴らしく、ヴィトの熱血的なものと怜悧なものが、絶妙なバランス感覚で表出しているといって良い。また、それを助けているのが優秀な録音で、ややソフト気味ながら、ホールトーンを良好に抑えた音場が良くとらえられていて、過度に刺激があるわけではなく、それでいて、強い音はその主張がしっかりとした存在感で伝わってくる。 第1楽章冒頭から運動美と推進力に溢れた音楽が展開するが、足並みを乱さない落ち着きもあり、安心して身をゆだねることが出来る。もちろん、この音楽自体は、聴き手に攻撃的な力で働きかけてくるものであり、安心して身をゆだねると言っても、それは無害であるというわけではない。負の心の表層を描いた楽曲に相応しい、文字通り「悲劇的」な諸相をもって音楽は響く。その主張を確かにするのは、弦楽パートの野太いしっかりした響きであり、ここでもホールトーンの抜群の効果を得て、感情的な起伏が濃厚に描かれるのである。 第2楽章は第1楽章の雰囲気をそのまま引き継ぎながらも、金管や打楽器との音場をち密に設計した彫像性があり、音楽の奥行きで聴かせる手腕を発揮する。この楽章における一つの理想的な表現方法を究めたものと言っても良いだろう。 第3楽章は甘いアンダンテであるが、テンポという点では、この楽章がもっとも特徴的で、平均的なものよりゆったりと流れる。しかし、音楽の弛緩がないように、旋律線の呼吸の持続性は、前後との関連性を維持し、音楽的な充足に満たされている。クライマックスではヴィトの熱血的な一面を強く感じさせてくれる。 第4楽章は平均的なテンポ。現在ではもう少し早めのテンポを取る指揮者が多いかもしれない。ここでは、ヴィトはホールトーンの効果を活かした打楽器の意味深な響きを引き出し、そこに焦点をあてるように周囲の音楽を形成した感がある。この楽章では、2度のハンマーが衝撃的に打たれることになるが、そこに向けて楽曲を高めていくという手法は一般的なものとはいえ、ヴィトの演奏は、その演出のバランスが良く、あざとすぎず、さりとて熱も失わずという点をよく突いている。またチェレスタのような楽器にも、情感を存分に感じさせる細かい演出を求めているのも、発色性の良さであり、全体の中でよく咀嚼されたものとなっている。 数あるマーラーの第6交響曲の録音の中でも、特に成功したものの一枚であると思う。 |
|
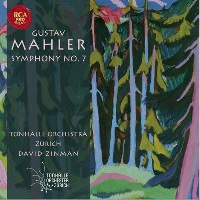 |
交響曲 第7番「夜の歌」 ジンマン指揮 チュリッヒ・トーンハレ管弦楽団 レビュー日:2009.11.7 |
| ★★★★★ 第3楽章に「夜の森の世界」を聴く
ジンマン指揮によるチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団によるマーラー・シリーズの1枚。2008年録音。このコンビはベーレンライター版によるベートーヴェンの交響曲全集を録音したころから注目度が高まってきたが、このマーラーのシリーズもレベルが高く、オーケストラの技術も一段と高まっているように思う。 さて、私はマーラーの交響曲の中では第6番とこの第7番が好きである。どちらも純粋器楽のための交響曲で、合唱や声楽が差し挟まれる作品と違い、マーラーの性質が真っ直ぐに表現されているように思えるし、なにより音楽そのものとしての魅力が凝縮した作品だと思う。第6番が劇性を表出し尽したのに対し、この第7番は「夜の歌」の標題の通り、不安の中にもどこかしら安寧を感じる不思議さが魅力だ。 ジンマンの演奏はきわめて誠実で、王道を歩む。シンフォニックな響きは多層的で、旋律の膨らみをよく活かしている。一方で過度な装飾には至らず、滋味のある響きがこれを支えている。 この交響曲は第2楽章、それと第4楽章が「夜曲」と称されていて、マンドリンの音色など印象的だが、私がこの演奏を聴いたとき、「この第3楽章こそ夜曲ではないのか?」との印象を持った。これは「森の夜曲」である。自然の森。昼の間に光合成を終えた木々が葉が閉じ、夜露をきらめかせる中、夜の生き物たちが「気配」となってうごめいている。聴き手はその森閑たる闇を導かれて歩いていく。様々な気配は時に不気味さを伴うが、全体として森はひとつの生き物の様に静かにしかしダイナミックな活動をやめることがない。 ジンマンの演奏を聴いて、そんなイメージが沸いた。現れては消えるような儚い音色とときおり明瞭さを見せる旋律の配置が不思議な働き掛けをしたようである。暖かさを宿しながらも、自然への畏怖と賛歌に満ちており、この交響曲の1つの醍醐味だと感じられた。 |
|
 |
交響曲 第7番「夜の歌」 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 レビュー日:2014.3.28 |
| ★★★★★ シャープな感性で、颯爽と奏でられたマーラーの第7交響曲
アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)指揮、シドニー交響楽団の演奏によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲第7番 ホ短調 「夜の歌」。2011年の録音。「ライヴ録音」となっているが、「ライヴ音源にセッション録音での手直しを加えたもの」と考えられる。ライヴ特有の雑音等はほとんど目立たたず、演奏上の技術的な綻びも感じないので、セッション録音に近い品質になっている。 私が所有しているのは、シドニー交響楽団の自主制作レーベル “sydneysymphony” によるCDメディア。参考までに、シドニー交響楽団のサイトに問い合わせたところ、CDとダウンロード製品とでは、ソースは同じとのこと。 アシュケナージがシドニー交響楽団の首席指揮者兼アーティスティック・アドヴァイザーに就任したのは2009年で、その後、日本ではExtonレーベルからマーラーの交響曲全曲録音に関するアナウンスがあった。実際に第1番、第5番、大地の歌の3曲についてはリリースされたのだが、後続がなく、計画が途絶えてしまった格好。しかし、前述したように、sydneysymphonyから全曲がCD化されている。 さて、アシュケナージとシドニー交響楽団による第7交響曲の演奏である。アシュケナージにとって、この曲の録音は今回が2度目で、以前チェコフィルハーモニー管弦楽団と2000年に録音したものがあった。基本的なスタイルは、以前の録音と共通。速めのテンポ設定で、ルバートの多用を避け、均質な音楽像を作り上げることに意識を集中させている。この曲の第1楽章は私の大好きな音楽で、演奏によっては様々にロマンティックな表現方法があるのだけれど、アシュケナージのマーラーはそのような演奏とは一線を画した厳しさが漂っている。ただ、そのような凛とした「正しさ」を感じる一方で、重い咆哮や重量感のある響きが少ないため、音色自体は明るいトーンに傾いている。そのため、全体的には「素朴で、流れの良い演奏」という印象になる。ミステリアスな要素は少なく、緊密な構成的整合性を求めたもの、と言っていいだろう。 最も多くの人に受け入れられるのは、後半の2楽章だと思う。第4楽章は、心地よいテンポが、音楽の「緩い」ところを、鮮明に清々しく響かせきったところが見事で、退屈させない。各奏者の力量も秀逸だと思う。シドニー交響楽団は、細やかな艶(つや)という点でヨーロッパの超一流オーケストラに今一歩のところはあるかもしれないが、全体的な機能美は十分だ。わけても、金管の配慮の行き届いた響きには、高度な洗練を感じる。第5楽章が圧巻。俊敏な開放感が爽快で、金管陣の大らかな響き、ティンパニの心地よい呼応と、実に気持ちがいい。録音も適切な距離感が反映されていて、立体感がよく出ている。 前半3楽章は、前述のように、流麗でシェイプアップされたスタイル。私は美しいと思うけれど、これらの楽章に備わっている性格が薄められているとの印象を持たれることも十分考えられる。特に第2楽章などは、人によっては「味気ない」という感想を持つかもしれない。濃厚な絢爛さが遠ざけられ、機能的な美観と、全体的なスタイリッシュなフォルムの保持に重点が置かれている。 以上、総合すると、線的な感覚で、スマートに磨き上げたマーラーの第7交響曲といった印象。この曲は演奏によって様々にその様相を変える音楽であるが、それらの中で、一つの価値観を集約させた演奏として、指標となるものと言えるだろう。 |
|
 |
交響曲 第7番「夜の歌」 ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 レビュー日:2014.8.20 |
| ★★★★★ マーラーの交響曲第7番の解釈を一新した画期的録音
ミヒャエル・ギ-レン(Michael Gielen 1927-)指揮、南西ドイツ放送交響楽団の演奏で、マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の 交響曲 第7番 ホ短調「夜の歌」。1993年録音。 マーラーの交響曲の中で、第7番という作品は、長らく日陰の存在だった。いや、今もって、人気曲とは言い難いだろう。私の父は、マーラーの交響曲を聴き始めたころの私に向かって「マーラーはいい。でも第7と第8はダメだ。分裂症の音楽みたいで、全然わからん」と言っていた。その影響のせいか、私も、これらの2曲へのアプローチは遅かった。 それでも、やっと「わかったような」感じがしたのは、知人がカセットテープで貸してくれたショルティ(Sir Georg Solti 1912-1997)の演奏を聴いてからだ。きびきびとしたテンポで、彫像的な金管とティンパニの咆哮に酔った。これはショルティの膂力で、この曲にまつわる「複雑さ」を極力避けたもので、それが私には分かり易く、助かった。 以来いくつかの演奏を聴く様になり、バーンスタインやアバド、それにハイティンクといった人たちの録音を聴き、なんとなくこの曲がわかったようになってきた。特にハイティンク(Bernard Johan Herman Haitink 1929-)の1982年の録音に出会ってからは、私はこの曲の第1楽章の中間部に、夕陽を反射して悠久の時を流れゆく大河の光景を浮かべ、浸ったものだ。 しかし、時代は変わった。 転機といえるのは1994年、ブーレーズ(Pierre Boulez 1925-)とシャイー(Riccardo Chailly 1953-)が相次いで「新解釈」といえる画期的スタイルを示した年だ。そう、彼らは、この作品が、前述の「悠久の時の大河」の様な、ロマン派的、物語的なものではなく、はるかにモダンな、現代音楽への橋渡しをする精緻なプロトタイプを集合させたものであることを示したのである。一気に視界が広がった。私は、難解さを感じていた中間楽章についても、霧が晴れるような思いをし、新鮮な感動を覚えながら、彼らの音楽に接した。そして、この音楽に対するイメージも一新した。 ところがである、私が転機と思っていた二つの録音の前に、すでにこれを証明する録音があったのだ。それが他ならぬ(ここまで長くてすみません)、当ギーレン盤である。ブーレーズ、シャイーに先んじた1993年の録音。演奏の価値を示す上で、録音年がここまで重要なケースは多くはないだろう。 ギーレンの解釈はまぎれもなく、この音楽が新ウィーン楽派への布石であることを示している。論理的かつ伏線的な声部を細やかに解きほぐし、独立させて扱った上で、その全体像としてモザイク画のように音楽を浮かび上がらせる。特に前半4楽章は、ブーレーズ以上にテンポ設定を厳密にし、ロマン派的な揺らぎを極力制約している。その成果が端的に表れているのが、第4楽章“第2の夜曲”である。録音によっては埋もれがちなマンドリンやグロッケンシュピールの響きを、明瞭に照らし、その音型の受け渡しや変容を緻密に描きだすことで、複層的なタペストリーを形作っていく。また、ハープや、ホルンにも、主題の変容に際して、第2の提示の役割があることがよくわかる。そして、肝心なのは、そのような細部を突き詰めた表現の全体像としての響きが、「音楽的」なものに帰結しているということだ。 これは明らかに画期的な解釈で、それまでのこの交響曲の演奏概念を一気に覆したものといって良い。そもそも、ギーレンは現代音楽を主戦とする指揮者だから、そのような彼ならではの背景が、この作品を解釈する上で、見事に活かされたものだろう。その翌年にブーレーズ、シャイーといった録音が出たために、指揮者のネームヴァリューの差もあって、当盤の存在は目立たなくなってしまったのだが、この作品の演奏史を語る際に、決して外すことのできない名盤であることは間違いない。なお、録音も良好、オーケストラの技術も申し分ない。 |
|
 |
交響曲 第7番「夜の歌」 歌曲集「亡き子を偲ぶ歌」 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 Br: ターフェル レビュー日:2016.12.15 |
| ★★★★★ 浪漫的第7交響曲演奏の一つの究極像を示した録音
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)とフィルハーモニア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲シリーズ、当盤はその第7弾となったもの。1992年録音の2枚組CD。収録内容は以下の通り。 1) 交響曲 第7番 ホ短調「夜の歌」 2) 亡き子を偲ぶ歌 第1曲 いま太陽が燦々と昇ろうとしている(Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n) 第2曲 いま私はわかった。なぜそんな暗い炎を(Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen) 第3曲 おまえたちのおかあさんが戸口から歩み入るとき(Wenn dein Mutterlein) 第4曲 あの子たちは、ただ散歩に出かけただけだ(Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen) 第5曲 こんな嵐の中で(In diesem Wetter!) 「亡き子を偲ぶ歌」のバリトン独唱はブリン・ターフェル(Bryn Terfel 1965-)。現在では世界を代表するバリトン歌手となったターフェルの20代のころの代表的録音の一つだろう。 さて、交響曲第7番「夜の歌」はCD時代に入って、大いにその評価を高めた曲だと言えるだろう。少なくとも、以前はマーラーの諸作の中でも、特に謎めいた、わかりにくい作品だと考えられていた。しかし、90年代に入っていくつかの画期的な録音が出現する。1993年録音のギ-レン(Michael Gielen 1927-)盤、1994年録音のブーレーズ(Pierre Boulez 1925-)盤とシャイー(Riccardo Chailly 1953-)盤がその代表的なものだと考える。私の場合、ブーレーズ、そしてシャイーによって、この曲の多彩な魅力を、始めて味わったという経験を持つ。 時系列的に、その直前にこのシノーポリ盤が存在することになる。だが、私は「新解釈」派としては、前掲の3者の録音であり、このシノーポリ盤は旧解釈の延長線上から逸脱するものではないと思う。ギーレン、ブーレーズ、シャイーが解析的な手法で怜悧に音響を再構築し、リアリズムで音楽に迫ったのに対し、シノーポリは浪漫的な熱を伴った前進性で描いているように感じられ、そういった点で、受け取るニュアンスがこの曲の旧来の録音、例えばバーンスタイン、ハイティンク、ショルティ、クーベリックといった人たちのものに近いからだ。 シノーポリはここで熱気のある演奏を示している。彼の当録音以前のマーラーの録音でいえば、第8交響曲に近いスタイルで、多少のテンポの揺れを伴いながらも、熱い高揚感で音楽を築き上げる。2つの夜曲(第2楽章と第4楽章)から伝わってくる印象も、どこか「熱い夏の夜」といった感じだ。また、終楽章の熱気にあふれた表現は、きわめてテンションが高く、揺れるテンポとあいまって、劇的な音楽効果を導いていく。なるほど、ブーレーズ、シャイーでこの曲に括目した私も、この演奏は、これはこれで面白い。この終楽章の迫力はショルティ以来のもの。 2つの夜曲では、優秀な録音の効果と相まって、各楽器の艶やかな響きが印象的。バズーン、ヴィオラといった楽器の瑞々しい響きが克明に伝わってくるのも魅力である。そのような意味で、ある意味浪漫的な第7交響曲の解釈の一つの到達点と言える。 また、ターフェルの歌唱による「亡き子を偲ぶ歌」も聴きものだ。十分なダイナミックレンジを用い、巧妙なルバートを繰り広げながらも、音楽的な構造に即した安定感がある。シノーポリの指揮によるオーケストラ、特に管楽器の鮮やかな効果も特筆したい。特に第5曲は絶品。 以上のように、交響曲、歌曲とも立派な演奏が収録された内容の濃いアルバムとなっています。 |
|
 |
交響曲 第7番「夜の歌」 ヤンソンス指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2018.3.2 |
| ★★★★☆ 音色は美しいが、リズムに弱含みな要素がある点が気になります
マリス・ヤンソンス(Mariss Jansons 1943-)指揮、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第7番ホ短調「夜の歌」。2016年のライヴ録音。 同じ顔合わせにより、既に第1番~第6番と第8番がリリースされているので、全集完成が間近に迫る一枚といったところ。ヤンソンスは第7番を2000年にオスロ・フィルハーモニー管弦楽団とも録音しているが、私は未聴。 当演奏を聴いた感想であるが、なかなか自分の中でも一つにまとまりにくい。時間を空けて、4回通して聴いてみたのだが、聴いていて「いいな」と思うところはいろいろあるのだけれど、時折なんか気が逸れるようなところがあると言うか、私自身の問題かもしれないと繰り返し聴いてみたわけだが、印象はあまり変わらなかった。 ちなみに、私はこの曲に関しては、ギーレン(Michael Gielen 1927-)、シャイー(Riccardo Chailly 1953-)、ブーレーズ(Pierre Boulez 1925-2016)の3種の録音が特に大好きなので、そういった観点でのレビューになる。 ヤンソンスのアプローチは全般にゆったり目であり、しかし緩急の差は結構ある。クライマックスで、エネルギーをためるように速度を落としたり、あるいは早めたり、そういった振幅はやや大きめだ。これに連れて暖かい音色で呼応するオーケストラの合奏音は美しく、時に耽美を感じさせてくれる。バランスも良好で、例えば第4楽章のマンドリンとヴァイオリンのやり取りのこまやかさなど、本当にきれい。それと、第3楽章も特に美しい演奏の一つと言えるだろう。 その一方で、この演奏は、輪郭を柔らかく覆う傾向が強い。もちろん、そのような音響美を目指すこと自体は、一つのやり方なのだけれど、その結果として、マーラーが楽譜に書き込んだスフォルツァンドの指示は、効果が弱まっていて、そのことが、全体的なリズムへの鋭敏性を弱めた印象につながっている。特にその点で私が気になるのは第1楽章で、ヤンソンスの指揮によって、ある意味浪漫的な美しさは十分に表出しているものの、それを支える駆動部の動きがさほど伝わってこない。 実は、私がこの曲で、ギーレン、シャイー、ブーレーズの録音が好きなのは、この駆動を支える構造を基礎に音楽を築くという明瞭な音楽の質感を聴きとるからで、それに比べると、ヤンソンスの演奏は、確かに美しいのだが、母屋をまず建てて、そのあと、それに合わせて基礎を成した感じで、これが私には若干以上の肌合いの違いを感じさせるのである。 その結果、前述のように「いいな」と思うところがいろいろあっても、それがどこかで途切れるような気持になってしまう。もちろん悪い演奏とまで言うものでもなく、オーケストラの全体的な音色の美しさは出色ものと言ってもいいくらいなのであるが、あるいはヤンソンスはこの曲はどこか得意ではないのかもしれない、という感じが残るのである。 もちろん、まだ4回聴いただけだし、ヤンソンスが素晴らしい指揮者であることは十分承知なのであるが、現時点では、以上踏まえて、星4つの評価にとどめたい。 |
|
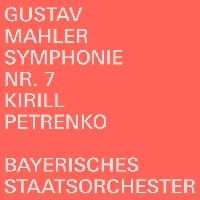 |
交響曲 第7番「夜の歌」 K.ペトレンコ指揮 バイエルン放送交響楽団 レビュー日:2021.11.2 |
| ★★★★☆ クールで精緻なキリル・ペトレンコの「夜の歌」
キリル・ペトレンコ(Kirill Petrenko 1972-)という指揮者の名前を聞くようになったのは比較的最近で、クラシック・フアンの多くは、サイモン・ラトル(Simon Rattle 1955-)の後任として、2019年からベルリン・フィルの首席指揮者・芸術監督となるという報で、突然「そこまでヨーロッパでは評価の高い指揮者だったのか」との驚きとともにその名を再認識した人が多かったと思う。それも仕方のない話で、それまでの彼の録音メディア作品は、ごくわずかなものしか無かったし、そこで取り上げる作品も、メジャーなものとは言い難かったから。 ベルリン・フィル首席指揮者就任のニュースを境に、彼の録音は、ペースを上げてリリースされるようになってきた。ただ、それらは、私の感覚では、比較的高値な感じもして、なんとなく聴きそびれていて、実は、CDとして購入してじっくり聴いたのは、当盤が初めてである。当盤は、バイエルン国立歌劇場が立ち上げた自主レーベル“Bayerische Staatsoper Recordings”の記念すべき第1弾ということで、すでにキリル・ペトレンコという指揮者は、ヨーロッパの主要なオーケストラの節目で招かれるべきステイタスを持つアーティストとなっていることを、あらためて印象付ける。2018年のライヴ録音で、マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第7番「夜の歌」である。私の大好きな曲でもある。 では、聴いた感想である。この曲の解釈は、大きく2分できると考えている。情熱を背景に夜の世界を描いたものと、精緻な書法を明瞭に描き分けたもの。前者の代表が、キリル・ペトレンコの前任であるラトルをはじめ、バーンスタイン (Leonard Bernstein 1918-1990)、アバド(Claudio Abbado 1933-2014)、ヤンソンス(Mariss Jansons 1943-2019)などの録音で、後者の代表が、ブーレーズ(Pierre Boulez 1925-2016)、シャイー(Riccardo Chailly 1953-)、ギーレン(Michael Gielen 1927-2019)、ジンマン(David Zinman 1936-)などの録音である。 それで、このキリル・ペトレンコのスタイルは、はっきりと明瞭に後者側のスタンスである。こまやかな音の調性により、ポリフォニーの効果を、限界を目指した精度で磨き上げ、そのためのテンポ設定を細心の配慮をもって行っている。そうして鳴る音楽は、とにかく鮮明で、くっきりしている。巧いのは、テンポ変化の自然さで、細部に明瞭でありながら、流れが良く、全体がとてもスムーズに進む。第1楽章のエンディングなど、スムーズすぎて、もっとタメが欲しいと感じる人もいるかもしれないが、とにかく方針が徹底しており、余計なことはしない、させないという音造りに感じられる。 この交響曲では、第2楽章と第4楽章に夜曲が配置され、そこでは、様々な楽器が登場するわけだが、当演奏では、それらの楽器の特徴的な音色は、もちろんきちんと鳴っているが、強調されるということはない。あくまで、全体の音響を構成するピースであって、それ以上の主張を慎むことによって、全体の解釈に統一感をもたらしている。これは、前述した同傾向の録音であっても、ジンマンの演奏とは大きく異なる点であり、私は、キリル・ペトレンコという指揮者のきわめてクールな感覚をそこに感じる。 確かに解釈はクールであるが、ここで面白いのは、バイエルン放送交響楽団というオーケストラのサウンドは常に暖かみがあり、結果的に、とてもバランスのとれた味わいが伝わる点である。あるいは、そこまで計算に入れた上での解釈なのだろうか。第3楽章のスケルツォもきわめて落ち着いている。中央部では、多くの演奏がスコアに従った加速を行うが、この演奏はほぼ等速で進んでおり、ここは指揮者の感性を押し通した感がある。ここに劇的な演出を増やす必要はないということだろうか。そこまで、私にはわからないが、特徴を感じる個所だ。 終楽章は速めのテンポで一貫しており、ティンパニの明瞭なリズムとあいまって、気持ちの良い清々しい響きだ。精緻なスコアのトレース作業は、徹底されているが、オーケストラの地の音が音楽的で、結果的に健やかでスタイリッシュな音像に仕上がっている。 最初に述べた通り、この演奏は、マーラーの第7交響曲を解析的な手法で精緻に表現したものであり、指揮者としてのペトレンコは、そのためのテンポの設定、音の強弱にきわめて細かい精度を要求したものだと感じられる。表現性の抑制という点で、好みは分かれるが、かなり尖った演奏で、個人的にはなかなか面白かった。 なお、このアイテムであるが、記念すべきレーベル第1号ということもあって、豪華なブックレットと一体化している。興味のある人にはうれしいのかもしれないが、私の様に多くのCDを収集しているコレクターにとって、スペースを圧迫する仕様は好ましくなく、その点も踏まえると、アイテムとしての価値はやや下がる。 |
|
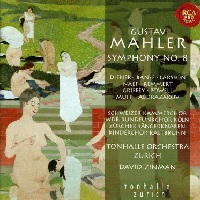 |
交響曲 第8番「一千人の交響曲」 ジンマン指揮 チュリッヒ・トーンハレ管弦楽団 チューリヒ児童合唱団 カルトブルン児童合唱団 スイス室内合唱団 WDR合唱団 S: ディーナー バンゼ ラーション A: ナエフ レンメルト グリフィー Br: パウエル B: アブドラザコフ レビュー日:2010.7.5 |
| ★★★★★ はたしてマーラーの最高傑作か?それはわからないが・・・
マーラーの交響曲第8番「一千人の交響曲」は複数の合唱団、8人の独奏者を必要とする作品だ。私はマーラーの交響曲の中で、この作品が一番苦手である。特に第2部の「ゲーテのファウスト第2部より」はテクストが宗教的だという以上に、その音楽表現の要素がなかなか把握できず、楽しんで聴くには至らなかった。もちろん美しい響きやメロディは散見されるのであるが、音楽としてのもう一つ確固たる何か方向を示すものが欲しくて、聴いていて迷い道に入ってしまったような感じになる。最後の「去り行く一切は比喩に過ぎない」は一体どういうことでこんな壮麗な合唱になるのだろう?ナゾだらけである。マーラーはこの第8交響曲を自賛し、「これまでの私の作品は、すべてこの作品のための序曲に過ぎない」とか言ったそうだけど、それはいくらなんでも違うだろう。 それでも、私がこの曲を聴いたのはショルティの名盤である。デッカの録音技術、豪華な独唱陣によりこの曲の巨大性を見事に表現した録音芸術と呼ぶに相応しいものであった。 しかし、今となっては別のアプローチで聴いてみたい。このジンマンの録音は素晴らしいと思う。いや、今もって私はこの曲を少しでも理解した気になれないのだけれど、この録音によって最初から最後まできちんと聴いたという充足感は得た。 ジンマンの演奏は、この交響曲の細部を克明に描き、徹底して見通しを良くするものだと思う。それはブーレーズもやったのだけれど、ジンマンの方が音に潤いを感じ、耳あたりが良いと思う。この曲は長いので、重要なポイントだ。また、合唱、独唱陣との距離感、パワーバランスが見事。すべてジンマンの手腕なのか、優れた合唱指揮者のサポートがあったのかわからないが、これだけの奏者がいながら音が潰し合うように感じるところがない。第1部の両端の合唱など、実に洗練されている。また、そのバランスは、静かな部分、例えば第2部の木霊の合唱とオーケストラの場面などでも活きていて、存在感があり、しかし果てしないほどの深い闇の森を思わせてくれる。 独唱陣のネーム・ヴァリューはあまりないが、粒ぞろいの好演だ。中でも存在感があるのがマリア崇拝の博士を務めているテノールのアンソニー・ディーン・グリフィー。2枚目の10トラックや16トラックでの広い高音域を自在に間断なく自然な力強さをもって歌う透明な美声は聴きモノといって間違いない。 総じてジンマンのマーラーとして期待に違わない高品質の録音だと思う。 |
|
 |
交響曲 第8番「一千人の交響曲」 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 シドニーフィルハーモニア合唱団 アデレード交響合唱団 西オーストラリア交響楽団合唱団 S: ロビンソン シャグチ マクリヴァー MS: ペツコヴァ キューレン T: オニール Br: アイヒェ B: スネル レビュー日:2012.2.20 |
| ★★★★★ シドニー交響楽団にとって記念碑的と言える録音でしょう
アシュケナージがシドニー交響楽団を指揮してライヴ収録したマーラーの大曲、交響曲第8番「一千人の交響曲」。合唱はシドニーフィルハーモニア合唱団、アデレード交響合唱団、西オーストラリア交響楽団合唱団の3つの合唱団の混合編成。独唱陣は、S: トワイラ・ロビンソン(Twyla Robinson)、マリアーナ・シャグチ(Marina Shaguch)、セイラ・マクリヴァー(Sara Macliver)、MS: ダグマル・ペツコヴァ(Dagmar Peckova)、バーナデット・キューレン(Bernadette Cullen)、T: サイモン・オニール(Simon O'Neill)、Br: マルクス・アイヒェ(Markus Eiche)、B: マーティン・スネル(Martin Snell)。 当ディスクはシドニー交響楽団による自主制作レーベルsydneysymphonyからリリースされたものであるが、現在、日本のExtonレーベルがアシュケナージとシドニー交響楽団による全集録音を進行中としている。既にリリースされた3曲以外もほとんど収録は終了しているらしいが、なぜか発売が遅れており、いまだ発売予定も告知されていないので、私は、第8交響曲については入手可能なこの輸入盤を購入した。おそらく、Extonによる発売も同じ音源によると推測される(この大曲のために何度も録音環境を設定するとは考え難いから)。いくぶん編集は異なるかもしれないが、内容は概ね変わらないとみていいだろう。ちなみに、音源は2010年 2月17日から20日にかけて、シドニー・オペラハウスでライヴ収録されたものが使用されている。 録音状態は良好で、前後の拍手がカットしてあるほか、ほとんど雑音も気にならず、4日間のライヴから適切な箇所が編集された印象だ。 さて、マーラーの第8交響曲は膨大数の演奏者を要する大曲という以上に、構成が複雑で難解な面を有する。私もいままで様々な録音を聴いてきたが、この曲を理解できたとはとても言い難い。なので、そのようなレベルでの感想であることをまずお断りしておく。 アシュケナージのスタイルはいつも通りで、過度な強奏を避け、適度にセーヴされたシンフォニックな音響を作っている。その響きは常に音楽的で、調和に満ちており、安定している。ジンマンのように解像度を上げて解析的にするわけでもなく、どちらかというと古典的なスタイルで、明るい音色で、インテンポを主体として音楽を進行させている。 第1部の二重フーガの扱いが明瞭なのはピアニスト出身の彼らしいスタイルで、該当部分は構造的にもわかりやすいだろう。第2部は序盤の不吉さ、不安さが適度に表出されていて、まずは無難な仕上がり。独唱陣も粒揃いで、足並みを乱さず、折り目正しい音楽になっている(オペラ的には扱われていない)。後半は合唱ともどもヴィヴィッドで活力に満ちた表現が魅力的に映える。従来、マーラー録音に限らず、大曲の録音ではあまり目立たなかったシドニー交響楽団にとって、画期的な新しいレパートリーへの録音であるというだけでなく、一定水準を越えた安定した品質を提供した演奏として、価値のある演奏になっているだろう。 |
|
 |
交響曲 第8番「一千人の交響曲」 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 合唱団 サウスエンド少年合唱団 S: スチューダー ブラーシ ジョー MS: マイヤー 永井和子 T: ルイス Br: アレン B: ゾーティン レビュー日:2016.12.13 |
| ★★★★★ シノーポリには珍しい?とても熱血的な演奏ぶり
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)とフィルハーモニア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)・チクルスの第5弾として、1990年に録音された 交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」。起用された独唱者と合唱団は以下の通り。 ソプラノ: シェリル・ステューダー(Cheryl Studer 1955-) ソプラノ: アンジェラ・マリア・ブラーシ(Angela Maria Blasi 1956-) ソプラノ: スミ・ジョー(Sumi Jo 1962-) メゾ・ソプラノ: ヴァルトラウト・マイヤー(Waltraud Meier 1956-) メゾ・ソプラノ: 永井和子(1955-) テノール: キース・ルイス(Keith Lewis) バリトン: トーマス・アレン(Thomas Allen 1944-) バス: ハンス・ゾーティン(Hans Sotin 1939-) サウスエンド少年合唱団 フィルハーモニア管弦楽団&合唱団 CD2枚に以下のようなindexで収録されている。 【CD1】 第1部賛歌「来よ、創造主なる聖霊よ」 1) 現われたまえ、創造の主、聖霊よ! 2) いと高きにある恵みにて満たしたまえ 3) われらが肉体の脆き弱さに 4) テンポ・プリモ 5) われらが肉の弱きを 6) そが光にてわれらが感ずる心を高めたまえ 7) 現われたまえ、創造の主、聖霊よ! 8) 父なる主に栄光あれ 【CD2】 第2部 ゲーテの「ファウスト」第2部からの終幕の場 1) ポコ・アダージョ 2) ピウ・モッソ 3) 合唱とこだま「森は揺らぎつつ来たり」 4) 法悦の教父「永遠の喜びの炎」 5) 黙想の教父「岩壁の断崖が、私の足もとで」 6) 天使の合唱「霊界の気高いひとりが悪から救われた」・昇天した少年たちの合唱「手と手をたのしく」 7) 若い天使たちの合唱「手から授けられたあのバラの花が」 8) 完成された天使たち「大地の残り屑を担うのは」 9) 若い天使たち「岩の頂に霧のように」 10) マリア崇拝の博士「世界を支配し給う最高の女王よ」 11) 触れることのできないあなたにも 12) 罪の女パリサイ人のあざけりを受けながらも」・サマリアの女「その昔、アブラハムが家畜を」 13) 贖罪の女「たぐいなきおん方、光あふれるおん方」 14) 祝福された少年たち「この人は僕たちよりも大きくなり」・贖罪の女「気高い霊の群がりにとりかこまれて」 15) 栄光の聖母「さあ、いっそう気高い天空へ昇って行きなさい」・マリア崇拝の博士「悔い改むる優しきかたがたよ」 16) 神秘の合唱「すべて無常のものは、ただ影像にすぎない」 マーラーの第8交響曲は、演奏規模が大きく、かついくぶんの難解さのある作品であるが、にもかかわらず現在まで様々な録音が製作されている。それらの録音を聴き、私もいくぶんこの曲がどのようなものであるのか、以前に比べれば分かるようになってきた。中でも1998年録音のギーレン(Michael Gielen 1927-)盤による精緻に解析された美しさはわかり易く、また、その方向性を、最高の録音精度で推し進めたと言える2009年録音のジンマン(David Zinman 1936-)盤は、私にとって、この曲の一つの決定打といえる録音となった。 他方で、一時代前のものとしては、1971年録音のショルティ(Georg Solti 1912-1997)が歴史的録音として広く認知されており、私もその壮麗にして壮大な、ある意味歌劇のようなゴージャスな響きは印象に強く残っている。 さて、このシノーポリの録音であるが、私には、これはショルティの演奏の延長線上にあるものに感じられる。これはやや意外な印象でもある。と言うのは、シノーポリが当録音の前に録音したマーラーの交響曲たちとは、また一風異なるスタイルだからである。 当演奏を形容するとしたら「熱血的」という表現がふさわしいだろう。実際、管弦楽、コーラスとも実によく「鳴る」のである。その全体的な鳴動感がなかなかに素晴らしく、聴き手の気持ちを激しく揺さぶるものとなっている。この時代の他のシノーポリの録音と比べると、テンポは一般的なものに近く、それほど動かさない。むしろ高らかに、大いに歌い上げる豊饒さに表現は集中している。 独唱陣は、特に女声が粒ぞろいで、うってつけの人材を揃えた感がある。男声ではルイスの肌理の細かい美しい歌唱が際立ち、全体の印象に貢献している。 シノーポリの熱いタクトは、とくに第1部、第2部それぞれのフィナーレでそのクライマックスを築き上げる。まあ、これらの個所は、どのような演奏で聴いても、おおむね印象は似通うのであるけれど、それにしてもシノーポリのもたらした演奏効果の圧倒的な性格は、やはりショルティ盤を彷彿とさせる。 当録音で見せるシノーポリの「熱さ」から、彼のこの曲に寄せる感情が伝わってくる。 |
|
 |
交響曲「大地の歌」 ショルティ指揮 シカゴ交響楽団 A: ミントン T: コロ レビュー日:2007.11.3 |
| ★★★★★ 葬列のあとを吹く風のような「大地の歌」
マーラーはことさら死生観や厭世観を作品に反映してきたけれど、その究極点にあると言えるのがこの「大地の歌」ということになる。それにしても、交響曲の概念を様々に解釈したマーラーであるが、男声と女声が代わる代わる独唱するという一つの「形態」を生んだのもマーラーということになるわけで、この「ジャンル」はその後、ツェムリンスキーの「叙情交響曲」に代表され、ショスタコーヴィチの「死者の歌」までやや形を変えながらも受け継がれていくことになる。 マーラーが古代中国の漢詩にどれほどの関心があったのか分からないが、このような重要な作品で用いられていることを考えると、やはり「死生観」のようなものに共鳴するところがあったのではないか。その寂寞とした抽象的な無力感が、音楽という芸術的媒体でここまで通じるというのは、やはりこの交響曲が傑作だからだろう。 ショルティのマーラー録音の中でもこの曲はやや特徴的であり、いつもの明朗な鳴りより、やや一歩さがったところで音楽が形成された感がある。特に終楽章は即物的な音色であり、そこに幽かな情緒を残している。他方、第1楽章は従前のショルティらしさが出ていると思う。とはいえ、全体的にシンフォニックな構成感を優先し、あくまで「歌曲ではなくて交響曲である」というスタンスは保たれていると思う。そこはショルティらしいところだ。二人の独唱者、ミントンとコロは、ショルティの録音にはよく参加しており、感情を若干沈めた歌いぶりはこの演奏にふさわしい。「葬列のあとを吹く風」とはショパンの葬送ソナタの終楽章の形容句だが、この演奏が体現する「大地の歌」もそんな雰囲気を持っている。 弦楽器がゆっくりと鳴りをひそめていく中で、チェレスタの挿入句は風に舞う枯れ葉のようでわびしく物悲しい。 |
|
 |
交響曲「大地の歌」 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 Ms: パーシキヴィ T: スケルトン レビュー日:2011.4.5 |
| ★★★★★ 優秀録音の美点を活かしきった透明な「大地の歌」
私も毎回楽しみにしているアシュケナージとシドニー交響楽団によるマーラーチクルスの第3弾。このたびは「大地の歌」である。独唱は、ステュアート・スケルトンのテノールとリリ・パーシキヴィのメゾ・ソプラノ。録音は2010年。スケルトンはティルソン・トーマス指揮の同曲でも独唱を担ったので、今回が2度目の録音となる。 アシュケナージが大地の歌にひょっとしてたびたび競演しているレイフェルクスを起用してくれないかな、と思っていた。その期待は外れたが(やはり男声と女声の方がいいでしょうね・・)相変わらずクオリティの高いアルバムとなっている。 まず録音の鮮明さが素晴らしい。第1楽章「大地の哀愁に寄せる酒の歌」冒頭のオーケストラのサウンドを捕らえる精度の高さ。距離感もほどよく、いかにも完成されたサウンド。また、オーケストラの技量も負けていない。アシュケナージが首席指揮者兼アーティスティック・アドバイザーに就任して以来、この顔合わせの録音をすべて聴いてきたが、どんどん上手くなっているように思う。それは技術的な面だけでなく、指揮者の意図をより敏感に感じ取り、細かく音に反映できるようになっている。それに加えてこの美録音である。このような「大地の歌」が聴けるのは音楽フアン冥利というものだろう。 私の気に入った箇所を挙げていくと、まずは、第3楽章「青春について」。全曲中もっとも短い楽章だけれどもいかにも東洋的な五音音階を用いている。その五音音階を奏でる木管とバックのハーモニーのブレンドの美しさが見事。スケルトンの声も麗しい爽快さがあって、瑞々しい。同様に第5楽章「春に酔える者」も良い。適当な距離感がありながら、チャーミングで麗しい。 そして、大地の歌の場合、演奏時間にして全曲の半分相当を占める第6楽章「告別」が重要だ。私は以前、クレンペラーの演奏でこの曲に親しんだ。メゾソプラノはルートヴィヒという歴史的名盤だが、それは低弦の咆哮が凄まじく、強烈なインパクトを残したものだ。アシュケナージの演奏はもちろんクレンペラーとは大きく異なる。そこまで感情を強く込めず、透明な音色で、今まで聴いたものの中ではシノーポリに近い。ここでも録音の鮮明さがやはり強力。ハ短調の楽曲特有の真面目な深刻さが表出する一方で、やや抑制されながらも、輪郭をくっきり浮き立たせた管弦楽のソノリティーは純度が高く、結晶化した美しさを誇っている。管弦楽による対位法的展開部も一つ一つの音色の絶対的な美しさを礎に、品のある歌を伴っている。 全曲の末尾に聴こえるチェレスタが、忘れられた風景を一瞬想起させるように消えていくのが、はかなく美しい。 |
|
 |
交響曲「大地の歌」 ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 Ms: カリッシュ T: イェルザレム レビュー日:2014.12.19 |
| ★★★★★ 10年のインターバルを持つ録音
ドイツの指揮者ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-)は、1988年から2003年にかけて、南西ドイツ放送響とマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲全集を録音し、これはBox-setとなって、輸入盤が入手可能となっているが、なぜか「大地の歌」はこの全集に組み込まれなかった。「大地の歌」を「歌曲」と考える向きもあるので、それに従ったのかもしれない。しかし、全集録音の間に、「大地の歌」についても収録が行われており、それが当盤ということになる。 しかし、当盤には一つ、他にはない特徴がある。「大地の歌」は全6楽章からなり、男声歌唱による第1、第3、第5楽章と、女声歌唱による第2、第4、第6楽章が交互に配列しているのだが、当盤では前者を1992年、後者2002年に録音しているのだ。じつに10年のインターバルを設けて一つの交響曲が録音されている。ちなみに当盤がリリースされたのは、さらに月日を費やした2009年である。 この背景に何があったのか、わからないが、起用歌手の問題というのが考えられる。当初は女声にソプラノのゾッフェル(Doris Soffel 1948)が起用されるとの案もあったらしい。最終的に、当録音は、メゾソプラノにコルネリア・カリッシュ(Cornelia Kallisch 1955-)、テノールにジークフリート・イェルザレム(Siegfried Jerusalem 1940-)を配して録音された。とはいえ、カリッシュは、ギーレンのマーラーの全集において、1996年録音の第2番、1997年録音の第3番でもソリストとして起用されていたくらいだから、いずれにしても2002年まで録音がずれこんだ理由とはなりにくい。何か、周囲にはあずかり知らぬマネージメント上の問題など、音楽とは直接には関係のない理由があったのかもしれない。 いずれにしても、私たちは成果物であるメディアを通して、録音を聴くのみである。この「大地の歌」で、ギーレンは、他の交響曲と同様の手法で音楽を作っている。すなわち、きわめて精緻で、ロマン派以後の音楽~新ウィーン楽派の肌合いに通じる繊細な音響の構築である。一つ一つの微細な音符を拾いつくし、モザイク画のようにして、全体を浮かび上がらせる。歌手たちも、歌曲として朗々と歌い尽くすスタイルではなく、一種のリミッタの存在の中で、細やかに歌唱を行っているという印象。 そのため、例えば第2楽章はふきすさぶ風の中を進むような音楽に思えるし、第6楽章での強奏は、全体的な音圧と言うより、より内省的な強靭さを導く様な表現になっている。二人の歌手もギーレンのスタイルに合致し、明晰な印象を保つ歌唱。この曲は、演奏によっては濃厚な不安感(生きることの心細さ)が宿るのであるが、本演奏は、そのようなエモーショナルなものより、現代的で感覚的に押し通したような感触がある。 人によっては物足りなさを感じさせるかもしれないが、聴きやすく、特に管弦楽の構造を把握する見通しの良さという点で、特徴のある録音となっている。 |
|
 |
交響曲「大地の歌」 シノーポリ指揮 ドレスデン国立管弦楽団 Ms: フェルミリオン T: ルイス レビュー日:2016.12.20 |
| ★★★★★ いつしか心を動かされているシノーポリの大地の歌
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)指揮、シュターツカペレ・ドレスデンによるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲「大地の歌」。独唱はメゾ・ソプラノがイリス・フェルミリオン(Iris Vermillion 1960-)、テノールがキース・ルイス(Keith Lewis)。1996年の録音。 シノーポリは、1985年から1994年にかけて、マーラーの番号付き交響曲全10曲を録音しており、その2年後にオーケストラを代えて、当盤が録音されたことになる。結果として、全集中、当曲のみ別のオーケストラが担っている形となった。 マーラーは、第8交響曲で生の讃歌を歌い上げた後、大地の歌、第9交響曲、未完の第10交響曲と、死のイメージと切り離せない作品を書いた。大地の歌の6つの楽章は、李白、銭起、孟浩然、王維らの古典漢詩からテキストを得、死生観を織り交ぜながら、背景にある偉大な自然の力を歌い上げている。 シノーポリの解釈は、生死にまつわる吐露というより、自然への思い、畏怖を歌い上げた印象が強い。全般にオーケストラの輝かしい音色が素晴らしく、オーボエをはじめとする木管楽器の透明な、それこそ風の舞う中をまっすぐに射す光を思わせる音が印象的で、歌唱との美しい交錯が見られる。 テノールのルイスは、シノーポリが録音したマーラーの第8交響曲でも独唱者を務めたが、肌理が細かいと言うか、なめらかでゴツゴツしたところのないしなやかな歌唱を示す。より野太い声を求める人もいつかもしれないが、当演奏では、シノーポリが引き出すオーケストラ・サウンドとの間の相性が良く、楽器との音の掛け合いが自然で、とてもしっくり行く。まとまりの良い演奏と言おうか。 メゾ・ソプラノのフェルミリオンも悪くはない。最後の告別など、例えば、ルートヴィヒ(Christa Ludwig 1928-)の歌唱になじんだ人には、淡すぎるように聴こえるところもあるかもしれない。しかし、何度も聴いていると、この淡さ、儚さが、この終曲の雰囲気になかなかに良くなじむ。白雲無盡時(白雲は果てることなく流れてゆく)で終わる最後の雰囲気も、どこか夕映えの味わいをともなって、静かに秋の空を見つめているように、幕が降りていくようだ。なかなか感動的だ。 仕上がりはマイルドな味わいながら、存外な深みを感じさせてくれる名演だ。 |
|
 |
交響曲「大地の歌」 ヨッフム指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 MS: メリマン T: ヘフリガー レビュー日:2018.5.28 |
| ★★★★★ ヨッフムが唯一録音に取り上げたマーラーの楽曲
ヨッフム(Eugen Jochum 1902-1987)指揮、コンセルトヘボウ管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲「大地の歌」。独唱者は、メゾソプラノがナン・メリマン(Nan Merriman 1920-2012)、テノールがエルンスト・ヘフリガー(Ernst Haefliger 1919-2007)で、1963年の録音。 ブルックナー指揮者として広く名を知られたヨッフムであるが、マーラーの作品で録音にとりあげた楽曲は、私の知る限り「大地の歌」しかない。ブルックナーとマーラーは、いずれもロマン派に大規模な交響曲を書いた人物として並び称されることが多いが、ヨッフムの時代にこれらの二人の作品の双方を積極的に取り上げた大指揮者というと、クーベリック(Rafael Kubelik 1914-1996)、カラヤン(Herbert von Karajan 1908-1989)、ショルティ(Georg Solti 1912-1997)、クレンペラー(Otto Klemperer 1885-1973)といったところが挙げられるが、それほど多くはなく、取り組むとしてもどちらか一方の作曲家に大きく比重が偏ったも場合がもっぱらといって良いと思う。 ヨッフムは、そういった点で、典型的なブルックナー振りだったから、まず、そんなヨッフムがマーラーで唯一取り組んだのが「大地の歌」であった、という点に注目される。これは、同様にブルックナーをよく取り上げたフルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler 1886-1954)やベーム(Karl Bohm 1894-1981)が、マーラーの交響曲を振らないにもかかわらず、その管弦楽伴奏付歌曲についてはレパートリーとしていたことにも重なる印象である。彼らにとって、マーラーの作曲家性が真に発揮された分野が、独唱と管弦楽による作品であったと考えられたのではないだろうか。ただ、そのマーラーの作品群内における評価軸と、ブルックナーとマーラーの両者の作品を比較する際の評価軸の相関が、どのようなものであるのか、私にはよくわからない。ただ、傾向としては、とても面白く、興味深いものでもある。 そんなヨッフムの「大地の歌」であるが、私はこれが素晴らしい名演だと思っている。なんといっても、この作曲家の作品に歴史上様々な名演を成し遂げてきたコンセルトヘボウ管弦楽団の勇壮な響きが素晴らしい。ヨッフムは、ここではブルックナーに対したときより、ストレートな切り口でインタンポに近いアプローチを見せるが、コンセルトヘボウの響きは立体的な彫像性に溢れ、輝かしく、要所の締まった、凛々しい響きを貫いてこれに応える。その凛々しさは、ヨッフムの知的なドライヴは万全に補完するばかりでなく、例えば第2楽章の「秋に孤独な者」な第6楽章の「告別」における木管のソロが醸し出す情緒に、蒸留されたような透明感とコクを感じさせてくれるのである。 二人の独唱者については、やはりヘフリガーの声量豊かなパフォーマンスが圧巻で、この楽曲が描く世界観の大きさを感じさせてくれる。それに比べると、メリマンはやや細身な声であり、これを補うように強いビブラートを使用するところで好悪を分けるかもしれないが、終楽章の「告別」では、それゆえの、生きること、そして、生を受けた大地からの離別するときを感じることの儚さが、妙に胸に迫る効果を出しているように思う。 いずれにしても、この録音だけ聴くと、「これほどの演奏が出来たのに、なぜヨッフムはマーラーの他の交響曲を録音しなかったのだろう」と思わずにいられないが、そこは芸術家本人にしか知れない鋭敏で感覚的なもの、あるいは論理的なものがあったのかもしれない。それは、今の私には、あれこれ推測して、思いを巡らすことしかできないが。それにしても、この録音、見事です。1963年という時期を考えると、録音技術的な面でも、レベルはとても高いでしょう。 |
|
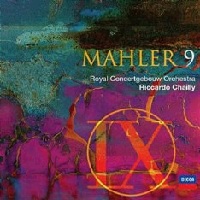 |
交響曲 第9番 シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2005.1.1 |
| ★★★★★ なんと美しいマーラーの第9!
第4楽章は長大で崇高なアダージョ。ブルーノ・ワルターは、この楽章を「青空にとけてゆく白雲」と語った。凛とした美しさに酔いたい名曲だ。だがこの曲はクラシック初心者向けの曲ではないだろう。 マーラーの葛藤と絶望、苦悩を突き抜けたベートーヴェンが歓喜に至ったのに対し、マーラーが辿りついたのは「生は暗く、死もまた暗い」という枯淡の彼岸である。そしてこの交響曲はそんな生の突き詰められた結節点に存在する。 シャイー&コンセルトヘボウの黄金コンビのマーラー・チクルスの最後を飾る録音となったが、ふさわしい美演だ。透明かつ耽美的なマーラー。28分以上かけた壮大なアダージョ・フィナーレは速いブーレーズ版より7分も長い。それでいて持続する緊張感があり,厭世的,耽美的な深みがゆっくりと増していく。録音もすごくいい。 マーラーの第9だから、とひたすら暗く重く演奏するのが主流と思うが、シャイーのマーラー像は若干違う。聴き手はリフレッシュさせられるだろう。その美しい音色とサウンドが暗い夜空に、満点の星空を描き出している。 ちなみにウディ・アレンの「夫たち、妻たち」、ゴダールの「マリア」などでこの曲が使われている。 |
|
 |
交響曲 第9番 ジンマン指揮 チュリッヒ・トーンハレ管弦楽団 レビュー日:2010.8.25 |
| ★★★★★ マーラー生誕150年になる2010年に存在感ある全集が完結
デイヴィッド・ジンマンとチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団によるクオリティの高いマーラーの交響曲全集が、2009年録音のこの第9番でひとまず完結したことになる。マーラー生誕150周年にあたる2010年のリリースも、このシリーズが順調に進行したことを物語る。また、このシリーズのために、RCAレーベルが元デッカの優秀な録音スタッフを招聘したことも、レーベルが「本腰で」取り組んだことを示しているだろう。 私は、いまの時点で、このシリーズの全部を聴いたわけではないけれど、聴いたものはいずれも見通しの良い明るさと、楽器の混濁のないハーモニーが印象的で、オーケストラの力量も含めて認識を新たにすることとなった。 この第9番も素晴らしい内容。第1楽章の厳かな冒頭、ちょっと暗く、だけど暖かい情感を宿す楽想を、弦のグラデーションが実に巧妙に再現してくれる。テンポは穏当だが、部分的にタメや揺れを利かすあたりにマーラーの濃密なロマンティシズムを感じさせる。これはやり過ぎてはいけないのだけれど、ジンマンのタメは「ここぞ」という時にのみ放たれる。そのためエネルギーの蓄積と放散の過程が、音楽のクライマックスに合致して心地よい。金管のファンフアーレは肌理が細かく、精密だが冷たい音にならないのが良い。絶え間なく揺れる振動に沿って、きれいに吹かれている。 中間2楽章も鮮明で分かり易い。木管の透明な音色に録音技術の高さを感じる。くっきりと階層分けのできているサウンドが、シンフォニックな豊かさに結びついている。第3楽章の短いが決然としたエンディングは陰影を際立てていて印象に残る。 終楽章の荘重なアダージョも弦楽器陣のサウンドが豊穣に広がっており、その上に築かれる合奏は立派な恰幅があり、頼もしい。静かに消え行く最後も淡い余韻が残る。 録音・演奏ともに秀でた全集の末尾を飾るに相応しいディスク。今後も、他のマーラーの楽曲を継続してリリースしてほしいと思う。 |
|
 |
交響曲 第9番 アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 レビュー日:2014.4.1 |
| ★★★★★ 暖かい「救済」の感覚に満ちているマーラーの第9交響曲
アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)指揮、シドニー交響楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲 第9番 ニ長調。2011年の録音。 アシュケナージがシドニー交響楽団の首席指揮者兼アーティスティック・アドヴァイザーに就任したのは2009年だったが、すぐにシドニー交響楽団との記念碑的イベントとして、マーラーの全曲演奏及び録音に関するアナウンスがあった。そして、マーラーの没後100年にあたる2011年までに録音はすべて終了した(当第9番の公演は、100年目の命日にあたる5月18日に行なわれた)。しかし、現在までのところ、一部の曲を除いて、CDメディアは、sydneysymphonyからの発売のみとなっている。 さて、当初この企画が広報されたとき、アシュケナージがインタビューで、特に「第9番を振ることを楽しみにしている」とコメントしていたことが記憶に残っている。アシュケナージは2002年にチェコフィルハーモニー管弦楽団とこの曲を録音している。マーラーの交響曲では、初めて録音する曲もいろいろあったにもかかわらず、すでに録音のある「第9番」を真っ先に挙げるところを見ると、アシュケナージにとって、この曲は特別のもののようだ。 また、別のところでアシュケナージは、この交響曲について、こんなコメントをしている。「それは暗闇と光明を越えたなにかです。もう一つの世界、存在と感覚のもう一つのあり方へと導くものです。最後のヴィオラとともに消えゆく瞬間。それは、全ての重さをもったものが、宇宙の果てに消えてゆくときです」 このコメントからは、命の果つる時を連想するが、実際、マーラーがこの音楽に秘めたのは、生との告別であった。自分の余命が長くないことを知りながら、マーラーは3つの傑作を世に遺した。すなわち「大地の歌」と「交響曲第9番」、そして未完に終わった「交響曲第10番のアダージョ」。しかし、この3曲の中で、第9番だけが、その末尾に不思議な安らぎと暖かさを覚える。アシュケナージがこの交響曲を演奏することで伝えたかったのは、ラストに込められた優しい救済の安寧であったに違いない。 以前、アシュケナージがチェコフィルと録音した同曲の演奏と比べて、このシドニー交響楽団との演奏は、ややテンポをスローに落とし、じっくりした音楽を練り上げている。そのため、旧録音がCD1枚に収まったものが、当録音は収録にCD2枚を要するようになった。この音楽に対する彼の考え方が変化したのだろう。全般に早めのテンポをとることが多いアシュケナージのマーラーにあって、ちょっと違ったスタンスを感じさせる。 第1楽章から豊饒な暖かさのあるサウンドが作られている。配慮の行き届いたバランスで、管弦楽が鳴り、金管のファンファーレも、調和を重んじながらも、明瞭に響く。木管、特にピッコロを印象的に演出する味付けがあり、この音楽にアクセントを与えている。中間楽章のクールな活力と跳躍力は鮮やかで、どこかシニカルなところを感じる興奮は、マーラーの音楽の一面を的確に切り取っているだろう。荘厳なフィナーレが実に美しい。葬送の音楽という性格を持ちながらも、内部にじっくりと熱を溜めこむように進展し、大きなエネルギーを含むうねりを作り出す。この終楽章のスタンスは、特に旧録音と印象の異なるところだと思う。 アシュケナージがシドニー交響楽団と録音した一連のマーラーの白眉といえる名演になったと思う。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第9番 ハルトマン アダージョ(交響曲 第2番) ドホナ-ニ指揮 クリ-ヴランド管弦楽団 レビュー日:2015.2.20 |
| ★★★★★ 個人的に、マーラーの第9交響曲の決定的録音と思っています
ドホナ-ニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)指揮、クリ-ヴランド管弦楽団の演奏で、以下の2曲を収録。 1) マーラー(Gustav Mahler 1860-1911)交響曲 第9番 ニ長調 2) ハルトマン(Karl Amadeus Hartmann 1905-1963) 交響曲 第2番 「アダージョ」 1)は1997年、2)は1994年の録音。 名盤である。 ドホナーニという指揮者が、世界でどのように評価されているか、私は詳しくは知らないが、ワーグナー(Richard Wagner 1813-1883)の「ニーベルングの指輪」録音企画が、その素晴らしい内容にもかかわらず、最初の2作を終了した時点で打ち切られたことや、再発売盤がそれほど多くないことを考えると、その実力は的確な評価を受けていないのではないか?と危惧してしまう。 この素晴らしいアルバムも、一度発売されたきりで、その後、再発売されたという話を聞かない。なぜだろう。 私が、これほどまでに思うのは、この録音を聴いて、いままで感じなかった様々な感慨を、マーラーの第9交響曲から受け取ったからである。今もって、この曲に関しては、私のベストはこのドホナーニ盤だ。 ドホナーニはオーケストラの機能美を、とことんまで追求し、恐ろしいまでに怜悧な感覚でこの作品を磨き上げた。この曲が持つ不安や悲劇と言った要素は、極限まで緊張を高める方法で伝えられる。クライマックスは衝撃的で、鮮明な切り口を見せる一方で、瞬時に訪れる静寂は、静謐で透明な安らぎに満たされる。それは綿密に設計した上で繰り返し行われる臨死体験のように。 これは主に両端楽章の印象だ。その広大さに私は思わず身を竦(すく)めるが、この演奏の成功の主因は実は中間楽章にあると思う。両端楽章は様々な方法論が可能だし、どのようにアプローチしても良く響くうまく出来た音楽だ。それに比べて中間2楽章は難しい。やりようによっては、突飛になったり、妙におどけた雰囲気になったりする。ドホナーニ盤はこの中間2楽章の処理が絶妙で、非常にコンパクトに、かつ全体の構造が求心力をもってまとめられる。すべての音が的確な場所に収まっていく心地よさに満ちており、力強いが、聴き疲れとも無縁である。 以上をもって、今なお、私はこのドホナーニのマーラーの第9交響曲を、決定的とい形容が相応しい名録音だと考える。 なお、ハルトマンのあまり聴く機会のない単一楽章の交響曲が収録されている。この作品は、ハルトマンが、戦前の反ナチスから共産主義思想に共鳴した組曲「新しい命」を改変し、交響曲に練り直したもの。やや朴訥としたところがありながら、和やかさのある主題を中心に進む音楽だ。ドホナーニの優れた手腕で聴けるのが嬉しい。 |
|
 |
交響曲 第9番 シノーポリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 レビュー日:2016.12.16 |
| ★★★★★ 濃厚な黄昏の気配がたちこめるマーラーの第9
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)とフィルハーモニア管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲シリーズ第8弾であった1993年録音の「交響曲 第9番 ニ長調」。本アルバムでは、細かくindexを振られて収録されており、参考までに記載すると以下の通り。 【CD1】 第1楽章 1) Andante Comodo / 2) いくらか活発に / 3) (ホルン) / 4) 激怒して Allegro Risoluto / 5) (ブラス) / 6) 感動して / 7) 最初のように / 8) 突然意味深長に遅く 第2楽章 9) ゆるやかなレントラーふうのテンポで / 10) Poco piu mosso subito(Tempo II) / 11) Tempo III 12) A tempo II / 13) Tempo I / 14) Tempo II / 15) Tempo I.subito 【CD2】 第3楽章 1) Allegro assai.極めて反抗的に / 2) L’istesso tempo / 3) Sempre l’istesso tempo / 4) / L’istesso tempo / 5) (クラリネット) / 6) Tempo I.subito / 7) Piu stretto 第4楽章 8) Adagio.極めてゆるやかに、控えめにならずに / 9) またもや突然ゆるやかに(最初のように)、いささかためらって / 10) Molto adagio subito / 11) a tempo(Molto Adagio) / 12) 終始音を充分に保って / 13) 流れるように、急がず徹底的に / 14) Tempo I.Molto adagio / 15) Adagissimo マーラーの第9交響曲は死を描いた作品と言われる。アンダンテでゆっくりとはじまり、締めくくりはアダージョで静かに止まる。マーラーはこのあと第10交響曲の第1楽章までを完成させて、この世から去ることとなるが、告別のメッセージは第9交響曲に詰まっている。名作とされる所以である。シノーポリのシリーズでは、第3番を最後に残しておいて、「一つ前に」録音された。この交響曲が、演奏者たちの精神に与える影響は相当大きいような気がする。そういった点で、最後の録音は別の曲に譲った方がいいように思う。 この交響曲を聴く場合、やはり両端楽章に聴き手は集中するだろう。私ももちろんこの両端楽章が恐ろしいほど美しい音楽に聴こえる。だが、この楽章は、わりとどのような演奏でもうまく行くのである。それぐらいに曲が「よく出来て」いる。 というわけで、全体の成功は、中間の2楽章でマーラーが放った不思議な(ブラックな?)ユーモアをどのように扱うかによると思う。私がこの点でいちばん見事だと思っているのは、ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)が1997年に録音したものである。それに次いでジンマン(David Zinman 1936-)の2009年の録音、だろうか。彼らはいずれも、鮮明なテクスチュアで、明確な音像を打ち出した。 一方でシノーポリは熱っぽい響きを聴かせる。この曲全体として、シノーポリは熱にうなされるような「うねり」を感じさせる表現をもちいていて、その中で、この中間楽章も役割を与えられている。全般に音の強弱のダイナミクスというより、厚みのある表現を持続させることで、濃厚な黄昏の時間が演出されており、これもまた一興と思える演奏だ。 終楽章は黄金の夕暮れ、そして日没、闇の訪れというシーンを思い浮かべる。それは、告別の句を十分に吐露することのできたのちの終末のように思える。 |
|
 |
マーラー 交響曲 第9番 R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 シノーポリ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン レビュー日:2020.2.14 |
| ★★★★☆ 悪くないが、旧録音と比較すると、指揮者の主張を、やわらげた雰囲気です
シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)指揮、シュターツカペレ・ドレスデンの演奏で、以下の2作品を収録したアルバム。 1) マーラー(Gustav Mahler 1860-1911) 交響曲 第9番 ニ長調 2) R.シュトラウス(Richard Strauss 1864-1949) 交響詩「死と変容」 op.24 1)は1997年、2)は2001年のライヴ録音。2枚目のCDにマーラーの第4楽章と「死と変容」が収録された構成。いずれもライヴ録音。 この「死と変容」が演奏された年に、シノーポリは指揮台で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。結果論ではあるが、録音年に目をやると、いやでもあのニュースが想起されてくる。 それはともかく、当盤に関することを書こう。 シノーポリは、当演奏の前に、フィルハーモニア管弦楽団を指揮してマーラーの交響曲全集を録音していたので、当盤は第9番の再録音という形になるが、ここで聴かれる演奏はだいぶスタイルが異なる。シノーポリはもともと、同じ楽曲でも、大きく解釈の異なるアプローチをするタイプだったので、それは別に普通のことだろう。 ただ、私の場合、フィルハーモニア管弦楽団との録音がとても気に入っていた。それは「熱さ」とともに、「鋭さ」があり、かつオーケストラ全体の鳴動感とでも言うべきものが感じられるもので、シノーポリならではのマーラーだと思う。 それに比べると、当盤で聴くマーラーの印象は、ムーディーと表現するとなんか変だろうか。とにかく先の録音であったシノーポリならではの「尖り」が削られて、ゆったりと地ならしされてしまったように感じる。いや、それでもいいのである。悪いと言うわけではない。ただ、このマーラーの第9番という作品、ある程度の指揮者とある程度のオーケストラが演奏すれば、第1楽章と第4楽章は、必ずうまく行くのである(と私は思っている)。失敗なし。世の中には、そういう音楽があって、例えばブルックナーの第7交響曲の第1楽章と第2楽章なんかも、私はどんな演奏で聴いても感動するのである。それは、私の感受性の問題と言われれば、それまでなのだが。 さて、というわけで、マーラーの第9交響曲を、「どこで」評価に差を付けるか、となると、私の場合、どうしても中間2楽章の処理に気が向くのであるが、シノーポリは全4楽章をオーケストラの豊かな中音域にゆだねて、ゆったりと音楽を流すのだが、どうもここが私には旧録音の方がしっくり行く。この中間2楽章では、やはり間延びは警戒されるべきであり、当録音では、やはり弛緩を感じるところが残る。私が、この中間2楽章の運びで一番気に入っているのは、ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)とクリーヴランド管弦楽団の録音である。機会があれば、ぜひ一聴をオススメしたい。 ただ、当盤のマーラーは、比較の上ではそういう感想となるが、もちろん悪くない。特に両端楽章のオーケストラのまろやかな音色は、陶酔度が高く、聴き手をマーラーの世界へ誘う力は強いと思う。 R.シュトラウスも同傾向で、とてもゆったりとしたテンポ設定で、黄昏を感じさせる音楽が流れていく。それは、人肌の暖かさを感じさせるもので、居心地が良い。 |
|
 |
交響曲 第9番 ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2020.3.3 |
| ★★★★☆ ラトルならではの情熱的なマーラーです
ラトル(Simon Rattle 1955-)指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の「交響曲 第9番 ニ長調」。2007年のライヴ録音。CD2枚組で、1枚目に第1楽章と第2楽章、2枚目に第3楽章と第4楽章が収録されている。 ラトルの個性が強く打ち出された演奏。マーラーの第9交響曲は、最終楽章の末尾に「死に絶えるように」の指示があることもあって、「死」や「告別」のイメージと分け隔てることは難しいが、このラトルの演奏は異なった印象をもたらす。一言で言うと「威勢が良い」。活力に溢れていて雄弁。終楽章も、まだまだ生きる気満々といった塩梅で、なかなかにユニークである。 これらの印象は、ラトルの楽譜指示以上に踏み込んだ表現によって達せられる。内声部をつかさどる弦の表出、即興的とも言えるアゴーギグ、濃厚なカンタービレ、幅広いダイナミックレンジ。それらの演出力が、様々に発色性を高め、時間軸にともなう濃淡の変化が大きくなり、それらが生命力として聴き手に伝わってくる。全曲の演奏時間が83分というのは、ほぼ平均的であるが、内的な伸縮が激しいので、聴いているときは早く感じる部分が多いだろう。 楽器の音色も様々な演出を感じさせる。木管の鋭い音色やハープの強調はわかりやすいところだろう。第2楽章は舞曲の要素を様々に感じさせる。情熱的な表現が随所に感じられる。第3楽章は熱血的といって良く、エネルギーに満ちたラッシュが畳み掛けてくるようだ。第4楽章は、前3楽章と比べると、少し控えめだが、それでも、従来以上の音楽の厚みを求めて、思いつくことは一通りやってみたという雰囲気がある。いずれにしても、ラトルならではの濃淡豊かなマーラーだ。 さて、それでは、当盤を私がどのように捉えているかと言うと、上記のようにラトルらしい意欲的な演奏が収録されているのだが、マーラーの第9としてオススメのディスクとはならない。その理由は2つあって、一つは演奏の精度がいま一つで、情熱的な踏み込みの表現に腐心するあまり、楽器のバランスがそこなわれ、音響がダマになるようなところがあること。そういったところ、例えば第2楽章のクライマックスの部分などでは、聴きとれなくて、その価値が失われている音があること。まあ、それは、ライヴの熱のうちと言えば、そうなのだが、もう一つは、録音が良くないことである。EMIでしばしばあるのだが、高音が硬い上に、遠近感に乏しく、特にトゥッティの個所など、ベタッとした印象になってしまう。もしかすると、第1の点も、演奏の精度ではなく、録音の不備によって引き起こされたものなのかもれないが・・・。 そのようなわけで、最終評価は星4つとなった。ただし、私が所有しているのはEMIの通常版であり、同音源には別規格版や、ワーナーからの再発売版もあるので、そちらでは、音響的な改善が施されている可能性があることを留意しておく。 |
|
 |
交響曲 第10番(バルシャイ版) バルシャイ指揮 ユンゲ・ドイチェ・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2011.4.4 |
| ★★★★☆ バルシャイのオリジナル・スコアによるマーラーの第10番
ルドルフ・バルシャイ(Rudol'f Borisovich Barshai 1924-2010)指揮、ユンゲ・ドイチェ・フィルによる演奏でマーラーの交響曲第10番。録音は2001年。 最近亡くなったバルシャイは存在感のあるユニークな音楽家だった。師の1人であるショスタコーヴィチの、「交響曲第14番」を初演した人だけれど、クリエーターとしての顔も併せ持っていて、ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲のうち第1番、第3番、第4番、第8番、第10番を室内オーケストラや弦楽オーケストラのために編曲した。特に第8番の編曲作は「室内交響曲」の名で、今や数多くの演奏家に取り上げられるようになっている。 話を当盤に戻そう。この録音は「バルシャイ版」というスコアによるもの。マーラーの交響曲第10番は未完成の作品であり、現在、全曲版としてもっとも使用されているのが「クック版」というスコアである。クック版は、マーラーが書き遺したスコアを抽出し、最小限の加筆にとどめてオーケストレーションを施した点に特徴がある。そのため、聴こえる音の多くは実際にマーラーが音符の形で残したものである。 しかし、クック版が「マーラーの音楽」になっているか、と言うとそうではない。つまり、当然のことながら、この作品が完成していれば、マーラーはこの骨組みのスコアに、様々な装飾を施したに違いなく、そして「マーラーの交響曲」を「マーラーの交響曲」たらしめているものの重要な要素の一つこそが、その装飾なのである。装飾の持つ含みは深遠だ。 そこで、バルシャイ版はどのようなスタンスか?というと、クック版をベースにさらに加筆を中心に修正をしたもの、と言える。中でも驚くのが楽器編成。マーラーは第1楽章と第3楽章についてはオーケストラ譜を書いていたので、そこにプラスして楽器を加えるという発想はバルシャイならではだろう。特に打楽器群の追加が凄まじい。その効果が顕著なのが第2楽章で、最低でも9人が必要となるほどの打楽器群が、あれやこれやと音響を加える様は圧巻でもありやや異様な気もする。 第4楽章もやや楽器の追加が目立つが、こちらの方が音楽のあり様としては冷静。終楽章はクック盤に比べて荘重な厚みがあり、第9交響曲の終楽章の弦楽合奏音を彷彿とさせる。演奏しているオーケストラはドイツの学生で編成されたものだが、技術的には十分なものを持っている。ときおり合奏音がダマになるところもあるが、それは録音上の問題かもしれない。バルシャイの表現は少し大仰で、野暮に聴こえるところもあるけれど、どちらかと言うと編曲自体もその方向性でなされていると思う。 いずれにせよ、マーラーの未完成交響曲について、1人の芸術家が試行の末導いた回答として、なかなか興味深く聴けるディスクだと思う。 |
|
 |
交響曲 第10番(カーペンター版) ジンマン指揮 チュリッヒ・トーンハレ管弦楽団 レビュー日:2011.4.4 |
| ★★★★★ 第1楽章、先駆型クラスター和音によるオーケストラの咆哮は圧巻の一語
この録音が出る少し前に同じ顔合わせによる第9交響曲がリリースされたおり、私はそこで、「マーラーの交響曲全集が、2009年録音のこの第9番でひとまず完結。」と書いてしまったのだが、すぐに当盤が出てくることとなった。マーラー生誕150年である2010年に相応しい質の高い全集がいよいよ完結したわけで、ますます嬉しい事態である。 そもそも、マーラーの交響曲第10番は扱いが難しい。国際マーラー協会は第1楽章のみを「マーラーの全集」に組み込んでいるが、残されたスケッチから他の楽章の復刻は多く試みられていて、中でも有名なのがデリック・クックによるものである。しかしそのクック版も複数の稿が存在しており、全楽章を演奏・録音する場合、どれをチョイスするか、またさらにアレンジを加えるのかなど様々な問題がある。最近ではバルシャイ版のようなオリジナリティの高いものも登場してきた。 ジンマンが選択したのは「カーペンター版」である。これは、クリントン・カーペンター(Clinton Carpenter 1921-2005)によるもので、クック版より早くに完成している。最も普及しているクック版との違いは、クックが出来るだけ最小限の加筆で楽曲を完成させようとしたのに対し、カーペンターはマーラーの他の交響曲からの引用も踏まえ自らのアイデアを加えながら完成した点である。なので、クック版を聴くと本当に必要なものだけで構成された「闇を背景にした音」のようなシーンがたびたびあったのに対し、カーペンター版は、いくぶん安らぐ要素を持ち合わせていると感じる。 それで、このジンマンの演奏であるが、この素晴らしい全集の結実と言うに相応しい内容で、冒頭のヴィオラによる主題提示から儚さと美しさを湛えたマーラーの耽美主義がナチュラルに引き出されていて、濁りのない美しい音色の連続となる。圧巻は1楽章の後半に登場する有名な12音階中9音同時にオーケストラが咆哮するシーンで(ペンデレツキらの「クラスター和音」の前身と言われる)、見事な楽器の力配分により、いとも美麗なグラデーションが一気に眼前で展開される思いがする。まるで美しすぎて不安に狩られる圧倒的な夕焼けを見るかのような・・・また、第9番のときも書いたが、旧デッカのサウンド・クリエイター・チームが素晴らしい音響効果の再現に完璧なほどの成功を収めていることも特筆したい。中間楽章から終楽章にかけてはカーペンター版ならではの太さがあり、音楽が安定した水量を持って脈々と供給される豊穣さを感じさせてくれる。終楽章は退廃的だが、この演奏はことさら悲劇性を強調しているわけではなく、いかにも完成された作品として、きれいに末尾を結んでいる。 |
|
 |
交響曲 第10番(アダージョ) 交響詩「葬礼」 花の章 野原の花々が私に語ること(ブリテン編) P.ヤルヴィ指揮 フランクフルト放送交響楽団 レビュー日:2012.11.15 |
| ★★★★☆ マーラーの遺した4つの「断片楽章」を繋いで・・
パーヴォ・ヤルヴィ(Paavo Jarvi 1962-)指揮フランクフルト放送交響楽団による興味深いマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の管弦楽曲集。アルバムのテーマは「交響曲から独立した楽章」で、収録曲は以下の通り。 (1) 交響詩「葬礼」 (2) 交響曲 第10番(アダージョ) (3) 「花の章」(Blumine) (4) 野原の花々が私に語ること <ブリテン(Benjamin Britten 1913-1976)編曲> (1)は後にブラッシュアップされ、交響曲第2番の第1楽章として生まれ変わったものの原型。(2)は未完に終わった交響曲第10番で、唯一フルスコアが作曲者により完成された第1楽章。(3)は、当初交響曲第1番「巨人」の第2楽章として書かれたが、後に削除されたもの。(4)は交響曲第3番の第2楽章をブリテンが1941年に独立した小編成オーケストラのための楽曲として編曲したもの。というわけで、ここに収められた4編はいずれも交響曲の楽章として構成されながら、独立した作品としてのステイタスを同時に併せ持ったものと言える。かなりユニークな着眼点で、特に、ちょっとマーラーに詳しい人なら(1)~(3)の曲目については思いつくが、(4)まで知っている人は稀だろう。私も当盤ではじめて知った。このような作品があることを知ること自体も、貴重なものと言えそうだ。また、その4つを続けざまに演奏することで、新たに一つの交響曲が生まれたかのような、不思議な印象を醸し出している。しかし、個人的には、第10番を最後(4曲目)に収録した方が、より雰囲気が出たようにも思う。 ヤルヴィのマーラーは、最近の演奏で言うと、ジンマン(David Zinman 1936-)あたりを連想させる語り口で、適度な明朗性を備えた暖かみと、クールな分析性を感じさせる。マーラーという作曲家は、自らの内から沸き起こる感情と、自分を見舞う人生の(多くは悲劇的な)出来事を、音楽を作る動機付けとして強く結びつけた人物で、その音楽には多様な感情の動きがあるのだが、最近の主流は、むしろ音楽解析的な基礎を重視したアプローチによるもので、この演奏もおおむね最近の主流の一つだろう。 だが、ここで少し疑問が起こるのであるが、これら4つの楽章をこのように配したコンセプトであれば、もっと一つの強いイデアのようなものを、演奏の中で訴えるようなものがあってもよかったのではないだろうか。これは何も演奏が良くないと言っているわけではない。むしろ品質の高い演奏なのだけれど、4つ並べたという以上の関係性をもっと強引な手法でも誘導した方が、面白みがあったと思う。もちろん、これは一素人の勝手な発想と言えばそれっきりなのだけど。 楽曲の中では、(1)は、その後の完成版とも言える交響曲第2番の第1楽章に馴染んでいるため、どうしても「完成途上の作品」に聴こえてしまう。しかし、改めてじっくり聴くと、この交響詩の中に、交響曲第2番の後半楽章で用いることになる微細な表現が織り込まれていることなどの発見もある。(2)は言うまでもなく最晩年、絶命寸前の大傑作だ。現在では、様々に他者によって手の加えられた「5楽章版」で演奏されることが多いが、この第1楽章の壮絶な音楽は、それだけで比類ない完成度を持っている。逆に言うと、当盤の他の収録曲とは、質が違いすぎるかもしれない。 (4)は編曲の価値をそれほど強く感じなかったが、前述のように、ブリテンがこのような仕事をしていたことを知れたことは良かった。この後、ヤルヴィは交響曲第2番の名録音を成し遂げているが、本録音の存在も踏まえ、今後のパーヴォ・ヤルヴィのマーラーへのさらなる展開を期待したい。 |
|
 |
交響曲 第10番(バルシャイ版) アシュケナージ指揮 シドニー交響楽団 レビュー日:2014.4.5 |
| ★★★★★ めずらしいバルシャイ版による録音です
アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)指揮、シドニー交響楽団によるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲 第10番 嬰ヘ短調。2011年の録音。ダウンロード版と同音源による、シドニー交響楽団自主制作レーベルsydneysymphonyからリリースされているCDメディア(SSO 201202)を聴いての所感等を書く。 まず、特徴的なのは、この未完の作の「全曲盤」として、一般的なデリック・クック(Deryck Cooke 1919-1976)による補筆完成版ではなく、ルドルフ・バルシャイ(Rudolf Barshai 1924-2010)版を用いている点である。この交響曲は、第1楽章はマーラーによって完成され、第3楽章もほぼフルスコアに近いものが遺されたが、他は草稿のみであった。これに様々な人が手を入れて「完成版」を作成したのだが、現在、圧倒的に使用されているのは、クックによるものである。クックの編集意図は「できるだけ手を加えない」ことにあったと言われる。そのため、簡素なスコアで、必要最低限と思われる音符で音楽が表現される。しかし、そのサウンドが、第10番の、特に大太鼓のドスン!という響きから始まる虚無的な雰囲気にマッチし、広く世間に受け入れられてきた、と思う。 そこに一石投じたのがバルシャイであり、彼は「簡素」と一線を画した一種の「複雑化」、それも数多くの楽器を登場させるオーケストレーションを試みた。そのために彼が選んだ楽器は「マーラーが、一度でも交響曲にもちいたことのある楽器」全てで、結果として、異常とも言えるほどの巨大編成による作品となった。特に凄まじいのが打楽器群の追加である。 このバルシャイ盤、私はこれまで自作(自編?)自演盤しか聴いたことがなかったのだが、第2楽章の打楽器の躍如ぶりに目をみはったものの、これほどの楽器を用いる内的必然性は薄く、特にギターなどは、あってもなくてもいいようなもの、というのが正直な感想で、むしろ「すべての楽器を登場させる」ことが主旨になってしまった印象が残った。一方で、クック版の闇を思わせる虚無が減じ、音楽に特有の厚みが加えられたことで、聴き易くなったという印象もあった。とにかく、クック版というのは、まともに聴くと陰鬱で、しかも怖いのだ。バルシャイ盤は、ずっと気持ちを楽にできる。それを「良さ」と捉えるか、「改悪」と捉えるかは、聴く人次第だし、聴き手の気持ちの持ちようでも、いろいろ変化するものだろう。 アシュケナージの演奏は、バルシャイのものに比べて、音楽の流れの良さに力点を置いたものだと思う。そのため、オーケストレーションの特異性をことさら強調せず、むしろバルシャイ盤によってもたらされる全体的な「厚み」を、音楽表現として十分に還元させることに意識を集中させている。だから「バルシャイ盤の特異さ」を求める聴き手には、バルシャイの自演盤の方がいいように思う。 しかし、アシュケナージの演奏の魅力は、流麗な淀みのなさにある。・・「淀み」と言うと、この交響曲では、第1楽章の後半に、音楽的な「淀み」の効果を追求した一つの結実とも言える“12音階中9音同時にオーケストラが咆哮する”超絶的な音響がある。そこでもアシュケナージのもたらす響きは、どこか調性的な調和感をもたらす強弱が与えられており、不協和性を強烈に押し出すことはしていない。この部分を、インパクトより、調和を目指したことがわかる特徴的箇所として指摘したい。第2楽章、第4楽章は追加の打楽器陣がさすがに目立つが、機能的な運動美の枠に収める解釈を優先している。終楽章の象徴的な「ドスン!」も、演出としては控えめで、やや軽い印象。一方で、この終楽章の豊饒な響きは、第9交響曲のアダージョ・フィナーレに近い雰囲気を醸し出している。 総じてクック版特有の虚無感とはやや異質ながら、耽美性を湛えた豊かな音楽の流れに十分な美しさを感じる演奏であり、バルシャイ版の録音が少ないこともあって、個人的にはライブラリを充実させてくれる一枚。ただ、この交響曲の全曲版の入門としては、一般的なクック版の演奏を先に聴いた方が適切に思います。 |
|
 |
交響曲 第10番(クック版) ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 レビュー日:2014.12.16 |
| ★★★★★ ギーレンならではのアプローチが堪能できるマーラーの第10番
ドイツの指揮者ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-)は、1988年から2003年にかけて、南西ドイツ放送響とマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲全集を録音したが、「交響曲 第10番 嬰ヘ長調」については、国際グスタフ・マーラー協会が認めた第1楽章のみの録音であった。 その後、2005年に、全集とは別に、クック版による全曲をあらためて収録することとなった。 言うまでもないかもしれないが、マーラーの交響曲第10番は作曲者の生前には完成しなかった作品で、しかし、第1楽章のアダージョについては、オーケストラ譜まで出来上がっていたので、これは全集として早くから出版されていた。第3楽章は、マーラー自身によって「Purgatorio(煉獄)」と名付けられていたが、従来のマーラーの交響曲の形式と比較すると、そのスコアはとても短いものではあった。この第3楽章と第2楽章はオーケストラ・スケッチまで手が付けられていた。第4楽章と第5楽章は、オーケストレーション前の段階まで進められていた。後年、多くの研究家によって、補筆完成版が作成され、現在もっとも一般的に演奏されるのは、イギリスの音楽学者、クック(Deryck Cooke 1919-1976)によるものである。 クック版の特徴は「必要最小限の加筆」にあり、できるだけ修飾的なものを施さず、スコアの骨格のみをストレートにオーケストラにトレースしたものである。しかし、その結果、第1楽章でマーラーが示した一種の虚無性と齟齬のない呼応が感じられるところがあり、部分的に未完の味わいを残しながらも、現在では広く受け入れられるようになってきた。 指揮者のギーレンは20世紀の音楽を得意とする一方、マーラーにも精力的に取り組んできた人なので、マーラーの作品でも最晩年のもので、しかも大いに20世紀的な退廃性を感じさせるこの曲には、うってつけの人材と言ってもいいだろう。 はたして演奏はとても充実している。当録音の特徴として、第2楽章の「第1のスケルツォ」と第3楽章「煉獄」の2つに対し、速いテンポできわめて機敏なスタイルを導入した点が最初に挙げられる。全体の演奏時間が77分というのは、他のクック版の録音と比べてもやや短い方だろう。特に面白いのが第3楽章で、短い時間に次々とドラマが発生し、またたくまに畳み込むように終結へ導くという、スピーディーな手腕が発揮される。第4楽章「第2のスケルツォ;悪魔の舞踏」がこれに続くのだが、前楽章の勢いを受けて、(テンポは通常に戻るが)様々な打楽器を効果的に配分し、現代的感覚に即した表現主義に徹した手法が繰り広げられる。このあたりが抜群に面白い。 両端楽章のアダージョは、ギーレンにしては情感を湛えた表現で、例えば第1楽章の有名なトーンクラスター的な全合奏も、不協和性より合奏音の美しさを引き出していて、衝撃的というより、むしろ耽美的な印象をもたらす。この第1楽章については、前述のようにギーレン2度目の録音となるのだが、以前の録音よりテンポを落とし、情感の入るスペースを増やしているのが面白い。これは、速いテンポをとった第2、第3楽章との対比の美にも効果を発揮しているので、「第1楽章のみの録音」と「クック版による全曲録音」の差による必然的な結果なのかもしれない。 終楽章はバスドラムの一撃が強烈だ。そして、この楽章で聴かれるフルートのメロディは、十分な情緒を湛え、感動的でもある。ギーレンの指揮が、理だけでなく、情にも十分なウェイトを配していることの証左だろう。不思議な安寧と安息を見出すかのように、全曲は締めくくられる。 |
|



