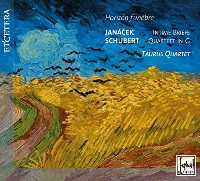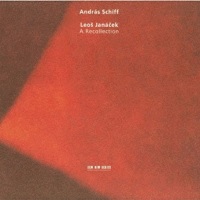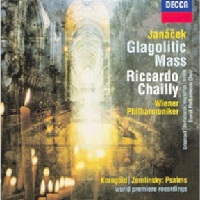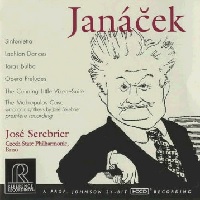 |
シンフォニエッタ 狂詩曲「タラス・ブーリバ」 ラシュスコ舞曲 組曲「利口な女狐の物語」(ターリヒ編/スメターチェク改訂) 交響的組曲「マクロプロス事件」(セレブリエール編) 序曲「嫉妬」 歌劇「死者の家から」前奏曲 セレブリエール指揮 ブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2017.4.4 |
| ★★★★★ ヤナーチェクの音楽世界への素敵な誘い
ホセ・セレブリエール(Jose Serebrier 1938-)指揮、ブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団の演奏による、ヤナーチェク(Leos Janacek 1854-1928)の管弦楽曲集。2枚のCDをセットにした再発売盤で、その収録曲は以下の通り。 【CD1】 1995年録音 1) シンフォニエッタ 2) ラシュスコ舞曲 3) 狂詩曲「タラス・ブーリバ」 【CD2】 1996年録音 4) 組曲「利口な女狐の物語」(ターリヒ(Vaclav Talich 1883-1961)編/スメターチェク(Vaclav Smetacek 1906-1986)改訂) 5) 序曲「嫉妬」 6) 歌劇「死者の家から」前奏曲 7) 交響的組曲「マクロプロス事件」(セレブリエール編) さて、私はヤナーチェクという作曲家の作品が好きで、様々なジャンルの作品を愛好しているのだけれど、「ヤナーチェクの音楽を聴いてみたい」という方に、まずどの録音を勧めるべきだろうか、と考えることがある。しかし、今回この2枚組の録音を聴いて、「これこそヤナーチェク入門に相応しい」と感じた。 もちろん、人によって好みがある。合唱が好きなら「グラゴル・ミサ」、室内楽が好きなら弦楽四重奏曲、あるいは、歌劇なら「利口な女狐の物語」も素敵だ。ただ、ヤナーチェクの音楽にある独特の語法に親しむにあたり、ヨーロッパの王道的な輝かしいオーケストラの響きを足場にすることは、手法としていちばん相応しい気がするし、しかも、このセレブリエールの録音、素晴らしいオーケストラのサウンドを十全に操って、ヤナーチェク特有の要素についても、十分に表現しつくした、見事な内容のものなのである。しかも録音も優秀。 ブルノは、ヤナーチェクが育った作曲者ゆかりの町である。だから、というのは単純に過ぎるかもしれないけれど、当演奏におけるオーケストラの自然で、しかも情感に溢れるサウンドは、聴いたとたんに、人を惹きこむような魅力に満ちている。輝かしく力強い。その一方で、過度な発色がなく、落ち着いた滋味があって、色合いに深みが感じられる。ヤナーチェクが描いた、どこか不思議で、童話的と形容したい音楽世界を表現するのに、理想的な音響で満たされている。 セレブリエールの共感あふれる指揮ぶりも素晴らしい。この指揮者の録音、たびたび聴いているけど、何を振っても立派。もっともっと評価されるべきだろう。シンフォニエッタでは民俗的なリズムの処理が鮮やかで臨場感に溢れているし、ラシュスコ舞曲の熱血的躍動もさすが。序曲「嫉妬」や交響的組曲「マクロプロス事件」第1部の圧倒的な迫力も比類ない。ちなみに交響的組曲「マクロプロス事件」では、第1幕から第3幕の音楽を、それぞれ一つの楽章に割り当てるように編曲しているが、この編曲もとても良くできたもの。最近の録音では、ペーター・ブレイナー(Peter Breiner 1957-)も、様々なヤナーチェクの歌劇を管弦楽組曲に編曲して録音しており、編曲の聞き比べも面白いだろう。それにしても、ヤナーチェクの歌劇に溢れる美しいメロディと土俗的な迫力は、管弦楽曲に編曲してみたいという動機付けに、十分すぎるもの。このような編曲で楽しんで、次は原曲である歌劇の音源に触れるというのも、ヤナーチェクの世界を楽しみやすくするアプローチになると思う。 そして、当盤の録音の素晴らしさ、生々しく、立体的な距離感が良く再現されていて、音響そのものも楽しめるものとなっている。もちろん、ヤナーチェクの音楽を良く知る人にも、存分に楽しめるアルバムだ。 |
|
 |
シンフォニエッタ グラゴル・ミサ ピアノと室内管弦楽団のためのコンチェルティーノ 歌曲集「消えた男の日記」 思い出 記憶の中で アンダンテ モデラート 金の指輪 あなたを待つ 主キリストがお生まれに ヴァイオリン・ソナタ カプリッチョ ラトル指揮 フィルハーモニア管弦楽団 バーミンガム市交響楽団 バーミンガム市交響楽団合唱団 p: ルディ マッケラス指揮 パリ国立オペラ管弦楽団員 T: ボストリッジ p: アデス vn: アモイアル レビュー日:2018.8.15 |
| ★★★★★ ヤナーチェクの世界に存分に浸れるお得な2枚組
EMIレーベルにおける、ヤナーチェク(1854-1928)の様々なジャンルの録音を、2枚組CDとしてまとめたオムニバス・アルバム。定評ある名曲とともに、演奏・録音機会の少ない楽曲も収録した面白い構成となっている。まず、その内容を以下に示そう。 【CD1】 1) シンフォニエッタ 1981年録音 サイモン・ラトル(Simon Rattle 1955-)指揮 フィルハーモニア管弦楽団 2) グラゴル・ミサ 1982年録音 サイモン・ラトル指揮 バーミンガム市交響楽団 同合唱団 ソプラノ: フェリシティ・パーマー(Felicity Palmer 1944-) アルト: アメラル・ガンソン(Ameral Gunson 1948-) テノール: ジョン・ミッチンソン(John Mitchinson1932-) バス: マルコム・キング(Malcolm King) オルガン: ジェーン・パーカー=スミス(Jane Parker-Smith) 3) ピアノと室内管弦楽団のためのコンチェルティーノ 1995年録音 ピアノ: ミハイル・ルディ(Mikhail Rudy 1953) チャールズ・マッケラス(Charles Mackerras 1925-2010)指揮 パリ国立オペラ管弦楽団員 【CD2】 1) 歌曲集「消えた男の日記」 2001年録音 青年ヤニーチク: イアン・ボストリッジ(Ian Bostridge 1964- テノール) ピアノ: トーマス・アデス(Thomas Ades 1971-) ジプシーの娘ゼフカ: ルビー・フィロジェーヌ (Ruby Philogene メゾ・ソプラノ) ジプシーの娘たち: ダイアン・アサートン (Diane Atherton ソプラノ)、デリン・エドワーズ (Deryn Edwards メゾ・ソプラノ)、スーザン・フランネリー (Susan Flanneryコントラルト) 2) 歌曲集(思い出、記憶の中で、アンダンテ、モデラート、金の指輪、あなたを待つ、主キリストがお生まれに 「消えた男の日記」から第10曲「天にまします、不滅の神よ」(初版)、第14曲「陽は高く昇り、影を追いはらう」(初版)) 2000年録音 テノール: イアン・ボストリッジ ピアノ: トーマス・アデス 3) ヴァイオリンとピアノのためのソナタ 1995年録音 ヴァイオリン: ピエール・アモイアル(Pierre Amoyal 1949-) ピアノ: ミハイル・ルディ 4) 左手のピアノと7つの管楽器のためのカプリッチョ 1995年録音 ピアノ: ミハイル・ルディ(ピアノ) チャールズ・マッケラス指揮 パリ国立オペラ管弦楽団員 すべてデジタル録音。(ただ、一連のルディの録音は、高音部がガサつき、分離もいまひとつ) ラトル指揮の2曲は、いずれも柔軟な包容力があって、劇性が抑制された感があるとは言え、代わって高い洗練を感じさせる響きで、全般にとてもスムーズに音楽が鳴っている印象がある。劇性が抑制されたと書いたけれど、決して迫力で劣っているというわけではない。華麗な個所では存分に盛り上がり、歌い上げている。その一方で、特に「グラゴル・ミサ」曲においては、チェコ語特有の強いアクセントが、適度に均されて、スタイリッシュな方向性で仕上がっていると感じられる。それが良いかどうかは聴き手の感じ方の違いであるが、私は、とても心地よく聴けたし、同じ洗練を感じさせるシャイー盤に比べると、当盤の方に野趣性も残っていると感じる部分があるので、よいところで踏みとどまっているように思える。 オーケストラの音色も、様々な意味でローカル色を感じさせない、流暢な美しさに貫かれている。そのきめの細やかな精緻なサウンドがことに堪能できる個所として、「アニュス・デイ」を挙げたい。パーカー=スミスのオルガンも、ラトルのスタイルに即したもので、非常に流麗。オーケストラ、合唱とあいまって、上質なレガートに美観がある。ただ、この楽曲の場合、聴く側に「もっといろいろなものを感じたい」という欲求が働く可能性はある。そういった点では、「シンフォニエッタ」の方が、インターナショナルな普遍性、模範性との親和性が高いだろう。輝かしさと大らかさを併せ持った金管と、細かいリズム処理を機敏にこなす弦楽器に、不満を感じる人は、ほとんどいないのではないだろうか。ラトルのこれらの楽曲への深い理解を感じさせる快演奏。 ボストリッジが独唱を務める「消えた男の日記」は、管弦楽版ではなくピアノ伴奏版の録音。また、女声3部合唱によるジプシーの娘たちは、3人の独唱によっているが、ピアノ伴奏という規模に応じた響きで、聴き味は、繊細な合唱に近く、雰囲気は十分だ。女声の登場する第9曲、第10曲は聴きどころであるが、それよりボストリッジの、この歌曲集特有の「妖しさ」を表現した歌唱が見事。またアデスのピアノも良く、第11曲「林には、いまを盛りの蕎麦の花の香りが」あたりから漂う艶めかしさ、あるいは神秘性を、存分に味わわせてくれる。 アモイアルによるヴァイオリン・ソナタは、ルディの正確な拍子に支えられ、この楽曲特有の野趣をとくに低音部の旋律を、あふれるような情感をもって表現しており、なかなかの佳演。また、「ピアノと室内管弦楽団のためのコンチェルティーノ」と「左手のピアノと7つの管楽器のためのカプリッチョ」は演奏機会の少ない楽曲であるが、やや朴訥とした旋律が、ヤナーチェクの施した巧妙な楽器構成の妙により、様々に色彩を帯びていくところが見事で、私は楽しむことができた。ただ、これらの録音に関しては、もうしこし録音が良ければもっと良かったのだが、という思いも残る。 収録時間をたっぷり利用した2枚組であり、名曲、秘曲をいずれも高いレベルの演奏で堪能できるものであり、その商品価値は十二分に高いものと言える。 |
|
 |
シンフォニエッタ 歌曲集「消えた男の日記」 アバド指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 T: ラングリッジ A: バリーズ 他 レビュー日:2017.1.31 |
| ★★★★★ アバドとベルリン・フィルによる、最初期のグラモフォン録音盤です
このヤナーチェク(Leos Janacek 1854-1928)のアルバムは、アバド(Claudio Abbado 1933-2014)がベルリン・フィルを指揮して、独グラモフォンからリリースした2枚目のアルバムで、1987年に録音されたもの。ちなみに1枚目はロシアのヴァイオリニスト、ミンツ(Shlomo Mintz 1957-)との協奏曲録音であった。 いずれにしても、スラヴ系の音楽に高い共感を持ち、多くの優れた録音を記録したアバドらしい足取りに感じられる。 収録されているのは「消えた男の日記」と「シンフォニエッタ」の2曲である。このうち「消えた男の日記」は、禁じられたジプシーとの恋愛の果て、故郷を捨てて放浪の生活に身を投じた無名の若者が残した詩文をテキストに、このニュースに心を動かされたヤナーチェクが音楽としたもので、元来はテノール、アルト、女声3部合唱とピアノのための作品である。 当アルバムに収録されているものは、オタ・ズィーテク(Ota Zitek 1892-1955)とヴァツラフ・セドラーチェク(Vaclav Sedlacek 1879-1944)によってオーケストレーションがなされたもの。当演奏では、テノール独唱をフィリップ・ラングリッジ(Philip Langridge 1939-2010)、アルト独唱をブリギッテ・バリーズ(Brigitte Balleys 1959-)、女声合唱をRIAS室内合唱団が担っている。 「消えた男の日記」は全部で22の小曲からなるが、そのうちテノール独唱曲が18曲で、他はテノール、アルトと合唱、アルトと合唱、テノールとアルト、管弦楽のみというものがそれぞれ1曲ずつとなる。管弦楽のみの部分は、青年がジプシーの少女と肉体関係を持つシーンを表現している。全般にヤナーチェクらしい童話的な色彩感と独創性を持ち合わせ、時に官能的な表現に卓越を見せる楽曲で、オーケストラ編曲はそんなヤナーチェクの世界を壊さないよう、配慮をもったものと感じられる。ヤナーチェクが書いた数々の名作オペラに近づこうという意識も感じられる。 「シンフォニエッタ」はヤナーチェクの代表作として知られる。冒頭とフィナーレに規模の大きいブラス群を要するが、中間楽章はこれとまったく異なった器楽編成で進められるなど、自由で形にとらわれていないようでいて、その一方で巧みに民謡の旋律を取り入れて、これを特有に音楽手法で消化していく洗練もみてとれる。 アバドとベルリン・フィルの演奏は、これらの曲に、卓越した演奏技術とサウンドにより、インターナショナルな万能性を持たせて仕上げたような、輝かしい完成度を感じさせるものだ。シンフォニエッタのファンファーレなど、いかにも近現代的なシャープさと恰幅の良さを併せて、存分に鳴り響いていて、気持ちの良いもの。録音もすぐれているから、その効果はなおさらである。「消えた男の日記」も、アバドの演奏は、前面に行き届いて、同じように曇りがなく、安定した美しさに満ちている。 アバドとベルリン・フィルならではの、燦然たる響きで、豊饒さを感じさせるヤナーチェクとなっている。 |
|
 |
シンフォニエッタ グラゴル・ミサ ラトル指揮 フィルハーモニア管弦楽団 バーミンガム市交響楽団 バーミンガム市交響楽団合唱団 S: パーマー A: ガンソン T: ミッチンソン B: キング org: パーカー=スミス レビュー日:2018.8.9 |
| ★★★★★ ラトルの現代的感性が良く映えたヤナーチェク
サイモン・ラトル(Simon Rattle 1955-)の指揮によるヤナーチェク(Leos Janacek 1854-1928)の2つの名曲を収録したアルバム。収録内容は以下の通り。 シンフォニエッタ 1) ファンファーレ 2) 城塞(シュピルベルク城) 3) 修道院(ブルノの王妃の修道院) 4) 街路(古城に至る道) 5) 市庁(ブルノ旧市庁舎) グラゴル・ミサ 6) 入祭文(Uvod) 7) キリエ(Gospodi pomiluj) 8) グローリア(Slava) 9) クレド(Veruju) 10) サンクトゥス(Svet) 11) アニュス・デイ (Agnece Bozij) 12) オルガン独奏;後奏曲(Varhany solo) 13) イントラーダ(Intrada) 「シンフォニエッタ」はフィルハーモニア管弦楽団、「グラゴル・ミサ」はバーミンガム市交響楽団とバーミンガム市交響楽団合唱団の演奏で、それぞれ1981年、1982年の録音。 グラゴル・ミサ曲における4人の独唱者とオルガン奏者は以下の通り。 ソプラノ: フェリシティ・パーマー(Felicity Palmer 1944-) アルト: アメラル・ガンソン(Ameral Gunson 1948-) テノール: ジョン・ミッチンソン(John Mitchinson1932-) バス: マルコム・キング(Malcolm King) オルガン: ジェーン・パーカー=スミス(Jane Parker-Smith) 2002年からベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者兼芸術監督を務めていることが示すように、ラトルは、中央ヨーロッパの音楽のまさに中心を担う芸術家であるが、かつて同様の存在だった人たちと比較すると、レパートリーがユニークで、北欧音楽やスラヴ音楽を、むしろ得意中の得意といった感じで、堂々とそこに据えている。そのため、彼がベルリンで芸術監督を務めるようになって、ベルリン・フィルが取り上げる音楽も多彩さを増しているようだ。 これらのヤナーチェクの楽曲も、ラトルはキャリア初期から積極的に取り上げているもので、当録音においても、そのこなれた扱いが際立っている。 収録された2曲とも、柔軟な包容力があって、劇性が抑制された感があるとは言え、代わって高い洗練を感じさせる響きで、全般にとてもスムーズに音楽が鳴っている印象がある。劇性が抑制されたと書いたけれど、決して迫力で劣っているというわけではない。華麗な個所では存分に盛り上がり、歌い上げている。その一方で、特に「グラゴル・ミサ」曲においては、チェコ語特有の強いアクセントが、適度に均されて、スタイリッシュな方向性で仕上がっていると感じられる。それが良いかどうかは聴き手の感じ方の違いであるが、私は、とても心地よく聴けたし、同じ洗練を感じさせるシャイー盤に比べると、当盤の方に野趣性も残っていると感じる部分があるので、よいところで踏みとどまっているように思える。 オーケストラの音色も、様々な意味でローカル色を感じさせない、流暢な美しさに貫かれている。そのきめの細やかな精緻なサウンドがことに堪能できる個所として、「アニュス・デイ」を挙げたい。パーカー=スミスのオルガンも、ラトルのスタイルに即したもので、非常に流麗。オーケストラ、合唱とあいまって、上質なレガートに美観がある。ただ、この楽曲の場合、聴く側に「もっといろいろなものを感じたい」という欲求が働く可能性はある。 そういった点では、「シンフォニエッタ」の方が、インターナショナルな普遍性、模範性との親和性が高いだろう。輝かしさと大らかさを併せ持った金管と、細かいリズム処理を機敏にこなす弦楽器に、不満を感じる人は、ほとんどいないのではないだろうか。ラトルのこれらの楽曲への深い理解を感じさせる快演奏となっている。 |
|
 |
歌劇「イェヌーファ」組曲(P.ブレイナー編) 歌劇「ブロウチェク氏の旅」組曲(P.ブレイナー編) ブレイナー指揮 ニュージーランド交響楽団 レビュー日:2010.3.20 |
| ★★★★★ ヤナーチェクのオペラ管弦楽組曲第1弾
ナクソス・レーベルからヤナーチェクの歌劇の「管弦楽組曲」のシリーズがリリースされた。当盤が第1弾で2007年の録音。収録されたのは「イェヌーファ」組曲と「ブロウチェク氏の旅」組曲。ペーター・ブレイナー指揮ニュージーランド交響楽団の演奏。 ニュージーランドのオーケストラがヤナーチェク?とちょっと意表を付かれた感じがあるが、ヤナーチェクの音楽は汎スラヴ的でありながら、インターナショナルな通力を併せ持っており、世界中あらゆる国で楽しまれるのに相応しい。さて、今回素晴らしい「編曲」をしてくれているのが、指揮者のペーター・ブレイナー(Peter Breiner)である。ブレイナーは1957年スロヴァキア出身なので、ヤナーチェクの音楽には早くから接していたに違いない。この録音を聴くと、編曲・演奏の両面で優れた手腕を持っていることがよくわかる。 ヤナーチェクの9つのオペラはいずれも名品として知られるが、言語の問題もあり、上演機会が少ない。このような「編曲」によって、その特有の作曲・管弦楽書法がより楽しみやすい存在となるのもうれしい。 「イェヌーファ」はドイツ的な重心のしっかりしたオーケストレーションでありながら、不思議な経過句や変容に満ちていて、親しみやすい音型が少しずつ「型」をはずしていくところなど面白い。主観的な音楽に聴こえるし、実際そうだと思うが、その自由さが散漫ではなく、音楽を濃厚なものに傾斜させているのが面白い。 「ブロウチェク氏の旅」は五音音階の使用により、どことなく東洋的な雰囲気に満ちていて、これを支える弦のユニゾンによるフォルテなどきわめて個性的だ。独特の舞踏感のある部分があり、テンポの頻繁な転換もある。それらのいずれもがヤナーチェクの色彩を成していく。 ニュージーランド交響楽団はなかなか安定した力量を持っており、日本の主要オーケストラと同等くらいの力量は十分に備えているだろう。あるいはヨーロッパ人が結構多く参加しているのではないだろうか。非常にモダンな現代ヨーロッパ・サウンドという気がする。少なくとも、問題の感じられるところはなく、安価で入手できるのはとても助かる。 |
|
 |
歌劇「カーチャ・カバノヴァー」組曲(P.ブレイナー編) 歌劇「マクロプロス事件」組曲(P.ブレイナー編) ブレイナー指揮 ニュージーランド交響楽団 レビュー日:2010.3.20 |
| ★★★★★ ヤナーチェクのオペラ管弦楽組曲第2弾
ペーター・ブレイナー編曲による、ブレイナー指揮ニュージーランド交響楽団によるヤナーチェクの歌劇から編まれた管弦楽組曲シリーズの第2弾。今回は「カーチャ・カバノヴァー」と「マクロプロス事件」。第1弾直後の2007年の録音。 私には、ヤナーチェクのオペラを聴くと思い出す映像作品がある。アメリカの双子の人形アニメーション作家、ブラザーズ・クエイの「レオス・ヤナーチェク」という作品だ。1983年にイギリスで製作されたものだが、ヤナーチェクの音楽をバックに流しながらヤナーチェクの「人生」と彼の創作した「劇話」が入り混ざった幻想的な世界を表現していて、その不思議な映像は強く印象付けられている。特に「死者の家から」と「マクロプロス事件」は題材が深刻だったり、ホラーっぽかったりするので、ブラザーズ・クエイの作品でもこれらの作品を引用した箇所はインパクトがあったと思う。 というわけで、私はこの「マクロプロス事件」の音楽が、幻想的な映像とともに記憶に刻まれていて、それが「管弦楽曲」として、一種の「追体験」を手ごろに味わえるようになった本ディスクに感慨を覚える。 「マクロプロス事件」は“年を取らないオペラ歌手”という都市伝説的なストーリーを扱っていて、不気味な音楽である一方で、しかしヤナーチェクならではの自由さや楽天性が混ざった実に奇特で面白い音楽だ。管弦楽の迫力も凄いし、変拍子の扱いも見事。ブレイナーの編曲も素晴らしく、フィナーレに向けて壮大なスケールで音楽がうねっていく。 もちろん「カーチャ・カバノヴァー」も素晴らしい。弦の力強い響きと共に鳴らされるティンパニの強打が圧巻であるが、官能的とも言える色彩がある。短いモチーフを動機として全体を構成立てていく感性が天才的なインスピレーションに満ちている。構成的には西欧古典とはまったく異なるが、不思議と親しみやすいメロウなところがあり暖かい。このようなディスクが出現することで、これらの楽曲を知る人が増えたら、非常に良いことだと思う。 |
|
 |
歌劇「利口な牝狐の物語」組曲(P.ブレイナー編) 歌劇「死者の家から」組曲(P.ブレイナー編) ブレイナー指揮 ニュージーランド交響楽団 レビュー日:2010.3.20 |
| ★★★★★ ヤナーチェクのオペラ管弦楽組曲第3弾
ペーター・ブレイナー編曲による、ブレイナー指揮ニュージーランド交響楽団によるヤナーチェクの歌劇から編まれた管弦楽組曲シリーズの第3弾。今回は「利口な女狐の物語」と「死者の家から」。第1弾、第2弾からほとんど間を空けず2007年8月の録音。 本当にヤナーチェクの音楽は面白い。自由だが法則があり、ポリリズムだが脈があり、メロディアスではないが簡明である。これらの要素を併せて成立させていることがすでに奇跡的だ。 「利口な女狐の物語」はターリッヒによる管弦楽組曲もあり、そちらは近年ではエリシュカ指揮札幌交響楽団の佳演があるが、ブレイナーの編曲はより多くの要素を取り込んでいて、聴き応えで勝っている。物語風とも言える旋法は日本の民謡と似て短調のパーツが多く、かつ五音音階への接近はアジアを感じさせるが、その由来がモラヴァ民謡であるというのもどこか不思議である。そう考えるとヤナーチェクの音楽は、もっと日本で受け入れられてしかるべき性質を持っているだろう。この録音もぜひ多くの人に聴いて欲しいものだ。とにかく不思議な親近感に満ちている。 「死者の家から」はドストエフスキーの原作のオペラ化であるが、ヤナーチェクは悲劇的な主題を扱ったとしても、生命肯定的なポジティヴなところに結ばれてゆく。それはドストエフスキーの小説とも共鳴する部分に思われる。室内楽的な緻密さと、大らかな楽器の響きがあいまってのどかであったり、メルヘンチックであったり野趣性に満ちたりするが、その変容の様がヤナーチェクならではの特異な独創性に礎を持っている。ニュージーランド交響楽団の好演ぶりも素晴らしい。各奏者の技量の高さが、より音楽の表現を豊かにしている。 この第3弾で、残すヤナーチェクのオペラは3曲となったが、ぜひ全ての「管弦楽組曲」を完成してほしい。そしてこれを新しいレパートリーとして、他の指揮者やオーケストラによる録音も出てくれば、面白いことこの上ない。 |
|