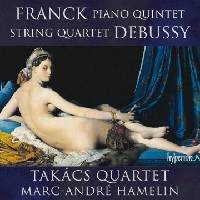|
交響曲 交響詩「プシシェ」より(プシシェの眠り 西風に運ばれたプシシェ エロスの花園 プシシェとエロス) 交響詩「ジン(鬼神)」 アシュケナージ指揮 ベルリン放送交響楽団 p: アシュケナージ レビュー日:2013.2.27 |
| ★★★★★ アシュケナージとベルリン放送交響楽団の録音には「知られざる名盤」が多いです
アシュケナージ(Vladimir Ashkenazy 1937-)がベルリン放送交響楽団を指揮して録音したフランク(Cesar Franck 1822-1890)の作品集。1988年から89年にかけての録音で、収録曲は以下の通り。 1) 交響曲 ニ短調 2) 交響詩「プシシェ」より(プシシェの眠り 西風に運ばれたプシシェ エロスの花園 プシシェとエロス) 3) 交響詩「ジン(鬼神)」 交響詩「ジン」はピアノを伴った編成であるが、ここでアシュケナージ自らがピアノを演奏している点が大きな特徴だ。「プシシェ」はギリシァ神話のプシシェとエロスの物語で、全6曲中4曲が取り上げられている。 フランクがこの交響曲を書きあげたのは1988年である。晩年になり、名作のみを一点集中型で書き残したフランク。その高貴な作品群に君臨するのがこの交響曲とヴァイオリン・ソナタだと思う。 この交響曲は1989年にパリで初演されたのだが、その評価は散々だったらしい。中でもグノー(Charles Gounod 1818-1893)による「ドグマの域にまで達した不能性の断言」という言葉は有名で、フランクがバッハを研究し、その成果である対位法を駆使ながら、一つの主題を繰り返し使う「循環形式」という独自の音楽形式へ至った過程を、一種の教条主義として、“なで斬り”にしたものだ。しかし、当のフランクはそんな評価を一向に気にしなかった。「どうでした?」と聴く周りにむかって、「ああ。思った通りの音が出たよ。」と満足げに頷いたそうである。なんという自信。そして、その自信が絶対的に正しかったことが、いまの世では証明されている。この自らの作品へ揺るぎのない信頼を、少しはブルックナーに分け与えてあげたかったが。ちなみに、当時の作曲家で、この交響曲の真価を見抜き、賛辞を送ったのがかのドビュッシー(Claude Achille Debussy 1862-1918)である。まさに「天才は、天才を知る」である。 さて、このアシュケナージの録音、私は素晴らしいと思うのであるが、あまり取り上げられる機会がなかったように思う。第1楽章は冒頭から内省的な力が秘められており、しかもクライマックスでの爆発力の底力が凄い。全体が突きあげられるように、エネルギッシュな頂点を築き上げる。第2楽章の高貴な歌も、たしかな質のある品格を持って、的確な間をもって表現されていて、瀟洒である。終楽章である第3楽章では、主題を回想しながら、鮮明な色合いを増していき、最後に力感に溢れる結実を得ている。 そして、このアルバムの価値をいよいよ高めているのが、交響詩「ジン」である。ピアノ付の交響詩というのは元来珍しいのだが、指揮をするアシュケナージが自らピアノを受け持つというのも、珍しいのではないか。このピアノの効果が実に素晴らしく、楽曲の雰囲気をよく引き出している。オーケストラが全般に重々しいイメージを与える音楽なのだが、ピアノの華麗な音色が、一気に感情の幅を広げていて、実に効果的。絶対的なソノリティーの美しさもこの人ならではで、お得感満載のアルバムとなっている。 |
|
 |
フランク 交響曲 フロラン・シュミット サロメの悲劇 ネゼ=セガン指揮 グラン・モントリオール・メトロポリタン管弦楽団 レビュー日:2014.8.25 |
| ★★★★★ カナダの若き名指揮者、ネゼ=セガンの実力を示した名演
ヤニック・ネゼ=セガン(Yannick Nezet-Seguin 1975-)指揮、グラン・モントリオール・メトロポリタン管弦楽団の演奏で、フロラン・シュミット(Florent Schmitt 1870-1958)のバレエ音楽「サロメの悲劇」組曲とフランク(Cesar Franck 1822-1890)の交響曲ニ短調を収録。2010年の録音。 現代、世界で注目される若手指揮者の中でも、ネゼ=セガンは特に重要な人物で、すでに多くの録音がリリースされている。当録音も、たいへん質の高い豊かな内容で、素晴らしいもの。 冒頭にフロラン・シュミットの代表作として知られる「サロメの悲劇」組曲が収録されていることに注目したい。フロラン・シュミットはドイツ系フランス人であったが、その作風もドイツの後期ロマン派と、フランスの印象派を折衷したようなところがある。この作品も、印象派的な音響と、ロマンティックで抒情的な旋律線を併せ持った、総じてダイナミックな作品だ。全曲だと1時間近くを要し、声楽も含まれるが、本組曲は2部から構成される純器楽曲。第1部は「序奏」と「真珠の踊り」、第2部は「海上の誘惑」「稲妻の踊り」「恐怖の踊り」からなる。特に第2部の官能的で土俗的な舞曲は、ラヴェル(-Maurice Ravel 1875-1937)の「ダフニスとクロエ」を彷彿とさせる。 ちなみに「サロメ」はR.シュトラウス(Richard Strauss 1864-1949)が楽劇の題材としたワイルド(Oscar Wilde 1854-1900)の戯曲ではなく、新約聖書のサロメの一説を引用したもで、神の怒りのシーンを含む。 ネゼ=セガンは、この音楽で柔軟性に満ちた迫力を引き出している。第1部の後半にあたる「真珠の踊り」では、これでもかという早いテンポで、切迫した勢いを音楽の奔流とし、巧みにその行先を制御する。スリリングな味わいを堪能できる瞬間だ。「稲妻の踊り」を頂点として構成した第2部は、いくぶん落ち着いた趣で、時にドビュッシー(Claude Achille Debussy 1862-1918)の海を彷彿とさせる和声進行を見せながら、音楽の大きなうねりを形成していく。この音楽の性格を余すことなく伝えた名演だ。 次に収録してあるのは名曲として名高く競合盤も多いフランクの交響曲。こちらは、際立って特徴的な演奏ではないが、たいへん真面目に慎重にアプローチした音楽作りで、全体として柔らかな響きから、自然な運動性を引き出している。オーケストラの十分な技術を背景としたしなやかな響きを活かした無理のない音が全編に満たされていて、ほとんど欠点のようなものを指摘できるところはない。 満ち足りた質の高い表現で、フランクの作品に特有の高貴さがよく表れている。 |
|
 |
フランク 交響曲 フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 バレンボイム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2024.12.2 |
| ★★★★☆ ゴージャスなサウンドで表現されたフランクとフォーレ
バレンボイム(Daniel Barenboim 1942-)指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による下記の2作品を収録したアルバム。 1-3) フランク(Cesar Franck 1822-1890) 交響曲 ニ短調 フォーレ(Gabriel Faure 1845-1924) 組曲「ペレアスとメリザンド」 op.80 4) 前奏曲 5) 糸を紡ぐ女 6) シシリエンヌ 7) メリザンドの死 2023年の録音。 バレンボイムにとって、フランクの交響曲は、実に50年ぶりの録音とのこと。ただし、私はその最初の録音は未聴。50年ぶりとなる大作と、没後100年のアニヴァーサリー・イヤーとなるフォーレの楽曲と組み合わせてアルバムにしており、そう考えると、世紀単位の区切りを感じさせる。 バレンボイムとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団は、長く良好な関係を継続しており、この録音でも、指揮者の表現したいところを、オーケストラがよくその通りに表現したという印象が強い。特にフランクの交響曲は、スローなテンポで、末広がりの音、テヌートを存分に謳わせながら、全般にゴージャスな響きに満ちている。 音響の輪郭はソフトであり、強靭な音も、音の圧というより幅によって迫力を得ている。緩急の表現はもちろんあるが、全体的にスローなベースを前提とした上でのものであり、それゆえに細部には緩さがある。とはいえ、逆に言うと、全体にソフトな聴き味を作ることに成功している、とも見なせるだろう。旋律は濃厚な甘味を帯び、合奏音の響きはやや重い。 つまり、バレンボイムの演奏は、この交響曲を、濃厚なロマン派の名作として扱ったものであり、循環形式の精緻な再現や、フランス的な瀟洒さの表出については、そこまで重要視していないと思う。今のバレンボイムが、フランクの交響曲をやりたいように振って、オーケストラがそれにしっかり応えたという演奏なのだろう。とはいえ、それは驚きをもって迎えるようなものではなく、今のバレンボイムが、その芸風をしっかりと反映させれば、このようになるだろう、といったところである。フランクの交響曲も、元来、様々な解釈幅があるものである。 以上のように興味深く聴かせていただいたが、個人的には、欠点も感じさせるところがあって、特に、あまりにも全体が一様になり過ぎているということである。そのため、この規模の楽曲にしては、どこの部分でも印象が似通い過ぎてしまっている。全体を通して、あそこが良かったとか、ここが凄かったというスポットな印象がほとんど残らず、つまりは、どうしても、聴いていた、長さを感じさせるところがあるのだ。これほどいい曲であるのにもかかわらず、である。 その点では、小曲集である組曲「ペレアスとメリザンド」の方が、私には好ましく、悲劇的なモチーフ、甘美な旋律など、率直に楽しみ、その世界に浸ることができた。フランクの交響曲については、バレンボイムの芸術表現を感じさせつつも、私には、もう一つなにかほしいという思いが残る。 |
|
 |
フランク 交響曲 ラヴェル クープランの墓 道化師の朝の歌 カラヤン指揮 パリ管弦楽団 レビュー日:2025.8.25 |
| ★★★★★ 1969年に記録された歴史的名演
往年の音楽ファンには、懐かしさいっぱいのカラヤン(Herbert von Karajan 1908-1989)による歴史的録音である。当録音が登場した経緯について簡単に説明すると、フランス文化省の肝いりの政策として、1967年に設立された「パリ管弦楽団」は、地元の巨匠、シャルル・ミュンシュ(Charles Munch 1891-1968)を音楽監督として発足した。しかし、その直後にミュンシュは急逝してしまう。それでは、この立ち上がったばかりの「パリ管弦楽団」を誰が率いるのか?その驚くべき人選として、カラヤン(Herbert von Karajan 1908-1989)に要請が行われ、カラヤンもこれを受諾。果たして、1969~71年の間、このオーケストラの音楽監督を務めることになる。そして、その名刺代わりの録音が、当盤に収録されたフランク(Cesar Franck 1822-1890)の「交響曲 ニ短調」であった。フランスが威信をかけたプロジェクト「パリ管弦楽団」を、ドイツの巨匠、カラヤンが振ってのその内容が、素晴らしい名演であったことから、世界の多くの音楽ファンが、この録音の登場に熱狂したとされる。 さて、そんな当盤の収録曲は以下の通り。 1-3) フランク 交響曲 ニ短調 ラヴェル(Maurice Ravel 1875-1937) クープランの墓(Le Tombeau de Couperin) 4) プレリュード(Prelude) 5) フォルラーヌ(Forlane) 6) メヌエット(Menuet) 7) リゴドン(Rigaudon) 8) 道化師の朝の歌(Alborada del gracioso) フランクの交響曲は1969年、ラヴェルの管弦楽曲は1971年の録音。 フランスが新たに芸術振興の象徴として設立したパリ管弦楽団、そこにドイツ文化を象徴する芸術家を音楽監督として迎える決断、その要請を受諾し、設立されたばかりのオーケストラから、情熱的で豪快な響きを引き出したカラヤン。というわけで、これは、単に音楽という枠を超えた文化の高まり、芸術のメッセージ性の普遍性を引き出した名録音であったわけである。 2025年となった今、改めてこの録音を聴いてみても、素晴らしい演奏だと思う。もちろん、1969年の録音なので、当時の録音水準としても音質は平均的なものに感じるが、演奏は溢れかえるような熱気に満ちている。フランクの交響曲が持っている特殊な構造を、ひたすら熱く太く表現するカラヤンとパリ管弦楽団のパワーは圧倒的だ。かつ、抒情的なメロディラインも、内に熱を帯びたように奏でられるのが印象的。決して瞑想的ではなく、耽美という印象に連なる。最近の同曲の一般的な録音と比べて、低音のヴォリューム感が厚いのも、迫力を底上げしている。 併録されているラヴェルの管弦楽曲も名演だ。こちらはフランクに比べると、楽曲の性格もあって、熱的なものは控えられるが、それでも木管の音色の華やかさ、的確なテンポで、心地よく響く。流麗にして華麗なラヴェルだ。 それにしても、このオーケストラが、カラヤン以後も、国外の芸術家を音楽監督して招聘し続けることになったのは、あるいは、カラヤンとパリ管弦楽団の成功のインパクトがあまりにも大きかったためかもしれない。そこまで想像を掻き立てさせられてしまう歴史的名録音だ。 |
|