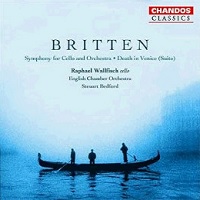|
ブリテン バレエ「パゴダの王子」組曲 マクフィー バリ島の儀式の音楽 2台のピアノと管弦楽のための「タブー・タブアン」 スラトキン指揮 BBC交響楽団 p: ブリテン マクフィー バーリー アレイ レビュー日:2007.8.27 |
| ★★★★★ エスニック情緒満載の痛快無比なアルバムです
これはかなり面白いアルバム。収録曲は以下の3曲である。マクフィーの「バリ島の儀式の音楽」、2台のピアノと管弦楽のための「タブー・タブアン」、ブリテンのバレエ「パゴダの王子」組曲。 共通点はずばり「ガムラン」!。コリン・マクフィー(Colin McPhee 1900-1964)はモントリオール出身のカナダの作曲家。ブリテンとは友好が深かった。民俗音楽を研究したマクフィーはなんとこの時代に6年間もバリ島に住んでいた。冒頭に収録された「バリ島の儀式の音楽」は2台のピアノ版ガムランである。しかもこれを弾いているのがマクフィー本人とブリテンである。録音は1941年。まずこの7分ほどの楽曲がめちゃくちゃ面白い。いやー、ピアノでガムランができちゃうんだ、と妙に感心してしまう。 他は2003年の録音で、演奏はスラットキン指揮のBBC交響楽団、ピアノはバーリーとアレイの二人。2台のピアノと管弦楽のための「タブー・タブアン」がこれまたガムランの傾倒音楽である。さらに西欧の伝統音楽に加えてジャズの要素までをも持ち合わせ、打楽器的に用いられる2台のピアノと色彩感あるオーケストレーションで、まさに音楽文化の融合(わかりやすいぞ!)が行われる。 負けじとブリテンの作品、バレエ音楽「パゴダの王子」。ここでも第3幕で、バリ島のガムラン音楽を思い切り良く組み込んだシーンが展開される。まさに露骨なマクフィー効果といったところ。なんでもこれが架空の国「パゴダ」の音楽になるのだとか。。。ジャケット写真にデザインされた三重の塔(なんでや!)と「ゲコ」(gecko;バリ島にいっぱいいますよね~)のイメージとあいまって、西欧からみたアジアのエキゾティズムが全開の痛快無比な面白さ満喫のアルバムです! |
|
 |
ブリテン シンフォニア・ダ・レクイエム 歌劇「ピーター・クライムズ」から「4つの海の間奏曲」と「パッサカリア」 ホルスト 組曲「どこまでも馬鹿な男」 エグドン・ヒース プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団 レビュー日:2008.8.16 |
| ★★★★★ イギリス音楽を得意としたプレヴィンの確信に満ちた演奏
ベンジャミン・ブリテン(Benjamin Britten 1913-1976)は近代イギリスを代表する作曲家で、指揮者、ピアニストとしても高名だった。そのブリテン自身から自作の演奏に関して高い評価を得ていたのがプレヴィンである。ともにクラシックだけでなく映画音楽など多様な活動幅を持っていた点も共通する。 ブリテンの「シンフォニア・ダ・レクイエム」は1940年に大日本帝国政府が皇紀2600年を記念して、ヨーロッパ各国政府に依頼し、代表的作曲家に新作を委嘱したことで生まれた作品群の一つ。ちなみにこの他には、リヒャルト・シュトラウスの「皇紀2600年祝典音楽」、イベールの「祝典序曲」、ピッツェッティの「交響曲 イ調」、ヴェレシュの「交響曲 第1番 「日本風 (ヤパン・シンフォニア)」 」がある。ブリテン作品は亡き父の想い出にと銘打たれて作曲された。3楽章からなるが重々しい荘厳さが漂い、祝典的とは言いがたいだろう。時代の空気を敏感に感じ取ったものに思える。ティンパニの痛烈な強打と金管陣の不安感漂う響きが印象的。力作というに相応しいできばえ。 第二次世界大戦中クーセヴィツキーがブリテンにオペラ作曲を委嘱し、「ピーター・グライムズ」が生まれる(ブリテンは良心的従軍拒否を敢行している)。「ピーター・クライムズ」からの間奏曲は「夜明け」「日曜日の朝」「月光」「嵐」の4曲で、牧歌的で長閑な「夜明け」、夜の雰囲気を描写する「月光」が印象深い。 同じイギリスの作曲家ホルストの珍しい作品が併せて収録されているが、この作曲家が「惑星」だけではないことを示してくれるチャーミング。「どこまでも馬鹿な男」は「惑星」にも通じるオーケストレーションが楽しめる。「エグドン・ヒース」はヴォーン・ウィリアムズを思わせるどこか荒涼としながらも風の吹きすさぶような音楽世界だ。 |
|