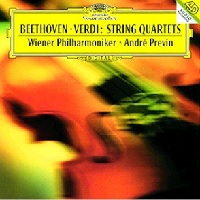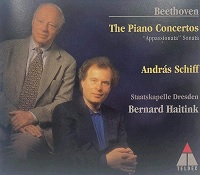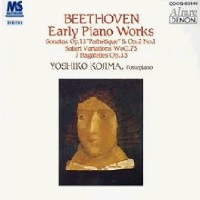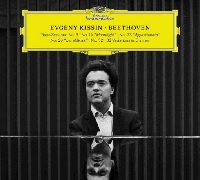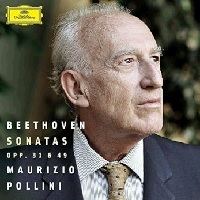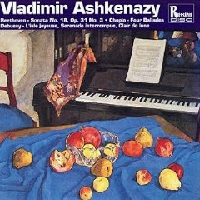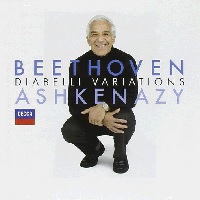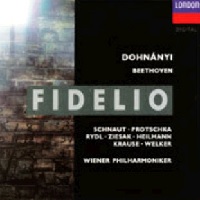|
交響曲 全集 バレエ「プロメテウスの創造物」序曲 コリオラン序曲 レオノーレ序曲 第3番 フィデリオ序曲 アテネの廃墟序曲 エグモント序曲 「命名祝日」序曲 劇付随音楽「シュテファン王」序曲 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 ゲヴァントハウス合唱団 ゲヴァントハウス児童合唱団 MDR放送合唱団 S: ベラノワ A: パーシキヴィ T: スミス B: ブラッハマン レビュー日:2011.11.29 |
| ★★★★★ 現代の代表的ベートーヴェン交響曲全集と言えるでしょう
突然、思いもしないような名演奏にめぐり合えた喜びというのはとても大きいものだけれど、今回のリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)によるベートーヴェンの交響曲全集に接した時の私も、まさにそのような幸せな気持ちに包まれた。 もともと、シャイーは私好みの指揮者で、数々の録音を聴いてきたのだけれど、長い間コンセルトヘボウ管弦楽団という素晴らしいオーケストラを振りながら、ベートーヴェンの交響曲ではBOXものに収録された第2番かかろうじて聴けるくらいであった。それで、私は、シャイーにはとって、ベートーヴェンはアプローチの難しい作曲家なのかもしれない、と思うようになっていた。なんといっても、パステルカラーの色彩をブルーのバックに敷き詰めたような彼のスタイルは、ロマン派や近代のレパートリーに強いハズだった。 そんなシャイーがライプツィヒに移り、バッハの録音を集中的に開始したときも、若干不思議な気がしたけれども、今度はベートーヴェン、しかもいきなりの全集である。 それでは、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団を指揮して2007年から2009年の間に録音されたこの全集の特徴は?・・それはもう凄まじいエネルギッシュな「迫力」だ。「血沸き肉踊る」というフレーズがあるが、まさしくそんな感じ。 とにかくテンポが速い。これはピリオド楽器の流行以来、一定の市民権を得たテンポではあるけれど、シャイーの演奏は速いだけでなく、音楽に厚みがあり、しかも曲想に応じて、瞬時にその厚みを変化させるのだ。その変化の際に放たれるエネルギーの量が凄い。聴いているものは、ハートを直接揺さぶられるような強靭なパワーに晒されるだろう。その快感たるや比類ない。これこそ現代楽器が持っているポテンシャルだ。 細かく挙げるとまさにキリがないのだけれど、交響曲第9番の終楽章、あの有名な声楽を伴った楽章で、ソロが入る直前の全管弦楽の嵐のように流れ落ちる激流、続けざまに壮絶に打ち鳴らされるティンパニの凄いこと!この瞬間にどれほどの集中力を投入したのだろうか?ライプツィヒという世界でも最も歴史あるオーケストラから、これほど清新な感興に満ちた音色を引き出すとは。やはりシャイーはとんでもない指揮者だ。 また、従来からのシャイーの良き特徴も損なわれていない。それどころか隅々で活かされている。運命交響曲の終楽章で鳴るピッコロのガラスのような透明感!なんと結晶化した美しさ。また、急速なギアチェンジの際にも、金管が淀みなく呼応する心地よさも無類だろう。最後になったが、9曲の交響曲に加えて、バレエ「プロメテウスの創造物」序曲、コリオラン序曲、レオノーレ序曲第3番、フィデリオ序曲、アテネの廃墟序曲、エグモント序曲、「命名祝日」序曲、劇付随音楽「シュテファン王」序曲まで収録されているのも素晴らしいサービス。いや、いずれもサービスの一語で片付けるのはもったいない名演揃い。“いまのベートーヴェン”、全集で聴くなら、迷わずこのシャイー盤を挙げたい。 |
|
 |
交響曲 全集 ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 ベルリン放送合唱団 S: ベーレ A: ナエフ T: ウィンスレイド Bs: ミュラー=ブラッハマン レビュー日:2015.9.14 |
| ★★★★★ 鮮度に溢れた表現で、現在を代表するベートーヴェンの一つ
ギーレン(Michael Gielen 1927-)指揮、南西ドイツ放送交響楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)交響曲全集。1997年から2000年にかけてライヴ録音されたもので、当アイテムはリマスターを経て再発売されたもの。ギーレンと南西ドイツ放送交響楽団は、すでに1986~1994年にかけてEMIに全集を録音していたから、それからあまり間を開けずに2度目の全集が完成されたことになる。CD5枚の収録内容は以下の通り。 【CD1】 2000年録音 交響曲 第1番 ハ長調 op.21 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」 【CD2】 1998年録音 交響曲 第2番 ニ長調 op.36 交響曲 第7番 イ長調 op.92 【CD3】 2000年録音 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93 【CD4】 1997年録音 交響曲 第5番 ハ短調 op.67「運命」 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68「田園」 【CD5】 1999年録音 交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱付」 交響曲第9番ではベルリン放送合唱団が加わるほか、4人の独唱者は以下の通り ソプラノ: レナーテ・べーレ(Renate Behle) アルト: イヴォンヌ・ナエフ(Yvonne Naef 1957-) テノール: グレン・ウィンスレイド(Glenn Winslade 1958-) バス: ハンノ・ミュラー=ブラッハマン(Hanno Muller-Brachmann 1970-) さて、私はギーレンのベートーヴェンを新旧両録音を通じて、このリマスター盤ではじめて聴いた。そのため、既出盤との比較という観点で論じることは出来ないけれど、これはとても素晴らしいベートーヴェンだと思う。少なくとも、今の時代において、加味すべき様々な重要な価値観の中で、とても意義深いプライオリティを配した録音であり、それが私の感覚にはよく馴染む。 私もクラシック音楽を聴き始めると同時にベートーヴェンの交響曲を聴き始めたから、これまでに相当な数のものを聴いてきた。でも、今、どれがいちばん好きかと問われると、まず挙げたいのは2007~09年に録音されたシャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮ゲヴァントハウス管弦楽団のものなのだけど、このギーレン盤はそれに次いで気に入った。とにかく何度も聴いている。ちなみに、もう一つ挙げよと言われたら、私の場合歴史的な録音になってしまうが、コンヴィチュニー(Franz Konwitschny 1901-1962)とゲヴァントハウス管弦楽団の名盤になるかな。 それはおいておいて、とにかく、私はこのギーレンのベートーヴェンは、とても良いと思う。何が良いのか?ベートーヴェンの音楽では、焚き付けるような高揚感、内燃的な情熱や興奮といったものを経て、勝利の歓喜が導かれ、そのための強烈な発汗作用があるのだけれど、ギーレンの演奏では一種の即物性をキープした明瞭な透明性によって、それらを高度にコントロールしているのだ。その結果、音の間隙の風通しが素晴らしく良くなり、私にはとても心地よい。 これはテンポ・ルバートを控えた表現、早めのテンポを主体とし、残響の広がりや音の揺れを一定範囲で厳密に制御することによって生まれる効果である。そう、だから、これは凄い演奏だと思うけれど、楽団員は演奏していて、それほど楽しくないのかもしれない(笑)。けれども、総体として生まれるサウンドは、清涼感に満ちていて、これが早いテンポとあいまって、最高に気持ち良い爽快性をもたらす。 こう書くと、いかにもオリジナル楽器演奏的な印象をもたれるだろうか?たしかにそういった面もある。だがギーレンの演奏で素晴らしいのは、適度に浪漫派から続く演奏史の表現を踏まえた「味わい」を残しているところにある。オリジナル楽器演奏のように、学術的なもので割り切らず、適度にエモーショナルなものが残っていて、それが様々な味として効いてくる。だから、何度聴いても楽しめるのだ。例えば第9交響曲の第3楽章、あの有名な祈りの音楽に、様々なものが浄化されていく時に放つ神々しい薫りが漂っていると思えるのは、合奏音に混濁がないだけでなく、音色に健やかな情感が息づいているためである。 そうして聴くと、このギーレンの演奏は、もう十数年前のものであるにもかかわらず、素晴らしい鮮度を持って聴き手に迫ってくるものだ。感情的な偏りが少ない分、何度聴いても飽きることのない快演奏と言えるだろう。 |
|
 |
交響曲全集 ブロムシュテット指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 MDR放送合唱団 ゲヴァントハウス合唱団 ゲヴァントハウス児童合唱団 S: シャトゥロヴァー A: 藤村実穂子 T: エルスナー Br: ゲルハーヘル レビュー日:2018.3.13 |
| ★★★★★ 90歳のブロムシュテットが示す清新なベートーヴェン解釈
ヘルベルト・ブロムシュテット(Herbert Blomstedt 1927-)が名誉指揮者を務めるライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と製作したベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の交響曲全集。CD5枚の収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ長調 op.21 2017年録音 2) 交響曲 第2番 ニ長調 op.36 2015年録音 【CD2】 3) 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」 2014年録音 4) 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60 2017年録音 【CD3】 5) 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」 2017年録音 6) 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」 2016年録音 【CD4】 7) 交響曲 第7番 イ長調 op.92 2015年録音 8) 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93 2014年録音 【CD5】 9) 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付」 2015年録音 第9番の合唱は、MDR放送合唱団、ゲヴァントハウス合唱団、ゲヴァントハウス児童合唱団の編成。4人の独奏者は、ソプラノがシモナ・シャトゥロヴァー(Simona Saturova)、アルトが藤村実穂子、テノールがクリスティアン・エルスナー(Christian Elsner 1965-)、バリトンがクリスティアン・ゲルハーヘル(Christian Gerhaher 1969-)。いずれの音源もライヴ収録されたもの。 まず、このシリーズ作製中に90歳となり、今なお世界を駆け巡り、あちこちのオーケストラの指揮台に立ち続けているブロムシュテットに敬意を表したい。 さて、演奏である。私はベートーヴェンの交響曲全集の録音で、このオーケストラによる二つの名盤を愛聴している。一つはコンヴィチュニー(Franz Konwitschny 1901-1962)盤、もう一つは、リッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)盤だ。 このうち、シャイーの録音が2007年から09年に行われていて、このオーケストラにとって直近のものと言える。それは、ベートーヴェンのメトロノーム指示をほぼ遵守し、きわめて快速でありながら、内燃的な表出力、エネルギーにも事欠かない見事なものだった。 対するにブロムシュテットは、80年代にドレスデンと録音したベートーヴェンを聴く限りでは、はるかに穏当なスタイルであったと思う。それからさらに30年を経て90歳になるころに振ったベートーヴェンは如何に?これが、なかなかびっくり。しばしばブロムシュテットの年齢から、当全集に「円熟」という形容が行われているようだが、私はこの演奏に「円熟」という言葉が適切だとは考えない。ブロムシュテットがこの30年間で、何をどう考えたのか、興味深いが、テンポは一貫して早い。以前の彼の録音よりずっと早い。 とはいっても、そのテンポの早さはシャイーほどではない。ブロムシュテットは、かつては「早すぎる」と考えられてきたベートーヴェンによるメトロノーム指示について、様々な試みが行われるようになってきた現代までの流れを鑑み、自分なりの再考を経て、「これだ」というものに至ったのだろう。それが「彼の旧録音よりかなり早く、しかしシャイーよりは少し遅い」というポジション。そのテンポの「置き所」が、まずは当盤の特徴であろう。そして、このテンポによる音楽表現について、ブロムシュテットは相当深く検討し、周到に準備したと思われる。そう思わせるくらい、この演奏のテンポは確信に、満ち溢れていて、輝かしさを感じさる。オーケストラがとても生き生きしていることは言うまでもない。それは円熟というより、颯爽とした新鮮味にあふれた響きといって良い。 ブロムシュテットの演奏からは、随所に「敏捷さ」が顔を出す。それは単にテンポが早いというだけの話ではない。音の減衰までち密に計算された強弱、適度に間合いを詰めた呼吸。それらが反映された音の長さと強弱。それらが組み合わさって、とても自然な味わいで演奏され、本格的な、まさにクラシックな響きを形成するのである。巨匠が培ったオーケストラを統御するノウハウを存分に感じさせるし、その結果、清新な音楽の流れが導き出されていることに感動する。音自体のすばらしさ、例えば弱音であっても、しっかりと芯の通った響きであり続けていることも、見事なところ。 また、全般にバズーンやクラリネットといった楽器の、幸福感に作用する音が、常に生気にあふれた明るさを持っているところも印象深い。心地よく流れる透明な響きのヴェールの中で、これらの木管楽器が添える色合いの美しさは、得難いものに違いない。 他方で、もしこの演奏に不満を感じる人がいるとしたら、重々しい劇性の効果が減じられて感じられるところだろうか。シャイー盤と比べると、ティンパニの効果は強くないだろう。とはいえ、それは徹頭徹尾計算された上でのことであり、全体のバランスは絶妙にキープされているといって良い。 第9では声楽陣の好演も目立つ。特にゲルハーエルの美声は、人を酔わせる力を持つ。 90歳を迎えるブロムシュテットが、周到に検討を重ね、これだと自信をもって提示したベートーヴェンが、ここで表現されている。 |
|
 |
交響曲 第1番 第2番 序曲「プロメテウスの創造物」 「レオノーレ」序曲第3番 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 レビュー日:2012.3.16 |
| ★★★★★ 「速きこと」に明瞭なプライオリティーを示した演奏
2007年から2009年にかてて録音されたリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全集からの分売。計5つに分かれての分売で、それぞれのディスクは全集中での5枚のディスクをそのまま抜き出した形で、曲順の変更などは行われていない。 これは全集の1枚目に相当するディスクで、交響曲第1番、第2番、序曲「プロメテウスの創造物」、「レオノーレ」序曲第3番が収録されている。 シャイーのように多彩なキャリアを積んできた指揮者が、これまでそれほど取り上げてこなかったベートーヴェンの交響曲を世に問うとき、おそらく相応の準備なり検討を重ねるに違いない。レコード時代から常に録音の王道レパートリーであり続けたベートーヴェンにおいて、自分(とオーケストラ)の名によりエントリーするためには、そこにどのような「新しい価値」を吹き込めるかが重要だ。 そういった意味で、シャイーのベートーヴェンの全集は極めて果敢な積極作に打って出たものであり、私もこの全集を聴いて、今までにない刺激を与えられた。これらの全集が「旧来の価値観と違う」という不満が人によってあるのは当然だと思うが、そのことは、決してこの演奏が劣っていることを指すものにはならないだろう。 この全集の主な注目点は(1)新鮮でダイナミックかつスピーディーな解釈、(2)それを可能とするオーケストラのヴィルトゥオジティ、(3)それらの特徴を克明に捉えた録音、ということになるだろう。 シャイーの演奏の抜群の特徴は「速さ」だ。最近よく使用されるベーレンライター版などのスコアを用いているわけではないのだが(むしろあえて旧来のオーソドックスなスコアを採用したのではないか)、明瞭に「速さ」中心のプライオリティーを打ち出したその手法は、「迅速を尊ぶ」の趣だ。これは基本的に(よく早すぎると指摘される)スコア中のメトロノーム指示に従った結果であるのだが、ピリオド奏法などにこだわらず、現代楽器で高いクオリティの演奏が再現できている点が見事。現在辿ることができるこのテンポの元祖はトスカニーニ(Arturo Toscanini 1867-1957)ということになるだろう。シャイーは現代の録音技術を意識し、一層の音色、音響を配慮しており、その点が「現代的」だ。交響曲第1番と第2番は大きく性格の異なる音楽だが、ベートーヴェンの強い主張はむしろアレグレットなどの急速楽章に強く打ち出されていると思える。それで、シャイーはその力点に畳み掛けるような、強烈なインパクトを設置している。「レオノーレ」序曲第3番では、鋭い金管の立ち上がりが印象的で、ベーレンライター版を用いたジンマン盤以上の先鋭性を感じさせる。最近聴いたベートーヴェンでもとりわけ強力に衝撃的な内容であり、爽快演奏だと感じられた。 |
|
 |
交響曲 第1番 第2番 ファイ指揮 ハイデルベルク交響楽団 レビュー日:2021.12.7 |
| ★★★★★ ファイとハイデルベルク交響楽団によるベートーヴェン。活力に満ちた表現が魅力
トーマス・ファイ(Thomas Fey 1960-)指揮、ハイデルベルク交響楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の以下の2つの交響曲を収録したアルバム。 1) 交響曲 第1番 ハ長調 op.21 2) 交響曲 第2番 ニ長調 op.36 2000年の録音。 非常にアグレッシヴで、前進する力に満ちたベートーヴェン。ハイデルベルク交響楽団は、トランペット、ホルン、ティンパニがピリオド楽器で、他が現代楽器という「混合編成」だが、ファイの演奏スタイルは、弦楽器陣のヴィブラートを抑制し、いわゆるベーレンライーター版準拠による快速進行である。ピリオド奏法を念頭に置いた上で、自分なりのベートーヴェンを積極的に描き出そうとした意欲の漲る演奏と言える。特徴は畳み掛けるようなアップテンポと、収束性の高い切り口の鋭さである。弦楽器陣は、ヴィブラートを抑えているため、やや硬く、輝きに乏しい面はあるものの、機敏な動き回り、瞬時の反応性でこれをカバーし、全体として、運動的な快感を強く刺激する方向へ向かっている。トランペットは、ピリオド楽器特有の不安定さを持ちながらも、タイミングを律義に守って、リズムの効果を高める役割を強めに担っており、全体としての方向性は齟齬が無い。一貫性の強い演奏だ。 第1番では、第3楽章に示されるベートーヴェンの新規性が、積極的に表現されている。第1番という楽曲は、基本的には、第2番以降の飛躍に比べ、ベートーヴェンが、いまだ保守的な作風を踏襲している傾向が強い作品なのだが、この第3楽章には、その後のベートーヴェンを示唆するものが多くあり、いわゆるスケルツォ的性格が表出している。ファイは、その新規性やユーモア、そしてどこか雰囲気の異なったものが流入してくる楽想を、恣意的な表現性で強く描き出しており、魅力的だ。 第2番は、さらにファイの解釈が活きた感がある。第2楽章では、「ラルゲット」としての活力とエネルギーが、スケールの大きさを感じさせつつ放出されており、爽快。第3楽章の「スケルツォ」も、明瞭な緩急とアクセントを織り交ぜて、活発で、生命力に満ちた音楽となっており、見事。そして、両端楽章では、勢いに勢いを重ね、ひたすらアクセルを踏み込むような躍動性があり、スピードそのものの魅力とあいまって、生気に溢れた音楽になっている。音の奔流と称したいその様子は、この交響曲の魅力を的確に表現している。 音色自体に好みが分かれるかもしれないし、人によっては、もう少し落ち着きが欲しいと感じられるところもあるかもしれない。ただ、私は、ファイのこれらの録音が、音楽的な魅力を湛えたものであり、演奏芸術として、高いレベルにあるものと感じます。 |
|
 |
交響曲 第1番 第2番 第3番「英雄」 ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2012.7.10 |
| ★★★★★ 今だからこそ、あえてやりたかった。このスタイルの演奏!
ドイツの指揮者、クリスティアン・ティーレマン(Christian Thielemann 1959-)が、2008年から2010年にかけてウィーンフィルと行ったベートーヴェンの交響曲全曲演奏プロジェクト「BEETHOVEN9」の模様を収録したCD。全3巻で分売されていて、本巻には第1番、第2番、第3番「英雄」の3曲が収録されている。録音は第1番と第2番が2008年、第3番が2009年。 今の時代では、あまり聞けない、むしろユニークとも言える演奏だと思う。しかし、決して奇異というわけではない。むしろ、かつてよく聴かれ、多くの人に好まれたスタイルを現代のオーケストラのスペックと録音技術で記録したというもので、意表を突いた領域を占める録音だと思う。 端的に傾向を示しているのが交響曲第2番の第1楽章。このAllegro con brio(輝きをもって速く)の指示のある音楽は、現代ではインテンポで颯爽とまとめることが多いが、ティーレマンの音作りは肉厚で、実に表情豊か。それだけでなく、音幅のあるアクセントの挿入により、時に、はっきり意識するほど指揮者の「こう振るんだ」という気持ちが伝わる。この交響曲から、このような感興を得る経験というのは、最近ではほとんどないと言っていいと思う。 もう一つ感心するのは肉厚な音響を導きながら、決して鈍重な音にはならないことで、むしろその状態である程度のスピードを維持することに迫力が感じられる。 第3番「英雄」も濃厚なポルタメントが印象的で、いかにも豪放で古風な英雄像を描いている。第2楽章も演出が施されており、現代の主流といえるシャープなスタイルに味気無さを感じる人には嬉しいところだろう。 私は、このティーレマンの演奏を聴き、いくつか近い音楽を聴かせてくれた指揮者の名を思い浮かべた。カラヤン、バーンスタイン、フルトヴェングラーなど、私の中では「近い」と感じる演奏である。現代で強いて言うならバレンボイムか?私はバレンボイムも、過去のスタイルに並々ならぬ憧憬を持った指揮者だと考えているが、このベートーヴェンを聴いて、ティーレマンもそうなのではないだろうかと思った。いかがだろうか? 英雄交響曲の終楽章は私も大好きな音楽であるが、これほどおおらかに鳴る金管と、たっぷりした弦楽器の響きを、衒いなく解放する演奏というのは、デジタル録音ではちょっと探し出せないぞ、と感じた。そういうこともあり、先に書いた「意表を突いた領域を占める」録音が登場したと実感したわけである。 この演奏、繰り返しの試聴を前提とする現代のメディアで、聴き手に飽きられないか?という心配は残るけれど、しかし、逆に、だからこそ、この演奏をしたかったんだ、というティーレマンの主張があると思う。そのようなハートが伝わってくるこの録音は、それなりの価値を伴うに違いない。 |
|
 |
交響曲 第1番 第2番 第3番「英雄」 第4番 シュイ指揮 コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2018.4.3 |
| ★★★★★ びっくりの名快演!ラン・シュイによるベートーヴェン
中国杭州市出身のラン・シュイ(Lan Shui 1957-)指揮、コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の交響曲集。CD2枚に以下の収録内容。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ長調 op.21 2011年録音 2) 交響曲 第2番 ニ長調 op.36 2009年録音 【CD2】 3) 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」 2012年録音 4) 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60 2010年録音 さて、ベートーヴェンの交響曲となると、録音の数自体、無数と言っていいほどのものがある。その中には、名盤と呼ばれるものがあったり、あるいは新解釈として名高いものがあったりする一方で、ほとんど表だってとりあげられるようなことのないものも、当然のことながら随分ある。 失礼をわきまえたうえで、言わせていただければ、この録音も、おそらく日本の批評界で、まともに取り扱われたことはなく、クラシック音楽フアンでさえ、その存在さえ知らない人が大部分ではないだろうか。しかし、そのような録音の中に、捨てがたいものが数多くあることもまた然り。それにしても、このラン・シュイのベートーヴェン、「捨てがたい」でくくってしまうレベルをぶち破るとんでもない快演だ。この録音を聴いて、私は、ベートーヴェンの交響曲に、まだまだ表現の突き詰められていない部分が残っていたことを痛感した。それくらい、発見の面白味と、音楽を聴くことの喜びを存分に提供してくれる、まさに痛快な演奏である。 ベートーヴェンのメトロノーム指示が、「早すぎる」と考えられ、その通りに演奏することに疑問を投げかけてきた歴史があることは言うまでもないかもしれない。そして、最近になって、やはりそのメトロノーム指示で表現する可能性について、様々な解釈が示されてきたことも。 その中で、このラン・シュイのベートーヴェンは、私の聴く限り、最高といって良い回答を導いたものに他ならない。オーケストラは、ティンパニと一部の金管楽器のみピリオド楽器で(パーヴォ・ヤルヴィも同様の試みを行っている)、かつ最大でも70人程度の編成。大規模なものではない。それゆえの各パートのバランスを徹底して緊密に磨き上げたうえで、連携を強化した鮮やかな快速運転を実現している。しかも、それが決して音楽表現として必要なものを置き去りにせず、いや、このテンポだからこそ「出来ること」をすべてやりつくしたような、圧巻の手際の演奏となっているのだ。ラン・シュイという指揮者、ただものではない。 交響曲第1番の両端楽章の見せる生気に溢れた推進力(弦の限界に挑むような鋭い表現!)、第3楽章の迫力満点の切迫感、通常は葬送行進と言われる第3番の第2楽章のスタイリッシュな抜けの良さ、第4番の終楽章のそれこそ疾風怒濤かくありといった趣き。しかも、それらがただ面白い、ユニークというだけでなく、音楽的な真実味と切迫性をともなったしっかりした手ごたえのある表現として、完成されているのである。 ベートーヴェンの交響曲にすっかり聴きなれて、いまさら、と思う人にこそ聴いてほしい。刺激と魅力に満ち溢れた内容だ。 |
|
 |
交響曲 第1番 第2番 第5番「運命」 第7番 ドホナーニ指揮 クリーヴランド管弦楽団 レビュー日:2011.1.20 |
| ★★★★★ まるで近代高層建築のビルディングのようなベートーヴェン
最近、ドホナーニ指揮クリーヴランド管弦楽団の録音を一通り聴こうと思っていろいろ聴いている。このTELARCレーベルへのベートーヴェンの全集も、ひととき評判になったと聞くけれど、私は今まで聴いたことがなかったので、あらためて聴いてみた。 本ディスクには、第1番、第2番、第5番「運命」、第7番の4曲が収録されている。録音年は第5番と第7番が1987年、第1番と第2番が1988年。 一聴して、(多少予測はしていたけど・・)そのクリアなサウンドに驚かされる。クリアというのは、それぞれの楽器の音色が直線的で、ハーモニーというよりいくつかの階層が存在していて、その階層の総体としてそこに交響曲が出来上がるというような、近代建築の枠組みのようなイメージなのだ。そのイメージ中の建築物には、非常に吹き抜けの良い空間があって、どこか人工的な観葉植物が等間隔でディスプレイされているような、高級感のある近代的空間が広がっている・・・ ベートーヴェンの音楽を演奏するにあたっての一つのポイントとして、「パッション」をどのように表出するのか、ということがあると思うのだけれど、ドホナーニのアプローチは均質的な音の配置により、むしろパッションの成分を分離抽出して純化させ、一段手前のパーツに還元してしまったような面白さがある。例えば運命交響曲でも、第3楽章から第4楽章にかけて。管弦楽の響きは多層的。従来この部分は「盛り上がって勝利の行進」という発汗作用の多いところだけれど、クールに、ドライにこなしてしまう。テンポも速く、その音楽の質について考えるより、ひたすら聴き手は感性で付いて行き、即時即時で感応していく、というような・・・そしてあっというまにフィナーレである。これほど発汗作用の少ないベートーヴェンというのはちょっと珍しい。 第1番と第2番はその快活さが全面に出ている。表現は解析的だが、第2番の第1楽章の颯爽たる進捗は、まるで初夏の深緑の中を心地よいスピードでドライヴしているような気持ちになり、広々とした開放感に満ちている! 第7番も透き通った音楽になっていて、くっきりとしたサウンド、明瞭な距離感が常にキープされている。これは、とても個性的なベートーヴェンだ。ベートーヴェンの交響曲の場合、とにかく膨大な録音数があるのだけれど、中にあってこれだけ指揮者の顔がはっきりと伝わる演奏も珍しいだろう。好悪が分かれる可能性があるけれど、突き抜けた魅力を持ったベートーヴェンの一つだと思う。 |
|
 |
交響曲 第1番 第3番「英雄」 ハイティンク指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2009.12.30 |
| ★★★★★ 素晴らしい作品をまっすぐに演奏した王道の名演
80年代にハイティンクが20年の永きに渡って蜜月関係にあったコンセルトヘボウ管弦楽団と録音した珠玉のベートーヴェン交響曲全集からの分売。第1番と第3番という贅沢な内容である。ベルナルト・ハイティンクという指揮者の評価は、当初日本ではあまり高くなかった。むしろブルックナーの第0番のようなマニアックなジャンルの録音なので、「全集請負人」的な便利屋の位置づけだったと思う。今にして思うととんでもない話で、いま例えば70年代のハイティンクの録音などを聴いてみても、その評価があまりに軽んじられたものであったことは明白だ。 そんなハイティンクの日本国内での名声を確固付けたのがこのコンセルトヘボウ管弦楽団との集大成とも言えるベートーヴェンだろう。 さて、ハイティンクの演奏であるが、なにも際立って特徴的なことをやっているわけではない。しかし、必要なことだけ指示し、輪郭をまとめた上で、オーケストラの自発性にゆだねたような拘束感のない音楽となっている。その印象は「喜び」といった感情となって聴き手に伝わるものだと思う。なので、第3番の第2楽章のような深刻な楽想も、強く悲劇性を感じさせるわけではない。しかし、もともとの音楽それ自体がもっている音楽的な性質だけで十分であるという確信があるため、未練のない堂々たる音楽になっている。 このころのハイティンクの音作りはやや柔らかめである。この後、ハイティンクはウィーンフィルとブルックナーを、ベルリンフィルとマーラーを精力的に録音したのだけれど、そちらは比較的引き締まったソリッドな音色である。今世紀になってロンドン交響楽団と録音したベートーヴェンもそう。どちらが優れているというわけではないが、コンセルトヘボウ時代の柔らかい曲線的な音色の方を好む人も多いのではないだろうか。 最近ではこういうベートーヴェンはもう一つインパクトがないということになるのかもしれないが、素晴らしい作品をまっすぐに演奏した王道の名演として、私には今後も愛聴盤として聴き続けたい名録音である。 |
|
 |
交響曲 第1番 第6番「田園」 第8番 アシュケナージ指揮 NHK交響楽団 レビュー日:2008.5.25 |
| ★★★★★ まさにアシュケナージとNHK交響楽団の「有終の美」
非常に素晴らしい演奏である。この録音を聴いてNHK交響楽団が確かな力量を備えた世界的なオーケストラであることを再認識した。 指揮は2004年か2007年までNHK交響楽団の音楽監督を務めたアシュケナージ。アシュケナージは、従来指揮者としてはベートーヴェンをほとんど取りあげてこなかった。しかしNHK交響楽団という、ドイツ・オーストリアものをレパートリーの中心としているオーケストラを振るにあたって、また彼の中でも、いまベートーヴェンを振ろうという要求があり、充実した録音のラインナップになったに違いない。今回は第6番がライヴ録音で、第1番と第8番がスタジオ収録された。いずれも2007年の録音。 当録音で特徴的なのは、チェロ、コントラバスの豊かな表情付けである。実際、ベートーヴェンの交響曲を聞いていて、これらの低弦楽器の細やかなニュアンスがこのように伝わってきたことはない。田園交響曲第1楽章の心地よいフレーズで、淡々としかし憂いを含みながら添えられるチェロバスの音色は絶品といっていい。 全般にいつものアシュケナージらしく健康的で明朗・軽快なテンポ設定であるが、音色の深みがいつも以上であり、その全体的な響きが高い品格となって曲調を支えている。現代楽器を用いたまさに「王道のベートーヴェン」だと言っていい。第1番や第8番の、木管主導のフレーズや、あるいは隠し味的に添えられる経過句も実に的確に決まっている。 金管の立体的な彫像も見事。田園交響曲の第3楽章でオーケストラ最後方から吹き鳴らされる音の伽藍は圧巻の迫力がある。第4楽章の嵐の描写の切迫感も精度の高いアプローチで驚かされる。そして嵐のあと、第5楽章への移行部で低弦による遠雷が残るなか、雲間から差すホルンの厳かな光の美しいこと!NHK交響楽団の録音の中でも最高傑作といえるものだと思う。 |
|
 |
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ブラームス 交響曲 第2番 ヤンソンス指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2006.3.21 |
| ★★★★★ ヤンソンスの充実を示すベートーヴェンとブラームス
1943年ラトヴィア生まれのマリス・ヤンソンス(Mariss Janssons)はすっかり現代を代表する指揮者となった。20年の長きに渡り手兵オスロフィルを磨き上げた後、2003年からバイエルン放送響の音楽監督に就任する一方で、2004年8月月からロイヤル・コンセルトヘボウ管の首席指揮者にも就任。まさにヨーロッパの中枢といえる2つのオーケストラを使い分ける一方で、2006年のウィーンフィルのニュー・イヤーコンサートにも抜擢された。さて、その録音活動であるが、ここにきてライヴ録音の比率がぐんと増えている。バイエルン放送交響楽団とのライヴはCBS系列から、そして当盤を含むコンセルトヘボウ管弦楽団とのライヴ録音は自主製作レーベルであるRCO LIVEから続々とリリースされている。 今回はベートーヴェンの第2交響曲とブラームスの第2交響曲を収録。2004年10月27日と28日のライヴを収録したもの。ヤンソンスのベートーヴェンは珍しいが、最近の若手指揮者では、比較的ベートーヴェンというと、この第2を取り上げる傾向があるように感じる。この曲の古典性からロマン派を遠謀するような、「時代の幕開け」的な趣きが共感を得やすいのか?たしかリッカルド・シャイーもベートーヴェンではこの曲をコンセルトヘボウと振っていた。 さて、演奏であるが、非常にふくよかで優しい演奏である。弦楽器陣の包容力のある響きが高級感をかもし出す。テンポはたいへん穏当なもので、早過ぎず、遅過ぎずという、いつものヤンソンスのスタイルだ。木管のチャーミングな響きも特筆される。ブラームスの第2交響曲第1楽章終結部の典雅な音色は天国的。録音はライヴにしては検討しており、ときおり合奏の強奏音がやや硬めにはなるが、気になるほどではない。適度な乾きのあるやや軽めの響きは、弦楽器の合奏の表情を細かく再現できている。 |
|
 |
交響曲 第2番 第3番「英雄」 第7番 ベーム指揮 バイエルン放送交響楽団 レビュー日:2008.3.20 |
| ★★★★★ まさしく貫禄の名演奏です
「カール・ベームがドイツのオーケストラを振ってのベートーヴェン、悪いはずがない」と乱暴な言い方をしてしまえばそうなるのだが、聴いた後は「ほら、ね!」となる貫禄の名演奏です。 ベーム(Karl Bohm 1894-1981)はオーストリアに生まれた名指揮者で同時代の演奏家たちに与えた影響は絶大であった。4回の来日公演で日本のファンにも広く親しまれていた。来日のたびに熱狂的なファンに囲まれ、TVや新聞も大きく報道した。いま現在では情報の価値観が多様化したこともあり、ベームに相当するようなアーティストはいないと言わざるをえないでしょう。 さて、演奏。当盤には十八番といえるベートーヴェンの交響曲が3曲収録されている。第2番、第3番「英雄」、第7番で、第7番のみ1973年、他の2曲は1978年のライヴ録音。オーケストラはバイエルン放送交響楽団(Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks)。~ベームはオーストリア生まれだが、私個人の感想としてはドイツのオーケストラ(ベルリンフィル、ドレスデン国立管弦楽団、ケルン放送交響楽団、ベルリン・ドイツオペラ、バイエルン放送交響楽団など・・・)との録音にことさら素晴らしいものが多いと思う~。この演奏にまさに勇壮そのものの演奏。時代背景もあって、いま流行の「オリジナル楽器的」演奏に一顧だにしないゆるぎない巨匠性を感じる。落ち着きのあるテンポでオーケストラから太く逞しい音色を引き出す。ホルンはアルプスの峰々から高らかに鳴り響くようだし、ティンパニは真ん中を叩いているかのごとく重量感を持って響き渡る。そしてその活力のよさ、心地よい疾走間。クライマックスで開放される音、その膨大なエネルギー量はすさまじい。それでいて筋肉質ともいえるバランスに満ちた均衡性。さすがと感服せずにはいられない。特に第7番は圧倒的。一瞬たりとも弛緩せずに脈々と生命感を供給し続ける熱が全編に満ちている。録音状況も良好。 |
|
 |
交響曲 第2番 第4番 ハイティンク指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2009.12.30 |
| ★★★★★ 現代楽器のパワーを感じる比類ない膂力ある名演
ベルナルト・ハイティンクが80年代にコンセルトヘボウ管弦楽団と録音したベートーヴェンの交響曲集が分売の形で再リリースとなった。レーベルの統廃合のため、従前フィリップスであったが、このたびはデッカに変わっている。 ハイティンクという指揮者は、今でこそ日本国内での評価も確立しているが、今一つ評価のタイミングが遅れたという感じがする。あくまで私見であるけれど、この指揮者の国内での評価が定まったのは、アシュケナージとのラフマニノフやブラームスの協奏曲録音あたりからではないだろうか?かく言う私も、あのラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の重厚にして厳かなサウンドで音楽の世界に引きずり込まれた1人である。 そこで、今回あらためてハイティンクとコンセルトヘボウ管弦楽団のベートーヴェンを聴いた。一聴していまとなっては懐かしい古典的なオーソドックスな名演だと思う。最近ではベートーヴェンの交響曲の録音となると、ちょっと編成を小さくしてみたり、ピリオド楽器を使ったり、版の問題に踏み込んだアプローチを試みるなど、「戦略的」な部分がそのカラーとなる。しかし、ここに聴くハイティンクの演奏は、まさに王道のど真ん中に投げ込んだ直球である。魅力的でないはずがない。 もちろん、ベートーヴェンの素晴らしい交響曲である。普通に演奏すれば十分魅力的な音楽となる。では、ハイティンクの当演奏のプラスアルファは何か?私の場合、オーケストラの各パートの織り成す暖色系のコントラストがたいへんな魅力だと思う。コンセルトヘボウ管弦楽団というオーケストラの持つまろやかなテイストが、自然で伸びやかに繰り広げられる。第2番は元来弦楽器のよく響く古典的な調性の音楽であるが、このオーケストラの場合さらに鮮やかな色彩感が添えられる。また過度な発色にはならないハイティンクの統率力も見事だ。第4番は序奏の後の全合奏の壮麗さが印象的。第2楽章の気品のある「たゆたい」も輝かしい表現だと思う。また全般に最近のピリオド楽器演奏に顕著な「あざとさ」がないという点もよい。もちろんピリオド楽器による演奏にもそれなりの魅力があるのだけれど、何十年にも渡って進化した現代の楽器による表現力を全開した演奏のパワーというのは比類ない。 |
|
 |
交響曲 第2番 第6番「田園」 クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団 レビュー日:2011.12.16 |
| ★★★★★ ライヴ録音で伝わるクーベリックの芸術家としてのみなぎる情熱
チェコの指揮者、ラファエル・クーベリック(Rafael Kubelik 1914-1996)による往年のライヴ録音。ベートーヴェンの交響曲第2番と第6番「田園」で、オーケストラはバイエルン放送交響楽団。録音は、交響曲第2番が1971年で、第6番が1967年。 クーベリックは独グラモフォンと多くの正規スタジオ録音があり、それらを通じて私もこの巨匠の音楽に触れてきたが、近年、Auditeレーベルによって、多くのライヴ音源がCD化され、私たちはそちらも聴くことができるようになってきた。 よく、スタジオ録音とライヴでは演奏のスタイルの異なる指揮者がいると言われる。古いところでは、フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler 1886-1954)などもその代表格で、ライヴの方が魂の宿ったような演奏になると表現される。また、チェリビダッケ(Sergiu Celibidache 1912-1996)みたいに録音自体を受け付けたがらなかった人もいる。 それで、最近クーベリックのライヴ録音など、どんどん巷に出るようになると、どうやらクーベリックもスタジオ録音とライヴ録音で、若干以上に雰囲気が変わる指揮者だったように思える。たとえば、彼の振ったマーラーの第5交響曲なんて、ライヴの激烈さはちょっとスタジオの正規録音からは考えられないものだったから。 それで、このベートーヴェンもなかなか凄い。たいへん熱気のある演奏だ。オーケストラ全体が聴衆に向かって前のめりになってくるような、そんな演奏。交響曲第2番はいかにも巨匠的で、大オーケストラを燦然と輝かしく鳴らしているのが特徴。弦楽器陣の多少の過度な残響も厭わないたっぷりした鳴りが力強い。個人的に、合奏音の末尾がやや広がって締まりがないところがあるのが少々気になるけれど、全体的な勇壮さは、最近の主流の演奏とは一線を画した風格を導いている。 交響曲第6番もほぼ同様のスタイルだが、こちらの方がややシェイプアップ感のあるフォルムかもしれない。しかし、有名な第4楽章の嵐のシーンのつんざく様なトランペットの咆哮に、この瞬間にあったクーベリックの芸術家としての留めようもない情熱が照らし出されているように思う。また、私はこの曲では、嵐の過ぎ去った後、つまり第4楽章から第5楽章へ移ろう部分が大好きなのだけれど、この部分でもクーベリックの美意識は存分に発揮されていて、陰影の濃い音楽を味わわせてくれる。 クーベリックの遺したこれらのライヴ音源をCD化してくれたAuditeレーベルに感謝したい。 |
|
 |
交響曲 第2番 第7番 アシュケナージ指揮 NHK交響楽団 レビュー日:2008.8.7 |
| ★★★★★ まさにアシュケナージとNHK交響楽団の「有終の美」
アシュケナージとNHK交響楽団によるベートーヴェンの交響曲全集が本盤をもって完結した。このオーケストラの力量が十全に表現された全集であり、アシュケナージとの録音も適切な時期だったと思う。国内の実力あるオーケストラの一つの金字塔の完成を祝いたい。 それにしても、その最後を飾るに相応しい名演である。私はTVで、この第7交響曲の演奏の模様を視聴したのだが、その闊達にして漲るエネルギーと爽快なパフォーマンスにCD化を心待ちにしていた。そんなわけで発売日に予約して購入した。NHKホールでの収録だったので、録音を心配したが(同じNHKホールで収録された第9番の録音は良くなかった)、今回の録音は十分現代の水準あり、そのことにほっとしたが、それよりも演奏である。 まず第2番も非常に的確なスケールで瀟洒に、しかし良心的で絶対的な音楽の範に即している。心持ち適度な距離感もあり風通しがあるのが心地よい。しかし圧巻はやはり第7番である。第1楽章の冒頭の和音から見事な質感である。そのあとの全合奏による主題の提示では音色のブレンドがきわめて秀逸。今まで聴いたことがない、しかし確かにやってみると「おおっ」と思う音色だ。これが「NHK交響楽団の音」なのだろうか。もちろん聴き手の好みの問題もあるだろうが、私はどうもアシュケナージの感性が伝わりやすい体質であるようだけど、それを差し引いても見事だと思う。第2楽章は高雅さと的確なリズムがあいまってとても心地よい。終楽章が圧巻中の圧巻。爽快なテンポ、もちろん速ければいいというわけではない。音楽的で、確信的で、論理的。それでいて感情の思い切った開放があり空に向かって解き放たれるような力感だ。終演後の熱狂的な拍手も必然の効果のように聴こえる。このような録音で全集の幕が閉じられるのは実に喜ばしい。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 朝比奈隆指揮 大阪フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2009.5.23 |
| ★★★★☆ 本当に「一番新しい録音」が、「いま聴いて欲しい直近の成果」だったのだろうか?
それにしても朝比奈隆はいったい同じ曲を何回録音したのだろう?と思ってしまう。もちろん再録音にも必要な場合がある。代表的な理由として(1)録音技術が進歩した場合、(2)自身の楽曲への解釈を変更した場合、(3)別の共演者(オーケストラ)とアプローチをする場合、(4)レーベルの変更等による商業的都合、(5)以前の録音に不満な点が残る場合。 たいていの場合、そのどれかもしくは複数に該当する正当な再録音理由があるのだけれど、朝比奈の遺した膨大な録音には、根拠の不明なものが多い。レパートリーが少ないとは思わないが、一部のコアなファンによる購買が確実なため、同曲異録音が多くなる状況を誘発してしまった面もある。 かくいう私も、そのために朝比奈の録音には手を出し難い状況である。本人にとって、本当に当時の「一番新しい録音」が、「いま聴いて欲しい直近の成果」だったのだろうか?これは私がこのアーティストに抱き続けた率直な感想である。さてこの演奏を聴く。演奏自体が悪いとは思わない。ややゆったりとしたテンポで裾野を広げつつ、スケールの大きい音楽を作っている。かつてこの指揮者にあった特有のアクが薄くなっているのは、私にはむしろ聴き易い。それでも部分的な強奏音など、やや唐突な箇所は残るが、音楽の愉悦性を引き出したと考えると、歓迎されてしかるべき表現だろう。それにしても「朝比奈のベートーヴェン」といって、この録音です、というわけでもないだろう。今となっては、なかなかリスナーには手ごわいアーティストになってしまった。 |
|
 |
ベートーヴェン 交響曲 第3番「英雄」 ワーグナー ジークフリート牧歌 ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2007.3.27 |
| ★★★★★ ニーベルングを彷彿とさせるような英雄交響曲
この「英雄交響曲」が録音されたのは1959年である。1959年といえば、ショルティが名プロデューサー、カルショウとともに歴史的名盤となるワーグナーの「ニーベルングの指輪 全四部作」に取り組んでいたところである。筆者もこの名録音をLPそしてCDで聴いてきたが、これは本当に「凄い」の一語に尽きる録音で、いわゆる音楽の「記録芸術」の金字塔ともいえるものである。技術も圧巻であるが、それに加えて圧倒的なエネルギーに満ちた歌手陣とオーケストラの演奏も神がかり的で、芸術家と技術者の見事なコラボレーション作品であった。そしてその時期にこの英雄交響曲の録音がある。 というわけで、これまた凄い演奏なんです。ショルティはこのあとシカゴ交響楽団とこの曲を2回録音していますが、それらと比較してこちらは気宇壮大というか、音楽の「踏み込み」がただならない。もう一歩も引かないという感じ。しかし一方でウィーンフィルはウィーンフィルで、その持ちうる限りの芳醇な音色でショルティの挑発(?)に応戦するものだから、いやが上にも尽きない戦国絵巻が繰り広げられるのです。たしかにこれは好みの分かれる演奏でしょう。一般的にはシカゴ交響楽団との録音の方が、スタイリッシュで理知的。私もやはりそちらを高く評価するかもしれない。でも「これにはこれの」と言うか本当に「この録音にしかない」魅力が縦横にあふれていることもまた然り。これはぜひ聴いておきたい一枚だ。録音もデッカならではの優秀さ。ニーベルングの指輪の神がかり的な録音が「必然」であったことをここに証明、と言った感じです。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 レオノーレ序曲 第3番 アシュケナージ指揮 NHK交響楽団 レビュー日:2008.7.1 |
| ★★★★★ 機敏なリズムで爽快、クライマックの恰幅も立派
アシュケナージとNHK交響楽団によるベートーヴェン・チクルスの第4弾。今回は第3交響曲と序曲レオノーレ第3番だ。前者が2006年、後者が2004年のライヴ録音。このシリーズは欠かさず購入しているが、NHKホールで収録された第9番が、なぜか録音の質が悪くて、響きが痩せていたのだけれど、今回のサントリー・ホールで録音されたものは、演奏の質ともども見事な出来栄えで、豊かなホールトーンと合わせて存分に堪能できる一枚となった。 第3番は、アシュケナージには初録音となる。元来、機敏なリズムで颯爽とした音色を好むこの指揮者にあって、なるほどと思える内容だ。同時に、この楽曲ならではのスケール感を巧みに盛り込んでいると思う。第1楽章冒頭、有名な和音連打からして響きが豊かで、不要な肉付きを排したシャープさを感じる。それに続く細やかなで丁寧なコントロールから紡がれる音楽は、明晰であると同時に、適度な柔和さを保つ。楽器間でのモチーフやメロディの受け渡しが回を重ねるごとに、どんどん小気味良くなり、テキパキと決まっていくのはとても気持ちがいい。そして全合奏におけるホルンを中心としたふくよかな金管の響きは深みがあって格調が高い。第1楽章終結近くでもホルンのニュアンスを込めた音色は絶品。終結部の畳み掛けるテンポも心地よい。 第2楽章も名演。ここでは弦の「憂い」が美しいし、決して過度にむせび泣いたりしないのがよい。また中間部からの壮絶なクライマックスの盛り上がりは圧巻で、この部分の演奏効果としては過去の名盤をも凌ぐとも思われる。第3楽章、第4楽章も爽快と言っていいテンポでありながら、必要な音楽的掘り下げや考察も十分にあり、これは実に見事なベートーヴェンの英雄交響曲であると感心させられた。 それに比べるとレオノーレ序曲第3番はやや淡白であったが、もちろん悪い演奏ではない。NHK交響楽団の力量が如何なく発揮された録音と思う。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 レオノーレ序曲 第3番 パイタ指揮 ロイヤル スコティシュ管弦楽団 オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2019.8.31 |
| ★★★★★ 英雄交響曲の名演の一つ
カルロス・パイタ(Carlos Paita 1932-2015)によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の下記の2作品を収録したアルバム。 1) 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」 2) レオノーレ序曲 第3番 op.77b オーケストラは英雄交響曲がロイヤル・スコティシュ管弦楽団、レオノーレ序曲がオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団。 当盤では録音年が不詳であるが、関連サイトで情報収集したところ、英雄交響曲については1975年とのこと。レオノーレ序曲については詳細不明ながら、音質的にほとんど差がないこともあり、いずれ当該年近傍に録音されたものであろう。 演奏はなかなか見事なものである。正直に言うと、当演奏を聴くまで、この時代のロイヤル・スコティシュ管弦楽団が、ここまで堂々たる演奏を繰り広げることが出来たとは考えていなかった。自らの不明を感じ入る。 パイタの指揮は、よく言われるように、フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler 1886-1954)への憧憬が感じられるもので、幅広く、熱気に溢れたもの。 第1楽章は、冒頭の2和音から、輝かしく、勇壮であり、金管は壮麗だ。そのあとも、パワーに溢れた表現で、肉厚でスピーディーな音楽が展開していく。恰幅豊かであるが、決して重すぎないバランスがあり、管弦楽の美麗な響きとあいまって、英雄交響曲に相応しい音像を築き上げていく。弦楽器陣の常に幅を感じさせるシンフォニックな響きは、ロマンティックで奥行きがある。熱を帯びていく展開部、一気果敢に駆け巡るコーダと実に頼もしい。 第2楽章も壮大なドラマ性を持った表現で、旋律は濃厚に扱われ、音楽は豊かに流れていく。決して外面的なものに特化した演奏ではなく、エモーショナルな表現を踏まえた掘り下げがあるため、劇的な高揚感の演出に必要な起伏も見事に再現されている。クライマックスの壮大な音の繋がりは、感動的だ。 第3楽章は機敏な瞬発性が支配的だが、音は決して細くならない。ホルンの音色は、柔らか味がありながらも大きく、それはヨーロッパ山岳地帯の狩を思わせる響きだ。 第4楽章も早めだが、そのテンポには闊達な自在性があり、その自在さが楽想に即していて気持ち良い。決してあざとさを強く感じるわけではなく、自然な太さと強さがあり、勢いが魅力的な音楽表現として消化されている。豊かな音量も好ましい。 レオノーレ序曲も同様のスタイル。 現在、これと似たようなスタイルの演奏をする指揮者として、私は、パイタと同郷の指揮者、バレンボイム(Daniel Barenboim 1942-)を思い出すのだけれど、英雄交響曲を聴く限り、私見では、パイタの方が、巧いと思う。外連味の発揮がとても周到で、自然に心地よく決まっている。バレンボイムの方が世評の高い芸術家なのかもしれないが、機会があれば、是非当盤を一聴して、パイタの芸術性をあらためて評価しても良いのではないか、と思う。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 第4番 歌劇「フィデリオ」序曲 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 レビュー日:2012.3.16 |
| ★★★★★ 「人類の傑作」交響曲を圧倒的な速さで体感
2007年から2009年にかてて録音されたリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全集からの分売。計5つに分かれての分売で、それぞれのディスクは全集中での5枚のディスクをそのまま抜き出した形で、曲順の変更などは行われていない。 これは全集の2枚目に相当するディスクで、交響曲第3番「英雄」、第4番、歌劇「フィデリオ」序曲が収録されている。8曲の序曲がそれぞれ5つのディスクに分割収録されている点もサービス感に溢れ、企画の良心性を感じさせる。 シャイーの演奏の圧倒的な特徴は「速さ」である。かつて、カセットテープに音楽を録音してカーステレオなどで聴いていた頃、英雄交響曲なんて、とても90分テープの片面で収まる音楽ではなかった。だいたい、普通、演奏に50分くらい要するだろう。しかし、このシャイーの録音は全曲が42分20秒で、余裕で45分を切っている。この「英雄交響曲」が完成した当時、「史上最長の交響曲」だったそうだが、42分ではこの肩書きも少し微妙かもしれない。 まったくの余談だが、この作品に関する私の原体験を一つ。アニメ「ルパン三世」でこんなストーリーがあった。「人工音」に反応する高精度保安装置の警戒網がなかなか突破できない。最終的にルパンの考案した方法は、“人類が作り出した最高の芸術品”「英雄交響曲」を保安装置の監視空間で流すことだった。保安装置は英雄交響曲の音楽が完璧であったため、これを異常音と感知できず作動しない、という話。もちろん、そこまで鋭敏な感性の機械があったらそれは見事なものなのだが、このエピソード、音楽愛好家には実に含みのある話であった。 シャイーの演奏は軽快な英雄だ。速い速い!風を切る速さとはこういうものか。第1楽章はこのスピードにより、むしろオフビート感が強いが、感性で押し切ったような、シェイプアップされた容姿を感じさせる。第2楽章の葬送行進曲では「荘厳さ」は示されないが、ライトなスタイルで颯爽としており、「規律」を感じさせるもの。終楽章は、ベーレンライターなどではない“古典的なスコア”(主要主題を告げるトランペットなどに象徴的)による快活テンポの演奏として、従来にない存在感を感じさせており面白い。シャイーの英雄交響曲は、速さゆえの非古典性、不安定さを持っており、批判も受け易いところだと思うが、私は新しい感性の漲る演奏として評価したい。 交響曲第4番はシャイーのスタイルが肯定的に強い生命力を引き出していると感じられ、より多くのリスナーに受け入れられるに違いない。終楽章はこれまた疾風のごとき勢いで、バズーンのソロなど弦合奏の嵐でかき消され気味だが、演奏のスタイルは強烈な刻印を残している。多少圧殺されるものがあるのは仕方ないだろう。それよりもまさに切れば血の出るようなスピーディーな迫力に満ちた躍動感を楽しみたい。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 第4番 第7番 シャラー指揮 フィルハーモニー・フェスティヴァ レビュー日:2025.5.28 |
| ★★★★★ オーケストラとホールのサイズに順応したベートーヴェン
ゲルト・シャラー(Gerd Schaller 1965-)指揮、フィルハーモニー・フェスティヴァの演奏で、ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の以下の3つの交響曲を収録したアルバム。 【CD1】 1) 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」 【CD2】 2) 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60 3) 交響曲 第7番 イ長調 op.92 第4番は2013年、第3番と第7番は2015年に、バイエルン州・エーブラハ・シトー会修道院の「皇帝の間」でライヴ収録されている。フィルハーモニー・フェスティヴァは、シャラーがドイツの名門オーケストラの首席奏者らを中心に設立したオーケストラで、常設のオーケストラのシーズン・オフを中心に活躍している。彼らのこれまでの録音業績は、圧倒的にブルックナー(Josef Anton Bruckner 1824-1896)に特化しており、様々な稿や版の違いも含めた網羅的なシリーズとして成果となっている。そんな彼らのブルックナーは、エーブラハ大修道院付属教会で演奏・録音が行われ、その豊かな残響を活かしたオルガン・トーンを丁寧に扱った音作りが特徴であった。そのことからも、シャラーは、オーケストラ演奏において、「演奏場所」を重視していることは明らかだ。 このベートーヴェンは、「エーブラハ修道院皇帝の間」で収録が行われている。これは、ベートーヴェンのこれらの交響曲が初演された当時の編成に適したサイズ感の演奏会場であり、そのため、オーケストラは全部で35人前後。これは、現代楽器のオーケストラでベートーヴェンを演奏する場合、かなり小規模なもので、特に弦楽器の奏者の数が少ない。とはいえ、かれらはピリオド楽器を用いてるわけでもなく、ノンビブラートで高速奏法を目指しているわけでもない。つまり、サイズ感をまず限定し、それにあったホールを設定し、そこで、現代なりのベートーヴェンを再現してみよう、というのが目論見だ。シャラーにとって、オーケストラ作品において、演奏ホールそのものが鳴動する楽器であり、様々なものが、そのプライオリティーに従ってデザインされていると私は考えている。 さて、結果として響くベートーヴェンであるが、その解釈は王道的なものであろう。ピリオド奏法を意識してテンポを早めるわけでもなく、浪漫的にゆったりろ進むのでもなく、現代楽器による演奏において、きわめてオーソドックスなスタイルと言って良い。ベートーヴェンの作品は完璧なのだから、あとは、きちんと音響をコントロールするだけで良い、といったところであろうか。なかなか説得力がある。 その音響であるが、決して弦楽器の響きが薄いわけではない。全合奏の音には十分なパンチがあるし、ここぞというところで的確に踏み込んでくる心地よさもある。これはもう、シャラーとオーケストラの団員たちが、すべて知り抜いているという呼吸で、しっかりと音楽をやっているという感じである。人数の少なさゆえに、部分的に固く感じる響きもあるが、その点も含めて、全般にうまくサポートされている。金管も、編成に合わせた強すぎない音をよく吟味しており、不自然なところなく、迫力を得ている。木管の存在感が相対的に高まっているが、それゆえの透明な感触が美しく、全体の伸びやかな印象に繋がっている。重量感を求める場合には適さない演奏ではあるが、それと別に彼らの意図は十分に達成されていると感じられるし、聴いていて、安心して楽しめるベートーヴェンとなっている。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 第8番 P.ヤルヴィ指揮 ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン レビュー日:2007.12.1 |
| ★★★★★ 「意図した表現」のためにすべてを合理的に鳴らした演奏
パーヴォ・ヤルヴィはエストニアの指揮者ネーメ・ヤルヴィの実子。本盤はドイツ・カンマーフィルとのベートーヴェン録音第1弾となったもの。第3番は2005年、第8番は2004年に収録されている。 現代、ベートーヴェンの交響曲を録音するにあたって、当然数多くある録音の中の一つとして存在感あるものであるために、様々な試行が重ねられると思う。それが指揮者にとってどこまで本来的なものだったのか、私にもときどき悩む場合がある(私が勝手に悩んでいるのですが)。ただ、結果として様々に面白い提案が現れてくるわけだし、それを聴けるのはもちろん楽しいわけで、この録音もそういった「ニーズに合った」録音といえる。つまり個性的で面白い。 まず楽器であるが、トランペットとティンパニにピリオド楽器を用いているらしい。これは、さらっと書いたけれどかなり特殊なことだ。いったい何ゆえか?と思うけれど、聴いてみるるとティンパニに関しては、かなりクローズアップしている。これはおそらく弦などの人数を少人数にしているということだと思うが、ティンパニの生々しい音を使って、あちこちで「決め打ち」気味に活躍させる。実にリズム感のある音楽となる。また金管の音色も現代楽器のような伸びよりも、多少不安定さがあっても鋭さを求めており、その表現に適した楽器をチョイスしたらこうなった、という感じである。その合理主義的精神も見事と思う。そうしてトントントントンと小気味のいい軽い音色で音楽を走らせながら、木管中心に歌わせるコントロールも巧みだ。これはもう深く悩まずに反応にまかせて楽しめばよいのだろう!・・でも終わって感想を言葉にしようとすると、ちょっと考えるところはあるわけです。 |
|
 |
交響曲 第3番「英雄」 第6番「田園」 レオノーレ序曲 第3番 合唱幻想曲 ドホナーニ指揮 クリーヴランド管弦楽団 p: R. ゼルキン 小澤指揮 ボストン交響楽団 タングルウッド音楽祭合唱団 S: ロビンソン バージス A: コーカシアン T: リーゲル Br: ゴードン Bs: ロビンス レビュー日:2011.1.21 |
| ★★★★★ 晴天の見晴らしの良い丘から見下ろす田園風景
ドホナーニがクリーヴランド管弦楽団と1980年代に録音したベートーヴェンの交響曲全集は、2CDずつ3組の廉価な輸入盤により分売されている。当ディスクには交響曲第3番「英雄」と交響曲第6番「田園」それにレオノーレ序曲第3番が収録されている。交響曲第3番が1983年、他は1986年の録音。 さらに当ディスクには、不思議なおまけとして「合唱幻想曲」が収録されている。これは奏者が異なっていて、ピアノがルドルフ・ゼルキン、オケが小沢指揮ボストン交響楽団、合唱がタングルウッド音楽祭合唱団、独唱陣がS: ロビンソン、バージス、A: コーカシアン、T: リーゲル、Br: ゴードン、Bs: ロビンスで1982年の録音。特にドホナーニの録音とは脈絡のない収録内容であるが、余白の収録時間を利用して、例え別種の録音でも追加しようというサービスは良心的でうれしい。(ただ、通販などで購入しようとする場合、当該サイトでそこまで明示してくれない場合があり、要注意でもある)。 私はドホナーニの全集の一環としてこのディスクを購入したので、俄然注目は「交響曲」である。ドホナーニのベートーヴェンへのスタイルは確固たるもので、ひたすら機能美に徹してクリアなサウンドを心がけたものだ。重さより速さ、感情より感性の勝負に徹していて、その際に不要となってしまったものは、省みることなく、あっさり振り切った潔さが聴き所である。交響曲第3番は冒頭の一撃からシャープな切り口で、以後もサッ、サッ、と場面が切り替わっていく。ティンパニの瞬激も刹那の迫力に満ちているし、第1楽章後半で主要主題を高らかに吹き鳴らすトランペットも衒いなく立派の一語。第2楽章では弦の精度の高い音響が鮮やかで、一点の聴きもらしもない。実はこの曲の後に小沢とゼルキンの合唱幻想曲が収録されていて、そちらも単品ではぬくもりの通った秀演なのだけれど、ドホナーニの英雄交響曲と続けて聴いてしまうと、何か曇ったような印象になってしまう。不思議なものである。 交響曲第6番はいくぶんしっとりした音響があり、少し違った印象を持つが、それでも全管弦楽による合奏シーンなどでは、ドホナーニならではの透き通った音色がまるで見晴らしの良い丘から見下ろす田園風景を描いているかのようで無類に心地よい。有名な嵐の音楽は機敏な音楽の移り変わりを瞬時で反応する機転が心地よく、一気に聴き通してしまう。 もちろん、このような感性で押し切ったベートーヴェンを異質と感じる人も多いに違いない。私も、そういう違和感をまったく感じないわけではないが、それにしても聴いていて圧倒される清清しさである。好きな人はとことん好きになるのではないか、そう思わせるベートーヴェンだ。 |
|
 |
ベートーヴェン 交響曲 第4番 リャードフ バーバ・ヤーガ グラズノフ バレエ「ライモンダ」より第3幕への前奏曲 ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2008.10.11 |
| ★★★★☆ ソ連の神秘的演奏家の1973年来日時の録音
1973年来日時のライヴ収録。エフゲニー・ムラヴィンスキー(Evgeny Muravinsky)は1903年ペテルブルク生まれの指揮者で、35歳の若さでレニングラード・フィルの常任指揮者に抜擢された。来日当時はソ連の実演に触れる機会の少ない指揮者とオーケストラであり、また録音活動もソ連国内のメロディア・レーベルのものだけだったので、「秘められた指揮者と演奏集団」というイメージだったと思う。東京文化会館の大ホールでNHKによるライヴ録音が行われたため、このようなCDとして復刻することになった。 ベートーヴェンの交響曲は名演として名高いものであるが、そこには一抹の古めかしさもただよう。つまり指揮者の強い個性が出ており、交響曲ではあるがどこか標題音楽のような演出がある。もちろんそれは悪いことではないし、様々に評価されるべきものであるが、現代的な演奏に慣れると、そのアクに戸惑うことも否めないと思う。 とややネガティヴな印象に書かせていただいたが、もちろんこれは存在感のある演奏だ。第1楽章の序奏の重々しさ、荘厳さは真に迫ってくるものがあり、その後のスピード感と金管、ティンパニの痛烈な響きもさすが。また、第2楽章では木管中心の音色の豊かさ彩豊かでロマン性を帯びている。第4楽章も快速だが、ややオーケストラの足並みの乱れは気にならないわけではない。しかし、現代では得られない独特のカリスマ音楽家の演奏だというのはよく分かる。 アンコール的小品としてリャードフの「バーバ・ヤーガ」とグラズノフの「ライモンダ、第3幕への前奏曲」があり、こちらも意気揚々たる演奏で、自信に溢れた音が漲っている。このような機会に日本のフアンにロシアのネームヴァリューの低い作曲家の作品を伝えたいという気持ちが伝わる。 |
|
 |
交響曲 第4番 第6番「田園」 ファイ指揮 ハイデルベルク交響楽団 レビュー日:2023.1.31 |
| ★★★★☆ 第4交響曲が素晴らしい出来栄え
トーマス・ファイ(Thomas Fey 1960-)指揮、ハイデルベルク交響楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の以下の2つの交響曲を収録したアルバム。 1) 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60 2) 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」 2001年の録音。 ファイとハイデルベルク交響楽団は、2000年に第1番と第2番を録音していたので、それに次ぐベートーヴェンの交響曲シリーズとなった。ただ、彼らは他の交響曲については録音しなかった。当欄をご覧の方はご存知のことと思うが、ファイは2014年に事故で重傷を負い、現時点で再起は難しい状態とのこと。なんとか回復してほしいというのは多くの音楽フアンの思うところだろう。 さて、録音内容に話を移す。ハイデルベルク交響楽団は、トランペット、ホルン、ティンパニがピリオド楽器で、他が現代楽器という「混合編成」だが、ファイの演奏スタイルは、弦楽器陣のヴィブラートを抑制し、いわゆるベーレンライター版準拠による快速進行である。 ここで、参考までに書いておくと、ベーレンライター版とは、イギリスの音楽学者ジョナサン・デル・マー(Jonathan Del Mar 1951-)がベートーヴェンの資料を研究し、あらためて原典譜から校訂し、ベーレンライター社が1996年に刊行したスコアである。ただ、このスコアに従うと「快速」になるというわけではなく、本来ベートーヴェンの交響曲のスコアにおける速度指示は、概して快速なものなのであり、それが演奏史の中で、テンポを落した解釈が主体となってきた背景がある。そこに、改めて、原典主義を謳ったベーレンライター版が登場したため、この版を扱う際、その原点主義の精神に則って、早い速度指示に改めて忠実に従う演奏となったわけである。つまり速いテンポというのは、ベーレンライター版の特徴というより、ベーレンライター版のイズムに従ったということになる。もちろん、その他にも、ベーレンライター版では、従来のスコアが前後の脈絡から整える傾向にあったものを、あえて不揃いな印象を与えるものをそのまま残すなどの特徴があり、そこにさらに指揮者の解釈が加わるので、一口にベーレンライター版といっても、非常に括りにくいもので、速いテンポばかりが概念として先行してしまった感はあるのである。 また、話がずれてしまった。あらためて当演奏に話を戻す。ファイの演奏の特徴は、第1番・第2番の録音と同様で、畳み掛けるようなアップテンポと、収束性の高い切り口の鋭さにある。弦楽器陣は、ヴィブラートを抑えているため、やや硬く、輝きに乏しい面はあるものの、機敏な動き回り、瞬時の反応性でこれをカバーし、全体として、運動的な快感を強く刺激する方向へ向かっている。トランペットは、ピリオド楽器特有の不安定さを持ちながらも、タイミングを律義に守って、リズムの効果を高める役割を強めに担っており、全体としての方向性は齟齬が無い。一貫性の強い演奏だ。 収録された2曲のうちでは、ファイの解釈は特に第4と相性が良く、冒頭の序奏の緊張感、第1主題の金管のアクセントの鮮やかさ、展開部の活き活きしたフレーズの連続的な処理が実に爽快。また、第3楽章のダイナミックレンジの広い演出は、快速なテンポとあいまって、胸のすく効果を導き出している。第4楽章も、ベーレンライター版がどうのこうのというよりも、とにかくアクセル全開の勢いそのものが魅力で、すべてがパタンパタンと勢いよく畳み込まれていく様が圧巻である。 それに比べると第6番は、やや相性が悪い。解釈としては同じなのだが、この曲の場合、特にヴィブラートの抑制が表現性を削って、全般的に表情の硬さとして聴き手に伝わってしまうところがある。ファイの演奏は、この楽曲を古典の範疇で取り扱っていると思うが、そのことが逆説的に、ベートーヴェンの第6交響曲の革新性を証明することになっている。それは、すなわち、従来に書かれてきた数々の交響曲と比較して、圧倒的な濃厚さで宿る表現性である。その部分において、当演奏では、いかにもかわいた素朴な感触にならざるをえない。それが美しくないわけではないが、他の名演と比べて優れているとまでは感じられなかった。 とはいえ、第4番の大成功だけでも、十分に聴く価値のある一枚であり、そのアグレッシヴな音の奔流は、他の演奏とは一味違った感慨を聴き手にもたらすだろう。 |
|
 |
交響曲 第4番 第7番 P.ヤルヴィ指揮 ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン レビュー日:2007.12.1 |
| ★★★★★ あらゆる楽器が機能的に働き、ひとつの臓器のように目的を果たす
話題になっているパーヴォ・ヤルヴィ(ネーメ・ヤルヴィの実子である)のベートーヴェンの交響曲を2枚まとめて聴いてみた。基本的な印象は第1弾(第3番&第8番)と同様で、ティンパニのくっきりした乾いた躍動感あるリズムとトランペット中心の刹那的ともいえる鋭い音色をいかして小編成のオーケストラならではの機動性を発揮した演奏だ。特に第4番は全面が鮮やかな生気に満ち溢れている。 ただ、録音データをみて思いついたのだけれど、第4番は2005年に録音されているが、第7番に関しては2004年の6月と2006年の9月にわけて収録している。これにはびっくりした。一つの交響曲を収録するのに、間に2年以上もインターバルを挟むようなスケジュールを普通、切るものだろうか?・・・絶対切らない。だいたいそんなに間があったら「前にやったこと」を忘れてしまう。・・いや優秀な音楽家なら忘れないのかもしれないけど、それにしても人数の多いオーケストラである。途中でメンバーが代わっても不思議じゃない。でも聴いてみるとちゃんとなっている。といことは、もうこの特徴的なベートーヴェンは、パーヴォ・ヤルヴィとこのオーケストラが完全に手中に収めた「究極形態」とでも言えるものなのではないだろうか?それにしても躍動感と生命感に満ちている。あらゆる楽器が機能的に働き、ひとつの臓器のように目的を果たす演奏となっている。インターバルの謎は残るが、逆にそれが私には更なるインパクトを与えた。パーヴォ・ヤルヴィとドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン、恐るべき芸術家集団だ。 |
|
 |
交響曲 第4番 第8番 第9番「合唱付」 ドホナーニ クリーヴランド管弦楽団 合唱団 S: ヴァネス MS: テイラー T: イェルザレム Br: ロイド レビュー日:2011.1.20 |
| ★★★★★ メタリックな光沢で鋭利に切り込むベートーヴェン!
ドホナーニ指揮クリーヴランド管弦楽団のベートーヴェン。本盤には交響曲第4番、第8番、第9番の3曲が収録されている。第9番はクリーヴランド合唱団にS: ヴァネス、MS: テイラー、T: イェルザレム、Br: ロイドといった独唱陣。録音年は、第4番が1988年、第8番が1983年、第9番が1985年。当時はちょっと話題になった録音ということだが、私は最近になって初めて聴くことになった。 ベートーヴェンの交響曲第9番は言うまでもなく巨大な歴史上の芸術モニュメントである。この作品の登場によって、ベートーヴェンは芸術家たちを既成の価値観から解き放ちった。まさしく、ロマン派開放を告げる砲声の一撃である。フルトヴェングラーの歴史的名演を始め、この曲には神性を宿したかのような豪演、爆演の類に事欠かないが、ドホナーニの演奏はかなりそれらの路線とは異なる。 そう。言ってみれば、ドホナーニのスタイルは「ただの合唱付きの交響曲」である。・・・この表現では誤解を招くかもしれない。私はこの演奏を肯定的に捉えているのである。 ドホナーニの音楽作りは非常にクールなのだ。この曲の偉大性とか神性とかを語ろうというのではなく、それぞれのスコアを各パートに純然と指示するのみで、それを計算づくで組み上げていったような風情。その結果、非常に陰影がはっきりし、細部まで明瞭。声部ははっきりと分けられていて、見通し抜群。そしてやや速めのテンポで急峻な崖を一気にすべり降りるようにクライマックを築き上げる。その瞬時のメタリックな光沢も鮮やか。合唱もおおらかに歌い上げるものではなく、確実に音符をトレースしていき、音量と美観にのみ細心の注意を払ったかのよう。イェルザレムを始めとする独唱陣もその方針の下、きれいな統率を見せている。 交響曲第4番、それに第8番でもドホナーニのスタイルは同様。鮮明で、音楽の推進性を高い統率能で維持し続ける。機能的なサウンドで、暖かい音色というわけではないけれど、あちこちで独特の鋭利さが輝く。とても面白い!。ベートーヴェンらしい熱量や、喜びの感情を積極的に感じさせるものではないが、必要なものは必要に応じて伝わっており、あとはまっすぐに自分のスタイルで行くことに専念した演奏と言えるだろう。80年代半ばにして、これほどシャープなスタイルを未練なく構築したドホナーニは、やはり超一流の指揮者であったのに違いない。 |
|
 |
交響曲 第5番「運命」 レオノーレ序曲 第3番 アシュケナージ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 レビュー日:2011.10.17 |
| ★★★★★ たまには久しぶりに「運命交響曲」でもいかがですか?
アシュケナージがフィルハーモニア管弦楽団を指揮してのベートーヴェンの交響曲第5番「運命」とレオノーレ序曲第3番。1981年の録音。 アシュケナージというアーティストは、なぜか批評家の評価が「今ひとつ」なところが多い。ピアニストとして、幅広いレパートリーに、完成度の高い多くの録音をしてきたが、突き抜けた強い主張がないため、批評家が積極的に取り上げたくような、「攻撃的な」側面に欠けるのかもしれない。しかし、一つ一つの録音を聴いてみると、とても安定した強度の高い仕事をしていて、私は彼の録音を今だっていろいろとよく聴く。また、アシュケナージが指揮者として活躍の場を広げたときも、その「万能ぶり」が、特に「エキスパート」を好む批評家からは疎ましがられたに違いない・・・と思うのだが。 となると、指揮者としてはまだキャリアの浅い、この1981年当時のベートーヴェンの「運命交響曲」のようなものは、いよいよきちんと聴かれたり、議論されたりしていないのではないだろうか?と思ってしまう。だって、ベートーヴェンの「運命」なんて、相当の昔から、それこそ歴史的録音のオンパレードなわけで、いまさらロシア出身のインターナショナルなアーティストが、イギリスのオーケストラを振ってそのキャリアの初期に録音したものなど、あまり興味をもって省みることなどないだろうから。 しかし、ここからが面白いのだけれど、この演奏、びっくりするぐらい「イイ」のである。何が「イイ」かって?それはもう、大胆に大きな波を揺らせるように、エネルギッシュな爆発力と破壊力を持っている点がいいのですよ。豪放なだけでなく、美麗で、細部に適度な音幅があるのも聴き味の柔らか味を保っていて良好。 と書くと、またまた「それって、アシュケナージのスタイルと違うのでは?」と思う人もいるでしょう。わかります。それこそが「先入観」です。実は、私でさえこのディスクを期待して聴いたわけではないのです。私はアシュケナージのすべての録音を収集することを一つのテーマとしていて、そのためにこのディスクも聴いたのですが、聴いてみて、その爆演ぶりにびっくりして椅子から立ち上がってしまったほどなのです。 このころのアシュケナージは、フィルハーモニア管弦楽団とのシベリウス、コンセルトヘボウ管弦楽団とのラフマニノフ、クリーヴランド管弦楽団とのR.シュトラウスなど、精力的に録音をしていた時期なのですが、このベートーヴェンでは、蓄えられている情念を一気果敢に解き放ったようなダイナミックな音楽が展開しているのです!それは、聴いた私がびっくりしたくらい。忘れられかけている録音とはいえ、この時期のアシュケナージとフィルハーモニア管弦楽団にしかなしえなかった貴重な記録でしょう。たまには久しぶりに「運命交響曲」でもいかがですか? |
|
 |
交響曲 第5番「運命」 コリオラン序曲番 パイタ指揮 フィルハーモニック交響楽団 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2019.9.28 |
| ★★★★★ カルロス・パイタの代表的録音の一つ
アルゼンチンの指揮者、カルロス・パイタ(Carlos Paita 1932-2015)は、クラシック音楽フアンにはある程度知られた存在だ。裕福な家庭に生まれ、音楽的素養を持ち合わせ、フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler 1886-1954)に傾倒した彼は指揮者となった。自由な音楽活動を獲得するため、オーケストラ「フィルハーモニック交響楽団」を自ら総説。またスイスを拠点にLodiaというレーベルを立ち上げ、その録音活動を行った。 当盤はそのLodiaレーベルからリリースされたもので、パイタの名演の一つとして知られるもの。ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の以下の2作品が収録されている。 1) 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」 2) 序曲「コリオラン」 op.62 交響曲は、フィルハーモニック交響楽団を指揮して1982年の録音。序曲はロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して1985年の録音。 演奏は、エネルギーの漲ったもので、隅々まで膂力を伝えながら、活力豊かな推進力を兼ね備えたもの。パイタの名は、いわゆる「爆演」のスペシャリスト的位置づけで通っていて、その仰々しいイメージから、コアなクラシック・フアンや批評家からは敬遠される傾向にあり、かく言う私も、あまり聴いてこなかったのであるが、当演奏は、どうしてどうして、音楽的素養をベースに感じさせながら、厚み、重み、スピードのいずれをも損なわない見事なコントロールで導かれたもので、清々しいほどの名演といって良い。 運命交響曲は、冒頭の主題提示から、低音のしっかりした響きの下支えのもと、弦楽合奏のみとは思えないほどの重さを感じさせる響きであり、かつ強くスリリングな音色。展開部は足早で、頂点までいちはやく達し、聴き手の鼓動を早くする。合奏音の連打は強烈なティンパニとともに迫力満点だが、音楽的で、しっかりした集中線を感じさせる。第2主題の扱いも、齟齬がなく、爽快だ。中間楽章も、クライマックスまでのステップアップで、確実に聴き手の気持ちを高める手順が踏襲され、奮い立つような勇敢さがあり、魅力的だ。終楽章の熱血性は言わずもがな。 序曲「コリオラン」も圧巻の演奏。弛緩のない早いテンポ、前面化を惜しまない金管の激しさあるが、この俊敏な情景転換で、フレーズが新たな魅力をまとっていると感じられることも新鮮だ。第2主題前の「タメ」の深さは、多少芝居がかっているものの、心憎い演出。そして、熱血的なテンションを蓄えて、あっと言う間にコーダに導かれる。「ああ、本当にこの曲は、カッコイイ曲なんだな」と改めて思わせてくれる快演奏だ。 2019年になってカルロス・パイタのベートーヴェンを聴いたのだが、聴かないで済ませてしまうのはもったいない一枚だったな、聴いて良かったな、と思える録音でした。 |
|
 |
ベートーヴェン 交響曲 第5番「運命」 バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 から 「エール」 (G線上のアリア) ケーゲル指揮 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2019.11.26 |
| ★★★★★ 1989年、ケーゲル日本公演の良質な記録
東ドイツの指揮者、ヘルベルト・ケーゲル(Herbert Kegel 1920-1990)は、いまなお一定の熱烈な支持を集める音楽家である。また、それにもかかわらず、録音の流通量や、専門誌での言及の機会に関しては、多いとはいえない。 また、ケーゲルにはミステリアスなイメージがある。東西ドイツ統一直後の1990年に拳銃自殺により世を去ったことにより、もたらされている部分もあるだろう。また、現代音楽への理解の薄い共産圏で長く活動しながら、積極的に現代音楽を手掛けたという芸術の在り方、またそのようなスタンスにも関わらず、指揮者としていっぱしのステイタスを築き上げた彼の人生も、どことなくミステリアスに思う。 そんなケーゲルの芸術性に触れたいと考えるなら、当録音は象徴的なものの一つだろう。ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団との来日公演のライヴの記録で、その日付は1989年10月18日。それからひと月もたたない11月9日に、ベルリンの壁崩壊という歴史的事件が起き、ケーゲルは、その1年後の1990年11月20日に、一発の銃声とともにこの世を去ることとなる。 もちろん、この手の歴史事象の羅列は、後世の人間が勝手に並べて、後付けでその意味を探している感が多分にあり、迂闊な言及は謹んで然るべきだとも思うが、このディスクを聴く人であれば、そのことを意識の外に追いやることは、かえって難しいだろう。 収録曲は以下の2曲。 1) ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827) 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」 2) バッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750) 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 から 「エール」 (G線上のアリア) 演奏は、なるほど個性的だ。特徴的なのは豊かな振幅だろう。エネルギー波の増減の効果を生み出すようなタメをつくっては、開放を行うが、開放によって流れだす音楽の勢いと美観が見事で、ドレスデンの作り出す極上の美音をつややかに仕立て上げていく。これを聴いていると、ケーゲルは、このオーケストラが作り出す音を前提に、アプローチを練り上げていった感が強い。ベートーヴェンの第2楽章はことのほか耽美的でありながら、その節々から感じられる情緒は清らかと表現したいものであり、奥行きがあって、表面的なものではない。 当演奏の特徴が最もよく出ているのが第4楽章で、ファンファーレのブレーキのかけ方。ホルンの深々とした応答など、懐の深いドライヴで、どんどん聴き手を導いていく。そのあり様は実に頼もしく、浪漫的かつ巨匠的である。現代では聴く機会の少ない職人芸的な個性があり、それが楽曲の表現方法として、しっくりいくものになっている。ライヴで聴いた人たちは、心を強く動かされたに違いない。 アンコール曲であるバッハは、永遠を感じさせる静謐から音楽がゆっくりと引き出されていく様が感動的で、尾を引くような、味わい深く長い余韻があって、こちらも耽美的だ。いずれも、美しさと、表現者の意志の強さを感じさせる演奏で、ドイツの音楽文化の脈流を感じさせる演奏であると思う。 以上のことをもって推薦としたい・・・が、ライナーノーツの大仰な書きっぷりによって気が削がれる点は如何ともしがたい(目を通さなければいいだけですが)。 |
|
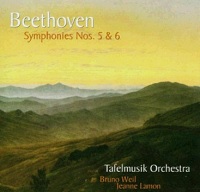 |
交響曲 第5番「運命」 第6番「田園」 ヴァイル指揮 ターフェル・ムジーク・オーケストラ レビュー日:2009.9.7 |
| ★★★★★ ピリオド楽器云々とは別に楽しく聴ける豊かな音楽
ブルーノ・ヴァイル指揮、ターフェルムジーク・オーケストラによるベートーヴェンの交響曲第5番「運命」と第6番「田園」。2004年の録音。 ターフェルムジーク・オーケストラはカナダのトロントに本拠を置くピリオド楽器によるオーケストラ。ブルーノ・ヴァイルと良質な録音活動をしており、もっと積極的に評価されてもいいと思う。 ベートーヴェンの交響曲へのピリオド楽器によるアプローチもいまや数多くあるのだが、ヨーロッパのオーケストラと比べても遜色のない質の高い演奏だ。 ピリオド楽器による演奏の場合、その特性を活かした奏法によりスピーディーで攻性のアプローチをとることが一般的だし、また金管やティンパニは鋭角的なリズムを刻むことが多い。しかし、ヴァイルの演奏にはそれらの過度な強調がないのが私には好ましい。 とはいってももちろん小編成ならでは機動力を活かしたたたみかけや足の速い展開、あるいは古風な付点的リズムの味付けはある。しかし決して音楽として表現したいものの主客が転倒することはない(つまりあざとさがない)。そうして流れる音楽は流暢で、人によっては「あまりにもナチュラル」と感ずるものかもしれない。しかし、この演奏を聴いていると、心地よいリズムが真まで貫いていて、要所要所の迫力も適度に表出しながら、トントントントンとテンポよく進んでいってしまうので、あっというまに曲の終結部が近づいてくる。演奏時間が極端に短いわけではない。それだけ聴き手が音楽を自然に楽しんだことの証左と言える。「運命交響曲」の第2楽章も、リピートを忠実にやる分、これくらいの軽やかさを持っていた方が、聴き手に優しいのである。 ピリオド楽器云々とは別に楽しく聴ける豊かな音楽、それを体現した演奏の1つと言える。 |
|
 |
交響曲 第5番「運命」 第6番「田園」 序曲「コリオラン」 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 レビュー日:2012.3.16 |
| ★★★★★ 現代楽器を用いた高速アプローチで、見事な成果を得たベートーヴェン
2007年から2009年にかてて録音されたリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全集からの分売。計5つに分かれての分売で、それぞれのディスクは全集中での5枚のディスクをそのまま抜き出した形で、曲順の変更などは行われていない。 これは全集の3枚目に相当するディスクで、交響曲第5番「運命」、第6番「田園」、序曲「コリオラン」が収録されている。 シャイーのベートーヴェンの全集を通じての特徴は、疾駆するような「速さ」である。従来から、ベートーヴェンの交響曲におけるメトロノーム指示は「速過ぎる」と解釈されてきた。しかし、20世紀末のピリオド楽器による奏法の研究から、「速過ぎる」と解釈されていた設定には、十分な演奏上の根拠があることが見出された。その後、ベーレンライター版などの新しいスコアにより、現代楽器による俊足演奏も試行されてきている。しかし、シャイーの演奏は「旧来のスコアを用いての現代楽器オーケストラによる高速演奏」を成したことが画期的だろう。もとよりこの方向性ではトスカニーニ(Arturo Toscanini 1867-1957)という大先輩がいるのだが、シャイーはその演奏を復興させ、なおかつ現代的な明るく切れ味のあるソノリティを体現させている。 「運命交響曲」はベートーヴェンのテーゼの一つ、「苦悩をつき抜け歓喜に至れ(暗黒から光明へ)」を、「余分な」枝葉をそぎ落とし、フレームワークだけで単刀直入に示した音楽だ。シャイーの演奏はこの音楽が持つ力強い肯定性、推進性をまっすぐに打ち出したものと言える。これはシャイーがそういった解釈を目指したというより、前述の奏法を追及した結果、必然的にそこに至ったのだと考える方が自然だろう。というわけで、きわめて熱いエネルギーを感じさせる演奏になっている。「熱い」のだが、濃厚ではなく、クリアな軽さを同時に獲得している点が面白い。抜群に聴き味が爽やかなのは終楽章で、ベートーヴェンの歓喜の謳歌を現代的な高揚感を持ってスタイリッシュに描ききった演奏と言ったところだろう。 田園交響曲も軽やかに、明るく溌剌とした音楽で進んでいく。時に繰り返し音型が、速さから硬めの響きになるところもあるが、全般を通してクリアな見通しに貢献できており、演奏としての全体的な主張は良く伝わっている。第2楽章も非常にあっさりした味わいだが、ほのかな気品がオーケストラから伝わるのが好ましい。第4楽章の有名な嵐の音楽も、「雨嵐」というより、まさしく「風の嵐」といった趣で、千切れた雲が凄い勢いで風に乗って流れて行きそうだ。 |
|
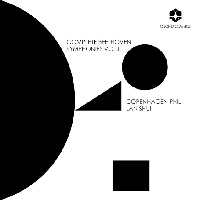 |
交響曲 第5番「運命」 第6番「田園」 第7番 第8番 シュイ指揮 コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2018.4.5 |
| ★★★★★ 快活で爽快!無比の生命力に溢れた薫風のようなベートーヴェン
中国杭州市出身のラン・シュイ(Lan Shui 1957-)指揮、コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の交響曲集。CD2枚に以下の収録内容。 【CD1】 1) 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」 2011年録音 2) 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」 2013年録音 【CD2】 3) 交響曲 第7番 イ長調 op.92 2012年録音 4) 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93 2012年録音 先に第1番から第4番までの4曲を収録した第1集にレビューを書いたばかりであるが、本当に見事な録音である。これまでにある、数えきれないほどのベートーヴェン録音の中にあっても、決して得埋もれることのないしっかりした輝きでその存在感を示しうる録音である。 ティンパニと一部の金管のみピリオド楽器という編成により、ベートーヴェンのメトロノーム指示の意味を積極的に解釈した意欲に満ち溢れた演奏だ。ラン・シュイという指揮者にしても、コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団というオーケストラにしても、私はこれらのベートーヴェンの録音を聴いて、その実力を圧倒的に知ることとなった。すでに数年前の録音である。それなりに、クラシック音楽の録音にアンテナを張っているつもりだった自分の不明さえ痛切に感じさせられる。それにしても、日本国内の評論で、これらの録音がまともに取り上げられていないのは不思議と感じざるを得ないが、それも私の不明だろうか。 ラン・シュイの解釈は、まずスピードの維持を念頭に置いている。その前提の上で、スコアを読み進めた時、どのような表現が可能であるか、またどのような表現であれば、そのスピードに音楽的な真価を与えられるかを徹底的にさぐり、方法論を打ち立て、それをオーケストラに浸透させた。その力量は並々ではない。そして、それを我が事のように理解り、表現するオーケストラの響きの美しいこと。フレッシュで、余分なものは一切なく、すべてが一つの意志に集約されている。そのあるしゅの絶対性が、ベートーヴェンの音楽を一層凛々しくひき立てるのである。 象徴的な個所として、第5交響曲の終楽章を挙げよう。この終楽章、暗黒から光明へ、そして勝利の行進への結びの部分であるのだけれど、ベートーヴェンのある種の熱血性と粘性が示された部分でもある。ラン・シュイはこの終楽章の起伏をスピードと精密なコントロールによって、薫風のような印象に一新させる。確かに熱血的なものを望む人には、その響きは全体に軽やかに感じるかもしれない。しかし、ラン・シュイのスピードはヴィヴィッドな感覚美に溢れ、一つ一つの表現は積極的な意志表出に満ちている。だから、その音楽はつねに明確な方向性をもっていて、集約されるべき地点は一瞬だって見失われることはないのである。その畳みかけるように集結するエネルギーの放つ光の美しいこと。いくたびも聴いてきた運命交響曲で、このような新しい興奮を得ることができるとは、この演奏を聴くまでは思いつかなかった。 田園交響曲はスピーディーな軽やかさの中で、「穏やかさ」を十全に表現する弦の柔らか味が素晴らしい。第7番、第8番も爽快な運動美に貫かれている。これらのスタイルは、パーヴォ・ヤルヴィ(Paavo Jarvi 1962-)とドイツ・カンマーフィルによるベートーヴェンと、精神的な親近性を感じさせる。(それに、パーヴォ・ヤルヴィも、ティンパニとトランペットをピリオド楽器に置換していた)。かつ、私には、緊密なパッセージのやりとり、それにより一層の快速テンポの徹底、さらにはそのテンポを説得する音楽表現といった点で、このラン・シュイ盤はヤルヴィを上回ると感じた。 録音もすこぶる良好。雑味がなく風通し抜群。多くの人にぜひ一聴を促したいベートーヴェンです。 |
|
 |
ベートーヴェン 交響曲 第6番「田園」 合唱幻想曲 ブラームス ヴァイオリンとチェロの為の協奏曲 ザンデルリンク指揮 ケルン放送交響楽団 vn: ツェートマイヤー vc: メネセス モスクワ放送交響楽団 ソヴィエト国立アカデミー合唱団 p: リヒテル レビュー日:2022.6.10 |
| ★★★★☆ 慈愛を感じさせる柔らかな響きに満ちたベートーヴェンとブラームス
2011年に亡くなったドイツの指揮者、クルト・ザンデルリング(Kurt Sanderling 1912-2011)の追悼企画としてProfilから発売された2枚組アルバム。収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827) 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」 【CD2】 2) ブラームス(Johannes Brahms1833-1897) ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 op.102 3) ベートーヴェン 合唱幻想曲 op.80 1,2)はケルン放送交響楽団との1985年のライヴの模様を収録したもの。 3)は当盤における「ボーナストラック」で、1952年にモスクワ放送交響楽団を指揮して、モスクワで録音されたもの。当然の事ながらモノラル録音。 2)のヴァイオリン独奏はトーマス・ツェートマイアー(Thomas Zehetmair 1961-)、チェロ独奏はアントニオ・メネセス(Antonio Meneses 1957-)。 3)のピアノはスヴャトスラフ・リヒテル(Sviatoslav Richter 1915-1997)、合唱はソヴィエト国立アカデミー合唱団。なお、独唱者の名前は、クレジットされておらず、ちょっと調べてみたけれど、分からなかった。 田園交響曲とブラームスの二重協奏曲は、いずれもこの時期のサンデルリンクならではの、ゆったりとした裾野の広い音楽で、急速部分であっても、大変落ち着いた足取りで、構えの大きな音楽を作っている。 田園交響曲は、常に柔らかで、温厚かつ慈愛を感じるような響きに包まれている。第1楽章で象徴的な付点のリズムも、運動的な前進性が抑制される一方で、よく吟味された合奏音を導き、あくまでふくよかな全体像を描き出すことが優先されている。第2楽章の耽美的ともいえる美しさは忘れがたく、神がかり的とでも称したいような響き。夕暮れ時に、天上からとどく柔らかな光が大地を覆っていくような、そんな感動的な自然美に満ちている。第3楽章、第4楽章は、他の演奏に比べると、より力強さが欲しくなるところもあるのだが、ブレンド感溢れたオーケストラの絶対的な美しさは見事である。第4楽章から第5楽章への移行部は、私が特に愛する個所だが、嵐が去り、雲間から再び光が射してくるような、天国的なホルンと弦楽合奏が、素晴らしい。 ブラームスの二重協奏曲は、私がこれまで聴いた中で、もっとも表現の柔らかな解釈と言って良い。ヴァイオリン、チェロもザンデルリンクが描く全体的な柔らかさの中に溶け込んだ響きを演出しており、その統率性に感心させられる。第2楽章の素朴な主題も、いかいも大事に扱われているのが良く伝わるし、普通ならかなりガチャガチャしたところの出てくる終楽章も、おや、と思うほど起伏が緩やかで、なだらかな聴き心地だ。大家の至芸を感じさせつつ、好悪が分かれるところかもしれない。 田園交響曲、二重協奏曲とも録音状態は良く、透明感があって、すっきりしたサウンドになっている。雑音も少ない。 ボーナス収録してあるベートーヴェンの合唱幻想曲は、前二者に比べると(楽曲が違うと言うこともあるが)、ずっと力強い前進性を感じさせる演奏。ただ、当然のことながら、音源自体が古いので、あくまで雰囲気が伝わるくらいである。リヒテルのピアノは直線的で堂々としたものであり、この時のザンデルリンクのスタイルと、よく合致している。 |
|
 |
交響曲 第6番「田園」 第8番 エグモント序曲 ハイティンク指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2009.12.30 |
| ★★★★★ 田園交響曲第2楽章は全集の白眉とも言える美しさ
ベルナルト・ハイティンクが20年に渡って良好な関係を築き上げたコンセルトヘボウ管弦楽団と80年代末に作成したベートーヴェンの交響曲全集からの分売。かつてはフィリップスだったがレーベルの統合によりデッカとなった。CDのタスキのデザインが変わるだけで、随分印象も変わるものだと感じる。 当ディスクは収録曲の量も十分だし、曲目も当時のハイティンクとコンセルトヘボウ管弦楽団の特徴を十全に伝えるものだと思う。その特徴はまろやかな肌触りであり、高級なブレンド感であり、かつ力強い芯の通った楽器の響きにある。現代では、このような大編成の現代楽器のオーケストラを存分に鳴らしたベートーヴェンは、ちょっと古めかしいスタイルと見られるのかもしれない。しかし、そのようなオーソドックスな演奏がかように魅力的に響くということもまた、とても大事な価値観だと思う。 交響曲第6番「田園」は、楽園アルカディアを描いた標題音楽であるが、「田園」というタイトルから受ける日本人が漠然と思い描く牧歌的な田舎の風景にもよくマッチしている。神への感謝で終わるこの交響曲は、自然賛美のための音楽として聴いていて何ら違和感がない。嵐の過ぎ去ったあとの神秘的な美しさはロマンの作曲家たちでさえその高度な「標題性」に打ち負かされたのではないだろうか。さて、ここでハイティンクの演奏であるが、非常に自然な屈託のない喜びに満ちたサウンドとなっている。しかも各楽器の繰り出す音が豊かな色と味を湛えているように思える。白眉は第2楽章の美しさだろう。弦楽器がこまやかな感情の基礎を築き、管楽器がそこから派生する自然光のようなニュアンスを細かに伝えてくれる。 第8番も「開放の音楽」である。ハイティンクの棒の下、溌剌たる生命感に溢れた音楽が展開する。決して急ぎ過ぎず、かと言って大家風になり過ぎるわけでもない。若々しい活力が感じられる。この曲はこういう音楽なのだとあらためて認識させられる。 「エグモント序曲」が収録されているのもウレシイ。交響曲に聴き劣らない充実した音楽と演奏だ。 |
|
 |
交響曲 第7番 序曲「コリオラン」 パイタ指揮 フィルハーモニック交響楽団 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2019.9.28 |
| ★★★★★ 血沸き肉躍るリズムの祭典。パイタによるベートーヴェンの第7
カルロス・パイタ(Carlos Paita 1932-2015)によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の下記の2作品を収録したアルバム。 1) 交響曲 第7番 イ長調 op.92 2) 序曲「コリオラン」 op.62 1)はフィルハーモニック交響楽団と1983年、2)はロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と1985年の録音。 たいへん力強い、推進力に溢れたベートーヴェン。駆り立てるような前進性は、両曲が持つ躍動的な一面を如実に示しており、その燃焼性は高い。パイタの音楽づくりは、楽曲が持つ外向的な一面を強調したもので、そのスタイルはしばしば批判の対象になったり、批評の対象に上げることさえ避けられる場合さえあるのだが、私は、これらのベートーヴェンが、とても魅力的な演奏であり、また、楽曲のもつ芸術性や、抽象的ではあるがいわゆる「精神性」を、貶めるよなものではないと考える。パイタの録音を取り扱うLodiaレーベル(パイタ自身が私財を投じて設立したことで有名)の音源が、入手しにくくなってきている背景もあって、私は最近になってパイタの録音を一部ながら入手して聴くようになったのだが、特にベートーヴェンの解釈は堂に入った感があり、当盤も見事なものだと思う。 それにしても、交響曲第7番という曲は、やはりリズムが命だと思う。そこさえ「キメる」ことができれば、聴き手の心は演奏に付いてくるだろう。当盤の魅力もスピーディーで心地よい躍動感につきる。停滞のない力の供給。その厚みと幅。それが魅力だ。オーケストラも、音色そのものの魅力にもう一つなにかほしいところが残るとはいえ、聴いているうちに、演奏の熱さに圧倒され、そんなことは気にならなくなるだろう。低音、金管、ティンパニの強さは、決して藪から棒ではなく、音楽的な脈の中でうまく吸収されている。第2楽章はフレーズの響きの太さ、そしてそこから紡がれる濃厚な情感が頼もしい。第3、第4楽章はまさに勢いの勝利。特に終楽章の迅速な展開の楽しさは、なかなか捨てがたい魅力に満ちている。 序曲「コリオラン」も圧巻の演奏。弛緩のない早いテンポ、前面化を惜しまない金管の激しさあるが、この俊敏な情景転換で、フレーズが新たな魅力をまとっていると感じられることも新鮮だ。第2主題前の「タメ」の深さは、多少芝居がかっているものの、心憎い演出。そして、熱血的なテンションを蓄えて、あっと言う間にコーダに導かれる。「ああ、本当にこの曲は、カッコイイ曲なんだな」と改めて思わせてくれる快演奏だ。 カルロス・パイタという指揮者、未聴で興味があるなら、まずはベートーヴェンがおすすめ。なお、第7交響曲の第1楽章はリピートあり。終楽章は省略している。 |
|
 |
交響曲 第7番 第8番 ショルティ指揮 シカゴ交響楽団 レビュー日:2007.3.12 |
| ★★★★★ 「聴かず嫌い」はもったいないですよ!
サー・ゲオルグ・ショルティの往年の録音が一気に再リリースされた。これを機にこの大指揮者の評価が再度高まることを期待したい。 さて、この録音はショルティが70年代に手兵シカゴ交響楽団と録音した最初のベートーヴェン交響曲全集に含まれるものである(再録音あり)。常日頃思うことだが、日本のクラシック音楽ファンには、どうも欧州幻想というものがある。例えば、オーケストラであっても、欧州に拠点を置くオーケストラを「本場」として、ちょっと一目高く置いてみる。別にそれは罪なことではないし、趣味というのは概ねそんなものかもしれないが、しかし、あらたまってこの録音を聴いてみてどう思うだろうか?私の場合「これほど勇壮で真にヒロイックなベートーヴェンは、そう簡単に聴けるものではない・・・」と感嘆してしまった。つまり、「とりあえず、聴いてみてください!」と宣伝したくなる“いい演奏”なのである。ショルティ/シカゴ響というと、条件反射的に、ややメタリックで機能美で押し通したような演奏を連想する人が多いと思う。しかし、この演奏、ふくよかな弦のニュアンスといい、管の呼応する距離感といい、実に的確で、かつ含蓄豊かな温かみがある。もちろん、贅肉を削ぎ落としたような凛々しさも漂っているし、まさにベートーヴェンの本流たる演奏なのである。第7番、壮大な序奏が終わり、開始5分ごろに提示される全合奏による第1主題、その完璧な響き!ブラスセクションと豊穣な音色とゆるぎない逞しさに圧倒されてしまう。「聴かず嫌い」はもったいないですよ! |
|
 |
交響曲 第7番 第8番 「エグモント」序曲 「アテネの廃墟」序曲 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 レビュー日:2012.3.16 |
| ★★★★★ 余計な(?)思考はおいておいて、このスピード感を楽しみましょう!
2007年から2009年にかてて録音されたリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全集からの分売。計5つに分かれての分売で、それぞれのディスクは全集中での5枚のディスクをそのまま抜き出した形で、曲順の変更などは行われていない。 これは全集の4枚目に相当するディスクで、交響曲第7番、第8番、「エグモント」序曲、「アテネの廃墟」序曲が収録されている。 これだけの曲数が収録できることからも示されている通り、たいへんな快速演奏が特徴である。しかも、交響曲第7番と第8番という楽曲の性格もあいまって、終結まで一気に一直線に引ききったような潔(いさぎよ)い音楽だ。濁りの少ない音色は、聴き味を軽やかなものする一方で、スピード感を一層高めており、急峻に畳み掛ける勢いを増幅している。少し、ショルティとシカゴ交響楽団の演奏を思い出させるところがあるが、シャイーのは一層、急(せ)くような息遣いがあり、それがこの演奏の迫力の要素になっている。 私が目にしたシャイーのベートーヴェンの批評の中に、「精神性が薄い」というようなコメントが、ネガティヴなニュアンスとして使用されていたものあったが、私はこの点に二重に懐疑的である。まず「精神性」というのは主観的なものである。もちろん、そういった「何か言い難い印象」を形容するのに使用することもあるし、ベートーヴェンの音楽に深い精神性があるというのは、確かにそうだろう。しかし、「精神性を感じる」という言い方は出来ても、「この演奏は精神性が薄い」と否定的に使うのは、あまりにも主観に過ぎるのではないか。第2に、そもそもベートーヴェンは、「さあ、私の音楽から深い精神性を感じてくれ」と考えて作品を書いていただろうか、ということ。ベートーヴェンは後年、自分の芸術は福祉のために存在する、と言っている。福祉とは、おそらく英語のwelfareに近く、音楽を通じて大衆に喜びを与えること、民衆の幸福を増すことに意識が赴いていたように思う。だから、「さあ、おれの音楽で楽しんでくれ」という気持ちが第一にあり、結果として、現在の私たちが深い精神性を彼の作品から感じているのではないだろうか。 つまり、シャイーの喜びや悦楽に強く作用し、人を鼓舞するようなアプローチに対し、「精神性が薄い」と言うのは、コメントとしてズレているように(私には)思えてならないのです・・。 まあ、そんな私の御託はどうでもいいですかね(笑)。聴きましょう聴きましょう!楽しいですよ、快活で屈託無く、オーケストラの力量も圧巻なシャイーのベートーヴェン。気持ちがスカッとする見事な快演です! |
|
 |
交響曲 第7番 第8番 第9番「合唱付」 ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン楽友協会合唱団 S: ダッシュ A: 藤村実穂子 T: ベチャワ B: ツェッペンフェルト レビュー日:2012.7.10 |
| ★★★★★ 50年代~70年代を彷彿とさせるようなベートーヴェン
ドイツの指揮者、クリスティアン・ティーレマン(Christian Thielemann 1959-)が、2008年から2010年にかけてウィーンフィルと行ったベートーヴェンの交響曲全曲演奏プロジェクト「BEETHOVEN9」の模様を収録したCD。全3巻で分売されていて、本巻には第7番、第8番、第9番「合唱付」の3曲が収録されている。録音は第7番と第8番が2009年、第9番が2010年。第9番では、ウィーン楽友協会合唱団の合唱に、以下の独唱陣が参加。S: アネッテ・ダッシュ(Annette Dasch)、A: 藤村実穂子、T: ピョートル・ベチャワ(Piotr Beczala)(テノール)、B: ゲオルク・ツェッペンフェルト(Georg Zeppenfeld)。 日本国内では2011年の秋に、リッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)の全集とほぼ同時期に発売となり、話題となったものの分売版。全集にはDVDが付属していたが、分売はCDのみで価格も安価に設定してある。さて、この2種の全集、対照的な特徴がある。シャイーの先鋭性に対し。ティーレマンの特徴は保守性と言える。 では、「保守性」とは何か。これは従来から名演と形容されてきたスタイルを踏襲した点にあると思う。それを感じさせる主な特徴は以下の通り。(1) カラヤン、ベームなどのドイツ・オーストリア本流に近いテンポ設定であること。 (2) 現代楽器の特性を生かしたオーケストラサウンドの構築していること。 (3) デュナーミクやアゴーギグを使ってフレージングを明瞭に設けていること。(4) ポルタメントやラレンタンドを多用すること。 結果として美麗で豪壮な、いかにも「あなたのイメージにある本来のベートーヴェンってこんな感じでしょう?」といった音楽が提示されている。中でも私が興味深いのは音楽への表情付けに係る演出。例えば交響曲第8番の第1楽章冒頭、燦然たる第1主題の提示に引き続いて、連続する弾むのような和音に、微妙な呼吸を与え、瞬間ぐっとタメを作って改めて加速する。このマニュアル車のギアチェンジさながらのタメは、インテンポ主体の現代では逆に新鮮だ。この手法はあちこちで顔を出すので、聴きながらリズムをとっていると、そのたびにぐっと体が前にのめるような、不思議な力を感じ取ることができる。これは聴く人によっては気になるのかもしれないけれど、(私もときおりそれが気になる個所もあったけど)、面白いことは面白いし、これがティーレマンのベートーヴェンなのだろうと思う。 第7番もそのタメと踏み込みの効果があちこちで見られる。オーケストラサウンドは、さすが天下のウィーンフィルといったところで、特に第7番では、豊かな情感を湛えたブラスの響きが素晴らしい。音楽に豊饒な恰幅を与えている。ティーレマンの演奏は、とくにフレージングの大きいところでデュナーミクやラレンタンドをはっきりと設定していることが多く、パート毎に音楽をまとめていくような趣がある。それで、聴き手に「さあ、ここまでよく分かりましたか?」とその都度、にこやかに問いかけてくるような感じで、そのことも昔風のスタイルに思える一因だろう。ちょっと親切な先生の授業のような感じかな? 第9番はことに浪漫的な音楽なので、ティーレマンの演奏にほとんど不自然さは感じられない。むしろ「これくらい演出をしてくれたら、それはそれで第9らしい」と思えるほど。ウィーンの素晴らしい音響を存分に味わうことのできる終楽章は、王道のベートーヴェンと呼ぶにふさわしい風格を感じさせてくれる。 |
|
 |
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ピアノ協奏曲 第3番 大フーガ(ギーレン編) ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 p: リトウィン レビュー日:2020.3.2 |
| ★★★★★ ギーレンならではの鋭利な解釈が光るベートーヴェン
ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-2019)指揮、南西ドイツ放送交響楽団の演奏で、ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の以下の楽曲を収録。 1) 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93 2) ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37 3) 大フーガ(ギーレン編) 変ロ長調 op.133 (ギーレン編による弦楽合奏版) 2)のピアノ独奏は、メキシコのピアニスト、ステファン・リトウィン(Stefan Litwin 1960-)。 2000年の録音。 ギーレンならではのベートーヴェンだ。全般に早目のテンポで一貫し、ルバート奏法は控えめ。楽器のバランスを厳密にコントロールしながら、明瞭なリズムとアクセントで、響きを統一している。 交響曲第8番は特に解釈の一貫性を強く感じさせるが、コントールされた刻み幅の綿密な設計により、常に整然とした輝かしさがあり、それによって音楽は情感や発色性を持っている。決して敷居の高い演奏ではなく、むしろリズムの妙が冴えており、この交響曲が持つ喜びの感情がストレートに出てくる。アクセントの明瞭さは、時に硬さを感じさせるもので、当演奏もその傾向と無縁ではないが、オーケストラの音色自体に暖かみがあり、結果として中和される。第2楽章は、平均より少し遅いかもしれないが、それとて、弛緩に繋がる要素はなく、ベートーヴェンらしい筋肉質な美観が貫いている。 ピアノ協奏曲第3番も同じスタイルで、正確なリズムの中で、きびきびとアクセントを入れて進んでいく。リトウィンのピアノはとにかく真面目。カデンツァなど、もっとピアニストの個性を感じさせてもいいのでは、と思うのだが、ギーレンの音楽性に触発されたか、進行の正確さを重んじ、緻密で、一定の緊張感を持続させる。総じて、ギーレンのベートーヴェンになっていると感じられる。 大フーガの弦楽合奏版は、いくつかスコアがあり、録音点数もそれなりにある。当盤はギーレン自身の編曲となっている。こちらも緻密な演奏で、強い響きによるアクセントもしっかり挿入している。ギーレンの厳密な作法に従った表現が、この曲の構造を解析的に照らす出す効果があって、面白い。 全体として、緻密な進行でありながら、感情も発色も豊かな演奏となっており、ギーレンならではの見事なベートーヴェンとして完成されている。 |
|
 |
交響曲 第9番「合唱付」 アシュケナージ指揮 NHK交響楽団 二期会合唱団 S: 森麻季 Ms: ヘルカント T: ポホヨネン Br: レイフェルクス レビュー日:2006.3.21 |
| ★★★★☆ 演奏はいいのですが、録音に疑問!
アシュケナージの指揮者としてのキャリアはもう20年以上になるが、NHK交響楽団の音楽監督となって以降、そのレパートリーは変化しているようだ。これまではネーム・ヴァリューのあまり大きくない作曲家、あるいは作品の録音が多くあり、ドイツ音楽の本流のようなジャンルはあまり多くはなかった。しかし、NHK交響楽団というドイツ・オーストリア系の音楽の経験がほとんどであるオーケストラを振るに当たって、そこにベートーヴェンを持ってくると言うのは、アシュケナージのキャリアとしてそこに至るタイミングと重なったとも感じられる。そして第9交響曲のライヴ録音がリリースされることになったのだろう。 演奏であるが、今までのアシュケナージのスタイルと違った顔が出ていて驚かされる。やや早めのテンポ設定はいつも通りであるが、元来の透明感溢れる瑞々しい指揮とは違い、音楽の色合いが深刻で、内省的な響きに満ち、緊迫感が強い。 それはベートーヴェンの第9だから、という以上にアシュケナージのベートーヴェンへの距離感そのものの変化と考えたほうが面白いだろう。1,2楽章の緊密な構成感、3楽章のクールで控えめな歌による内面の掘り下げ、そして終楽章もリズム感豊かでありながら、均質な密度を保っている。 と、演奏はなかなか一興をそそるのだが、このディスクの問題点は録音にある。 NHKホールという場所の問題なのか、録音セッションの不備によるものかわからないが、音がこもりがちで、音色が曇ってしまうのだ。エクストン特有のハイブリッド仕様であるが、仕様云々の前にそもそもの録音レベルが水準に達しないのは残念である。できれば、あらためてスタジオで収録しなおしてほしいものだ。演奏がもったいない。 |
|
 |
交響曲 第9番「合唱付」 シノーポリ指揮 ドレスデン・シュターツカペレ ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 S: クリンゲン MS: パーマー T: モーザー B: タイタス レビュー日:2012.8.3 |
| ★★★★☆ 録音の点で問題を残した、もったいないシノーポリの第9
2001年、公演中の指揮台で倒れ、そのまま急逝したイタリアの名指揮者、ジュゼッペ・シノーポリ(Giuseppe Sinopoli 1946-2001)は、早すぎるその死を惜しまれたが、その一方で、幅広いジャンルに録音を遺した。2012年になってグラモフォン・レーベルから、その録音から抜粋した16枚組の廉価Box-セットが発売されたので、私はこれを購入し、聴いている。 この16枚組のセットで、「1枚目」に収録されているものが、当盤に当たる。シノーポリ指揮、ドレスデン・シュターツカペレとドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の交響曲第9番「合唱付」。独唱陣は、S: クリンゲン(Solveig Kringelborn 1963-) MS: パーマー(Felicity Palmer 1944-) T: モーザー(Thomas Moser 1967-) B: タイタス(Alan Titus 1945-)。1996年のライヴ録音。 シノーポリはロマン派から近現代に至るまで、実に幅広い音楽をやってきたが、一般的に、古典派を振ることは多くなかった。この第9交響曲も自身が50歳になってからの録音で、おそらく、これから古典派にも取り組んでいこうと考えていたのではないだろうか。他にも同様の足跡をたどるアーティストがいるので、そう思う。今となっては私の想像の範囲でしかないけれど。 さて、それではシノーポリが遺した第9交響曲を聴いてみよう。まず、基本的にかなり速いテンポである。また、音作りが固めで、他のシノーポリの演奏とは大きく異なる印象であるのに驚いた。私は、この作品であっても、シノーポリらしいふくよかさや、透明感が感じられるのではと期待していたのだが、むしろ多少の濁りが生じても、テンポを押し通すような、ちょっとした強引さが感じられ、「本当にシノーポリの演奏なの?」とびっくりしてしまった。 もう一つ、このディスクを聴いての大きな印象だが、録音の品質に問題が感じられた。響きに潤いが足りなく、一様な薄味を伴ってしまう。第1楽章、第2楽章とも早めのテンポで押し通しているのだけれど、この録音の品質のせいもあって、単調な感をぬぐえない。第3楽章は美しさを増すが、こちらもソリッドな肌触りがあり、録音が演奏を活かしていないと感じられる。せっかくのシノーポリの遺した第9がもったいないことだ。 このディスクの良いところを挙げるならば、第4楽章であろう。合唱とソリストの充実もあって、音楽は全般に息を吹き返したように色づき、音楽の喜びが伝わるものとなっている。ただ、私のようにBox-セットで買った場合は別だけれど、ベートーヴェンの第9交響曲のCDとしてこれを上位で推せるかと言われれば、上記の理由によりためらいが残る。 |
|
 |
交響曲 第9番「合唱付」 「命名祝日」序曲 劇付随音楽「シュテファン王」序曲 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 ゲヴァントハウス合唱団 ゲヴァントハウス児童合唱団 MDR放送合唱団 S: ベラノワ A: パーシキヴィ T: スミス B: ブラッハマン レビュー日:2012.3.16 |
| ★★★★★ 全集中でも白眉と思える第9交響曲第4楽章を堪能
2007年から2009年にかてて録音されたリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全集からの分売。計5つに分かれての分売で、それぞれのディスクは全集中での5枚のディスクをそのまま抜き出した形で、曲順の変更などは行われていない。 これは全集の5枚目に相当するディスクで、交響曲第9番「合唱付」、「命名祝日」序曲、劇付随音楽「シュテファン王」序曲が収録されている。合唱は、ゲヴァントハウス合唱団、ゲヴァントハウス児童合唱団、MDR放送合唱団の混合編成で、独唱陣は、S: カテリーナ・ベラノワ(Katerina Beranova)、A: リリー・パーシキヴィ(Lili Paasikivi)、T: ロバート・ディーン・スミス(Robert Dean Smith)、B: ハンノ・ミュラー=ブラッハマン(Hanno M'ller-Brachmann)。 私は、シャイーのベートーヴェンを全集で購入させていただいたのだが、その全集のレビューに「“いまのベートーヴェン”、全集で聴くなら、迷わずこのシャイー盤を挙げたい」と書かせていただいた。その後、分売が発売されることとなり、自分の中でもたいへんインパクトのある録音だったので、それぞれに言い足りなかったことを付け加えて改めてレビューをさせていただいている。 中で、自分が「いまのベートーヴェン」の代表としてシャイーを推すにあたり、この第9交響曲の名演は決め手とも言える内容だったと思う。この曲でも、シャイーはベートーヴェン時代のメトロノーム指示に従った高速演奏を披露しているが、第4楽章の合唱、ソロのバランス感覚の卓越は圧巻で、ただ速いだけではなく、速いテンポならではの美観をどうやって獲得するかという問いに、実に鮮やかな解答を提示していると思う。 声楽が導入される直前の雪崩の様なオーケストラの迫力、ティンパニの効果も実に見事だが、それに続いて展開する声楽陣の活躍ぶりもまた圧巻の見事さで、ソリストたちの掛け合いは弦楽四重奏でも聴く様に緻密で音量のバランスが絶妙。合唱は中声部の充実により、速いテンポでも乱れない安定感があり、決して叫びにならない高貴さを保っている。オーケストラ共々みごとな透明感があり、純器楽的で緻密な演奏を繰り広げる。音楽における喜びの表現というだけでなく、美しく焦点を合わせるためのテクニカルな方法論まで提示した成功例だと思う。 他の楽章も速さが特徴であるが、特に第2楽章の峻険な鋭さは聴き手にぐいぐいと迫るような迫力を感じさせている。第3楽章はサラッとした印象になるが、むしろ長さを感じさせず、流線型の美観が貫かれていると考える。第1楽章は暗示的ではないが、開放感があり、十分に聴き手の気持ちをつかみうるものだ。あまり有名ではない序曲まで収録されているのも、企画の価値を高めており、フアンの購買意欲に繋がるものだと思う。 |
|
 |
交響曲 第9番「合唱付」 アバド指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ベルリン放送合唱団 スウェーデン放送合唱団 エリク・エリクソン室内合唱団 S: イーグレン MS: マイヤー T: ヘップナー Br: ターフェル レビュー日:2015.7.24 |
| ★★★★☆ 登場時に、様々な話題を提供した録音です。
アバド(Claudio Abbado 1933-2014)指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、スウェーデン放送合唱団、エリク・エリクソン室内合唱団演奏による1996年のザルツブルク祭音楽祭でライヴ収録されたベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の交響曲第9番ニ短調op.125「合唱」。4人の独唱者はソプラノがジェーン・イーグレン(Jane Eaglen1960-)、メゾソプラノがヴァルトラウト・マイヤー(Waltraud Meier 1956-)、テノールがベン・ヘップナー(Ben Heppner 1956-)、バス・バリトンがブリン・ターフェル(Bryn Terfel 1965-)である。 いろいろと有名な録音である。注目点は大きく2つある。 1) イギリスの音楽学者ジョナサン・デル・マー(Jonathan Del Mar 1951-)により、1996年に刊行された「ベーレンライター版」のスコアを用いていること 2) エストニアの名合唱指導者、トヌ・カリユステ(Tonu Kaljuste 1953-)が合唱を担当していること まず、1)についてである。ベートーヴェンのスコアは、長らくブライトコプフ版が使用されてきた。しかし、このスコアがその基本資料としたパート譜及びヴィルヘルム3世への献呈譜については、当時の演奏事情による変更があったこと、ベートーヴェン自身の厳密な校訂がなされていないこと、写譜者のミスがあること、慣例的な修正が加えられていること、等によりベートーヴェンのオリジナルなアイデアのいくつかが失われていると考えられてきた。それまでも別箇部分的に、より古いスコアを研究して、反映させた演奏はあったのだが、ベーレンライター版は、前述の価値観を鑑み、9曲の交響曲すべてについて、スコアをオリジナル主義で見直した。第9交響曲の場合、ブライトコプフ版が原典としたスコアより1年前の写譜等に基づいた編集を行っている。 最近ではジンマン(David Zinman 1936-)やラトル(Simon Rattle 1955-)がこのベーレンライター版を積極的に取り上げているが、このアバドの演奏がその祖と言えるもの。ただし、アバドの演奏は、場所によっては旧来のブライトコプフ版を使用しているところもある。詳細はわからないが、アバドが無効と判断したのか、よく知っている楽曲を単に慣行的に従来のまま演奏した場所があったのかのどちらかだろう。例えば第1楽章のフルートの音程などである。 とはいえ、第2楽章の反復の短縮化や、いくつかのメトロノーム指示の変更により、聴き味は「速めの演奏」となっている。そのため、終楽章の冒頭部と中間部などを中心にアクセントの強さを感じる部分がいろいろ出てくる。とはいえ、演奏自体に、ラトルやジンマンのような「従来版との違い」を強調する趣向は採用されていない。スコアは新しいが、アバドの基本的な解釈は、わりとスタンダードなのである。 (ちなみに、終楽章のピッコロのオクターブ変更については、ベーレンライター版ではなく、本演奏独自のものである) 2)についてであるが、終楽章の合唱について、全般に当アルバムは高い評価を得ているようである。たしかに純度の高い、明瞭さを感じさせる合唱である。その一方で、私は妙に表面部に刺々しさの残った合唱にも聴こえる。従来の表現への慣れのせいかもしれないが、神々しさよりも、はるかに人間的な地べたに通じるパワーを感じるもので、それがこれまで長く築いてきたこの楽曲の印象と(私の場合)若干の違和感になって伝わる。もちろん、新鮮さはあるのだけれど。また、前述のベーレンライター版のテンポの新規性と合わさって、そのような突起のある印象を持つのかもしれない。 スコア云々の話は別として、私が当盤でいちばん気に入ったのは第2楽章である。キビキビとした音楽の運びで、快活無比に仕上がっており、アバドならではのリズム感と機能美の融合を楽しんだ。 それにしても、この注目を集めた録音から早くも20年近くが経過したのか、と感慨深い。その後登場した様々なベーレンライター版の演奏と聴き比べてみるのも面白いです。 |
|
 |
交響曲 第9番「合唱付」 シュイ指揮 コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団 アルス・ノヴァ・コペンハーゲン ラトヴィア放送合唱団 S: エック A: ヤンソン T: クーリー Br: チャンヤン レビュー日:2018.4.6 |
| ★★★★★ 第九交響曲から新しい魅力を引き出した意欲的録音
中国杭州市出身のラン・シュイ(Lan Shui 1957-)指揮、コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の、交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付」。2013年の録音。合唱はアルス・ノヴァ・コペンハーゲンとラトヴィア放送合唱団。独唱者は以下の通り。 ソプラノ: クララ・エック(Klara Ek) アルト: エリザベト・ヤンソン(Elisabeth Jansson 1976-) テノール: トーマス・クーリー(Thomas Cooley 1970-) バリトン: リァオ・チャンヤン(Liao Changyong 1968-) 2013年の録音。ラン・シュイとコペンハーゲン・フィルによるベートーヴェンの交響曲全集シリーズの最後を飾る一枚。 すでに、彼らの第1集と第2集のアルバムにもレビューを書かせていただいたが、同様に見事な一枚となっている。ティンパニと金管楽器の一部のみをピリオド楽器に置換した編成で、ベートーヴェンのメトロノーム指示を守ることを第一義とし、そのために必要な表現とサウンドを究極まで突き詰めたような演奏だ。 ベートーヴェンの第9交響曲は、誰もがご存知の通り、第4楽章で声楽が加わる。その冒頭のバリトンよるレチタティーヴォは「おお、友よ! このような調べではない!そんな調べより、もっと心地よいものを歌おうではないか。もっと喜びに満ち溢れるものを。」 ~これはシラー(Friedrich von Schiller 1759-1805)の詩に基づくテキストに入る前に、ベートーヴェン自身が書き加えた歌詞である。では、その前段部は、心地よくない、喜びのない音楽なのか? 断じてそんなことはないのである。確かにニ短調の第1楽章から深刻で神秘的な気配が支配的ではあるが、そこに込められた音楽の機微は多彩で、魅力に溢れているのである。このレチタティーヴォの歌詞に拘泥することに、私はさほど音楽的な価値を見出さない。 ラン・シュイの演奏を聴く。ベートーヴェンのメトロノーム指示に従い、素早くさばき畳みかけるようなテンポは、前述の合唱前導入前の3つの楽章を、きわめて軽やかで、活力に溢れたものとしている。颯爽と機敏に駆け回り、鮮やかな色彩を瞬時に放つ。それは、「心地よい」響きであり、他の一般的な演奏に比べて、「喜び」に作用する要素が大きく増大していると感じる。あのレチタティーヴォの言葉など一切意に介さないほどに、ここまで自由に、清々しく解釈された第9交響曲は、かつてなく新鮮な魅力に溢れている。そして、この演奏から得た手掛かりをもとに、全曲を俯瞰すると、前半3つの楽章が、序奏的な役割を帯びていることに気づく。 もちろん、それは単に序奏と呼ぶには、圧倒的に偉大で大きな存在でもある。しかし、演奏時間の短縮と、音色の軽量化、そして機動性の確保は、速やかな連携性を発揮し、さながら2部構成のオラトリオのように楽曲の表情を整える。そのような観点でみると、あらためて、シュイが周到な考察をもとに、各パッセージに、その役割を与えなおしていたことに思い当たる。たいへんな策士である。 もちろん、そのような「解釈」に、「従前と違う」と異を唱えるのはたやすい。しかし、この演奏は、捨てがたい独特の魅力に溢れている。巨大性や神秘性とまったく異なる新しい領域に、従来とは違った生命力を息吹かせた。これは得難い経験といって良い。 声楽についても言及しておくと、4声の独唱とても協調性、親和性の高い歌唱、ということができる。それは独唱同士のバランスとともに、オーケストラの各楽器との間でも緊密なコントロールを感じさせ鵜ものだ。合唱も、その価値観に従った誠実な響きといって良い。 録音優秀なこともあり、存在感のある第九交響曲の録音というべき内容である。ラン・シュイのベートーヴェン・シリーズの成功を端的に物語る。 |
|
 |
交響曲 第9番「合唱付」 クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団 バイエルン放送合唱団 S: ドナート A: ファスベンダー T: ラウベンタール B: ゾーティン レビュー日:2019.8.31 |
| ★★★★☆ 巨匠クーベリックの棒による熱血的な第9のライヴ録音
チェコが生んだ名匠、ラファエル・クーベリック(Rafael Kubelik 1914-1996)が、蜜月の関係にあったバイエルン放送交響楽団を振っての、1982年のライヴ音源をCD化したもの。ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付」。合唱はバイエルン放送合唱団。4人の独唱者は以下の通り。 ソプラノ: ヘレン・ドナート(Helen Donath 1940-) アルト: ブリギッテ・ファスベンダー(Brigitte Fasbaender 1939-) テノール: ホルスト・ラウベンタール(Horst Laubenthal 1939-) バス: ハンス・ゾーティン(Hans Sotin 1939-) クーベリックのライヴ特有の熱血性が良く伝わってくる録音。現代の感覚で言えば、「大時代的」と形容したいフォルムだが、その表現の濃さは、この楽曲が持つ世俗性を、強烈に聴衆に突き付けた感があり、なかなか気持ち良い。 第1楽章の冒頭はややゆっくりしたテンポによるが、第1主題のクライマックスから込められた力が辺りを支配し、弾力的な進展があたりを支配していく。激しいリズム、強靭なフォルテは、時にその外形を荒々しくするが、この時代ならではの迫力をもっている。クーベリックという指揮者に備わっている燃焼的な性質が、オーケストラにのり移った様な、異様な迫力を感じるが、その一方で、演奏の完成度と言う点では、高いというわけではなく、よりリズム的な鋭さを感じさせるものが欲しい部分も残す。 第2楽章も同様で、第1楽章から引き続く流れが、とめどなく打ち寄せてくる。熱的な性質は、とても人間臭さを感じさせるが、その突き抜けた部分に、崇高な気配があるのが、この楽曲に相応しいだろう。第3楽章は静かな音楽であっても、そのうちに秘めた情熱が、隠すことなどできないという風に首をもたげてくるのが、この演奏の特徴である。 第4楽章も同様の熱さを持っている。ただ、合唱、独唱それぞれの力強さが、やや一面的に聴こえる部分もある。現在の演奏に耳慣れたからかもしれないが、あまりに大らかで明朗な方向で、力強過ぎる・・・というと、伝わるだろうか。 以上のように、全般に大味に感じられてしまうところもあるが、クーベリックのライヴならではの、滾るような熱さに満ちていて、この時代の音楽表現の一つのスタイルをよく伝えてくれる記録となっている。 |
|