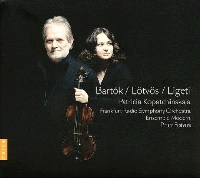|
管弦楽の為の協奏曲 バレエ音楽「中国の不思議な役人」 シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2010.5.20 |
| ★★★★★ シャイー&コンセルトヘボウ管弦楽団は、バルトークも素晴らしい
リッカルド・シャイーとコンセルトヘボウ管弦楽団によるバルトークの管弦楽曲集。なかなか見事な内容で、この顔合わせでもっと多くのバルトークの作品を録音して欲しかったと思わせる。シャイーのバルトークの録音として、シュロモ・ミンツの独奏によるヴァイオリン協奏曲第1番が企画ボックスから出ているが、個人的には、かつてFM放送されたアシュケナージとのピアノ協奏曲をぜひなにかの折にリリースしてくれればと思う。 いきなり話がずれてしまったが、当盤は1995年と97年の録音で、シャイーとコンセルトヘボウ管弦楽団の一連の録音の中でも特に聴き応えのあるものが集中している時期だと思う。このバルトークでもオーケストラの良さを巧みに引き出したシャイーのドライヴが聴きモノだ。 管弦楽のための協奏曲は、一聴してその細やかな配慮の行き届いた音造りに唸らされる。テンポはやや遅めであるが、細部を磨き上げることで、緩みを感じさせるものとはなっていない。弦楽器の暖色系の音色が心地よく、管、打楽器も音量とフレージングが高度に制御されていて、よくブレンドしている。そうして引き出される特性は、バルトークならではの野趣性とはまた一味違った「洗練」に通じる価値観にあり、それも「究めた」と言ってよい完成度に到達している。中間楽章のスケルツォ的な表情付けも、軽妙にして巧妙といったところ。終楽章の祭典もことのほか華やかで、しかし高尚な視点から制御が行き届き、音楽に鮮やかなコントラストを与えている。 バレエ音楽「中国の不思議な役人」は、日本ではバルトークの代表作としてあまり名を挙げられる作品とはなっていない気がするが、私の大好きな作品である。楽想の移り変わりの速さと土俗感溢れる迫力が魅力だ。このシャイー盤は、インデックスが細かく振られているので、そういった意味でも曲のことがよくわかる面白さがある。演奏スタイルは「管弦楽のための協奏曲」と同様で、いかにも現代的な洗練されたオーケストラサウンドが堪能できる。コンセルトヘボウ管弦楽団の音色は多彩なギアを持っていることもよく伝わるし、そのギアを曲想に併せて細やかに操作するシャイーの手腕も当代一品だろう。舞曲風の部分では、分離の良い素晴らしい録音が効果的で、聴き手の感情に強く働きかける。演奏・録音の両面においてデッカのカラーの良く出た名盤だと思う。 |
|
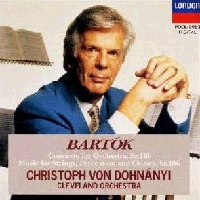 |
管弦楽の為の協奏曲 弦楽器、打楽器とチェレスタの為の音楽 ドホナーニ指揮 クリーヴランド管弦楽団 レビュー日:2010.4.8 |
| ★★★★★ これまたドホナーニの不遇な名盤の一つ。
最近、良くドホナーニとクリーヴランド管弦楽団の録音を聴いている。確かに昔からこれらの録音を聴いてきたけど、それにしても今現在、ほとんどこれらの録音が省みられないのは、損失と思えるので、その分自分は聴こう・・・とまあ勝手に思っているだけなのですが、それにしても埋もれさせておくのはもったいないものがたくさんある。 この1988年と92年に録音されたバルトークも素晴らしい演奏。「管弦楽のための協奏曲」と「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」といういずれも晩年の傑作だけに聴き応えがある。このCDは一時期国内版で、廉価シリーズで1,200円で出ていたものなので、そういうときにちゃんと買っている人は「買い物上手」と言えるでしょう。私は廃盤になってから探して、割高な中古品を買うこととなりました。 バルトークの「管弦楽のための協奏曲」は曲自体私の大好きなものだ。バルトークは、晩年、病苦と貧困から、非常に厳しい生活を強いられたのだが、しかしこの「管弦楽のための協奏曲」は喜びと遊戯性、そして生命肯定的なポジティヴな感情に満ちていて、聴き手を勇気付けてくれる曲とも言える。この曲の名盤としては、フリッツ・ライナーやゲオルグ・ショルティの様なスリムでシャープな演奏が多く挙げられるが、ドホナーニもほぼ同系列とみていいと思う。ただドホナーニの演奏の方が、もう少し音色がエモーショナルな面があり、悲しみや喜びがもう少し色づいて表現されていると思う。金管の音色もパレットが豊かだ。テンポは穏当で、早くも遅くもないが、クライマックスを中心とした構成感に卓越しているので、聴いていて「長さ」を感じさせることはない。 「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」は以前からバルトークの最高傑作として知られる。本当に、こんな素晴らしい音楽を書いた人が、なぜ晩年、赤貧に喘いだのだろう?当時のアメリカ(バルトークはナチスを避けアメリカに移っていた)にはまともな審美眼を持った人が極度に少なかったのではないかと勘ぐってしまうが、今とメディアによる情報伝達能なども違うということかもしれない。それにしても不遇だった。さて、ドホナーニは十二音音楽と民族性を融合し、さらに室内楽的な緊密性・緻密性に特化したこの作品を、克明な光で照らし出している。「管弦楽のための協奏曲」に比べてやや響きが冷たく感じられるが、それがこの作品の特性をよく引き出したものと思える。 いずれにしても、この名盤がいずれ復活・再評価されるのを待ちたい。 |
|
 |
管弦楽の為の協奏曲 弦楽器、打楽器とチェレスタの為の音楽 クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団 レビュー日:2019.8.31 |
| ★★★★★ アコースティックなトーンで情感豊かなクーベリックのバルトーク
ラファエル・クーベリック(Rafael Kubelik 1914-1996)指揮、バイエルン放送交響楽団によるライヴ音源で、バルトーク(Bela Bartok 1881-1945)の以下の傑作管弦楽曲2編を収録。 1) 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 1981年録音 2) 管弦楽のための協奏曲 1978年録音 いずれもクーベリックが得意としてきた楽曲だが、ここでも自信に溢れた輝かしく正統的なサウンドを聴くことが出来る。響きは「豊か」という形容がもっともふさわしいだろう。バルトークの音楽は、しばしば「無機的」と表現される。ただ、私には、この表現はあまりしっくりこない。確かに非常に緻密に設計された音楽ではあるのだが、そこには有機的と呼びたい様々な情感が満ちているし、旋律に宿される様々な感情がある。クーベリックの演奏も、まさにその点をついており、ある意味シンフォニックで保守的な響きとも言えるが、そのふくよかな安心感とともに、熱さや緊張のほどよいブレンド感があって、管弦楽のための大曲を味わう醍醐味に満ちた演奏となっている。 「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」では、その第1楽章に緊張の表現を認めるが、より素晴らしいのは第2楽章以降だろう。第2楽章は、弦のピチカート、そしてパーカッションの劇的な効果があるが、クーベリックのテンポはきびきびとした筋肉質なものであり、そこに十分な色づきの感じられる音色が添えられていく。このシーンだけでも、バルトークの音楽がもつ多様な表現力が明らかになっている。第3楽章も素晴らしい。やや速めのテンポを中心に、アコースティックな抒情が鮮やかに繰り広げられていき、大いに心を動かされる。これこそ名演の薫りだ。第4楽章は華やかで祭典的だが、そこに加えられる力が、一気に音楽を熱くしている。 「管弦楽のための協奏曲」では、自然な間断のないテンポがあり、普遍性を感じさせる解釈だ。中間3楽章を一貫性の感じられるテンポでまとめているのもクーベリック流であろう。様々な独奏楽器による技巧的なフレーズは、音楽として機能的に組み上げられている様は、当然かもしれないが、やはり見事であるし、全体を覆うややソフトなトーンが、音楽を親しみやすい暖かさで包んでいる。第1楽章、そして第5楽章の力強い勇壮な響きとその質感もさすが。 クーベリックの様々なライヴ録音の中でも、特に名演として指折りたいものの一つだろう。 |
|
 |
バルトーク 管弦楽のための協奏曲 ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲 ルイヴィルのためのファンファーレ P. ヤルヴィ指揮 シンシナティ交響楽団 レビュー日:2007.3.14 |
| ★★★★☆ ルトスワフスキとバルトークの接点が分かりやすいです
パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団による注目の録音。競合盤の多いバルトークよりも、ヴィトルド・ルトスワフスキ(Witold Lutoslawski 1913-1994 )の2作品が注目されるだろう。もちろん、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」の成功を経て、ロヴィツキの委嘱があって、ルトスワフスキの同名の作品が生まれた経緯があり、そこにこのアルバムの企画性がある。ルトスワフスキの作品は非常になじみ易いもので、バルトークの影響ももちろんのことながら、ポーランド土着のメロディ等も取り入れたルトスワフスキならではの着色がある。第1楽章の力強いリズム感などは聴き手に訴える力が強いだろう。バルトークの影響は様々に感じられるが、第2楽章のピチカートの連続する部分など、「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」を彷彿とさせる。演奏は、録音のせいかやや弦が引っ込んだ感じで地味な色合いだが、ルトスワフスキという作曲家を知るのに、まずはいい録音であろう。バルトークの「管弦楽のための協奏曲」は、他の名演を差し置いても「これ」というほどのインパクトはさすがにないが、それでも良心的な演奏であると言えるだろう。細やかな気配りで音色がつぶれるようなこともない。私が一番印象にのこったのは終楽章で展開の開始にあたって、突如テンポを落とし、弦、木管を柔らかに歌わせるシーンである。ここは今までの名演でも聴けなかった新たな情動を感じさせてくれた。 |
|
 |
管弦楽の為の協奏曲 舞踏組曲 ヴァイオリンと管弦楽のためのラプソディ 第1番 第2番 ラプソディ第1番 第2番(別エンディング版) ガードナー指揮 ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 vn: エーネス レビュー日:2017.12.14 |
| ★★★★★ オーケストラの明晰なサウンドが楽曲に新鮮な味わいをもたらした快録音
2015年からベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者となったエドワード・ガードナー(Edward Gardner 1974-)が、同オケを振って録音したバルトーク(Bartok Bela 1881-1945)の作品集。ガードナーは数年前にメルボルン交響楽団を振ってやはりバルトークを録音しているので、シリーズ第2弾といったところ。収録曲は以下の通り。 1) 管弦楽のための協奏曲 BB.123 2) ヴァイオリンと管弦楽のためのラプソディ 第1番 BB.94B 3) 同曲第2部の別エンディング版 4) ヴァイオリンと管弦楽のためのラプソディ 第2番 BB.96B 5) 舞踏組曲 BB.86A 管弦楽のための協奏曲は2016年、他は2017年の録音。 2~4) のヴァイオリン独奏はジェイムズ・エーネス(James Ehnes 1976-)。エーネスはバルトークのヴァイオリン協奏曲とヴィオラ協奏曲で秀演を録音しており、またソナタ、さらにラプソディも「ヴァイオリンとピアノ版」で録音済であり、すでにその高いクオリティは保証済みといったところだろう。 エーネスのヴァイオリンももちろん素晴らしいのだが、本盤のもう一つの聴きどころは、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団の音響にあるだろう。なんとも透明感にあふれたバルトーク。オーケストラの響きが、とにかく研ぎ澄まされたように精密で、一つ一つの楽器の音色に、光沢を感じさせるものがあって、とても新鮮なのだ。 バルトークの「管弦楽の協奏曲」は、オーケストラがその力量を試す際、外せない楽曲の一つであるだろう。しかし、最近考えてみると、意外に新録音が少ない。いくつか名盤と呼ばれるものの存在があって、そこに付け加えるべきものをなかなか見いだせない状況があるのかもしれない。 そのような中で、ガードナーのアプローチは、「まだまだやるべきことがある」と示した価値あるものだと思う。例えば終楽章、きわめてきっちりとした早いテンポを維持ながら、正確なリズムでクリアな処理の徹底を繰り返すことで、清冽な旋風のような音楽が獲得されている。もちろん、この楽曲によりマジャール的な熱狂性を求める人もいるだろうが、ガードナーの指揮のもと、正確無比に動くオーケストラは、別種の興奮があり、楽しい。第4楽章も、通常あまり表面だつことのないフレーズが浮かび上がるなど、発見がある。 エーネスがヴァイオリンを担ったラプソディはさすがの安定感。これらの楽曲にしてはエレガントな性向を持った演奏と言えるが、エーネスの技巧が素晴らしく、濁りと無縁の音色がバックのオーケストラと見事にマッチしている。テンポも、つねに生き生きとしていて、生命力を感じさせるもの。 舞踏組曲は、管弦楽のための協奏曲とおおむね同じ感想になるだろう。とにかく明晰にして俊敏。パワーより機動性を感じさせる表現で、一気に書ききったような爽快さが満ちている。鮮やかな快演だ。 |
|
 |
管弦楽の為の協奏曲 「かかし王子」組曲 ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 レビュー日:2019.12.25 |
| ★★★★★ バランス美を維持しながら情感豊かに表現されたバルトーク
ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-2019)指揮、南西ドイツ放送交響楽団の演奏で、バルトーク(Bartok Bela 1881-1945)の以下の2つの管弦楽作品を収録したもの。 1) バレエ音楽「かかし王子」組曲 2) 管弦楽のための協奏曲 「かかし王子」は2006年、管弦楽組曲は2005年、それぞれライヴ収録されたもの。「かかし」王子の組曲版は幾通りか存在し、定型化していないが、当盤では(序曲、王女、森、王子の歌、小川、かかし王子の踊り)という6編により構成されている。 現代音楽に精通するだけでなく、ロマン派や古典に関しても、精緻で精妙な音作りをするギーレンのバルトークが悪いはずがない、というわけであるが、聴いてみると、たしかに良い演奏なのだが、むしろオーソドックスな聴き味で、ギーレンらしい刻印のようなものは、(私は)それほど感じなかった。 「かかし王子」は、序曲の冒頭がまず印象的で、この部分はラインの黄金の幕開けのような厳かさがあり、ロマンティシズムに満ちた情緒に溢れている。ギーレンは、彼にしては柔和な表情で、ぬくもり豊かに情景を描き出していて、この指揮者にこのような表現性も備わっていたのか、と感じさせるところだ。この作品は、打楽器の使用等により、舞曲におけるバーバリズムが聴かせどころの一つとなっているのだが、当組曲は、むしろ全体的なバランスを配慮した構成になっていて、そのこともあって、むしろ流れの良さと抒情性に感じ入る部分が多い。といっても、後半中心に熱血的なところがあり、そこではギーレンならではの卓越した棒さばきにより、整理の行き届いた音響を楽しむことができる。 管弦楽組曲も同志向の演奏と言えるだろう。この曲には、古今様々な名演奏、名録音があって、その中で当ギーレン盤がきわだった特徴をもっているわけではないと思うが、それでも良演の一つであることは間違いない。バランスに配慮しながらも、音楽に血の通った感情豊かな表現となっているところが魅力だろう。中でも「対の遊び」と題された第2楽章は、そのタイトルにふさわしい楽器間のやりとりが楽しく描かれている。第3楽章のエレジーは品よく仕上がっている。第5楽章は爽やかにまとめた感があるが、ここでは、より粘りや熱血性を求める聴き手も多いかもしれない。 また、全体的に、ライヴ録音とは感じさせないオーケストラの客観性を感じさせる機能美は、このオーケストラの特質をよく示すものだろう。 |
|
 |
弦楽器、打楽器とチェレスタの為の音楽 4つの小品 ヴァイオリン協奏曲 第1番 ギーレン指揮 南西ドイツ放送交響楽団 vn: オステルターク レビュー日:2019.12.30 |
| ★★★★★ ギーレンと南西ドイツ放送交響楽団 2003年のバルトーク・ライヴ
ミヒャエル・ギーレン(Michael Gielen 1927-2019)指揮、南西ドイツ放送交響楽団の演奏で、バルトーク(Bartok Bela 1881-1945)の以下の3つの作品を収録したもの。 1) 管弦楽のための4つの小品(前奏曲、スケルツォ、間奏曲、葬送行進曲) 2) ヴァイオリン協奏曲 第1番 3) 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 ヴァイオリン協奏曲におけるヴァイオリン独奏はクリスティアン・オステルターク(Christian Ostertag 1963-)。2003年のライヴ録音。 ギーレンと南西ドイツ放送交響楽団という現代音楽の奏法に精通した顔合わせによるバルトークであり、そういった点で興味深いわけであるが、聴いてみると、意外なほど、柔軟な対応で、楽曲の情緒的な面を十分に生かした良演といった味わいを感じる。 「管弦楽のための4つの小品」では、静謐から開始される冒頭曲の、透明な音色が重なっていく進行が美しい。この個所で聴き手の気持ちを掴むことに成功したギーレンは、音響とリズムの交錯に冴えを示し、この楽曲ならではの色彩感とメリハリの効いた演出を施していく。スケルツォの切れ味も忘れがたいが、野趣性あるこの作曲家ならではの「葬送行進曲」において、ギーレンの繰り出すリズム感は、力強い表現力となって、劇的に繰り出されている。 一方で、ヴァイオリン協奏曲は、この楽曲の性格もあって、情緒的な表現にシフトを置いた味わい。オステルタークの独奏は、品が良いというか、軽い聴き味でまとまった感があり、この楽曲ならではの北国の冬を思わせるような凛とした諸相はやや控えられた感じがする。ギーレンの音作りも、独奏ヴァイオリンを中心に置いた感があり、私にはその聴き味は少し以外であった。当盤の収録曲では、ギーレンらしさの感じにくいものとなっているだろう。 最後に収録された名作「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」は、いかにも慎重に計算された表現が聴ける。繊細なタッチであり、ときとして、もっと躍動的なものが聴きたい感じもあるのだけれど、特に偶数楽章は、ギーレンとこのオーケストラらしい厳格さがあり、緊迫感のある演奏になっている。第2楽章のピチカートとチェレスタのバランス、第4楽章の感性の鋭さを感じさせるリズムは特に印象に残るところ。第1楽章は、聴く前に想像していた音より、ずっとロマンティックな暖かさがあるのだが、それは私の思い込みのせいというのが大部分なのであろう。何度も聴いていると、全体にとてもうまくいっているように感じられてくる。 全3曲、79分を越える収録時間であり、ライヴとは思えないほどに録音状況も良好であるので、バルトークのアルバムとして、よく出来たものと言えるだろう。 |
|
 |
バレエ音楽「中国の不思議な役人」 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 ドラティ指揮 デトロイト交響楽団 レビュー日:2007.10.6 再レビュー日:2016.6.27 |
| ★★★★★ オーケストラの機能美を徹底した演奏
デッカからアンタル・ドラティの一連の貴重な録音がまとめて再販された。これはデトロイト交響楽団との代表的な録音のひとつ。1983年のデジタル録音で、同交響楽団のストラヴィンスキーの名録音と同じ時期の録音であり、一つ一つが確かな手ごたえに満ちた音で構成されている。 「中国の不思議な役人」はグロテスクな要素を持っているが、ドラティのアプローチは純然としていて、規律正しい音楽の運びがある。特定の楽器を際立たせるような効果を狙わず、全管弦楽の機能美の中であらゆる細部を動かし、巧みな配置により楽曲を構成する。しかも、音楽の全容は引き締まっていてシャープな迫力がある。聴いていると、しっかりとした足取りの中で躍動感が感じられ、しかも不自然さのない心地よさを同時に持っている。 「弦楽器。打楽器とチェレスタのための音楽」も同様で、2楽章のピチカートにのったリズム命の音楽も際立った誇張がないにもかかわらず、オーケストラの音色は迫力にみち、緊迫した中で楽器の鮮烈な音色の組み合わせを堪能させてくれる。 まさに職人芸といえる録音でしょう。 |
|
| ★★★★★ 黄金期のドラティとデトロイト交響楽団が記録した見事なバルトーク
アンタル・ドラティ(Antal Dorati 1906-1988)指揮、デトロイト交響楽団の演奏で、バルトーク(Bartok Bela 1881-1945)の以下の傑作2曲を収録したアルバム。 1) バレエ音楽「中国の不思議な役人」全曲 2) 弦楽器、打楽器とチェレスタのため音楽 1983年の録音。 これら2曲はいずれもバルトークの名品として知られるが、「中国の不思議な役人」については、初演のほかには、その演奏機会を得ることが出来なかった。その理由は、性の問題や、殺人といったシーンを持つストーリーの不道徳性にあったと言われる。併せて、バルトーク特有の原始的な荒々しい表情を見せる音楽が、当時の大衆が求めるものと齟齬があったのかもしれない。いずれにしても、この作品の評価は、初演直後の封印から、数十年の時を経る必要があり、現代のように、演奏、録音の機会が得られるようになったのは、バルトークの死後のことであった。 それにもかかわらず、この曲には「組曲版」も存在する。前述の理由で、ストーリーを取り除いた純器による音楽作品としての再生をバルトークが試みたためである。バルトーク自身がこの作品にひときわ愛着と自信を持っていたことの証左でもある。 現代では、組曲版、全曲版、双方に様々な録音があるが、私としては、是非とも全曲版をおすすめしたい。というのは、組曲版で編集割愛された部分に、音楽的な魅力の高いものが様々にあるからである。全曲版では、歴史的には、まずブーレーズ)(Pierre Boulez 1925-2016)の1971年の名録音が見事であったのだけれど、録音面でさすがに古くなった感もあり、現在の代表的録音としては、このドラティ盤あたりも、有力な一枚となってくるだろう。 当時ストラヴィンスキー(Igor Stravinsky 1882-1971)の数々の目覚ましい録音で高い評価を得ていたドラティとデトロイト交響楽団の顔合わせだけあって、ストラヴィンスキーからの影響を感じさせる当作品へのアプローチは、確信を感じさせる堂々たるもの。また、ハンガリーの民俗音楽をベースとした音楽の抑揚に関するドラティならではの洞察もあって、野趣的なリズム処理も見事なものだ。特にマエストーソの部分の狂乱ぶりの迫力、オルガンを加えてのサウンドのスリリングな交錯など、聴きごたえ十分だ。すべての器楽が、オーケストラの中の機能を果たし、有機的な響きへと結びつけている。 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽では、速度変化を適宜織り込んだ表現で、高揚や迫力を獲得している。現代にあっても、なんら前時代的な印象を感じさせない、普遍的なアプローチだ。 |
|
 |
バレエ音楽「中国の不思議な役人」 2つのポートレート ディヴェルティメント デュトワ指揮 モントリオール交響楽団 vn: ジュイエ ロバーツ レビュー日:2018.6.28 |
| ★★★★★ デュトワが描き出す鮮烈な「中国の不思議な役人」
デュトワ(Charles Dutoit 1936-)指揮、モントリオール交響楽団によるバルトーク(Bartok Bela 1881-1945)の管弦楽曲集。収録曲は以下の通り。 1) パントマイム音楽「中国の不思議な役人」 Sz.73 2) 2つの肖像 Sz.37 3) ディヴェルティメント Sz.113 2)のヴァイオリン独奏は、シャンタル・ジュイエ(Chantal Juillet 1960-)、3)のヴァイオリン独奏は、長くモントリオール交響楽団のコンサート・マスターを務めたリチャード・ロバーツ(Richard Roberts)。1991年の録音。 私は、「中国の不思議な役人」という曲に思い入れがあって、というのも、音楽をいろいろ聴き始めた頃に、ブーレーズが指揮したこの曲の録音を聴くことがあって、「こんなカッコイイ曲があったのか」とたちまち虜になり、毎日のように聴いていた時期があったからである。その反動のせいなのか、最近ではそれほど聴くことはなくなったのだが、最近ふと思い出してみて、このデュトワの録音を聴いてみた。 この楽曲は、ハンガリーの脚本家、メルヒオル・レンジェル(Melchior Lengyel 1880-1974)のテキストに沿ったパントマイムのための舞踏音楽として作られた。その脚本というのが、ホラー、グロテスクの要素を含んでいたこともあって、作品が書かれたころはほとんど上演機会に恵まれなかったわけだ。私がかつて聴いていたブーレーズの録音は、いかにもといった要素が強かったのだけれど、このデュトワの演奏は、(ある意味期待通りに)ブーレーズとは異なっている。なにより、全体的な音色の美しさ、それもパステル・カラーといって良いような透明感が目覚ましく、どこの部分も鮮烈で、リズムや旋律が激しく暗くなっても、その音響は透き通っていて、ステンドグラスを透過した光のように降り注ぐのである。 私は、この演奏を聴いて、ブーレーズの録音とは違った興奮を味わった。それはバルトークのオーケストレーションの見事さへの感動であり、それを鮮やかな音像として描き出したデュトワとオーケストラの好演、さらに録音の素晴らしさへの感動が相まったものである。確かに、この演奏の場合、ストーリーと同じような退廃性は感じにくいのではあるが、純粋な器楽作品として、圧倒的な完成度をもって再現されたものに違いなく、聴き手の心に伝わるものは、十分に大きいのである。さすが、この時代のデュトワとモントリオール交響楽団は、どのような作品であっても、自分たちのやり方を貫いて、芸術性を打ち立てる力に満ちている。 また、その演奏は決して迫力に不足するわけではない。役人が少女を追い回すチェイスのシーンなど、低弦、金管の応答が立体的で、その爽快なテンポとあいまって、臨場感に満ちている。 また、当盤には、バルトークの隠れた名作と言える「ディヴェルティメント」も収録されている。独奏ヴァイオリンの他に独奏弦楽器陣を配した独特の編成で、巧みな演出を楽しませてくれる。さらに「2つの肖像」も収録されていて、バルトークの主用とは言い難いが魅力ある作品を、併せて聴くことができる。現在廃盤のようだが、定盤化してほしいアルバムである。 |
|