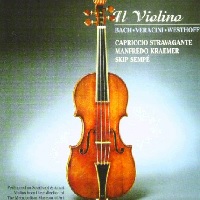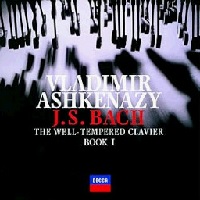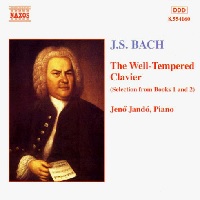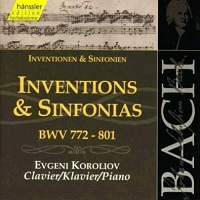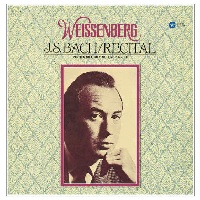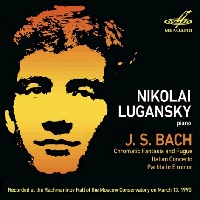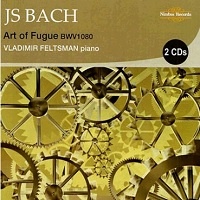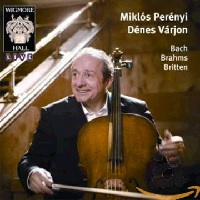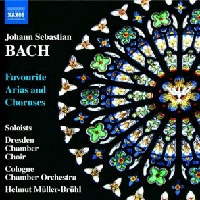|
管弦楽組曲全集 音楽の捧げもの ブランデンブルグ協奏曲全集 フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲 チェンバロ協奏曲 第1番~第5番 2台のチェンバロのための協奏曲 第1番 第2番 3台のチェンバロのための協奏曲 第2番 4台のチェンバロのための協奏曲 ヴァイオリン協奏曲 第1番 第2番 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 メニューイン指揮 バース祝祭管弦楽団 vn: メニューイン フェラス cemb: マルコム プレストン fl: シェファー ob: グーゼンス 他 レビュー日:2019.4.22 |
| ★★★★★ 往年の名芸術家、メニューインによる録音を集めた良心的なボックスセット
メニューイン(Yehudi Menuhin 1916-1999)指揮、バース祝祭管弦楽団を中心としたバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)作品集で、以下の楽曲が収録されている。 【CD1】 1) 管弦楽組曲 第1番 ハ長調 BWV1066 1960年録音 2) 管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067 1960年録音 3) 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 1960年録音 【CD2】 4) 管弦楽組曲 第4番 ニ長調 BWV1069 1960年録音 5) 音楽の捧げもの BWV1079 1960年録音 【CD3】 7) ブランデンブルグ協奏曲 第1番 ヘ長調 BWV1046 1958年録音 8) ブランデンブルク協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV1047 1958年録音 9) ブランデンブルグ協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048 1958年録音 10) ブランデンブルグ協奏曲 第4番 ト長調 BWN1049 1958年録音 【CD4】 11) ブランデンブルク協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050 1958年録音 12) ブランデンブルグ協奏曲 第6番 ロ短調 BWV1051 1958年録音 13) フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV1044 1965年録音 【CD5】 14) チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052 1973年録音 15) チェンバロ協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1053 1973年録音 16) チェンバロ協奏曲 第3番 ニ長調 BWV1054 1970年録音 17) チェンバロ協奏曲 第4番 イ長調 BWV1055 1970年録音 【CD6】 18) チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056 1969年録音 19) 2台のチェンバロのための協奏曲 第1番 ハ短調 BWV1060 1969年録音 20) 2台のチェンバロのための協奏曲 第2番 ハ長調 BWV1061 1969年録音 21) 3台のチェンバロのための協奏曲 第2番 ハ長調 BWV1064 1956年録音 モノラル 22) 4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV1065 1956年録音 モノラル 【CD7】 23) ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV1041 1958年録音 24) 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 1959年録音 25) ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042 1958年録音 26) ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 ニ短調 BWV1060 1962年録音 独奏者、協演者は以下の通り。 ヴァイオリン: ユーディ・メニューイン 5,7,8,9,10,12,23-26)、クリスティアン・フェラス(Christian Ferras) 24) フルート: エレーヌ・シェファー(Elaine Shaffer 1925-1973) 2,5,10)、ウィリアム・ベネット(William Bennett 1936-) 12) ファゴット: アーチー・カムデン(Archie Camden 1888-1979) 5) チェンバロ: ロナルド・キンロック・アンダーソン(Ronald Kinloch Anderson 1911-1984) 5)、ジョージ・マルコム(George Malcolm 1917-1997) 10,12,14-22)、サイモン・プレストン(Simon Preston 1938-) 19,20)、アイリーン・ジョイス(Eileen Joyce) 21,22)、サーストン・ダート(Thurston Dart) 21,22)、デニス・ヴォーン(Denis Vaughan) 22) トランペット: デニス・クリフト(Denis Clift) 7) リコーダー: クリストファー・テイラー(Christopher Taylor 1929-1982) 7,9)、リチャード・テイラー(Richard Taylor) 9) オーボエ: ジャネット・クラクストン(Janet Craxton 1929-1981) 7)、レオン・グーセンス(Leon Goossens) 26) ヴィオラ: パトリック・アイルランド(Patrick Ireland) 8,11)、ユーディ・メニューイン 11) ヴィオラ・ダ・ガンバ: アンブローズ・ゴーントレット(Ambrose Gauntlet) 11)、デニス・ネスビット(Dennis Nesbitt) 11) 21,22)はボリス・オード(Boris Ord 1897-1961)指揮、プロ・アルテ・オーケストラ 23,25)はメニューイン指揮、ロバート・マスターズ室内管弦楽団 他は、メニューイン指揮、バース祝祭管弦楽団 21,22)の録音は、マルコムによるチェンバロ協奏曲集というコンセプトで集められたものであり、メニューインは参加していない。なお、ブランデンブルグ協奏曲第3番では、通常独奏楽器の扱いはないが、原曲では末尾の2和音しか書かれていない第2楽章に関して、当盤はブリテン(Benjamin Britten 1913-1976)によって、バッハの「トリオ・ソナタ 第6番 ト長調 BWV530」の第二楽章を、独奏ヴァイオリン、独奏ヴィオラ、通奏低音のために編曲したスコアが用いており、そのため、独奏者が存在する形となる。 これらの演奏様式は、現代のそれと比べると、テンポはゆったりしていて、ビブラートも用いられているが、しかし、音楽を通して伝わってくる感情の豊かさは立派なものである。この録音が行われた時代は、すでにアーノンクール(Nikolaus Harnoncourt 1929-2016)をはじめとする古楽奏法に関する提案は行われていたが、まだ学術的な範囲を越えて人心を獲得したとはいえない頃である。ただ、メニューインが採用したスタイルは、大時代的なものとはまた異なり、コンパクトな楽団構成で、ポリフォニーの効果の分かりやすい透明性を意識したものでもある。それでいて、例えば管弦楽組曲第3番の序曲では、ティンパニ、トランペットの効果も高らかに勇壮な音楽を繰り広げており、音楽的効果と、様式的美観の双方のバランスを巧みに突いた演奏であったと感じられる。有名な管弦楽組曲第3番のエアーも、とても透明で清々しく、音が厚ぼったくなることを避けており、そのことが、楽曲全体の構成感を良く保っていると思う。 管弦楽組曲第2番のエレーヌ・シーファーのフルートも聴きモノの一つだ。アメリカの女流フルート奏者の草分け的存在として知られる演奏者だが、その演奏は高貴と形容したい響きで、音質が安定し、かつとても輪郭のくっきりしたストレートさがある。安定した響きは、しばしば落ち着き過ぎという気もしないでもないが、淡々と奏でるバディヌリーは、楽曲の性格と見事な合致を見せて、健やかで美しい。 「音楽の捧げもの」は、様々なヴァージョンで演奏されるが、ボーイリングの編曲は、進行にともなって加わる楽器にスポットライトを当てるもので、演奏会に相応しいものの一つと思う。そのスタイルに従ったメニューインの解釈で、各奏者の腕前を堪能することが出来る。 「ブランデンブルグ協奏曲」も、最近流行のピリオド奏法によるものと比較するとテンポはややゆっくり目である。それゆえ、現代楽器ならではの中間色の豊富な音は、豊かで健康的な華やかさを持っている。メニューインは、ポリフォニーを明確に描く透明感あるサウンドを作りながら、適度な肉付けと情感を施し、暖かく潤いのある音楽を導いている。 このような演奏は、今となっては、「往年の」名演、といった感じで、名演と呼ぶ際であっても、ある程度の条件が付されてしまうのかもしれない。録音状態を加味して、という以上に、ロマン派的な解釈との折衷的な性格の演奏だからである。しかし、その音楽は美しく、ピリオド楽器の演奏では、乾いて、刺々しくなってしまう部分であっても、ほどよいふくよかさがあり、私には聴き易い。もちろん、それゆえの音の重さもある。フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲の冒頭など、今の感覚で言えば、いかにも腰が重い感じがする。それをどう捉えるかは人それぞれだが、ブランデンブルグ協奏曲集に関して言えば、独奏楽器と合奏の対比など、いくぶん重みづけの付された響きで配色を整えられていた方が、楽曲ごとの個性が映えるし、面白味は増すと私は思う。 当盤では、特に明朗な祭典的華やかさが好ましい。ブランデンブルグ協奏曲では第6番や、第3番の終楽章など、交錯する音色、そのそれぞれが歌謡性をもって響く音楽的な感触が絶好だ。第5番では、管弦楽組曲第2番でもソロを担ったシェファーのフルートの折り目正しい響きが美しい。第2番のテイラーのリコーダーも典雅だ。 マルコムのチェンバロ協奏曲集もまた「往年の佳演」といったところ。マルコム、プレストン、ダートといった名手を揃え、全般に明朗なテイストの響き。テンポは現在聴かれるピリオド奏法に比べると、ゆったりしていて、オーケストラは厚い響きも辞さないわけだが、それゆえに独奏楽器の絶対的な音量の不足を感じるところはある。私は、バロックの作品だからといって、ピリオド楽器によるピリオド奏法で演奏するべきだ、とはまったく思わないが、ことこれらの楽曲の独奏楽器にチェンバロを用いるのなら、オーケストラもピリオド楽器で演奏し、編成も縮小した方が、バランスは良くなるだろう。とはいえ、それでも重厚な主題を奏でる際、チェンバロという楽器で演奏すると、絶対的な出力不足は感じられる。だから、これらの楽曲を録音するのであれば、ピノック(Trevor Pinnock 1946-)盤のように、録音技術でメリハリをつけるか、もしくは現代楽器であるピアノで奏するのが、いちばん良いと思う。 ただ、それに代わる当盤の魅力は、自然なマイルドさである。人工的なものを感じさせない、おおらかな明るさは、全体の印象となっていて、「古き佳き」と形容したい典雅な響きに満ちている。各チェンバロ奏者は、真摯さを感じさせるアプローチをしており、楽器自体の出力不足を百も承知の上で、一生懸命弾いているというふうに感じる。協奏曲というイメージから離れて、チェンバロを含む合奏音楽というイメージで聴いたほうが、その音楽世界に入り込みやすいだろう。「チェンバロ協奏曲 第3番」や「3台のチェンバロのための協奏曲 第2番」のような明朗で祭典的な雰囲気をもった楽曲が、特にそのスタイルに合っているように思う。 ヴァイオリン協奏曲集については、メニューインの録音は複数あって、私はその多くを聴いてはいないが、当演奏で聴かれるメニューインのスタイルは落ち着きがあり、響きはソフトなぬくもりを感じさせる。おそらく若いころの録音の方が、力強い膂力を感じさせるものだったと思うが、さすがに今となっては、録音が古くなった。一方で、当盤の録音は、比較的良好な品質といって良く、聴いていてそれほど「聴きづらさ」は、感じない。 第1番の冒頭は、情感豊かで憂いのある合奏音が印象的・・(しかし、この点で個人的にもっとも印象深いのは、バリリ(Walter Barylli 1921-)シェルヘン(Hermann Scherchen 1891-1966)盤である)・・だ。管弦楽の豊かな情緒に導かれるようにしてはじまるヴァイオリン・ソロは、泣かせ節を自然なテイストで表出し、滋味を感じさせる。第2楽章のソロに宿るロマンティックな感興も胸に迫るものがある。 2つのヴァイオリンのための協奏曲は、当時模範的といっても良い解釈だろう。第2楽章では豊かなポルタメントも聴かれるが、決して胃もたれするようなものではなく、全体の雰囲気はわりと清澄だ。両端楽章のスマートな響きはむしろ最近主流の解釈に近いものを感じさせる。 第2番も落ち着いた解釈であるが、第1番に比べると、やや平板な印象を感じさせるところがある。訥々とした語り口であるが、あえて情感を抑えた表現を目指したような感じだろうか。ただ、音色は前述の通りで聴き易く、疲れない演奏といった感じ。 ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲は、悪くはないのだが、当時の録音技術では、オーボエの音量が弱く、芯のある音色として伝わりにくいところがある。オーケストラとの音量バランスの関係で仕方ないとは言え、難点に感じるところ。ただ、グーセンスのオーボエは、高音が醸す典雅な風合いは良い感じで、古めかしい貫禄があり、味わいのある響きにはなっている。 |
|
 |
管弦楽組曲全集 鈴木雅昭指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン fl: 前田りり子 レビュー日:2006.4.2 |
| ★★★★★ ピリオド楽器のイネガル(不均等)奏法による到達点
鈴木雅昭の棒の下、バッハ・コレギウム・ジャパンがついにバッハの管弦楽組曲全曲をレコーディング。フラウト・トラヴェルソは前田りり子。2枚組みで、1枚目には、第3番、第1番、第2番の順番で3曲が、2枚目に第4番の1曲のみが収録されている。 カンタータや協奏曲を録音して十分に蓄えられた奏法、解釈を、如何なく発揮した秀演となった。いわゆるピリオド楽器によるイネガル(不均等)奏法を追求しており、付点に近いアクセント変更よる装飾音化により、特有の流れと典雅な音色を獲得している。つまり、メロディラインにある音は均等に存在するのではなく、長く保持される音と、短縮される音により構成されるわけだが、もちろん節々におけるテンポはインテンポであるし、それがピリオド楽器奏法のたどり着いた「こなれた」表現としてここに正に聴く事ができる。そして、合奏そのものの精度の高さが、その奏法による表現をより純化しており、その結果、テイストとしてはとても軽い。たとえばかつてカラヤンやメニューインがタクトをとったときの豪放さは完全に遺棄されているわけだし、この時代にあってこの表現形態があらためて再構成された意義は大きいと思う。 というわけで、非常に質の高い演奏で、一つの到達点を感じさせる内容となっている。 |
|
 |
管弦楽組曲全集 ミュラー=ブリュール指揮 ケルン室内管弦楽団 fl: カイザー レビュー日:2017.6.21 |
| ★★★★★ バッハの管弦楽組曲の「決定盤」と言ってもいいくらいの録音です
ヘルムート・ミュラー=ブリュール(Helmut Muller-Bruhl 1933-2012)指揮、ケルン室内管弦楽団によるバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)の管弦楽組曲全4曲を1枚のディスクに収録したアルバム。収録内容は以下の通り。 1) 管弦楽組曲 第1番 ハ長調 BWV1066 2) 管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067 3) 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 4) 管弦楽組曲 第4番 ニ長調 BWN1069 1998年の録音。第2番のフルート独奏はカール・カイザー(Karl Kaiser 1934-) 非常に素晴らしい演奏で、これらの名曲における現代の代表的な録音と言って差し支えない。 ケルン室内管弦楽団は、現代楽器による合奏団で、現代楽器によるバロック演奏は、現代では少数派となった観があるが、このような素晴らしい演奏を聴くと、ピリオド楽器派の人も、いろいろ再考するところが出てくるのではないかと思う。 また、現代楽器による演奏といっても、この楽団も一時期はピリオド楽器の演奏を行っていたことがあり、そのような経験に裏付けられたやや早めのピリオド奏法を応用した進行は、現代的な感覚美に溢れている。 現代楽器を用いた最大の特徴は、完璧なイントネーションによる再現性の確かさにあり、可能な限り偶発的なものを削いだ合奏音の見事なフォルムは圧巻と言える。ピリオド楽器の演奏では、楽器自体の不安定さに伴った幅があり、そのことによって、独特の風味があったことは確かであるが、しかし、この演奏の様に、メカニカルな正確さの裏付けという前提があったうえで、隅々にまで感覚を研ぎ澄まして音楽を表現することは、絶対的で不可侵な価値を持つものなのである。 不用意な膨らみのないスリムな外形を持ちながら、時に激しい弾力を感じさせる踏込は、完全燃焼を感じさせる美しさで、不純物のない完成度に満たされている。だからといって演奏が味気ないということは決してない。隅々まで行き届いた表現は、人間的な感情の機微、特に「喜び」を聴き手に伝え、暖かい感動をもたらしてくれる。 第2番の名手カイザーのフルートも見事。管弦楽と絶妙なバランスを保ちながら、艶を欠くところがない。 全般にとにかく素晴らしい演奏の一語なのだが、象徴的な個所を一か所挙げるとすれば、第3番の序曲、それも序奏部が終わって展開が始まる瞬間。一陣の爽やかな夏風が吹き抜けるような、涼やかで健康的な幸福を満喫させてくれる。 |
|
 |
管弦楽組曲全集 ポンマー指揮 札幌交響楽団 fl: 髙橋聖純 レビュー日:2017.8.16 |
| ★★★★★ モダン楽器によるバッハの素晴らしさを再証明するポンマーと札幌交響楽団の偉大な業績
2015年から札幌交響楽団の主席客演指揮者を務めるマックス・ポンマー(Max Pommer 1936-)指揮によるバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)の管弦楽組曲全曲がリリースされた。2017年のライヴ録音である。1枚のCDに以下の順番に全曲が収録されている。 1) 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068 2) 管弦楽組曲 第1番 ハ長調 BWV.1066 3) 管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV.1067 4) 管弦楽組曲 第4番 ニ長調 BWV.1069 チェンバロ奏者に辰巳美納子を迎えているほか、第2番のフルート独奏を髙橋聖純(1975-)が務める。 札幌交響楽団の奏でる素晴らしいバッハを聴いて、感慨は大きいが、それにもまして特筆したいのが、本アルバム作製にあたってのポンマーの意気込みである。バッハゆかりの地、ライプツィヒで生まれ、バッハの作品を永年にわたって研究し、当録音以前にも管弦楽組曲を何度となく演奏してきたポンマーは、当CDの解説に寄せて、ハンス・ツェンダー(Hans Zender 1936-)の「“作曲家の正しい解釈は、その時代の演奏様式の中に見出すべきだ” という主張は誤りである」という言葉を引用した上で、本来の響きだけで正しい解釈の方法が見えるという考えに危険性があることを指摘し、モダン楽器による演奏を強く推奨している。 ポンマーは、この録音の前年、髙橋聖純も教鞭をとる札幌大谷大学で、研究者として、バッハの音楽に関するレクチャーを行った。私はそれを聞く機会はなかったのだけれど、そこで、ポンマーはバッハが当時いかにしてフランス様式が高度に集約された管弦楽組曲を書くに至ったか、またそれを現在演奏するに当たって、どのようなことに配慮して望むべきであるのかについて、とても内容の深い講義を行ったとのこと。 私も、現代「バロックを演奏するならピリオド楽器」というのが、定説的になっていることに、普段から大いに疑問を感じ、今こそバロック作品の演奏におけるモダン楽器の素晴らしさに、もう一度着目すべきであろう、と思っていたので、このポンマーの言は、とても納得でき、かつ勇気づけられるものなのである。 そして、それを証明するように、当盤に収録された演奏の素晴らしいこと。現代楽器ならではの安定感を土台に、すべてが過不足なく、バランスよく調和された響き、正確な音程と音長から導かれた輝かしく愉悦に満ちたリズムと音感、そしてここぞというとき盛り上がる中音域の豊な音圧に、たいへん感動させられる。そこに見出されるのは、疑いもない音楽への愛であり、音楽を演奏し、享受することへの喜びと感謝である。これほど美しい豊かな感情に溢れたものを、そう簡単に傍流におしやってはならない。ヨーロッパの本流から地理的に離れた日本の北辺にあるオーケストラが、そのことを堂々と主張し証明するたくましさに浸り、地元の人間として、これ以上ない幸福を味わうことができた。 ポンマーと札幌交響楽団に喝采。 |
|
 |
管弦楽組曲全集 音楽の捧げもの メニューイン指揮 バース祝祭管弦楽団 fl: シェファー レビュー日:2019.4.16 |
| ★★★★★ モダン楽器によるバッハの素晴らしさを再証明するポンマーと札幌交響楽団の偉大な業績
メニューイン(Yehudi Menuhin 1916-1999)指揮、バース祝祭管弦楽団によるバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)作品集で、以下の楽曲が収録されている。 【CD1】 1) 管弦楽組曲 第1番 ハ長調 BWV1066 2) 管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067 3) 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 【CD2】 4) 管弦楽組曲 第4番 ニ長調 BWV1069 5) 音楽の捧げもの BWV1079 1960年の録音。 2,5)のフルート独奏はエレーヌ・シェファー(Elaine Shaffer 1925-1973)、5)のファゴットはアーチー・カムデン(Archie Camden 1888-1979)、チェンバロはロナルド・キンロック・アンダーソン(Ronald Kinloch Anderson 1911-1984)、そしてヴァイオリンはメニューイン。「音楽の捧げもの」は、バース祝祭管弦楽団の演奏のため、ネヴィル・ボーイリング(Neville Boyling)がアレンジしたスコアによる録音。 私は、両親がクラシック音楽を愛好していたため、その影響を受けて、子どものころから名曲の旋律に馴染んできたのだけれど、高校生になったころから、ふだん両親が聴くもの以外にも、家のLPコレクションから、いろいろ引っ張り出してきて、再生することを楽しむようになった。当時、私の両親は、もっぱら古典派とロマン派の音楽が好きで、バッハを聴くことはめったになかったのだが、そのコレクションの中に、このメニューインが指揮したバッハの管弦楽曲集があった。それは第2番と第3番が裏表になったもので、バッハの音楽に馴染みのなかった私は、その第3番を聴いて、なんて素敵な音楽なんだろう、と思ったのである。以来、私の中で、バッハの管弦楽組曲というと、いちばん深くに刷り込まれているのが、このメニューインの演奏ということになる。 これらの演奏様式は、現代のそれと比べると、テンポはゆったりしていて、ビブラートも用いられているが、しかし、音楽を通して伝わってくる感情の豊かさは立派なものである。この録音が行われた時代は、すでにアーノンクール(Nikolaus Harnoncourt 1929-2016)をはじめとする古楽奏法に関する提案は行われていたが、まだ学術的な範囲を越えて人心を獲得したとはいえない頃である。ただ、メニューインが採用したスタイルは、大時代的なものとはまた異なり、コンパクトな楽団構成で、ポリフォニーの効果の分かりやすい透明性を意識したものでもある。それでいて、例えば管弦楽組曲第3番の序曲では、ティンパニ、トランペットの効果も高らかに勇壮な音楽を繰り広げており、音楽的効果と、様式的美観の双方のバランスを巧みに突いた演奏であったと感じられる。有名な管弦楽組曲第3番のエアーも、とても透明で清々しく、音が厚ぼったくなることを避けており、そのことが、楽曲全体の構成感を良く保っていると思う。 エレーヌ・シーファーのフルートも聴きモノの一つだ。アメリカの女流フルート奏者の草分け的存在として知られる演奏者だが、その演奏は高貴と形容したい響きで、音質が安定し、かつとても輪郭のくっきりしたストレートさがある。安定した響きは、しばしば落ち着き過ぎという気もしないでもないが、淡々と奏でるバディヌリーは、楽曲の性格と見事な合致を見せて、健やかで美しい。 「音楽の捧げもの」は、様々なヴァージョンで演奏されるが、ボーイリングの編曲は、進行にともなって加わる楽器にスポットライトを当てるもので、演奏会に相応しいものの一つと思う。そのスタイルに従ったメニューインの解釈で、各奏者の腕前を堪能することが出来る。 これらの録音は、現在となっては「かなり昔のもの」となったが、オリジナル楽器による演奏とは異なった肉付けの豊かさがあり、それでいて引き締まったプロポーションを持っている。私の場合、この録音には深い思い入れがあるのだが、そのことを別にしても、魅力的な演奏であり、今なお捨てがたいものであると思う。 |
|
 |
ブランデンブルグ協奏曲 全曲 シャイー指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団 レビュー日:2012.5.31 |
| ★★★★★ 作曲者ゆかりの地から、シャイーならではの麗しいロマンあるバッハ
2005年にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のカペルマイスターに就任したリッカルド・シャイー(Riccardo Chailly 1953-)は、この地にゆかりの深い偉大な作曲家、バッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)の作品を積極的に取り上げるようになった。これまでシャイーという音楽家からバッハという作曲家へのアプローチが行われることは、あまり想像してなかったのだけれど、これらが聴いてみるとなかなか良い。 当盤は、その取り組みの一つで、ブランデンブルグ協奏曲全曲が2枚のディスクに収録されている。録音は2007年。 ブランデンブルク協奏曲は全6曲からなる作品群で、バッハの代表作の一つとして知られる。曲名の由来は、これらの作品が、ブランデンブルク辺境伯クリスティアン・ルートヴィッヒ(Christian Ludwig 1677-1734)に捧げられたことにある。1721年当時、すでに作曲されていた作品から6曲が選ばれたという説が定説で、これら楽曲の作曲年代は1718-21年と推定されている。 6曲はそれぞれ楽器編成を異にしている。また、これらの曲をすべて「合奏協奏曲」と呼ぶのは正確ではないだろう。すなわち、本来「合奏協奏曲」とは、独奏楽器陣と合奏楽器陣が交互に主題を奏す様式を指すのだが、第3番と第6番の2曲に関しては、独奏楽器陣が存在しないため、一種の「管弦楽組曲」と称した方が、実態に合っていることになる。また、「合奏協奏曲」では、独奏楽器が一つではなく複数存在しているところが、古典派以後の「協奏曲」との大きな相違点となる。圧倒的に有名なのが第5番であるが、第1楽章に登場する長大なチェンバロ・ソロは、後の“独奏楽器が一つ”の協奏曲、「チェンバロ協奏曲」の発展の礎となった作品と言える。そのため、音楽史の上でも、重要な役割を果たした楽曲となるだろう。楽章は3または4つで構成されるが、第6番以外は、長調の両端楽章が短調の中間楽章を挟む形になっている共通項も注目できるだろう。 このシャイーとライプツィヒ・ゲヴァントハウスの録音は素晴らしい。まず、どのような編成であっても、精巧なオーケストラのアンサンブルが保たれていることが特筆できる。次に、最近では、バッハの楽曲というと、判で押したようにピリオド楽器が用いられるが、現代楽器特有のふくよかな感触を、精緻に縫い上げた彩が見事だ。ピリオド楽器の演奏に聴きなれた現代では、シャイーのテンポはややゆったりめに思えるが(もちろん、アンティークな演奏と比べれば、十分速いのだが)、このテンポであってこそ掬い取られる情感が適切に得られており、それが高貴な雰囲気をまとって聴き手に「魅力的に」伝わってくるのが最大の美点である。「こうでなくちゃ」と思うファンは相当数いるのではないだろうか?(私もその一人ですが・・・) 更には、楽器の麗しい柔らかな響きも存分に堪能できる。ことに管楽器の豊かな円熟した味わいは現代楽器ならではのまろやかな情感に満ちている。バッハの音楽が秘めるロマン性をほのかに漂わせた香気を抜群の距離感でとらえた録音も秀逸だと思う。総じて、バッハの音楽の特性を見事に表出させることに成功した価値あるディスクと言えるだろう。 |
|
 |
ブランデンブルグ協奏曲 全曲 アバド指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団 レビュー日:2015.8.26 |
| ★★★★☆ 今となっては、の感もあるが、懐かしい美点を感じる演奏です。
クラウディオ・アバド(Claudio Abbado 1933-2014)が1975年と76年に、ミラノ・スカラ座管弦楽団を指揮して録音したバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)のブランデンブルグ協奏曲集。全6曲を収録。 ブランデンブルグ協奏曲は、独奏楽器と、弦楽合奏・通奏低音からなる合奏が、互い違いに登場する様式で書かれた代表的な作品集。全6曲について独奏が割り当てられた楽器と併せて記載し直すと以下の通り。 第1番 ヘ長調 BWV1046 ホルン2、オーボエ3、ファゴット、ヴィオリーノピッコロ 第2番 ヘ長調 BWV1047 トランペット、リコーダー、オーボエ、ヴァイオリン 第3番 ト長調 BWV1048 ヴァイオリン3、ヴィオラ3、チェロ3 第4番 ト長調 BWV1049 ヴァイオリン、リコーダー2 第5番 ニ長調 BWV1050 フルート、ヴァイオリン、チェンバロ 第6番 変ロ長調 WV1051 独奏、合奏の区別なし 当盤も上記の通り収録されている。 このアバドの録音、海外では、最近までCD化されておらず、日本国内でも一度リリースされたのみだったらしい。最近になってbox-setなどに収録されることがあり、CDというメディアで広範に流通するようになった。 とはいってもアバドはこれらの楽曲を2007年にモーツァルト管弦楽団と録音しており、解釈もモダンに変わっているため、いま現在アバドのブランデンブルグ協奏曲をとるなら、新しい方の録音を採るべきだろう。 当盤で聴かれる音楽は、当時の現代楽器を用いた解釈で、ロマン派的な香りのただようもの。それはそれで悪くないのだけれど、あきらかに現在の主流の解釈とはことなった路線のものだと思う。落ち着いたテンポで、旋律にはたっぷりとした情緒があり、例えば第1番の第2楽章で朗々と歌われるヴィオリーノピッコロを聴くと、さすがに解釈面での時代的なギャップを感じるところがある。 とはいえ、アバドとミラノ・スカラ座管弦楽団が繰り広げる明朗で開放的な演奏は、これらの楽曲の華やかな一面をよく示したものともいえるだろう。 聴きどころとしては、有名な第5番で起用されたブルーノ・カニーノ(Bruno Canino 1935-)のチェンバロを挙げたい。カニーノはピアニストとし名を知られる人で、特に室内楽の伴奏などで録音もいくつかあるのだけれど、チェンバロをここまで闊達に響かせる人だとは知らなかった。特に有名なあの長いカデンツァの流れるように鮮烈な音のつながりは、とても爽快だ。 かつてのアバドの解釈に思いを馳せながら、ときどきステレオから流してみても良いアルバムといったところ。 |
|
 |
ブランデンブルグ協奏曲 全曲 フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲 メニューイン指揮 バース祝祭管弦楽団 vn: メニューイン 他 レビュー日:2019.4.17 |
| ★★★★★ メニューインの貫禄が味わえる名演です
ユーディ・メニューイン(Yehudi Menuhin 1916-1999)指揮、バース祝祭管弦楽団による、バッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)のブランデンブルグ協奏曲全曲を中心としたアルバム。収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) ブランデンブルグ協奏曲 第1番 ヘ長調 BWV1046 2) ブランデンブルク協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV1047 3) ブランデンブルグ協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048 4) ブランデンブルグ協奏曲 第4番 ト長調 BWN1049 【CD2】 5) ブランデンブルク協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050 6) ブランデンブルグ協奏曲 第6番 ロ短調 BWV1051 7) フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV1044 7)のみ1965年、他は1958年の録音。 各協奏曲の独奏楽器の担い手は以下の通り。 ヴァイオリン: ユーディ・メニューイン 2,3,4,5,7) トランペット: デニス・クリフト(Denis Clift) 2) リコーダー: クリストファー・テイラー(Christopher Taylor 1929-1982) 2,4)、リチャード・テイラー(Richard Taylor) 4) オーボエ: ジャネット・クラクストン(Janet Craxton 1929-1981) 2) ヴィオラ: パトリック・アイルランド(Patrick Ireland) 3,6)、ユーディ・メニューイン 6) フルート: エレーヌ・シェファー(Elaine Shaffer 1925-1973) 5)、ウィリアム・ベネット(William Bennett 1936-) 7) チェンバロ: ジョージ・マルコム(George Malcolm 1917-1997) 5,7) ヴィオラ・ダ・ガンバ: アンブローズ・ゴーントレット(Ambrose Gauntlet) 6)、デニス・ネスビット(Dennis Nesbitt) 6) なお、ブランデンブルグ協奏曲第3番では、通常独奏楽器の扱いはないが、原曲では末尾の2和音しか書かれていない第2楽章に関して、当盤はブリテン(Benjamin Britten 1913-1976)によって、バッハの「トリオ・ソナタ 第6番 ト長調 BWV530」の第二楽章を、独奏ヴァイオリン、独奏ヴィオラ、通奏低音のために編曲したスコアが用いており、そのため、独奏者が存在する形となる。 現代楽器による演奏で、最近流行のピリオド奏法によるものと比較するとテンポはややゆっくり目である。また現代楽器ならではの中間色の豊富な音は、豊かで健康的な華やかさを持っている。メニューインは、ポリフォニーを明確に描く透明感あるサウンドを作りながら、適度な情感を与え、肉付けを施し、暖かく潤いのある音楽を導いている。 このような演奏は、今となっては、「往年の」名演、といった感じで、名演と呼ぶ際であっても、ある程度の条件が付されてしまうのかもしれない。録音状態を加味して、という以上に、ロマン派的な解釈との折衷的な性格の演奏だからである。しかし、その音楽は美しく、ピリオド楽器の演奏では、乾いて、刺々しくなってしまう部分であっても、ほどよいふくよかさがあり、私には聴き易い。もちろん、それゆえの音の重さもある。フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲の冒頭など、今の感覚で言えば、いかにも腰が重い感じがする。それをどう捉えるかは人それぞれだが、ブランデンブルグ協奏曲集に関して言えば、独奏楽器と合奏の対比など、いくぶん重みづけの付された響きで配色を整えられていた方が、楽曲ごとの個性が映えるし、面白味は増すと私は思う。 当盤では、特に明朗な祭典的華やかさが好ましい。ブランデンブルグ協奏曲では第6番や、第3番の終楽章など、交錯する音色、そのそれぞれが歌謡性をもって響く音楽的な感触が絶好だ。第5番では、管弦楽組曲第2番でもソロを担ったシェファーのフルートの折り目正しい響きが美しい。第2番のテイラーのリコーダーも典雅だ。 確かに録音としては、さすがに古くなったのは否めないが、録音年代を考えるとその状態は良好と言えるし、「往年の」といった冠をつけなくても、今なお堂々たる名演と呼んで、差し支えないだろう。 |
|
 |
ストコフスキーによるバッハ作品の交響的編曲集 セレブリエール指揮 ボーンマス交響楽団 レビュー日:2011.6.14 |
| ★★★★★ だれもが共有できる「あの曲!」を想起させるストコフスキーの名編曲
1938年ウルグアイ生まれの指揮者ホセ・セレブリエール(Jose Serebrier)によるボーンマス交響楽団とのレオポルド・ストコフスキー(Leopold Stokowski 1882-1977)の編曲集。当盤にはバッハの他、ヘンデル、パーセルの作品からの編曲などが収められた。2005年録音。 いきなりちょっと別の話を書く。結構前だが、とりたててクラシック音楽には詳しくない妻が、「パッヘルベルのカノンを聴きたい」と言ったとき、ちょっと試しに所謂ピリオド楽器によるピリオド楽器奏法の演奏を聴かせたところ、予想通り「なんじゃこりゃ?」という反応であった。「こんなに早く弾いて、CDの故障?」と・・・。「いや、故障じゃないよ、こういう解釈の演奏なんだよ・・、じゃあこっちの方がきっとイメージ通りだね」とミュンヒンガーのいわゆる「古典的な」演奏を聴かせると、今度はとっても納得していた。「この曲が聴きたかったんだ・・」「いや、まあ同じ曲なんだけどね」と・・(笑)。 何が言いたいかというと、ピリオド楽器だ、アラ・ブレーヴェだ、イネガル奏法だ・・と研究的解釈に基づいた演奏がさかんになり、それを聴いて楽しむ一方で、もう一つの音楽の要素、人への「近づき易さ」という価値が、最近置いていかれているように思う。いや、もちろんピリオド楽器など、様々な試みは価値があって、それを否定するわけではまったくないのですが。 それで、その「近づき易さ」を最重点に音楽をやっていた人というのが、ストコフスキーだったのじゃないかな、と思う。彼の編曲はどれもロマンティックで少し回顧調なのだ。なので、例えばこのアルバムの冒頭に収録された有名な「G線上のアリア」であっても、鳴り始めたとたんに、誰もが「ああ、この曲知ってる!」と思えるような、オーソドックスで人の心に残り易いテンポと音色が巧妙に選択されている。だから、妙にクラシック音楽に詳しくない人(そしてそれが世の大部分!)にとっては、むしろこの編曲こそが、カンタンにみんなと共有できる「あの曲」足りえるのである! ・・と書くとただ俗っぽいイメージだろうか?そうではない。編曲だけでなく、セレブリエールの指揮も見事。決してこれらの編曲ものも「分り易い」だけでなく、懐の大きなフォローで、必要な場所は適度に「掘り下げた」表現を見せてくれる。だから、聴いていても、通俗的で飽きるという思いも抱かせない。まさにコクのある演奏だ。また、ストコフスキー自身の編曲により巷に登場することとなった「2つの古い典礼歌の旋律」も、美しい作品で、様々な意味でストコフスキーとセレブリエールに感謝したくなるディスクだ。 |
|
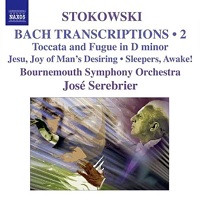 |
ストコフスキーによるバッハ作品の交響的編曲集 2 セレブリエール指揮 ボーンマス交響楽団 レビュー日:2011.6.14 |
| ★★★★★ 名画「ファンタジア」を彷彿とさせるストコフスキー・サウンド
ホセ・セレブリエール(Jose Serebrier)とボーンマス交響楽団によるレオポルド・ストコフスキー(Leopold Stokowski 1882-1977)のバッハ編曲集、2枚目。2008年録音。バッハだけではなく、バロックから古典にかけての他の作曲家の作品の編曲も収録されている。 冒頭はトッカータとフーガ。そう、この曲は冒頭に置かねばならない・・・。1940年にディズニーが製作した映画「ファンタジア」はクラシックの名曲から物語を紡ぎだした名作中の名作である。日本で公開されたのは1955年で、私が生まれるよりずっとずっと前の出来事。しかし、何らかのリヴァイヴァル上演の再、私も映画館でこの映画を観た。その記念すべき第1曲がストコフスキー編曲によるトッカータとフーガである。 映画の中で、この「トッカータとフーガ」による物語だけが抽象的な内容で、音楽の世界から少しずつ映画の世界に分け入っていくような、摩訶不思議な演出がなされていた。幼少の自分がその意図を理解していたとはとても思えないが、弦を弾く弓の重なった絵や、大きな岩の様なものがゴロゴロ動いていくシーンなど、とても印象に残っている。思えば、この作品ではじめて「ステレオ技術」の導入が果たされたのである。音楽を務めたストコフスキーの役割の多彩さを改めて思い知る。 それで、このアルバムも「トッカータとフーガ」から、ストコフスキーの編曲の世界に入っていくことになる。ストコフスキーの編曲には衒いがない。オーケストラのパワーの最大の限りの尽くし、必要とあらば壮大な音の伽藍を築き上げる。また、セレブリエールの指揮も全合奏の迫力からデリケートなピアニシモまでストコフスキーの編曲を再現するダイナミクスを存分に表現している。 「アリオーソ」はチェンバロ協奏曲へ短調(BWV1056)のラルゴ楽章の編曲で、弦楽器の豊かな表情が聴きモノ。また、編曲は常にフル・オーケストラというわけでなく、前奏曲第24番やシチリアーノのように弦楽合奏によるものもある。いずれにしてもセレブリエールはオーケストラから最高の能力を引き出しているように思う。「目覚めよと、呼ぶ声あり」、「主イエス・キリスト、われ汝を呼ぶ」、「トッカータ、アダージョとフーガからアダージョ」など多分にロマンティックでありながら、適度な拘束があり、音楽を自由に流し過ぎない美点もある。 最後に収録されたハ短調のフーガは、ストコフスキーの「ワグネリアン」としての一面を端緒に示すだろう。 |
|